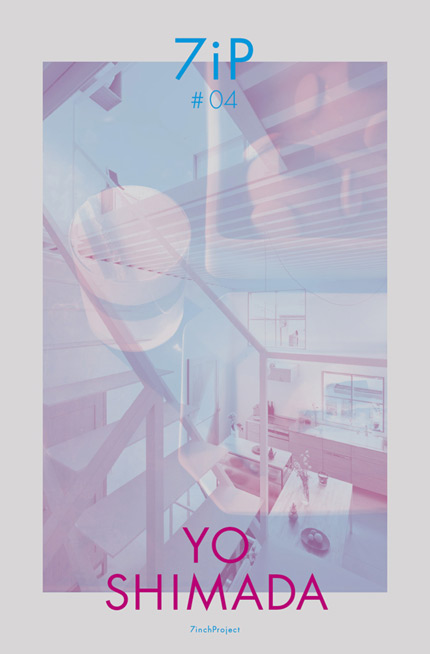書籍『Fab ―パーソナルコンピュータからパーソナルファブリケーションへ』がamazonで発売されています
書籍『Fab ―パーソナルコンピュータからパーソナルファブリケーションへ』がamazonで発売されています。
本書は、MITビット・アンド・アトムズセンター所長の著者による「ものづくりのデジタル化」と「パーソナルファブリケーション」を解説する書籍です。
インド、ボストン、ノルウェー、ガーナなどにおいて、ものづくりとは縁のなかった人々が、自分だけが必要としているものをどんな方法で作ったのか、先進的な事例を紹介。
デジタルデータを物体に変換するための2つの手法(減産的技法、加算的技法)や、プログラミング、計測技術、通信技術など、新しいものづくりに必要な技術の解説と合わせて、パーソナルコンピュータの登場に匹敵するこのムーブメントの可能性を明らかにします。2006年、ソフトバンククリエイティブより刊行された『ものづくり革命 ── パーソナル・ファブリケーションの夜明け』を、田中浩也氏(ファブラボジャパン発起人)の監修のもと、書名および翻訳文の一部変更を行い、再刊しました。
Fab ―パーソナルコンピュータからパーソナルファブリケーションへ (Make: Japan Books)
Neil Gershenfeld 田中 浩也 





![サムネイル:book『宮脇檀の[間取り]図鑑』](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51rZ3a4al%2BL._SL160_.jpg)