中村竜治やノイズアーキテクツらが出展する「マテリアライジング展―情報と物質とそのあいだ 23名の建築家・アーティストによる思索」が東京藝術大学大学美術館で開催されます
中村竜治やノイズアーキテクツらが出展する「マテリアライジング展―情報と物質とそのあいだ 23名の建築家・アーティストによる思索」が東京藝術大学大学美術館で開催されます。会期は、2013年6月8日~6月23日。会場構成は西澤徹夫。
出展:アンズスタジオ 谷口暁彦 doubleNegatives Architecture gh/e 吉田博則 藤木淳 後藤一真+天野裕(Arup) 土岐謙次 岩岡孝太郎 kwwek(木内俊克+砂山太一) 三木優彰 マイケル・ハンスマイヤー+ベンジャミン・ディレンバーガー 増渕基 ノイズアーキテクツ N&R フォールディングス+ヘビーバックパック プロキシ・デザイン・スタジオ 今井紫緒 Source Organization Network(杉田宗+小西啓睦) スタジオゼロイチ(浜田晶則 アレックス ニゾ)+ヤックル(穴井佑樹 大山宗哉) 中村竜治 舘知宏 美濃部幸郎 慶応義塾大学SFC松川昌平研究室
現在、建築・デザイン・美術の領域において、「アルゴリズミック」や「ジェネラティブ」という言葉に代表されるような、システムをベースとした表現のあり方が注目を集めています。
構造や流体をはじめとする力学系や幾何学、印象、記憶といった不過視的なシステムを理知的に形象するこれらの手法は今日におけるデザインのプロセス、ひいてはその対象さえも変えつつあります。この背景には、コンピュータが広く普及したことに加え、レーザーカッターや3Dプリンターのようなデジタルファブリケーション技術の発展が大きく関与していることが挙げられるでしょう。
このような技術的躍進によってもたらされた変化は、作品について「考えること」から「制作すること」までをプロセスとして同じ平面上に融合し、 シームレスに連動させることを可能にしました。この制作(同時に思考)プロセスは合理性・効率性の探求のみならず、 これまでは情報として扱われていたものが素材化(プロセスそのもの自体の素材化含め)されることによって「物質としての価値を体現」し、新しい「モノ(表現)」の質感を表出させています。昨今のこうした潮流は、建築/デザイン/美術の領域を超えて、作品が作品として提示される以上の意味を示唆することになりました。それは「モノを考えること」から「モノを作ること」への一連のプロセスに対する美意識、さらにはこのような表現メディアの質感が生んだ「身体性」「日常性」の芽生えといえるでしょう。本展は、このような背景によってもたらされた文化的一潮流を、この潮流にまつわる現代の研究および作品を一様に集め、そこにみられるプロセス・質感にフォーカスして展示することで、その多様性の再確認と新しい価値の発見の場を生み出すことを目的としています。

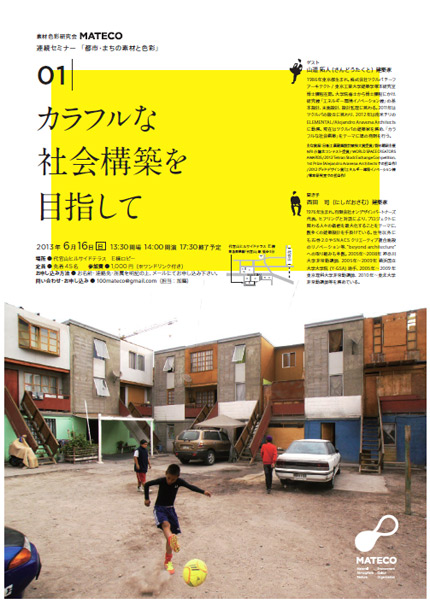

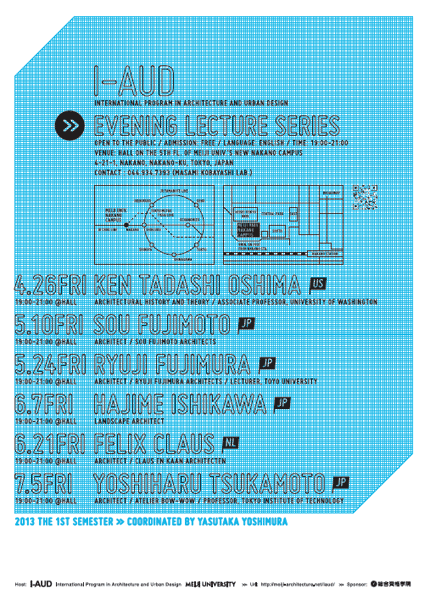
![サムネイル:アエダスのアンドリュー・ブロムバーグの講演会が京都工芸繊維大学で開催[2013/4/25]](/jp/Andrew-Bromberg.jpg)