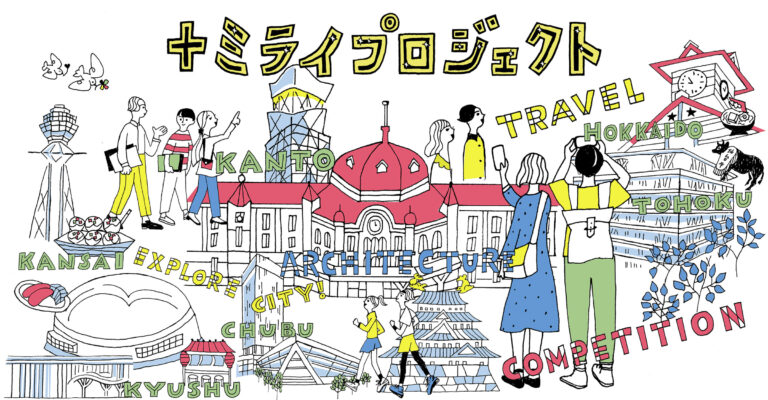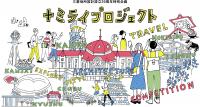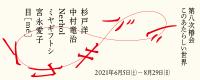写真家Gottinghamの撮影・制作マネジメント等を行う「Studio Xxingham株式会社」の、プロダクションマネジャー(正社員)募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
Studio Xxingham株式会社は、写真家Gottinghamの撮影・制作マネジメントと著作権の管理・運用を行う法人です。2021年に10期目を迎え、新たなフェーズへと前進するため商号を株式会社ゴッティンガムから変更しました。
写真家Gottinghamは、これまで美術館、博物館、行政、学会、研究開発機関、メーカー、ファッションブランド、建築設計事務所、デザイン事務所、広告代理店、出版社等との協働のもとに撮影を行ってきました。様々な分野に画像のライセンスを提供する一方で、そのプリントはコレクションへ。その協働の仕組みは、写真家Gottinghamの表現と不可分です。協働=「コラボレーション/コミッション」のあり方を提示する写真家の実践は、Studio Xxingham株式会社の活動に支えられています。
この度、Studio Xxingham株式会社は、写真家Gottinghamによるオリジナルプリントの展示機会の増加に伴い、以下の職種で正社員を募集いたします。
募集する職種は、多岐にわたる業務をサポートいただくポジションです。プロトタイピングを志向するチーム環境なので、マネジメントやレタッチの実務未経験者でも会社と個人の成長を意識しながら業務に取り組んでいただけます。美術、写真、デザインの領域境界に関心の高い方や、作家と伴走するのが好きな方、第一線の専門家たちと現場でコミュニケーションを取りたい方、感性と論理性を大切にしたい方、知識と技術を両方磨きたい方などにおすすめです。
業務内容には、写真作品に関するフレームや展示の設計なども含まれます。ですので、建築学科等でで学んだり、設計事務所等に勤務経験がある方で、写真を含むその他のクリエ―ション分野に飛び込んでみたい方も適していると思います。
Gottinghamの建築に関わる作品はこちらでも閲覧できます。
https://architecturephoto.net/tag/gottingham/皆様のご応募をお待ちしております。