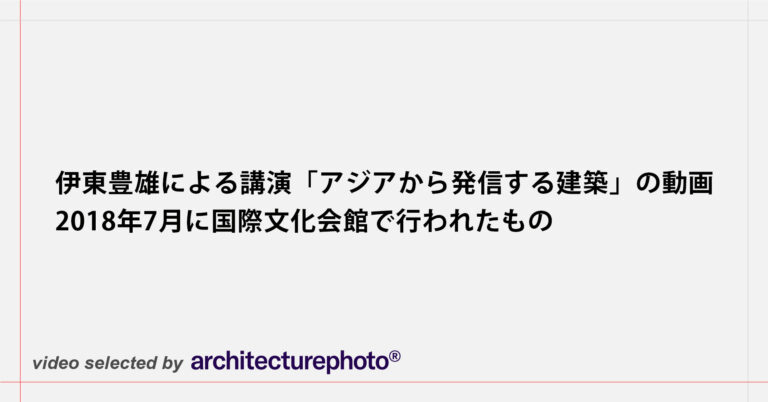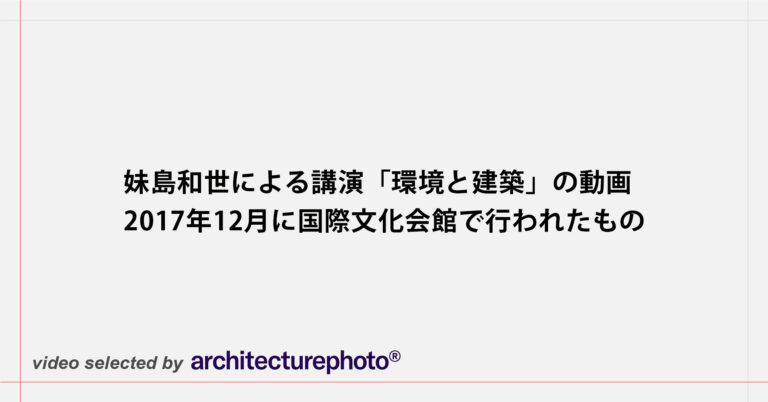ラインハウスが設計した、香港の、建築的な形態操作と大衆性を感じるテキスタイル選定の融合が特徴的なレストランの写真が12枚、dezeenに掲載されています。
remarkable archive

フォスター+パートナーズの設計でオープンした、パリのシャンゼリゼ通りのアップルストアの写真です。
坂茂がデザインする、アメリカの、蒸溜施設・ヴィジターセンター等が420エーカーの敷地に作られる「Kentucky Owl Park」の画像が8枚archdailyに掲載されています。こちらのサイトに日本語での建設計画の概要が説明されていました。
ピーター・ズントーが、建築家のユハニ・パルラスマ(Juhani Pallasmaa)と、アアルト大学で行った対話の動画です。2018年1月17日に開催されたものです。
隈研吾のウェブサイトに、高知の、図書館と福祉施設の複合建築「雲の上の図書館 / YURURIゆすはら」の写真と図面が12枚掲載されています。
高知と愛媛の県境の「雲の上の町」梼原に、図書館/福祉施設の複合体を梼原の杉を使ってたてた。体育館・こども園とが芝生広場をはさんで向かい合い、多世代の交流するコミュニティのコアが生まれた。森の中の町梼原にふさわしい、森のような空間、木漏れ日のふりそそぐ室内を、鉄と杉の混構造で実現した。フラットな床ではなく、起伏のある大地を作り、盛り上がった大地はステージともなって、トークやコンサートなどの様々なイベントに利用できる。図書館の中では皆裸足になり、杉を圧密して作った木の床のぬくもりを感じることができ、各々の気に入った場所に寝転んで、本を読むこともできる。図書館と向かい合う福祉施設では、梼原の和紙職人、ロギール・アウテンボーガルトによる梼原の木の皮を漉き込んだ和紙が多用され、あたたかく、「家のような」福祉施設が実現した。
ヘルツォーク&ド・ムーロンが設計した、ロシア・モスクワの、空から見た図式の明確さと内部空間の柔らかなデザインが印象的な「スコルコボ研究所」の写真が12枚、archdailyに掲載されています。スコルコボはロシアの郊外に存在し、「ロシアのシリコンバレー」と呼ばれ様々なスタートアップ企業が集まっている場所との事。ウェブ上にも様々な記事があるので閲覧しても面白いと思います。また同地域にデイビッド・アジャイが経営大学院を完成させていたりします。
栗原健太郎+岩月美穂 / studio velocityが設計した、愛知・美浜町の「美浜町営住宅河和団地」の写真が9枚、designboomに掲載されています。プロポーザールが行われ2014年9月にベロシティが最優秀に選ばれていました。選定当時の提案書のPDFはこちらで閲覧可能。プロポの講評やその他の最終候補者の提案書も現在でも閲覧可能です。
坂茂のウェブサイトに、長野・軽井沢の、切妻屋根を持つ有機的な平面の「ししいわハウス」の写真が11枚掲載されています。
隈研吾のサイトに、螺旋状に居住空間が作られ、そこに内部的な外部空間も盛り込まれた住宅「WOOD/PEEL」の写真が10枚掲載されています。2016年10月竣工の作品です。
高密住宅地の中に、ラセン状の居住空間を挿入した。巨大な階段のような床が、ラセン状に連続して大地と空をつなぎ、その外に、剥いたリンゴ皮のような外皮が、ぐるぐると取り巻く。外皮を構成する木のパネルと緑化パネルは、日差しや視線を和らげるスクリーンとしてリンゴを守ってくれる。
SHARE 隈研吾による、群馬・富岡市の「富岡市役所」の写真
隈研吾のウェブサイトに、群馬・富岡市の「富岡市役所」の写真が10枚掲載されています。
明治時代の日本の人の情熱を今に伝える世界遺産、富岡製糸場の街にふさわしい、ヒューマンで開かれた市庁舎を作った。鉄道の駅前、富岡製糸場へ向かう経路上にある立地を生かし、分棟型で、棟と棟の間を通り抜けできる、ストリート型の公共建築を実現した。「小さな屋根の集まり」としての分棟型建築とし、大きく張り出した庇は、日よけや雨やどりの空間としてストリートにやわらかさと躍動感を与えている。二重の勾配屋根の間に、通風・遮光の高窓をとる形式は、養蚕の街富岡に伝わる越屋根からヒントを得た。外装には、表裏で素材の異なるアルミと木をハイブリッドにしたルーバーを使用し、雁行するストリートを行き交う人々は、ファサードの多様な質感とリズムを楽しむことができる。
ターナー賞2018にノミネートされた、各種事件の空間的証拠の制作公開を行う建築系研究機関「フォレンジック・アーキテクチャー」の展示レポートが、公開されています。写真も多数掲載。執筆したのは『「物乞い」の行為をデザインする』でもネット上の注目を集めたデザインリサーチャーの木原共です。
彼らのアプローチを見ていて、過去に青木健が公開した、新国立競技場問題を議論するためのシミュレーションサイト「myscape.jp」というものがあり(弊サイトの特集ページで1500件以上のいいね!を集めるなど注目されました)、建築家が習得した技術を自身の作品とは異なる形で社会に提供する事例として近いものを感じました。フォレンジック・アーキテクチャーは、今後、建築を学んだ人たちの生き方としても示唆的な活動をしているようにも見えます。
山田誠一建築設計事務所のサイトに、静岡・富士宮市の住宅「富士南麓の家」の写真が掲載されています。サイトがリニューアルされていて過去の作品の写真も大きく見ることができるようになっています。
伊東豊雄が2018年7月に行った国際文化会館での講演「アジアから発信する建築」(モデレータ:藤村龍至・小林正美)の動画です。
妹島和世の設計で近く完成する、波打つような曲面のスラブが重なる、大阪芸術大学の新校舎の写真がtwitterに投稿されていました。こちらのPDFでCG画像・模型写真と簡易的な図面を閲覧できます。
大阪芸大アートサイエンス学科棟(妹島和世2018)
妹島先生の新作、完成が待ちきれず訪問してきました。近くまでは寄れなかったけど、目茶苦茶良いですよ✨。第一工房のブルータルな校舎群の中に一際可愛い転校生がやって来たような感じ(笑) pic.twitter.com/Jcfx5bkpY3— つーさんの休暇(バカンス) (@LL2eeJTpVkcI8Yo) 2018年11月10日