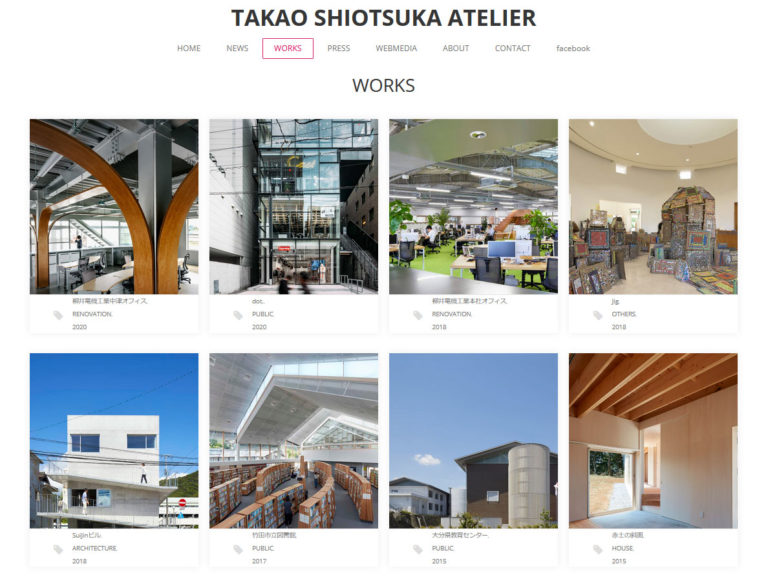SHARE 中本尋之 / FATHOMによる、広島市のヘアーサロン「créde hair’s inokuchi」




中本尋之 / FATHOMが設計した、広島市のヘアーサロン「créde hair’s inokuchi」です。
現在井口は周辺にマンションが乱立していて新たなファミリー層など新規顧客の獲得への改装としてクライアントより依頼を受けた。
建物の形状は線路と並行の方向で奥に向かう細長い空間。
人通りは多いが、ファサードが少し奥まって間口も狭いため存在感が感じられず。
既存店舗は店頭に大きな縦型の赤い箱を看板として取付ることで調和ではなく違和感として悪目立ちしていたように感じる。
この特殊な環境因子を上手く空間に落とし込む事はできないだろうかと考えた。人通りの視線は流れるような動的、人だまりの視線は踏切で待つ静的である。
この二つの視線に対応するためにファサードには二つのギミックを考えた。動的視線に対しては人工的な変化
静的視線に対しては自然的な変化が産まれるようにファサードをデザインしている。
奥に細長い空間の特性をポジティブにとらえ、それをより強調するためにエントランスから奥まで細長い道を作るプランを考えた。
その道から人々は様々なサロンの機能的な空間へと進んでいく。
以下の写真はクリックで拡大します





























以下、建築家によるテキストです。
広島市西区井口のヘアーサロン。
井口は私にとっては大学時代に通い慣れた場所でもあり、勤めてからも取引先があり車でよく通った場所である。
この場所は川と道路によって産まれた角地部分を市電とJRの線路が横断し、踏切で道路が分断される事で人だまりと車だまりが1日のうちに何度もできる特異な場所になる。
電車の運行によって毎日決まった時間に生まれる人だまり。
踏切が上がると同時に人々はそれぞれの目的地に向かうために解き放たれたように歩を進めていく。
踏切から一軒間を空いた建物の一階がcrede hairs inokuchi になる。
現在井口は周辺にマンションが乱立していて新たなファミリー層など新規顧客の獲得への改装としてクライアントより依頼を受けた。
建物の形状は線路と並行の方向で奥に向かう細長い空間。
人通りは多いが、ファサードが少し奥まって間口も狭いため存在感が感じられず。
既存店舗は店頭に大きな縦型の赤い箱を看板として取付ることで調和ではなく違和感として悪目立ちしていたように感じる。
この特殊な環境因子を上手く空間に落とし込む事はできないだろうかと考えた。
人通りの視線は流れるような動的、人だまりの視線は踏切で待つ静的である。
この二つの視線に対応するためにファサードには二つのギミックを考えた。
動的視線に対しては人工的な変化
静的視線に対しては自然的な変化が
産まれるようにファサードをデザインしている。
奥に細長い空間の特性をポジティブにとらえ、それをより強調するためにエントランスから奥まで細長い道を作るプランを考えた。
その道から人々は様々なサロンの機能的な空間へと進んでいく。
その建物の持つ空間特性と周辺環境を上手く利用する事で、既存建築物との調和をとりなが視覚のみでなく人々の五感に訴えかける事で、店舗空間全体に建築的な存在感を作ることができないか考えている。
DETAIL:
若い家族層が多いベッドタウンになりつつある井口、その顧客層を獲得するためにファミリーVIPルームを作ってはどうかと提案した。
小さい子供を持つ世帯は髪を切りに行くとなれば、子供を預けないと難しかったりする。
キッズルーム併設の個室空間を作れば 子供を遊ばせて安心して施術してもらうことができるのではないだろうか?
だだこの手のVIPルームはプライバシー確保のために奥に作りがちなのだが、長細い一直線の動線の中、奥まで歩くのは他のお客様の視線を集めてしまうことに繋がる事で、逆にプライバシーの観点上あまりよろしくないと感じ、思い切って最前面に配置した。
お客様が店内に入った時に分かるようにした方がより良いという考えももちろんある。
ここで問題になるのは視認性である。
プライベート感が強いほど空間のプライバシーも高くなってしまい。せっかくの空間も誰の目にも触れる事なく廃れてしまう・・・・
キッズルームをファサード面に配置した事によって、中を見せたい時とそうでない時など様々な状況が産まれると感じた。
そこでフレキシブルに開口の高さが変えられるように亜鉛鉄板の折れ戸のスクリーンを取り付けた。
折る位置は4段階調節可能で上に上がるほど折れ面積は細く開口は大きくなる。
キッズルームを使う時はその子の目線に合わせて開口高さを決めることが可能となり、過ごす人の気持ちによって外部との繋がりをコントロールできる事でファサードはその都度変容し、親御さんは安心と自分の為だけの空間という特別感を感じながら施術してもらう事ができる。
この折れ戸開口の変化は外部からもとても面白く見ることができ、前述の静的な視線に対する人工的なファサードの変容へと答えが繋がっていく。
ファサードの看板は以前の大きく赤い看板があった同じ位置に同じスケール感を保ちながらスケルトンフレームをつくり、そのグリッド部分にアクリル内照ボックスとグリーンディスプレイを取り込んだ。
グリーンの日々の成長が均等なグリッドフレーム越しに見える事で、動的な視線に対する自然な経年変化によるファサードの変容へと繋がらせている。
アクリルボックスにはサークライン蛍光灯を嵌め込みロゴを円形の光るライン越しに象徴的に浮かび上がらせることに成功した。
エントランス右側は外部ベンチになっていて店内奥まで続く通路に沿って待合ソファ→カウンセリングテーブル→レセプションカウンター→クローク→造作天井と段々畑のように様々な素材を組み合わせて作り上げた。
高さ方向に緩やかに機能の階段を作る事で、エントランスから続く水平的な通路に縦方向の力を与える事ができ、より通路がコンセプチャルに感じらレルように考えた。
カットブースは各壁面に二台と三台に分けて設け、躯体と空間全体で大きなアーチを形成させ、それを通路の両側に作る事で躯体を生かしながらシンプルなだけでなく解放的なブースとなっている。
カット台は間柱材で作る事で無機質な空間に少しの温もりをアクセントとし、お客様が読む本がディスプレイとしても映えるように縦おきできるように試みている。
ミラーは厚みをもたせて手鏡を収納できるようにする事で、より空間をコンパクトにソリッドに見せる事ができた。
細長い動線通路の空間コンセプトと店名にあるアクセント記号(アキュート)より派生したスラッシュのシンボルマークを壁面に取り付けて、どの視線からもロゴが視認できる事でお客様や働く人にコンセプトが意識化に浸透していくように考えている。
カットブースを抜けると左側にはシャンプースペース、その隣にヘッドスパルームを設けている。
奥のスタッフルームの扉と壁をミラーにする事で通路の終わりを反射する風景に溶け込ませる事で永続性を表現している。
踏切という閉塞感のストレスを感じながらこの場所を行き交う人々にとって、この一本の直線から産まれるサロン空間が、地域に解き放たれた一筋の光のように感じらる事で、
この場所に風穴が開いて、新たなる風が吹いてくれたらと考える。
■建築概要
名称:créde hair’s inokuchi
計画地:広島県西区
用途:ヘアーサロン
DIRECTION:榎本太一(BEAUTY GARAGE)
LOGO:オリシゲシュウジ
GREEN:大塩健三郎
FLOWER:大井愛美(Listen to Nature)
設計協力/施工:沼尾一(沼尾工芸)
竣工年:2020年7月
PHOTO:足袋井竜也(足袋井写真事務所)
| 種別 | 使用箇所 | 商品名(メーカー名) |
|---|---|---|
| 内装・床 | カットスペース床 | 100角タイル(KY TILE) |
| 内装・床 | シャンプースペース床 | |
| 内装・床 | キッズスペース床 | タイルカーペット(SANGETSU) |
| 内装・壁 | 壁 | PB+AEP |
| 内装・造作家具 | クローク | ラワンベニヤUC(扇産業) |
※企業様による建材情報についてのご意見や「PR」のご相談はこちらから
※この情報は弊サイトや設計者が建材の性能等を保証するものではありません