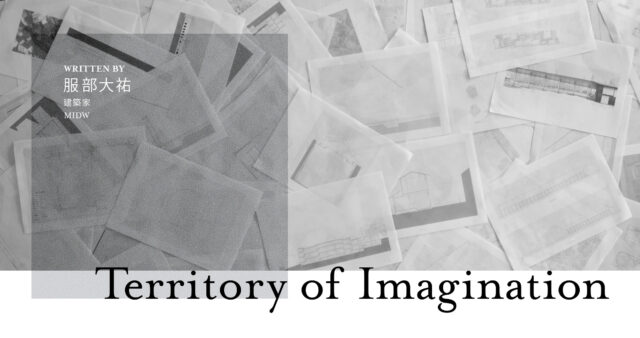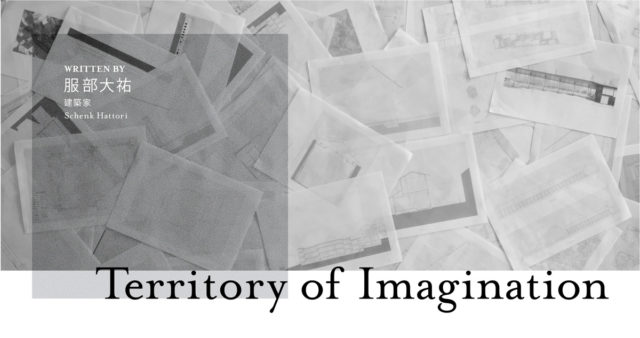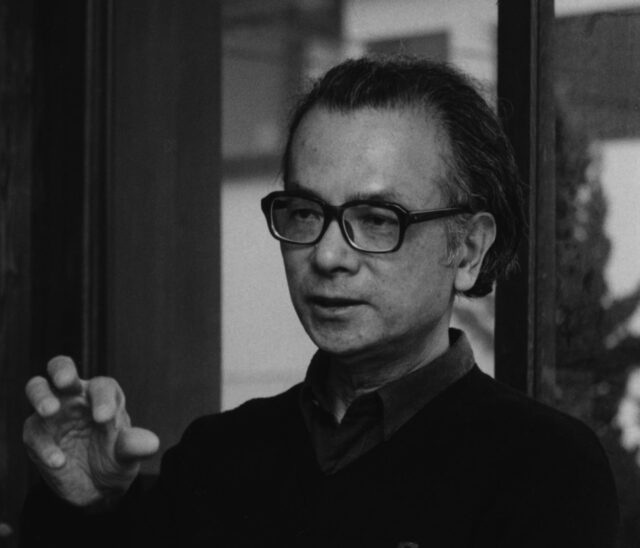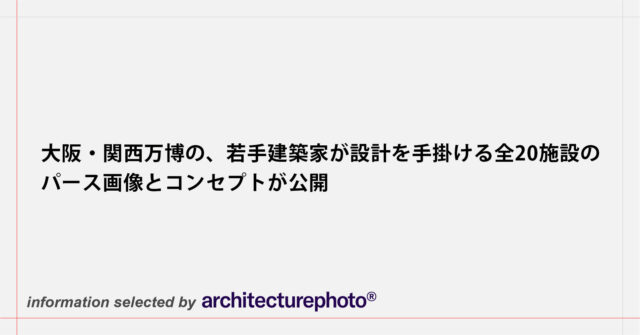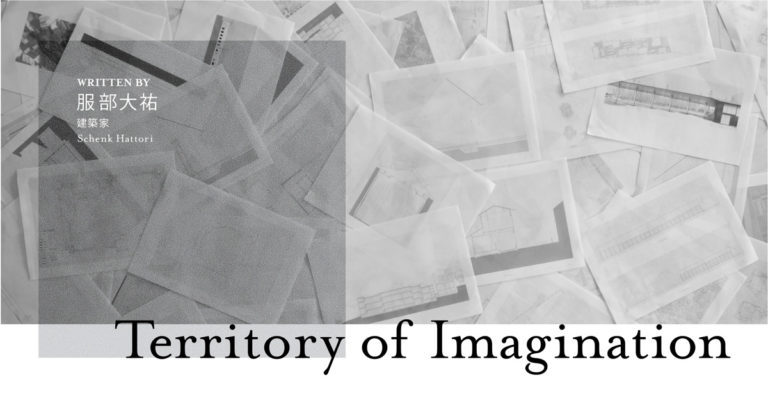
SHARE 服部大祐による連載エッセイ“Territory of Imagination” 第1回「感覚に訴えかける建築をめざして」

感覚に訴えかける建築をめざして
自己紹介 / アントワープと京都、二拠点で活動する設計事務所
大学でなんとなく始めた建築の勉強でしたが、設計課題に取り組み、色々な街や建物巡りをするうちに、自分の中で世界の見え方が拡張していくような感覚と共に、どんどん面白さや奥深さを感じるようになっていきました。その反面、アイデアコンペや学外の設計展を見るたびに、「このまま日本で勉強していたら建築が嫌いになる」という謎の危機感が大きくなり、半ば思いつきでスイスのメンドリジオという街に留学したのが2008年。
大学院の卒業といくつかの国での実務経験を経て、これまた夜更けの酔いと思いつきで設計事務所Schenk Hattoriを開設したのが2014年の春。相方のスティーブンと二人、スイスからベルギーのアントワープという街へ移りましたが、当初はなにも仕事が無いので、昼間からカフェでビールを飲みながらブラジルW杯を観る毎日でした。
いくつかのコンペに勝ち仕事もある程度増え「じゃあ日本でもやってみよう」と帰国したのが2017年の秋。
しばらく東京で過ごしたのち、今年2020年の春、京都に引っ越しました。
京都が寝静まる頃、アントワープで日中の仕事を終えた相方とビール片手にオンラインで話す、というのが事務所の日常。ある意味、このコロナ時代を何年も先取る形で、遠隔でのコラボレーションを継続してきました。(ただし二人ともアナログ人間なので、未だにzoomとか上手く使えません。)
違いを上げればキリがないですが、コンパクトなスケール感や、かつての繁栄を色濃く残す街並み、川と運河が一つのアイデンティティである点など、どことなく似ているこの二つの街を拠点に設計活動を行なっています。
以下の写真はクリックで拡大します
ふたつの試み
今回与えられた連載という機会を通して、ふたつのことを試みたいと考えています。
ひとつは、僕らのこれまでの経験を紹介すること。
僕もスティーブンも、いくつかの異なる文化圏で建築教育を受け、実務の経験を積んだのち、一緒に独立しました。それからは、ベルギーやスイス、日本での設計活動や、ベルギーやオランダ、日本での建築教育に携わっています。これだけ小規模な事務所でありながら、全く異なる文化圏で多拠点的に活動を行なっている例はさほど多くないと思います。その中で見えてきた建築文化や制度、また建築家の働き方の違いなどを紹介していきます。
ふたつ目の試みは、今までの設計活動における自分たちの価値感を言語化するということ。これまで、そのような作業をほとんど行って来ませんでしたが、この機会にある仮説を設定し、その検証・展望という流れに沿って自分たちの取り組みを書き記してみます。
これまでSchenk Hattoriとして実践してきた活動は、建築理論的なバックボーンに貫かれたものでも、特定の社会的なコンテクストに応えようとしたものでもありません。
全く異なるバックボーンを持つ僕ら二人が、外国の大学で出会い、偶然にも共通した類の興味を持っていたことから意気投合し、一緒に事務所を設立し、その興味を実社会の中で検証するための手段として、建築を作ってきました。
そうした実践を通してなんとなく見えてきたひとつの仮説を設定してみたいと思います。
それは、<「感覚に訴えかける建築」は組み立てることができる>というものです。
「感覚に訴えかける建築」というと、生々しいざらっとした手触りや、ぼんやりとした仄暗さを思い浮かべるのは自分だけではないと思います。
あるいはボッロミーニの建築のように幾何学の重複が織りなす躍動感、ル・トロネ修道院のようにストイックなマッスが持つ重厚感、ローマのパンテオンのように圧倒的な架構と光が作り出す神秘性、廃墟の持つ哀愁や物々しさ。
そこには人の手の動きによって捏ねられ作られたような作家性、あるいは長い時の経過と共に物質がもちうる物語性も関係しているかもしれません。
以下の写真はクリックで拡大します
建築を通して人の感覚に訴えかけるには、与えられた機能や用途といったクライアントやコミュニティの要望からは一見逸脱あるいは飛躍した、別の何かが必要になると思います。
ただ、そういったものは現代の建築を語る際の、いわゆる「コンセプト」の中には登場する機会が与えられなかったり、場合によっては、余計なものとして否定的に受け止められることすらあるように思います。
もちろん、ここで挙げたいくつかの例は、過去のそれぞれの時代、それぞれ特殊な背景の元で作られた建築たちだから、単純に同じ土俵で現代の建築と比較することはあまり意味がないかもしれません。
過去の名建築が生まれた時代とは建築を取り巻くコンテクストが違うと言ってしまえばそれまでだけど、それを重々承知の上で、コストやスケジュール、機能や用途といった与件と向き合いながら、いかにして過去の名作に近付くか、という問題は、過去の名作に心動かされ、この時代に建築を志す一人として、真正面から向き合うに値する命題だと思っています。
だからこそ今回検証してみたいと思うのは、現代に合った方法で、リーズナブルに、システマティックに、ドライに、それでいて感覚に訴える建築を作る方法はないか?ということです。
「組み立てる」にはそういったニュアンスが込められています。
Territory of Imagination
この連載のタイトルを「Territory of Imagination」としました。
直訳すると「想像の領域」ということですが、とりわけ人の想像力の背後にある「意識と無意識の中間領域」がいかに僕らの知覚や感情、あるいは情念といったものに影響を及ぼしているか、というようなことに興味を持っています。
モノの持つ状態について言えば、コンセプトダイアグラムがそのまま立ち現れたような隙のないロジックが生み出す明快さよりも、視点の置き所によって多義的な読み取りが可能だったり、状態が移り変わったり、答えが一つでは無いような曖昧さに強く惹かれます。
無意識は捉えられないからこそ無意識と呼ばれるわけですが、建築設計においても少しでもそこに近づいていくように自分の意識の領域を押し広げていくことが、そういった捉えどころのない豊かさを生み出す鍵ではないかと思っています。そういう意味を込めて「Imagination」という言葉を使っています。
これから複数回に渡って連載をしていく予定ですが、初回では僕らがこれまでいくつかの大学で受け持ったスタジオ(設計課題)について書きたいと思います。
Studio “Being blue might not be exactly a matter of looking blue”
ベルギーやオランダでは、若い講師陣にかなりの自由度を持たせて自分たちのスタジオをオーガナイズさせる、という雰囲気があるように思います。
例えば、教授陣にローカルの建築家が多いアントワープ大学では、国外で活動する建築家やアーティストを講師に招き、学部3年生と大学院生向け(あっちの学校は学部3年、大学院2年の5年制)の一週間集中ワークショップを毎年春に行っています。
このワークショップでは、ローカルの担当教授が設定した抽象度の高いテーマに基づいて招かれた講師が自由にスタジオ課題を設定し、10人程度の学生と一緒にワークショップを行います。そして、最終日には全スタジオの成果物を学内で一般展示するという形式を取っています。
僕らが最初にこのワークショップに呼ばれたのは2014年。ちょうどスイスからアントワープに移る頃でしたが、スティーブンの恩師で当時もアントワープ大学の教授だったクリスチャン・キーケンスが担当教授だったこともあり、声を掛けて貰いました。(ちなみに、このクリスチャンという建築家は、ゲントのセントルーカスで建築を学んだ後、若い頃からベルギー建築界の第一線で活躍する傍、教育にも非常に熱心で、長くアントワープ大学で教鞭を執っていました。僕らのこともとても気にかけてくれ、度々一緒にプロジェクトに関わる機会もあり非常にお世話になっていたのですが、残念ながら先日他界されました。)
クリスチャンが設定したテーマは ”Absence”( 存在を意味する ”Presence” の対義語)。
それについて二人で議論していた中で、質量を伴わず自身の根拠を限りなく周囲の物質に依存している一方で、僕らがその現象を当然のように認識しているモノ、つまりはモノに投影される光やモノに対しての影なんかはAbsentなのかPresentなのか、という話になりました。「他の何かに依存することなく、それ自体としてあること」をPresenceだとするならば、光や影はAbsentであるように思えるし、「現象として人の意識に映じているものや人が経験している内容」をPresenceだとすると、一転して影や光はPresentであるように思えてきます。
ただ、少なくとも僕らにとってはその定義を見つける作業よりも、そのどちらでもあってどちらでもないような、視点一つで在り方がひっくり返るような曖昧なモノについて考えること自体が面白いということで、スタジオ名を「Studio “Being blue might not be exactly a matter of looking blue”(青いということが必ずしも青く映ることとは限らない)」とし、学生たちにはロウソクを制作し、それを燃やす炎によって映し出されるロウソク自体の影を最終成果物として設計することを求めました。
以下の写真はクリックで拡大します
本来は光源と実体があり、影はそれに従属するものだと思います。あるいはその関係を逆転させたもの、例えば日時計なんかのように光源と実体、投影面の距離や位置関係を調整することで必要な影を得ることは容易に可能ですが、光源(炎)と実体(ロウソク)が一体であるという強い制約の中で影を主題にした場合に、どういった意味を持つ影を設計出来るのか、その時出来上がるワックスはどんな形をしているのか、ということに興味がありました。
ある学生チームは、「炎のゆらぎはどこか永久性を感じさせるが、実際には着実に終わりに向かっている。炎自体からは感じ取ることができないその始まりから終わりまでの時間の蓄積を影によって表現出来ないか。」ということを考え、“Time” をテーマに課題に取り組みました。
彼らが作ったのは正三角形(最も辺数の少ない多角形)平面に、重心から少しだけ一辺に寄せた芯を埋め込んだ柱形状のロウソク。
火を付けると時間の経過とともにその一辺には炎による谷が形作られます。谷は徐々に深さを増してゆき、谷底を燃え進む炎は、正対する壁面に一筋の光を抱いた二本の垂直な影を映し出します。絶えず揺れ動く炎が抉り出す複雑な形状の谷は、それまでの時間の蓄積を表す影へと翻訳されて壁面に立ち現れ、流れ出たロウは少しずつ柱の足元に溜まってゆきます。
また、作業工程で一度に溶かせるロウの量に限りがあったため、三角柱の側面には複数回に分けて流し込まれたロウが、柱の外観に層状の紋様となって現れていました。
以下の写真はクリックで拡大します



アントワープ大学ではこの他にも別の年に課題を出しました。それは、紙素材のみで作った模型を撮影し、使用する紙の選定・光源やカメラ位置の操作により、模型写真だからこそ可能な現実では起こり得ない空間・現象を作り出し(ただし撮影後の写真加工はNG)、特大サイズで出力して展示する、というものでした。
頭では自分たちで作った模型による欺瞞の空間・現象だと認識しながらも、目の前に置かれた特大サイズの写真が持つ確からしさとの対面を通して、自身の知覚の働きが如何に繊細かつ曖昧であるかを注意深く観察する、というようなことを意図していました。
以下の写真はクリックで拡大します



Studio “The imaginary”
続いてのスタジオは2016年秋学期にロッテルダム建築アカデミーの大学院で社会人学生を対象に行ったものです。
ここの学生は主に製図技師としての教育を受けた後、大半が設計事務所に勤務しながら「建築設計の理念について学び、ゆくゆくは設計者としても働きたい」というモチベーションで職場のサポートを得て通っているだけあって、とてもアグレッシブだったように思います(そもそもオランダの学生が元気だというのはよく聞く話ですが)。
学生の大半が技師として働いているため、学長からは「tectonはひとまず置いておき、archeにフォーカスした内容のスタジオをやって欲しい」と言われていました。要するに、技術的なことはさておき、設計におけるアイデアの生み出し方や、そのために必要とされるモノの見方といった根本的かつ最も重要なことについて考えるきっかけを学生に与えて欲しい、というような事だったかと思います。
アントワープのワークショップでは火を使ったせいで警備員に何度も怒られたので(学校からは何も言われなかったのがむしろ不思議。)、今回はもっと安全な素材にしようということで液体を使ったスタジオとしました。
学生たちにはある状態の液体(水・アルコール・液化アンモニアなど)を選ばせ、観察を通してその液体の持つ特性を最も端的に表現する容器を設計することを求めました。
「Studio “The imaginary”」というタイトルのこのスタジオでは、普段特に気にも留めない身近なモノでも注意深く観察する事で見え方が全く違ってくることもあり得るし、世界に対する独自の視点を獲得することが設計者としての第一歩なんじゃないかということを学生と共有したいと考えました。
ある学生は、小さい頃から家族で毎年訪れている湖の水面が常に揺れ動いている様子と、いつか飛行機の窓から見たある湖の水面のまるで時が止まったかのような表情から、水面の持つ静と動の二面性に興味を持っていました。そして、コップの水を小さなスケールの水面と見立て観察したところ、コップの縁では表面張力により水平に見える水面にも起伏があることに気がつきました。
その表面張力にヒントを得て設計された容器には、着色された水による黒い湖が、スポイトのわずか一滴でその均衡があっという間に崩れ去る危うさと緊張感を持って、静と動の両面を同時に表現しています。
以下の写真はクリックで拡大します



始まりの作業
これらいずれのスタジオも、敷地やクライアント・プログラムといった具体的な外的要因に注意を払いながら建物を設計するオーソドックスな設計スタジオの形式を取らず、敢えて与条件を極力シンプルにして抽象度を上げた課題を設定するという共通点があります。そうすることで、学生が自身の思考や感覚のみを頼りに核(コア)になるアイデアを見つけることと、それを極力素直にモノや形に翻訳していくことのみに集中出来るよう意図しています。
その上で、学生には対象とするモノ(ロウソク・炎・影、紙、液体)の立ち現れ方とそれに対して生じる自身の感覚や感情の動きを注意深く具に観察するようにと伝えています。その過程で捉えた発見や驚きは、先に触れた「意識と無意識の中間の領域」に踏み込むための第一歩になると思うし、そしてそれは「感覚に訴えかける建築」を組み立てていく上で欠かせない作業なのでは無いかと思っています。
服部大祐
1985年 横浜生まれ。2008年 慶應義塾大学環境情報学部, 神奈川 – 学部卒業。2012年 Accademia di Architettura, Mendrisio (CH) – 修士課程修了。2014年 Schenk Hattori, Antwerp (BE) / 京都 – 共同主宰。2014-15年 University Antwerp (BE) – ワークショップ講師。2016-17年 Academie van Bouwkunst, Rotterdam (NL) – 非常勤講師。2019年- 慶應義塾大学環境情報学部, 神奈川 – 非常勤講師。