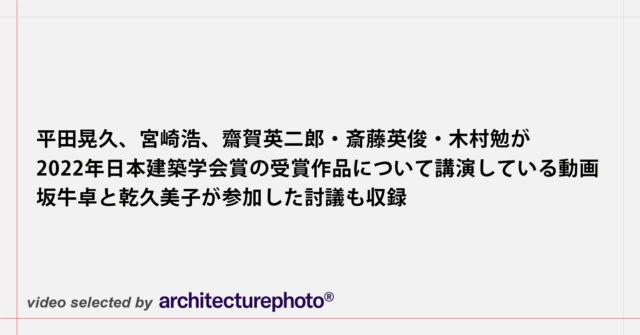SHARE 坂牛卓とエンリク・マシップ=ボッシュの対話「建築、都市、理論」と、坂牛卓のモノグラフ『Taku Sakaushi. Unfolding architecture』プレビュー

坂牛卓とエンリク・マシップ=ボッシュ(ENRIC MASSIP-BOSCH)の対話「建築、都市、理論」を掲載、坂牛卓のモノグラフ『Taku Sakaushi. Unfolding architecture』をプレビューします。
エンリクはスペインの建築家で東工大への留学時代に篠原一男を研究していた経験もあります。
この対話の日本語版は、坂牛のモノグラフに収録しきれなかったもので、許可を得てアーキテクチャーフォトで特別に公開するものです。この書籍はGA gallery BOOKSHOPなどでも販売されています。
建築、都市、理論:坂牛卓とエンリク・マシップ=ボッシュの対話
エンリク・マシップ=ボッシュ(以下、エンリク):あなたの作品からは様々な方向性が見て取れます。明確な理論、社会に対する認識、そして建築の自律性など、一見お互いに矛盾した要素が糸となって織り上げられ作品となっています。最終的にどのような模様のタペストリーが織り上がるのかは分からないし、もしかしたら最終的な模様は永遠に出来上がらないかもしれません。この不確実性というか予測不能性があなたの建築を魅力的なものにしているのだと思います。あなたの作品の中には分かりやすいメッセージや形式論は見えませんが、それでもある種の統一感が感じられます。対話を始めるにあたり、このように様々な方向性が存在する中で、まずはあなたの仕事のベースにある理論的なアプローチについての熱い思いを語っていただきたいと思います。私が聞きたいのは、このモノグラフ作成に当たって指針となった理論的概念が、作品の構想が出来上がってから形成されたものなのか、そうではなくて作品の設計における前提条件だったのかということです。
坂牛卓(以下、坂牛):作品の方向性については、仕事を始める前に既にあったアイデアが元になりそれらが何らかの形で表出したものであったり、作品を制作した後で気づいたことや「発見」したことから発展したものであったりします。建築の理論的フレームワークとは常に言葉では表現できないものを起点としており、先験的なものと経験に基づいたものとのフュージョンのようなものであるというのが私の考えです。
エンリク:建築に対するアプローチについて説明した本を何冊か書いていらっしゃいますね。それらを「理論」と呼ぶことにしましょう。最近『建築の設計力』を出版されましたが、建築における理論の必要性を正当化しているように読み取れます。多くの日本人建築家が理論的概念を提示して来ましたが、その意義について、そして特にそうすることの必要性についてどう考えたらよいのか私はずっと考え答えに行き着いていません。なぜあなたにとって理論は大切なのでしょうか?そして一般的に日本人建築家が理論を重視するのはなぜだと思いますか?
坂牛:そうですね、私の場合はこれまでに受けてきた教育への反動でもあり成果でもあります。私は1980年代に日本で建築を学びました。当時の建築家は、教えることが本職ではない一種の芸術家のような存在であるか、あるいは自分の作品だけを見せながら教える大学教授のどちらかであり、建築をどのように考えたらよいのかということは真剣に教えませんでした。学生に対して、ひたすら「言われた通りにしろ」「自分が見せた建築作品から学べ」とだけ言っていました。建築に必要な知的なプロセスが欠けていたのです。
エンリク:しかし、例えば篠原一男はどうだったのでしょうか?
坂牛:篠原は言葉をとても大切にし、著作を多く残しましたが、彼が残した言葉を理論と呼べるかどうかはわかりません。彼の文章はどちらかというと詩のようなものでしたから。とはいえ、自分が知っている手法しか教えないような建築家たちとは明らかに違う存在でした。優秀な建築家はいましたが、篠原と比べれば彼らはただの専門家に過ぎません。私が思うに、その当時理論を重視していた建築家は篠原一男と磯崎新の二人だけで、たまたま私は東京工業大学で篠原の教えを受けました。私は建築とは一つの理論であると思っていたので、篠原と磯崎を追随すべきモデルとしたのです。私はその後UCLAに行きチャールズ・ムーアの指導の下で修士論文を書き上げました。
エンリク:そうでした、あなたのように理論や教育が作品に与える影響を重視する建築家のもう一つの例ですね。現代の日本建築家の間で、理論へのこだわりはまだ普通に見られるのでしょうか?
坂牛:こだわりが普通に見られるかと言えばそうは言えませんが、私が例外かというとそういうわけでもありません。
エンリク:坂本一成は、彼がまだ若かりし教授時代にあなたも教わり、その後東工大で篠原の後を継ぎましたが、彼も自分の作風に対して理論づけを行っています。しかし、そのようにする建築がその他大勢いるというわけではありませんね、日本であれ他の国であれ。
坂牛:これは篠原の師匠である清家清が1950年代に始めたと思うのですが、それ以来の東工大の伝統のようなもので、今でも続いています。
エンリク:あなたの近著の中で、建築作品の多くにはパトスとロゴスという二つの要素が存在している、あるいは存在していなければならないと述べています。パトスとは口では言い表せないもの、言葉では語れないものであり、一方ロゴスとは言葉で語るしかないものではあるが、それで形を作ることはできない。もしもロゴスだけで形を作ろうとしたら、一巻の終わり。そこには命が吹き込まれない。そうですね?
坂牛:その通り。
エンリク:つまり、有意義な建築作品を作るにはその二つを結び付ける必要があると。これは、設計プロセスに関する明確な思想のように思われます。この本の中では哲学者の小川仁志の著作も紹介し、建築との関連性に言及しています。彼は「感情」、「物」、「技術」そして「共同性」を語っているということですが、それらがあなたの作品に与えた影響についてお話下さい。
坂牛:ご存じの通り私は哲学書を読むのが好きなのですが、あなたが述べた彼の四つのコンセプトからインスピレーションを得ています。彼は若い哲学者として、世界の現代哲学に関する議論の中に身を置いています。彼は『哲学の最新キーワードを読む―「私」と社会をつなぐ知』という短い著作の中において、現代哲学におけるこれらの四つの中心的概念について語っています。私は、この四つは建築にとっても非常に重要なコンセプトであると思います。
エンリク:この「感情(emotion)」というコンセプトはとても興味深いですね。なぜなら、ご存じのようにそれは私にとって、篠原の作品も含め、建築の中心的概念だからです。篠原自身はこの言葉を使うことはほとんどありませんでしたが。小川氏がどの漢字を使って自分の考えを表現しているのか知りたいですね。西欧の言語ではemotionという言葉はラテン語の「動かす(moving)」から来ています。あなたを「動かす」、あなたが「動かされる」ということです。
坂牛:emotionの日本語表現について説明しましょう。emotionに相当する日本語として、「情動(jōdō)」という言葉があります。「情(jō)」が「心」、「動(dō)」が「動かす」ということであり、ラテン語ととても似た感覚で、私はこのような意味で使っています。あなたがさっき言った通りです。しかし実際には小川氏は「感情(kanjō)」という言葉を使いました。「情(jō)」は同じですが、「感(kan)」はどちらかというと「直観(perception)」という意味です。ですから、「感情(kanjō)」は「感覚(sense)」、「感じ(sensation)」、「気持ち(feeling)」といったような意味になります。私が「情動(jōdō)」を使うのは、信原幸弘という哲学者が書いた『情動の哲学入門―価値・道徳・生きる意味』という素晴らしい本からインスピレーションを受けたのですが、その中で彼が使っているからです。私はこの二つをごちゃ混ぜにして使っています。
エンリク:これらの言葉は全く別々ということはなく、かなり重なる部分がありますね。そして小川氏の「物」という概念ですが、これはあなたが数年前に提起した「物と間」の概念と同じでしょうか?この二つの基本的概念から後に「流れ」の概念に導かれていったのでしょうか?
坂牛:そうですね、小川氏は当然「物」を一般的な概念として使っています。イマヌエル・カントの認識論の批判のようなものですね。カントは、我々は物自体、空間自体、あるいは時間自体を認識することができないと考えました。しかし現代においてこの考え方に反論する多くの哲学者がいます。小川氏もその一人です。
エンリク:なるほど、こういった批判が日本で起こっても不思議ではないですね。なぜならカントは観念主義の先駆者であり、日本の伝統というのは反観念主義的だからです。私が言いたいのは、日本の神を考えた時に、それは日本の神道の伝統においては「物」ですよね?樹木が神様になることがあり、岩も、そして山も。精霊が「物」に宿る。このような考え方が形ある物への賛美にある程度つながっていくのではないでしょうか?
坂牛:これに沿った議論が今まさに行われています。私が最近参加した討論会において、歴史家の加藤耕一氏が、モダニズム建築においては自律的なモノが主張されていたが、ポストモダニズム以降の建築においては優先事項が変わったのだと言っています。現代の日本において、建築は社会問題のある種の産物であり、ソリューションであるという見方がありますが、私は建築を理解するためにはこのような二元的なものの見方をするべきではないと考えています。私は、二つの極について同時に考慮すべきだと述べました。さもなければ建築家が建築物を作ることは出来ません。ですから、私は建築において自律的(物的)な側面と他律的(社会的)な側面の両方を見るようにしています。こういった見方をすれば建築が簡単に成り立つかと言えばそういうわけではありませんが、デザインにおいて両立している必要があります。それは今私がやろうとしていることです。
エンリク:このような明らかに理論性を指向する論議が学生たちにどう受けとめられていると思いますか?彼らはしっかりとこれらの議論に付いてきているのか、それとも専門家の領域で行われている議論については疎いのでしょうか?
坂牛:私が教えている東京理科大学における建築教育は、社会的な議論や最近取り上げられている様々な社会問題の影響を大きく受けていると言って良いと思います。学生たちは2年生以降設計製図を学び、様々な規模の設計を行い、社会的視点を持ちながら徐々に都市デザインの作業を始めていきます。そして後に、例えば地方の町にその地域との関連性を持ったデザインの公共施設を設計したりするようになるのです。
エンリク:そうなんですか!しかしこういった社会的アプローチが日本の大学の建築学科で普通に行われているとは言えないのでは...
坂牛:最近では一般的になってきましたし、理科大では全く普通のことです。ただ、こういったやり方は建築的ないしは理論的な観点からではなく、むしろ社会学的見地、つまりダイアグラムを描いたり統計を取ったりするところから発展したのです。私の研究室においては、都市批判や建築学を教えると同時に私が「公共性(publicness)」と呼ぶテーマに焦点を当てています。そうすることによって、純粋な建築を設計するのではなく、建築デザインの考え方そのものを中心にすえた都市デザインを学生たちに考えさせるようにしています。
エンリク:一般的に言って学生たちは建築が一定の自律性を持つことについて興味を持っていると思いますか?
坂牛:恐らくそうだと思います。ですから、色々な社会問題をどうにかしなければということだけだとやってられないという学生も私の研究室に来ます(笑)。
エンリク:私が教えるバルセロナ工科大学(Escola del Vallès-BarcelonaTECH)は、長年にわたって社会問題や環境問題に力を入れて来ました。
坂牛:あなたの大学だけではありません。私はウィーン工科大学で短期間教えたことが有りますが、やはり同じようにサステナビリティを中心とした問題に力を入れています。ただ、そうすることに少し疲れてきたのかなとも感じています。
エンリク:確かに、このようなプロジェクトには独自のやり方があるようです。プロジェクトは一般に公開されたり、市民と議論を行ったり、他の専門家を招き入れたりすることもあるのですが、こういった複雑な要素をまとめ一つの整合性のとれた結論を出さないわけにはいきません。こう見ていくと、「共同性(community)」という考え方、そして日本の都市、特に東京の現実ということに突き当たります。公共空間が次々に私有化され、東京で見つけることができる公共空間はほとんど建物の中だけになり、しかも監視カメラ付きです。そこはコントロールされた空間です。このコントロールという考え方は、民主主義そして思想の自由の発展にとって死活的な問題です。建築家の間で、あるいは大学において、まさに今東京がどう変化しているかについて議論されているのでしょうか?
坂牛:そうですね、特に東京についてということはないと思います。ただ、より小規模な都市においてそのような意識が育ちつつありますね。私の研究室は、富士吉田市における幾つかのプロジェクトに参加しています。
エンリク:そうですね、社会性を意識したプロジェクトです。
坂牛:その通りです。私たちは、実際に建物を作りながら、自治体当局の指導の下教授陣と学生たち双方が一体となって都市の様相を一変させようと取り組んでいます。このプロジェクトの基本は、空き家となった住居、閉鎖された工場、閉店したレストランのような使われなくなった建物の改装です。地元の自治体側は当初私たちに対してこれらの建物の新しい使い方(プログラム)を提案するよう要請しました。それに対して私たちが行ったのは、基本的にこれらの建物を周囲と一体化させ公共性を高めることでした。
エンリク:それは東京で起こっていることとまさに正反対の方向を向いていますね。それこそが、あなたのプロジェクトを日本における今の大きな流れとは全く違うものにしている要素の一つだと言えます。
坂牛:富士吉田市における私たちのクライアントは、市ないしはその関連の非営利団体です。そのために、無料のギャラリーやコワーキングスペースなど社会的課題を強く意識したプログラムをより多く提案し、建物の内部に公共性を創り出すことができたのです。こういったケースにおいて、「流れ(flow)」や「フレーム(frame)」といったコンセプトは、建物の中に人を呼び込むのに非常に効果的です。
エンリク:これらのケースではあなたの「流れ(flow)」のコンセプトは当然重要になってきますね。内側と外側の間の流れ、建物と街の間の流れ。
坂牛:それが、富士吉田における私たちの作品が持つ他律的側面、あるいは私の建築の社会性であると言っても良いのですが、それは「流れ(flow)」という考え方に支えられたものです。一方、私は設計を始める時に、自律的な空間についても考えを巡らせます。社会的課題を考察することはプログラムの考案に当たって非常に重要ですが、建築の自律的な一面を考えることは、空間そのものを設計する際にはとても大切であると言えます。私は、この二つの考え方をつなぎ合わせて一つにしたいと思っています。
エンリク:しかし、建築にとってプログラムはそんなに大切なものでしょうか?
坂牛:そう思います。私の自宅「坂牛ハウス」には、私が「アルファスペース」と呼ぶ空間が地下にあります。「アルファスペース」はその空間のプログラムの名前であり、家族だけではなく誰でも使えるスペースのことです。靴を履いたまま入って行っても構いません。日本では極めて珍しいことですが。
エンリク:それは家の前の通り、あるいは公共空間の一部、ということでしょうか。
坂牛:その通りです。この家を建てるにあたり、「アルファスペース」は妻の祐子と私が最重要視したプログラムなのです。ただし、「アルファスペース」の形状や広さはプログラムそのものとは関係ありません。それはいわば自律した空間を指すものです。
エンリク:私がこういうことを言うのは、プログラムは建築にとって重要なのだろうかと常に疑念を抱いているからです。プログラムは時間と共に変化するかもしれないが建築物はそのまま残るという意味において、今私はプログラムを伴わない建築に注目しています。建物は存続するものだというこの考え方は日本的ではないですよね?しかし、日本においても建物にはそれぞれの寿命があって、ある世代が建てた建物を次の世代が使うこともあるのです。ある意味頑丈でなければならず、あるいは建物としての特色を変えることなく違った使用法を受け容れることができなければなりません。プログラムは建築の出発点であるともいえますが、建物はプログラムを超えて生き残るものです。プログラムは暫定的要因に過ぎないという考えについてあなたにも分かっていただけるかどうかを知りたいですね。
坂牛:はい、良く分かっています。私は、プログラムとは建築について考え始めようとする時に一時的に使う仕掛けだと思っています。
エンリク:最近のサステナビリティに関する議論の中で、建物を壊さずに再利用するということが重要なテーマの一つとなっていますが、これは富士吉田市の空きビルを使ったプロジェクトにおいてあなたの研究室が既に行っていることですね。
坂牛:はい。製氷倉庫をギャラリーに転用したのがその一例です。建物を社会的な目的で使用するために、建物の中に人々を招き入れることができるようにし、その空間を公共空間に仕立て上げました。もちろんギャラリーとしてどのくらい長く使えるのかは誰も分かりません。もしかしたら1年しか続かないかもしれない。それでもかまいません。そうなったら、今度はレストランにしたり、あるいは学校にしたり、何にでもできるのです。大事なのは、建物あるいは空間があること、そしてそれがどのように都市と繋がっているかということであり、そのためにこの空間を自律的な存在にして様々な使い方ができるようとても気を使いながら設計したのです。このプロジェクトにおいては、「流れ(flow)」は自律的空間のコンセプトにもなっていると言えるでしょう。
エンリク:あなた方は、富士吉田において都市改造の可能性に関するあなたのビジョンを政治家と共有し信頼を獲得したわけですが、これは極めて稀な経験だと思います。人々の自由な活動を建築家が後押しする、そのようなことが再びできるようになると思いますか?社会の中で、建築家そして建築そのものに未来はあると思いますか?
坂牛:建築家は、建築を通じて、あるいは都市デザインを通じて何かできると思っています。
エンリク:あなたは建築の力を信じていますが、私たちには、人々の間に議論を盛り上げていくために献身的に政治的な動きができる人も必要です。そのためにはどうすればよいでしょうか?例えば1960年代、丹下健三の存在は非常に大きな影響力を持っていました。20~30年前にはバルセロナでも同じような状況でした。今はどうでしょうか?
坂牛:1868年に日本が近代化を始めた時、建築家という新しい職業が発生しました。英国人のジョサイア・コンドルが1877年に10名ほどの学生たちに建築学を教え始めましたが、彼らは全員上流階級に属していました。時間を経て学生の数は増えていきましたが、建築家になれるのは上流階級の者だけという状況が続きました。丹下も前川もそうです。こういった人たちは皆最初から政府上層部との繋がりを持っていたので、決裁権者も彼らが言うことに耳を傾けたのです。さて、例えば妹島さんのことを考えた時、彼女に同じようなことができるかというと昔と状況は同じではないでしょう。加えて、今の時代、建築家の数があまりにも多すぎます。
エンリク:恐らく社会的階級の問題だけではなく、政治家が建築や公共空間に対して払う関心の程度の問題だと思います。今は世界中が凡庸化していて、政治家はこれらのことに見向きもせず、ほとんどのことを民間企業にやりたいようにやらせている状況です。あなたたちは富士吉田市を動かした。限定的とはいえ、貴重な経験だと思います。
坂牛:今は東京のような大都市の役所を動かすのは極めて困難です。特に東京の場合、多くの国の一国の人口や予算を上回っていますからね。しかしながら富士吉田のような地方都市ならやり易いと思います。
エンリク:どういう経緯で富士吉田市の改造プロジェクトにかかわるようになったのでしょうか?
坂牛:富士吉田市との出会いは全くの偶然でした。5、6年前に私たちは富士吉田市にある製氷工場の改装という小規模プロジェクトのコンペに勝ちました。市の方々は最終的な建築物を見てとても喜んでくれました。そこから、彼らのこだわりに対する理解が深まっていったのです。私たちが普段お付き合いしていたのは市の所属機関であるNPOで、市の改造に取り組んでいました。そのうちの何名かは富士吉田市からの出向者なので、市との関係は非常に緊密でした。さらに私のスタッフの一人が建築の専門家として事務所とNPOを兼務していました。彼らは私たちの作業を信頼してくれるので、市ともとても良い関係を築くことができたのです。ただ、私は彼らに対して、建築物が重要であるということを証明しなければなりませんでした。製氷工場のオープニングセレモニーにおけるスピーチで、富士吉田市長がこう言いました。製氷工場のような役に立ちそうもない場所を改装しても何も変わらないだろうと思っていた、と。
エンリク:しかし彼は光明を見た!
坂牛:こんなことが出来るんだということを目の前にして、本当に驚いたのです。そして、建築が街を美しくし、意味を与えてくれるものであることが分かった、と言っていました。建築には人を惹きつける力がある。これはとても大切なことです。プロジェクトに着手した時、私は魅力的なフォルムを作ることにあまり関心を払いませんでしたが、結果的に見てそれはある程度重要なことでした。それだからこそ、富士吉田市の市長や市役所の方々の信頼を勝ち取ることができた、というのが実情なのです。もちろん、富士吉田市の体制が東京よりもはるかにシンプルだったということもあります。そして最近、実際には新型コロナウイルス感染症が流行する前から観察されていることですが、感染症がもたらした状況の変化もあり、人々が大切だと思うことに興味深い変化が見られるようになりました。地方は東京よりももっと豊かになっていかなければならないと人々が考えるようになったのです。ご存じのように、東京の人口は高止まりしていますが、その理由は地方からの流入人口が依然として大きいからです。しかし彼らは東京に出たいと心から思っている訳ではなく、特定の仕事が東京にしかないため必要にせまられて出てきているのです。もしも自分が住んでいる地方で仕事が見つかるのであれば、彼らがそこを離れることはないでしょう。そこでの生活はより豊かになり、それが地域全体に及んで行くことになります。近頃大企業の中で本社を東京の都心部から北海道、四国、淡路島などに移すところが出て来ました。淡路島は瀬戸内海にある大きな島で、安藤忠雄の有名な作品が沢山ある所です。これらの企業は環境が良い場所を求めていました。会社の本社が移転すれば、社員も引っ越さなければならないですよね。だから、移転先は魅力的な場所でなくてはならない。気候も良くなければならない。東京を離れてもいいと思っている会社員は大勢います。ということは、建築が持つ変革力を発揮する場は、もはや大都市を中心とした巨大で高額なプロジェクトではなく、地方の現状を理解し、既存の建築物を可能な限り再利用し、それを外部に開放し、建物の内部に共同体の流れを引き込んでいくことにあるのだと思います。
坂牛卓のモノグラフ『Taku Sakaushi. Unfolding architecture』プレビュー
以下の写真はクリックで拡大します






Taku Sakaushi is increasingly becoming a reference point when talking seriously about new interests in Japanese architecture, be it social consciousness, reuse of buildings, or ecology. One of the qualities of his architecture derives from this interest in the public aspect of architecture.
His buildings always recognize an outside to relate to, consciously, and some of his projects are based precisely in this sort of connection. This is not quite as common in the Japanese context as it may sound. Two other qualities are a basso continuo running throughout his works.
This monograph collects 20 years in the career of this Japanese architect. 264 pages of works and reflections, photographs, plans and details, and with texts by Enric Massip, David Stewart, Shunsuke Kuwahara, Diego Grass, Manabu Chiba and Shinichi Takiguchi.
264Pages
Spanish, English
23×29,5cm
Soft cover
ISBN:978-84-17753-25-2
こちらのサイトで作品集の45ページ分のプレビューも閲覧可能です