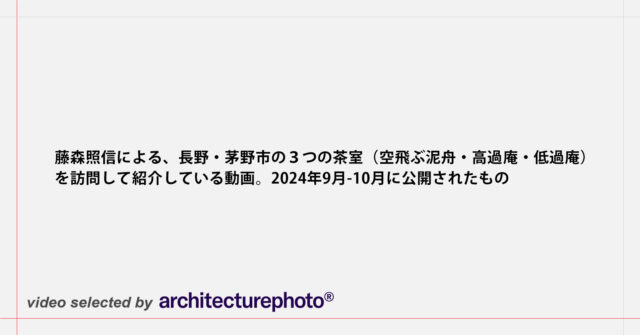kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 外観、東側の商店街より見る。 photo©迎崇 kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 外観、東側の商店街より見る。 photo©迎崇 kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 1階、正面:遊戯室、右:商店街 photo©迎崇 kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 1階、「靴履き替えスペース」から遊戯室を見る。 photo©迎崇 土用下淳也+山本純平+福井竜馬 / kyma が設計した、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」です。
長野県駒ケ根市の駅前商店街に建つ小さな保育園の計画。
平面計画における特徴の一つは遊戯室の配置にある。
遊戯室は土足仕様とし、より自由に内外を行き来できるようにしている。
「見る」という行為がきっかけとなって交流は生まれていくと考えている。
保育園の中の子どもたちからは商店街の様子を見ることができ、町を身近に感じられる環境をつくっている。
以下の写真はクリックで拡大します
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 外観、東側の商店街より見る。 photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 外観、東側の商店街より見る。 photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 外観、東側の商店街より見る。 photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 外観、屋外広場から遊戯室を見る。 photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 1階、正面:遊戯室、右:商店街 photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 1階、遊戯室から屋外広場側を見る。 photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 1階、「靴履き替えスペース」から遊戯室を見る。 photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 1階、「靴履き替えスペース」から遊戯室を見る。 photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 1階、保育室1から開口部越しに遊戯室を見る。 photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 1階、左:保育室1、右:遊戯室 photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 1階、左:「靴履き替えスペース」、正面手前:保育室1、正面奥:保育室2 photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 1階、保育室2 photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 1階、保育室3から保育室2側を見る。 photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 1階、遊戯室から2階への階段を見る。 photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 2階、オフィス photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 2階、オフィスから保育室1の吹抜とネット遊具を見る。 photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 2階、吹抜から1階の保育室1と遊戯室を見る。 photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 2階、吹抜から1階の保育室1と遊戯室を見る。 photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 外観、東側の商店街より見る。夜景 photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 外観、東側の商店街より見る。夜景 photo©迎崇
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 1階平面図 image©kyma
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 2階平面図 image©kyma
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 商店街マップ image©kyma
kymaによる、長野・駒ケ根市の「商店街の小さな保育園」。商店街の中にある敷地での計画。行政と連携した“まちづくり”の一環として、“子どもたちが豊かに育つ”と共に“商店街に賑わいをもたらす”存在を志向。遊戯室を前面に配置して地域にも開放する構成の建築を考案 外観、東側の歩行者専用道路より見る。商店街や周辺住民など、多くの地域関係者が集まった保育園のオープニングセレモニー。地域に根差した保育園の出発点を共に祝した。 photo©kyma 以下、建築家によるテキストです。
商店街の小さな保育園―J’sほいくえん駒ヶ根
長野県駒ケ根市の駅前商店街に建つ小さな保育園の計画。
この保育園は未満児に特化した小規模保育施設で、0~2歳児まで各6名、計18名の子どもたちが通う。
吹抜けにネットを張り巡らせた遊戯室や屋外の広場は地域に開放され、保育園に通う子どもだけでなく地域の子どもやその家族も商店街に呼び込み、多くの交流を生むことを意図している。
駒ヶ根市と連携したまちづくりプロジェクト
銀座商店街でのまちづくりは2016年にスタートした。
遊び場を地域に開く
平面計画における特徴の一つは遊戯室の配置にある。
遊戯室は土足仕様とし、より自由に内外を行き来できるようにしている。
遊びの回遊性
子どもたちをワクワクさせる遊び場として回遊性を重視した。
活動を商店街に見せる / 商店街を子どもたちに見せる
「見る」という行為がきっかけとなって交流は生まれていくと考えている。
保育園の中の子どもたちからは商店街の様子を見ることができ、町を身近に感じられる環境をつくっている。
保育園と商店街をつなぐ木製カーテンウォール
遊戯室には木製の大開口を設け、保育園と商店街を視覚的につないでいる。
活性化の新しい形-商店街は地域コミュニティの拠点
商店街は単なる商業施設ではなく、地域コミュニティの拠点としての役割を担ってきたはずである。そう捉えなおせば、高いポテンシャルが残されているのではないだろうか。
■建築概要
題名:商店街の小さな保育園