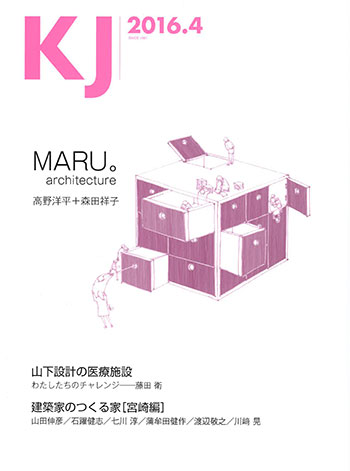エイトブランディングデザイン・西澤明洋の対談集『クリエイティブのつかいかた』がamazonで発売中です
エイトブランディングデザイン・西澤明洋の対談集『クリエイティブのつかいかた』がamazonで発売中です。建築分野では、谷尻誠が登場しています。2016/4/15発売予定です。
日本を代表するトップクリエイター12人が語る、クリエイティブの本質とは。
デザインやビジネスに生かせるヒントやノウハウ満載東京・青山ブックセンターで1年間にわたって開催され、12人のクリエイターに迫ったセミナー「クリエイティブのABC」。
その内容は日経デザイン誌でも連載され毎回好評を博した。
これにブランディングデザイナー西澤明洋による分析を大幅加筆し、クリエイティブとは何か、彼らはどんな思考法なのかなど、
クリエイターの生き様にも迫りながら、デザインやビジネスに生かせるクリエイティブの本質を明らかにした。
デザインやビジネスに生かせるヒントやノウハウが満載の一冊。12人のクリエイターはいずれも日本を代表する方たちばかり。編集からプロダクト、グラフィックなど分野は多岐にわたる。
・柴田文江(プロダクトデザイナー)「プロダクトデザインもブランディングを意識する時代に」
・猪子寿之(チームラボ代表)「テクノロジーで“かっけぇー”世界を創りたい」
・KIGI(植原亮輔 渡邉良重)「コンセプトづくりも踏まえ、グラフィックの新領域を開拓」
・谷尻誠(建築家)「人と人が関わる「環境づくり」こそが建築家の役目に」
・柿沢安耶 (「パティスリーポタジエ」オーナーパティシエール)「野菜を生かした商品開発で、農業の大切さを伝えたい」
・田川欣哉(takram design engineering 代表)「ノット・デザイン・オア・エンジニアリングで自由な発想を」
・山崎亮(コミュニティデザイナー)「地元のために立ち上がる人を増やすのが僕らのミッション」
・岸勇希(電通)「課題の本質を見極め、デザイン力で解決策を徹底的に考え抜く」
・佐渡島庸平(コルク代表)「編集能力は情報の順番工学、大変革の時代にこそ不可欠」
・山田遊(バイヤー/method代表)「経験の積み上げこそがバイイングのセンスにつながる」
・津田大介(ジャーナリスト/メディア・アクティビスト)「人が変わるきっかけをつくるのがメディアの役割」
クリエイティブのつかいかた
西澤明洋