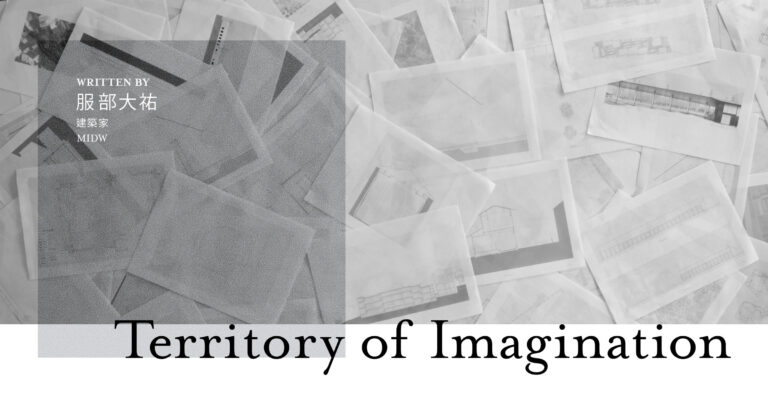万博 休憩所4(前編)
2025年頭、これまでの事務所Schenk Hattoriをたたみ、京都にて新たにMIDW(メドウ)という名前の事務所を設立しました。
2014年にメンドリジオ建築アカデミーの同級生、スティーブンと共にアントワープでSchenk Hattoriを開設してから、あっという間に10年が経ち、僕がベルギーにいた間に始まった案件が全て一段落したことや、コロナ禍の影響で協働が難しい状況が続いたこともあり、このタイミングでそれぞれの新しい事務所を開設することになりました。
そして、MIDWとして最初に竣工した作品が、会期残り僅かとなった万博の「休憩所4」になります。
(Niimori Jamisonと協働で設計。プロポーザル応募時はSchenk Hattoriの名義で提出)
今回と次回の二回に分けて、この休憩所の設計段階からこれまで、そして今後について、段階を追って書いてみたいと思います。
以下の写真はクリックで拡大します
参加を決心するまで
2022年開催のプロポーザルで選定されて以来、万博開幕まで、3年掛かりで進めてきた「休憩所4」。実はプロポーザルが告示された当初、今の時代に万博を開催すること、そしてそれに関わることに果たしてどれだけ意義があるのか、といったことが引っかかり、参加するかどうか、とても迷っていました。
そんな時、Niimori Jamisonの新森くんから連絡を貰い、「どうせ誰かが作ることになるんだから、一緒に提案しましょう」と誘われました。
未来社会とざっくり言われてもピンとこないけれど、確かに、少なくとも建築文化に限って考えたら、万博は未だ見ぬ建築の可能性を示すための実験場としての役割があるはずです。そうであるならば、この時代に生き、建築に携わる者として、今この場で考えるべきことを提示する義務があるだろうと考えました。
そして何より、チャンスが与えられているにも関わらず、参加しない言い訳を見つけて、提案もしないで偉そうに批判だけをするのは嫌だという思いで参加を決めました。
プロポーザルにて
このプロポーザルは少し変わった形式になっていて、全部で20ある施設の受託者を一挙に選定する、というものでした。提案する対象として、休憩所、サテライトスタジオ、トイレという3つのプログラムがあり、その中から任意に選択し提案することが求められており、僕らは、せっかくなら一番大きな施設を作りたい、ということで休憩所を選択しました。
「そもそも休憩所ってなんだろう?」ということですが、休憩所という名前がついているからといって、ただ椅子があって座れることだけが求められているわけではないはずです。特に、万博という特殊な場においては、もっと多様な休憩の形があって良いと考えました。
会期中、たくさんのパビリオンを回って、疲れ果てた人がこの場所に休息に来るはずです。歩き疲れて、座ったり寝転んだり、うたた寝をしたい人もいるでしょう。あるいは、少し頭を休めようと、散歩したり、走り回りたい人だっているかも知れません。
そういった様々な人が、様々なあり方で同居することの出来る場所として、閉じた建物ではなく、ランドスケープのような、あるいはランドスケープと建築の間を繋ぐような場を作るべきだと考えました。休息という人間の本能的な欲求が喚起されるような空間を作りたい、そこから設計が始まりました。
万博の開催地である夢洲は人工島。会期前にはほとんど何も無い、まさに荒野でした。
以下の写真はクリックで拡大します
こんなところで果たして何をコンテクストとして設計の手掛かりにすれば良いのか。途方に暮れながらプロポーザルの配布資料を何度も読み返しているうちに、一つのことが目に留まりました。僕らの設計の方針を決定付けることになる、建物の基礎についての要件でした。