三分一博志の講演会「風、水、太陽」が、東京のイイノホールで開催されます
三分一博志の講演会「風、水、太陽」が、東京のイイノホールで開催されます。開催日は、2016年4月15日です。要事前申し込みで、期間は3月27日まで。
三分一博志の講演会「風、水、太陽」が、東京のイイノホールで開催されます
三分一博志の講演会「風、水、太陽」が、東京のイイノホールで開催されます。開催日は、2016年4月15日です。要事前申し込みで、期間は3月27日まで。
ライアン・マッギンレーの展覧会が、東京オペラシティアートギャラリーで開催されます
ライアン・マッギンレーの展覧会が、東京オペラシティアートギャラリーで開催されます。会期は、2016年4月16日~7月10日。
2003年に25歳という若さでホイットニー美術館で個展を開催したライアン・マッギンレー(1977- )は、多くの美術館に作品が所蔵され、今日「アメリカで最も重要な写真家」と高く評価されています。マッギンレーは、北米の田園風景、野外コンサート会場、あるいはスタジオのなかで、巧妙に光を操りながら場面を設定し、35ミリの粒子の粗いフィルムで、まるで映画を撮るかのように自らが作り出す「ハプニング」を撮影します。微細で洗練された色彩と構図の写真作品が表現する、自由で過激、そしてときに純粋なユートピアのような世界は、古き良きアメリカのイメージとも重なりながら、同時に、仮想と現実が混在する現代という時代の空気を読み取ることができます。日本の美術館では初となる個展として、作家自選の約40点でその全貌を紹介します。
妹島和世が1996年に完成させた岡山の住宅「S-HOUSE」を転用した美術館「S-HOUSEミュージアム」の公式サイトが公開されています
妹島和世が1996年に完成させた岡山の住宅「S-HOUSE」を転用した美術館「S-HOUSEミュージアム」の公式サイトが公開されています。開館日の情報や、展示作家の情報、地図などが掲載されています。S-HOUSEについて妹島が語っているテキスト・図面・写真はこちらで見ることができます。
木下昌大の展覧会「最適化する建築」が、アーツ千代田3331のD-lab東京ギャラリーで開催されます
木下昌大の展覧会「最適化する建築」が、アーツ千代田3331のD-lab東京ギャラリーで開催されます。開催期間は、2016年2月27日~3月27日。
KYOTO Design Labでは、2月27日(土)〜3月27日(日)の1ヶ月間、「木下昌大展 最適化する建築」を開催いたします。本展覧会では、本学助教で建築家の木下昌大が「最適化する建築」を求めた結果、実現した6つのプロジェクトと、木下研究室で3人の学生が取り組んだ卒業製作を紹介します。9つのプロジェクトには、それぞれに異なる与件があり、その与件から導かれた姿があります。与件がどのように「建築」へと昇華されていったのか、「建築」がどのようにその内外の環境を最適化しているのかをご覧いただければ幸いです。
私が大学で建築を学び始めたころ、既に日本ではバブルが崩壊し、建設行為が必ずしも肯定的に受け入れられなくなっていました。しかし、建設行為に逆風が吹く中でこそ、建築家が果たすべき役割があるのではないかと考えました。
建築がつくられる時、そこには多くの与条件が存在します。その建築で何が行われるのか? かけられる予算はいくらか? いつまでに必要なのか? 周辺環境に与える影響は? 法的な制限は? 何年間使用されるのか? 費用対効果は? などなど…これら多くの与件を切り捨てることなくすくい上げたうえで、それでもなお人の心を動かす「建築」はいかに可能だろうか?
この問いに応える理想の建築の姿を「最適化する建築」(Optimized Architecture)と呼び、その実現を目指しています。
−−−−−−
「最適化する建築」とは、建築が内包する空間とその建築を取り巻く環境を、人間が活動するために最適な状態にかえる行為の過程全体、あるいは一部のこと。また、そのような行為によって作られた構造物そのものを指す
−−−−−−
木下昌大
美術ジャーナリストの鈴木芳雄による、横浜美術館での村上隆コレクション展の紹介テキストがSPUR.JPに掲載されています
美術ジャーナリストの鈴木芳雄による、横浜美術館での村上隆コレクション展の紹介テキストがSPUR.JPに掲載されています。村上隆がコレクションを始めるきっかけになった出来事などのエピソードか多数紹介されており、実際の展示をより深く見ることができるようになるテキストだと思います。
田中功起の展覧会「共にいることの可能性、その試み」が水戸芸術館で開催されます
アーティストの田中功起の展覧会「共にいることの可能性、その試み」が水戸芸術館で開催されます。展覧会期は、2016年2月20日~5月15日。田中は、青木淳の作品集にテキストを寄稿していたりと建築とも近い位置にいるアーティストだと思います。10+1websiteには、「Dialogue:美術館建築研究」というタイトルの、青木淳と田中功起の対談が掲載されています。(公開は2000年代初め頃だったと思います。)
本展は、田中功起による国内初の大規模な個展です。田中は、映像記録、インスタレーション、執筆、パフォーマンスおよびイベント企画といったさまざまな方法を通して、現在の社会状況や既成の枠組みに対し、別の視点やあり方を模索する活動で近年、注目されています。2013年の第55回ヴェネツィア・ビエンナーレでは、5名の陶芸家がひとつの陶器をともにつくる様子をとらえた映像作品などで、複数の人びとがひとつのことにともに携わるときの、その行為の美しさと難しさを表し、国際的に評価されました。
本展では、協働による営みに関心を抱くようになった2010年以降の田中の活動に焦点をあて、新作を中心に、近年の取り組みとあわせて紹介します。
本展のために制作された新作は、一般参加者とファシリテーター、撮影チームらと一つ屋根の下をともにした6日間の滞在とそのなかでのワークショップがもとになります。朗読、料理、陶芸、社会運動にまつわるワークショップ、ディスカッション、インタビューなどで構成された6日間を通して、移動や共同体についてそれぞれが考え、また対話し、実践する機会が設けられました。本展では、これらのワークショップの記録映像をもとにつくられた複数の映像に、作家が制作中に書いたノートなどが添えられ展示されます。

photo©Takumi Ota

photo©Takumi Ota
山田紗子建築設計事務所による、京橋のAGCスタジオでの建築模型の展覧会「新しい建築の楽しさ」の会場構成です。展覧会の会期は2016年2月27日まで。
毎年東京・京橋のAGCスタジオで行われている建築模型の展覧会「新しい建築の楽しさ」の会場構成である。この展覧会は2期に分かれ、1期に6組の建築事務所の作品を展示するもので、それぞれ全く異なる背景、コンセプト、スケールを持つ6つの建築模型が並ぶ。来場者は新しい模型が目に入るとその都度その模型の世界に自らの縮尺を合わせなくてはいけない。そこで今回は展示台の高さを1300mmと通常よりも思い切って高く設定し、それぞれの模型のアイレベルの高さを来場者の目線の高さに揃えることよって、来場者が自然に模型の持つ縮小された世界に引き込まれるような展示にしたいと考えた。
「村上隆のスーパーフラット・コレクション」展の会場写真と動画がinternet museumに掲載されています
横浜美術館で行われている「村上隆のスーパーフラット・コレクション」展の会場写真と動画がinternet museumに掲載されています。
以下は、展覧会公式の概要です。
アーティストとしての精力的な創作の一方で、村上隆はキュレーター、ギャラリスト、プロデューサーなど多岐にわたる活動も展開しています。特に、近年、独自の眼と美意識で国内外の様々な美術品を積極的に蒐集し続けており、その知られざるコレクションは、現代美術を中心に日本をはじめとするアジアの骨董やヨーロッパのアンティーク、現代陶芸や民俗資料にまで及んでいます。村上隆にとって「スーパーフラット」とは、平面性や装飾性といった造形的な意味のみに限定されるのではなく、時代やジャンル、既存のヒエラルキーから解放された個々の作品の並列性、枠組みを超えた活動そのものを示しており、「芸術とは何か?」という大命題に様々な角度から挑み続ける作家の活動全体(人生)を包括的に表す広範かつ動的な概念と捉えられるでしょう。
圧倒的な物量と多様さを誇るこれら作品群を通して、村上隆の美意識の源泉、さらには芸術と欲望、現代社会における価値成立のメカニズムについて考えるとともに、既存の美術の文脈に問いを投げ掛ける、またとない機会となるでしょう。
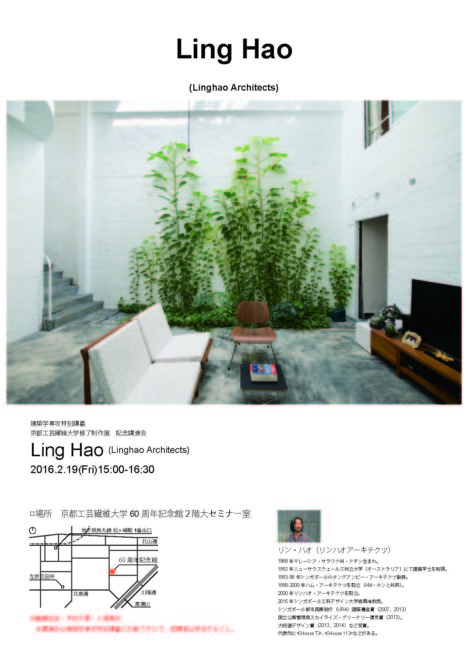
シンガポールを拠点とする建築家リン・ハオの講演会が京都工芸繊維大学で開催されます。開催日は、2016年2月19日15時~16時30分。リン・ハオの講演会の後には、カルソ・セント・ジョンのアダム・カルソの講演が連続して行われるようです。リン・ハオは、ギャラリー間での「アジアの日常から」展の出展建築家であった事も記憶に新しいですが、アーキテクチャーフォトでも以前よりその作品に注目して紹介を続けていました。
また、翌日の2016年2月20日(土)13:30-には、京都文化博物館別館ホールにて、リン・ハオ、アダム・カルソ、千葉学がゲストで参加する京都工芸繊維大学建築学専攻修了制作の公開講評会も行われるとの事。
ギャラリー間での展覧会「WARO KISHI 岸 和郎:京都に還る_home away from home」の会場写真とレビューがa+eに掲載されています
ギャラリー間での展覧会「WARO KISHI 岸 和郎:京都に還る_home away from home」の会場写真が22枚とレビューがa+eに掲載されています。
以下は展覧会公式の概要。
横浜で生まれた岸氏が1981年に京都に事務所を構えてから30年あまり。京都の歴史や伝統の重圧に押しつぶされそうになりながらも、建築家としての立ち位置を模索し、自身が京都で設計することの意味を問い続けてきました。合理性や秩序を追求するモダニストを標榜してきた岸氏は、今や、確かな歴史感に立脚した日本的な美を継承しつつ、場所の特性を丁寧に読み解くことのできる現代建築家の第一人者としての評価を確立。拠点の京都のみならず、関西、東京、海外へとその活躍の場を拡げています。
本展では、建築家として、また教育者として活動している氏のパラレルな活動の軌跡を、2016年現在の切断面として紹介します。京都をメインとした数多くのプロジェクトに加え、これまで携わってきた3つの大学でのアクティビティ、さらには東京のプロジェクトから近作まで、模型やドローイング、映像等、さまざまな切り口で展示します。
カルソ・セント・ジョンのアダム・カルーソの講演会が京都で開催されます
カルソ・セント・ジョンのアダム・カルーソの講演会が京都工芸繊維大学で開催されます。カルソ・セント・ジョンはロンドンをベースとする建築設計事務所です。彼らは、歴史的建築に敬意を払い、周囲の既存の建築に対し、違和感なく調和しながらも、現代的価値を持った建物を設計しています。2014年には、アスプルンドのストックホルム図書館の改修コンペに勝利したりと注目を集めている建築家です。
KYOTO Design Labは、ロンドンとチューリッヒを拠点にイノベーティブな建築・都市再生を数多く手掛ける建築家アダム・カルーソ(スイス連邦工科大学チューリッヒ校教授、Caruso St John Architects)の講演会を開催いたします。ぜひご参加ください。
パブリック・レクチャー
アダム・カルーソ講演会
日程 2016年2月19日(金)16:30-18:00
講師 アダム・カルーソ(スイス連邦工科大学チューリッヒ校教授、Caruso St John Architects)
会場 京都工芸繊維大学 60周年記念館2階大セミナー室
定員 100名(当日先着順。参加費無料)
講師
アダム・カルーソ Adam Caruso
建築家。カナダ・モントリオールのマックギル大学を卒業し、Florian Beigel とArup Associates で働いてのち、1990年にPeter St. Johnと事務所を設立。2011年スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ)教授に就任
横浜美術館での展覧会「村上隆のスーパーフラット・コレクション ―蕭白、魯山人からキーファーまで―」のメイキング動画です。
以下は展覧会公式の概要。
アーティストとしての精力的な創作の一方で、村上隆はキュレーター、ギャラリスト、プロデューサーなど多岐にわたる活動も展開しています。特に、近年、独自の眼と美意識で国内外の様々な美術品を積極的に蒐集し続けており、その知られざるコレクションは、現代美術を中心に日本をはじめとするアジアの骨董やヨーロッパのアンティーク、現代陶芸や民俗資料にまで及んでいます。村上隆にとって「スーパーフラット」とは、平面性や装飾性といった造形的な意味のみに限定されるのではなく、時代やジャンル、既存のヒエラルキーから解放された個々の作品の並列性、枠組みを超えた活動そのものを示しており、「芸術とは何か?」という大命題に様々な角度から挑み続ける作家の活動全体(人生)を包括的に表す広範かつ動的な概念と捉えられるでしょう。
浅田彰による論考「村上隆なら森美術館より横浜美術館で」がrealkyotoに掲載されています
浅田彰による論考「村上隆なら森美術館より横浜美術館で」がrealkyotoに掲載されています。現在ネット上で注目を集めている論考です。
飯田善彦建築工房による、東京都千代田区の集合住宅「(仮称)番町プロジェクト」の内覧会が開催されます(PDF)
飯田善彦建築工房が設計した、東京都千代田区の集合住宅「(仮称)番町プロジェクト」の内覧会が開催されます。開催日は、2016年2月7日(日)AM11:00~PM5:00。場所はJR四谷駅(麹町口)より徒歩7分との事。
私どもでを進めてきました(仮称)番町プロジェクトが竣工を迎えます。
このたび、施主様のご厚意により見学会を開催することとなりましたので、お知らせいたします。
皆様お誘いあわせの上お越しいただければ幸いです。
オラファー・エリアソンが、ヴェルサイユ宮殿で2016年夏に展覧会を行うことになったそうです
アーティストのオラファー・エリアソンが、ヴェルサイユ宮殿で2016年夏に展覧会を行うことになったそうです。自身のtwitterアカウントに情報を投稿していました。過去にはアニッシュ・カプーアや村上隆などの著名なアーティストが展示を行っています。
以下は、今年夏のオラファーの展示を伝えるtwitterの投稿。
Very excited to announce upcoming exhibition at Versailles this summer! @CVersailles
https://t.co/IW5v3KLc4k pic.twitter.com/OWfv0ZaeT8
— StudioOlafurEliasson (@olafureliasson) 2016, 1月 28
岸和郎のギャラリー間での個展「京都に還る_home away from home」の会場写真がjapan-architects.comに掲載されています
岸和郎のギャラリー間での個展「京都に還る_home away from home」の会場写真がjapan-architects.comに掲載されています。
以下は、展覧会公式の概要。
横浜で生まれた岸氏が1981年に京都に事務所を構えてから30年あまり。京都の歴史や伝統の重圧に押しつぶされそうになりながらも、建築家としての立ち位置を模索し、自身が京都で設計することの意味を問い続けてきました。合理性や秩序を追求するモダニストを標榜してきた岸氏は、今や、確かな歴史感に立脚した日本的な美を継承しつつ、場所の特性を丁寧に読み解くことのできる現代建築家の第一人者としての評価を確立。拠点の京都のみならず、関西、東京、海外へとその活躍の場を拡げています。
また同時に、京都芸術短期大学(現・京都造形芸術大学)、京都工芸繊維大学、京都大学と、3つの大学において教鞭を執り、多くの建築家を輩出してきました。大学では、設計・デザインの教育のみならず、一建築家として、場所、歴史、文化、都市、自然等々、あらゆる側面からの建築との向きあい方を自身のことばで語る等、設計することの意味を伝えてきました。
本展では、建築家として、また教育者として活動している氏のパラレルな活動の軌跡を、2016年現在の切断面として紹介します。京都をメインとした数多くのプロジェクトに加え、これまで携わってきた3つの大学でのアクティビティ、さらには東京のプロジェクトから近作まで、模型やドローイング、映像等、さまざまな切り口で展示します。
メールマガジンでも最新の更新情報を配信中