本野精吾が設計した京都・山科の住宅「栗原邸」の一般公開が開催されます
本野精吾が設計した京都・山科の住宅「栗原邸」の一般公開が開催されます。開催日は、2015/5/23・24・30・31。詳細はリンク先でどうぞ。
この建物は、染色家で京都高等工芸学校(現・京都工芸繊維大学)校長、鶴巻鶴一の邸宅として1929年に建設されたものです。設計者は同校教授であった建築家・本野精吾(1882-1944)。当時最先端の工法「中村式鉄筋コンクリート建築」による特殊なコンクリートブロックで建てられた、合理性を追及したモダニズム建築です。しかしウィーン分離派やアール・デコの影響を受けたと思われる装飾的で表現的なデザインも見られ、時代の転換期に生み出されたものであることを感じさせます。2007年にはモダニズム建築の保存に関する国際組織DOCOMOMO Japanより優れた日本のモダニズム建築の1つとして選定され、2014年には国の登録有形文化財に登録されるなど、近年その文化財的評価が高まっています。

![サムネイル:長谷川豪が、書籍『カンバセーションズ』の出版記念イベントで、保坂健二朗と対談[2015/4/16]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41pGU9nD1tL._SL160_.jpg)

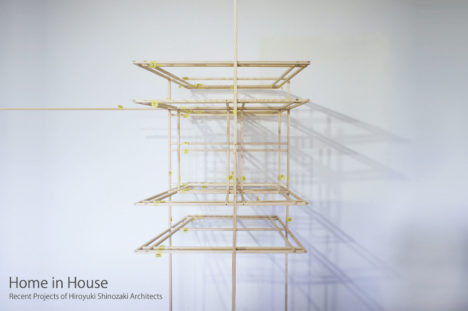

![サムネイル:スイスの建築設計事務所ミューラー・シグリスト・アーキテクツの講演会「住宅という小都市」が京都工芸繊維大学で開催[2015/4/3]](https://d6pmnsnqga8dz.cloudfront.net/wp/wp-content/uploads/2015/04/kousen-eth.jpg)
![サムネイル:遠藤克彦建築研究所による、東京都大田区の集合住宅「Ark」のオープンハウスが開催[2015/4/4]](https://d6pmnsnqga8dz.cloudfront.net/wp/wp-content/uploads/2015/03/endosama001-468x692.jpg)