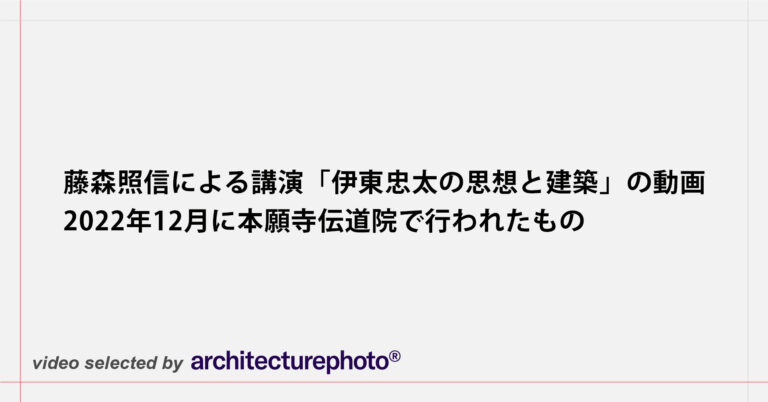スノヘッタによる、オーストリア・チロルの展望施設「Top of Alpbachtal」。海抜2千メートルの建築。来訪者の山岳体験を高めるランドマークを目指し、アルプスの“建築の伝統”と“見事な環境”にひらめきを得た設計を志向。誰もが自由に出入り可能で“消費なしに”休憩できる場を作る photo©Christian Flatscher スノヘッタによる、オーストリア・チロルの展望施設「Top of Alpbachtal」。海抜2千メートルの建築。来訪者の山岳体験を高めるランドマークを目指し、アルプスの“建築の伝統”と“見事な環境”にひらめきを得た設計を志向。誰もが自由に出入り可能で“消費なしに”休憩できる場を作る photo©Christian Flatscher スノヘッタによる、オーストリア・チロルの展望施設「Top of Alpbachtal」。海抜2千メートルの建築。来訪者の山岳体験を高めるランドマークを目指し、アルプスの“建築の伝統”と“見事な環境”にひらめきを得た設計を志向。誰もが自由に出入り可能で“消費なしに”休憩できる場を作る photo©Christian Flatscher スノヘッタによる、オーストリア・チロルの展望施設「Top of Alpbachtal」。海抜2千メートルの建築。来訪者の山岳体験を高めるランドマークを目指し、アルプスの“建築の伝統”と“見事な環境”にひらめきを得た設計を志向。誰もが自由に出入り可能で“消費なしに”休憩できる場を作る photo©Christian Flatscher スノヘッタ による、オーストリア・チロルの展望施設「Top of Alpbachtal」です。
こちらはリリーステキストの翻訳です
スノヘッタ、チロル・アルプスのランドマークをデザイン
スノヘッタは、スキー・ユウェル・アルプバハタル・ヴィルトショナウ・スキー・エリアの依頼を受け、海抜2030メートルにある一般公開される展望台とパノラマルームを設計しました。新しい木造の建物は、ヴィーダーベルガーホルンの山頂付近、ケーブルカーのホーンバーン2000の山頂駅に隣接する絶好の場所に位置しています。アルプスの建築の伝統とその見事な環境は、スノヘッタのこのユニークな建築物をデザインのインスピレーションになりました。
スキー・ユウェル・アルプバハタル・ヴィルトショナウ・スキー場の10周年を記念して、スキー場は老朽化したスキーリフトに代わる新しいチェアリフト「ホーンバーン2000」に投資し、スノヘッタをケーブルカーのサービスルームの上に位置する展望塔の設計に招待しました。それは、来訪者の山の体験を高めるランドマークとするためです。「Top of Alpbachtal」と名付けられた、チロル・アルプスの高さ13mの木造タワーのデザインコンセプトは、アルプスの建物の伝統を参照しています。
スノヘッタ・スタジオ・インスブルックのパートナー兼マネージング・ディレクターであるパトリック・ルースは言います。
伝統的なデザインにインスパイアされた
上部が細くなる新しい木造建築は、地元の板金業者による手作りの屋根板で覆われています。パノラマルームは、スキーヤーはもちろん、スノーシューウォーカー、スキーツアラー、夏のハイカーも利用できます。木造建築のコンクリートの土台にあるリフトのコントロールルームを抜けると、来場者は一般に開放されたラウンジに到達します伝統的なチロルの農家のパーラーからインスピレーションを得て、2階のパノラマルームをデザインしました。2層の部屋の下部は、木製の壁パネルで覆われており、伝統的なパーラーをイメージしています。一方、上層部では、屋根の構造がオープンになっており、伝統的な農業建築を彷彿とさせます。