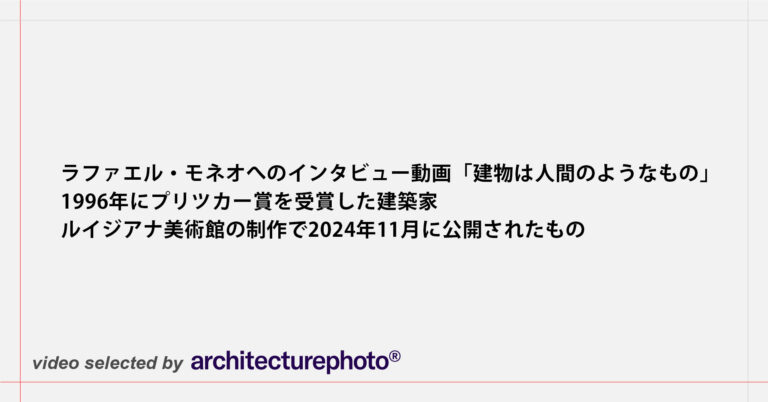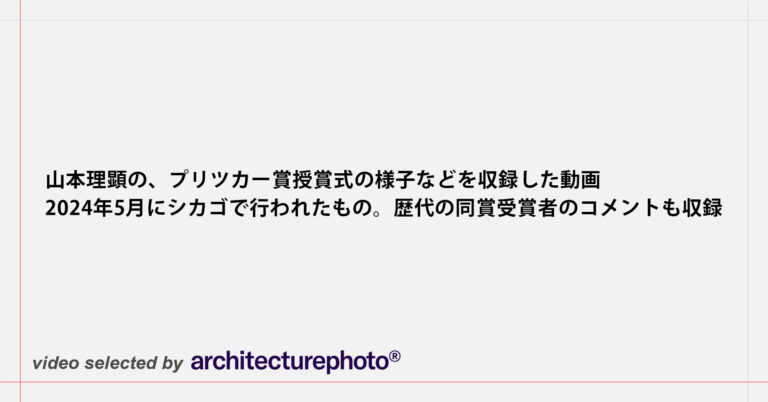アーキテクチャーフォトで、先週(期間:2024/11/11-11/17)注目を集めたトピックスをまとめてご紹介します。リアルタイムでの一週間の集計は、トップページの「Weekly Top Topics」よりご覧いただけます。
- 建築家の妹島和世が、文化功労者に選ばれました
- JAMZAによる、東京・江東区の「深川えんみち」。子供から高齢者までを受入れる“多世代共生の複合型福祉施設”。日常に福祉が存在する状況を目指し、地域の人々を招き入れる“道を引き込む動線計画”の建築を考案。街と繋がる為に“施設らしくない”境界面も作る
- 胡実建築設計事務所による、静岡・駿東郡の「東海道沿いの家」。交通量の多い道に面した敷地。中庭を中心に生活空間が展開する構成とし、床を部分的に下げる操作で“大地に身を埋めて寛げる”場も創出。外装の杉板は歴史が残る環境との連続性に加えて騒音への対応も意図
- 宮川清志 / SESNによる、愛知・名古屋市の店舗「RENATUS CLINIC NAGOYA」。都心のビル内の美容クリニック。これからの店舗空間の在り方も考慮し、形などの“意匠性”だけでない“体験を超えた現象のある空間”を志向。照明の細かな設定等で“朝焼けの様な”現象の中で過ごす状態を創り出す
- 田邉雄之建築設計事務所による、長野・茅野市の「ウキゴヤ / Hovering Cabin」。植栽家の為の“地域の立ち寄り場兼事務所”。ランドスケープとの新たな関係性を考慮し、一本足の様な基礎で浮遊させた“土地との縁を切り離す”建築を考案。小振りな基礎は凍結深度が深い敷地でのコスト削減も意図
- 妹島和世と西沢立衛の対談「穴が開くほど見る―建築写真から読み解く暮らしとその先 第10回」の動画がLIXILのサイトで期間限定で無料配信。其々が選んだ、厳島神社、中野本町の家、サヴォア邸、スカイハウスの写真を題材に議論
- 長坂常 / スキーマ建築計画による、東京・中央区の店舗「アンドワンダー GINZA SIX」。高級品が多く並ぶ商業施設内の店。同じブランドの店を複数手掛ける背景から、既存の仕組みを共有しつつ“環境に合わせてカスタム”する設計を志向。金属板を床に用いて周囲と調和する“硬質感”を空間に与える
- 河内尚子による、奈良市での展覧会「家具と空間」。“家具と空間”をテーマに実践的研究も行う建築家の展示。登録有形文化財の正木家住宅を会場とし、革・大理石・杉を用いて制作した家具を配置。訪問者に空間と家具が“相互に与える影響”についての考察を促す
- 山口健太郎 / KNT Architectsによる、北海道・札幌市の「House in MARUYAMA」。山裾に計画された設計者の自邸。豊かな緑に囲まれた敷地に対して、様々な開口部を通じて“視線が山へと抜ける”建築を考案。素材自体の表出は“職人の手”から生まれる“建築の骨”での“纏う空気”の創出も意図
- 鎌倉市の新庁舎等基本設計プロポーザルで、日建設計が最優秀者に選定。コンセプトは「ひとつながりの未来の庁舎『鎌倉ONE』」。提案のイメージも公開
- 北村直也建築設計事務所による、岐阜の「かまや多治見」。明治の長屋を改修した複合施設。伝統も新規も尊重する地域性に着想を得て、道側は周辺と調和する“黒色”とし庭側を“銀色”とした“表裏の印象”が異なる建築を考案。用途同士の相乗効果も意図して透明素材を多用
- 青木真研究室による、東京・新宿区のトレーニングスタジオ「NewAns西新宿店」。ビルの4階の区画での計画。ネットと対面でサービスを展開する店舗として、動画と現実が相互関係を結ぶような体験ができる空間を志向。SNSの投稿までをトレーニング体験と捉えて出入口に撮影ポイントも作る
- 大峯竣平+堤康浩 / デザインオツによる、石川・輪島市の「二ツ屋町ハウス」。五差路に面する敷地。“風土的な振舞い”が背景にある住居を求め、人々の“懐のひろさ”に着目して“ひろさ”の“懐”となる建築を志向。土間・広間・物見縁台を繋いだ気積のある空間で様々な受入れを可能にする
- 成瀬・猪熊建築設計事務所による、東京・杉並区の「高円寺のオフィス」。設計者が監修した製品を用いて構成した自社の事務所。改善や可能性のフィードバックを得る為の“実験の場”を求め、システムパーティション等を実装した空間を考案。働く場の在り方の捉え直しと更新にも繋げる
- ザハ・ハディド・アーキテクツによる、カタールの集合住宅「ザ・グローブ」。湾岸沿いの敷地での計画。店舗が並び“交流の中心となる遊歩道”のある、先進的な冷却技術で“屋外でも快適に過ごせる”建築を考案。様々な再生可能エネルギーを取入れてラグジュアリーと持続可能の両立も意図
- 日建設計が最優秀者に選定された、鎌倉市の新庁舎等基本設計プロポーザルの、最終プレゼンの動画。石本建築事務所 横浜事務所、内藤廣・松田平田設計共同企業体、隈研吾建築都市設計事務所・梓設計共同体のプレゼン動画も公開
- 矢野泰司+矢野雄司 / 矢野建築設計事務所による、高知・吾川郡の「いの町観光拠点施設」。地域の憩いの場となっている河川敷に面する敷地。隣接地が持つ“余白のある広がり”に着目し、“柔らかく接続”して一体的な環境を形成する建築を志向。機能毎に建物を分けて行止まりのない連続性も生み出す
- 東孝光による「塔の家」(1966) と 伊東豊雄による「花小金井の家」(1983) の建築ツアーが開催。妹島和世の監修でアートウィーク東京の一環として実施
- ヘルツォーグ&ド・ムーロンが、マルセル・ブロイヤー設計の旧ホイットニー美術館(1966年竣工)を改修へ。オークションハウスのサザビーズが建物を取得して計画を発表
- UAoによる、栃木の「那須塩原市図書館 みるる+駅前広場」