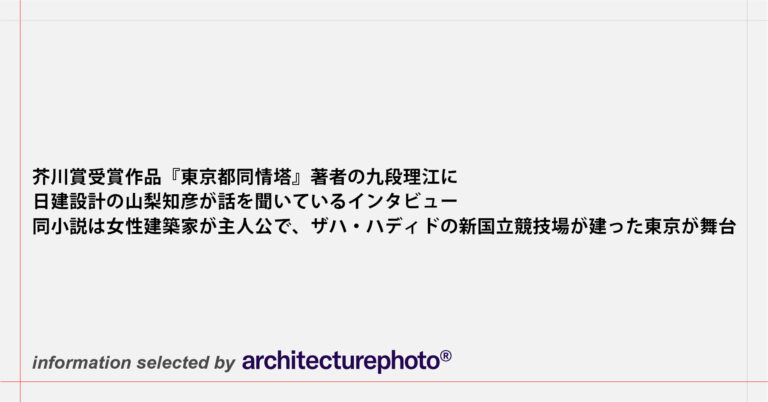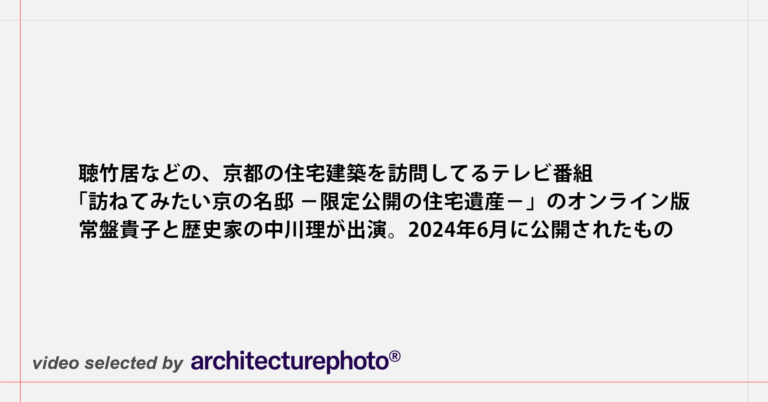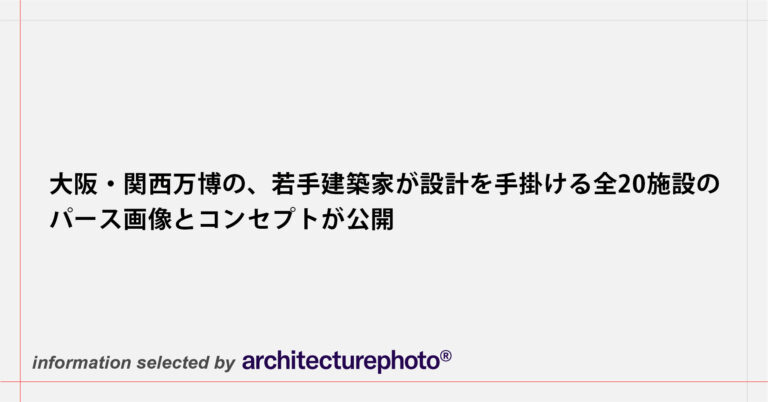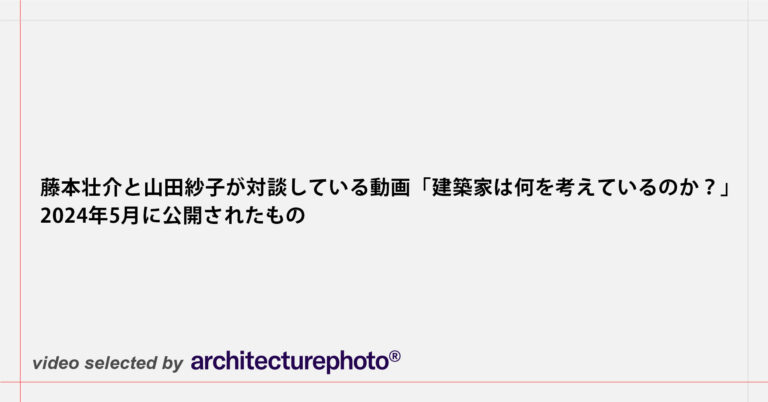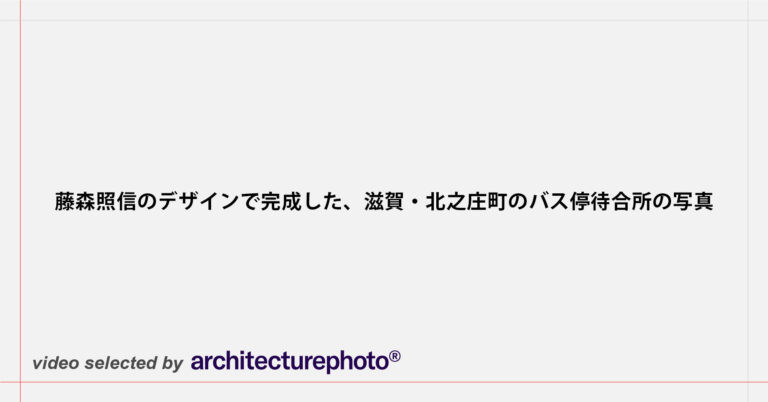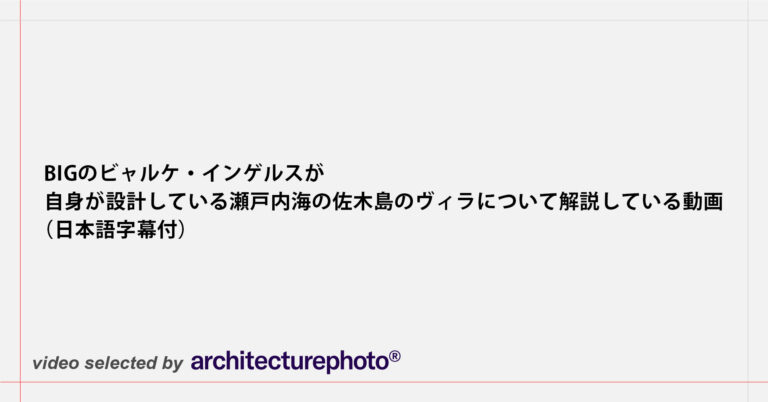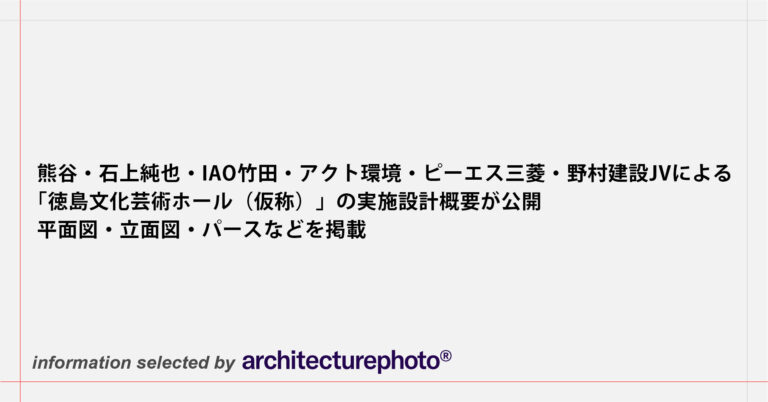culture archive
Open Aの馬場正尊を、NHKのテレビ番組「プロフェッショナル 仕事の流儀」が特集します。放送日時は、2024年7月5日22時~。


隈研吾とフェンディがコラボして制作したバッグが、オンラインでも販売中です。
上記のリンク先のバッグの価格は、2,970,000円。こちらのタイプは、1,631,300円となっています。小ぶりな、438,900円のものもあります。
発売されているバッグは、隈が同ブランドの2024年春夏メンズコレクションの為にアイデアを提供しました。2023年に行われたコレクションで発表されたものが販売されているようです。
フェンディは、隈研吾を「自然主義建築の巨匠」と評価して、協働を依頼しました。
ブランドのアイコンとなっているバッグには、コットンと樹皮繊維から作られる「和蘭紙」を用いています。また、スニーカー等も手掛け、その3Dプリントで作られるソールなどは、細い竹をイレギュラーに編み上げる「やたら編み」を参照した格子のデザインとなっています。
隈研吾はこのプロジェクトに関して以下の様に述べています。
「自然とクラフトは、建築家そしてデザイナーとして私が生み出す作品の中心であり続けています。フェンディからフェンディのバッグやシューズについて考えてほしいと依頼があったとき、それらがヒューマンスケールにおける 小さなアーキテクチュラルプロジェクトであると考えました。シルヴィア・フェンディが手がけるメンズデザインの シグネチャーを、自然と軽やかさ、革新的なデザインに対する私たちの共通の情熱を表現しながら、伝統的な日本の技法と素材で変化させました」
以下に、その他のプロダクトの写真などを掲載します。



重松象平 / OMAの空間デザインによる、六本木ミュージアムでの「ミス ディオール展覧会 ある女性の物語」です。
香水“ミス ディオール”を主題とした展示です。建築家は、多様な要素や世界観を反映する為に、時代を超えた一貫性を持ちつつ各テーマの理解を促す設計を志向しました。また、非日常的な空間でモチーフとなった製品の世界へと誘うことも意図されました。会期は2024年7月15日まで。完全予約制(無料)です。
重松象平 OMAパートナーによるコメント
香りのように見えないものを体験できる空間をデザインすることは興味深い挑戦でした。ミス ディオールは多くのストーリを持った、メゾンのアイデンティティの根幹となるフレグランスです。その多様な要素や世界観を反映すべく、時代を超えた視点を明確にし、一貫性を持ちつつも、各テーマを理解していただけるよう本展覧会をデザインしました。様々なモチーフとインスピレーションが非日常的な空間へと昇華されていて、みなさまをミス ディオールの世界へと誘う展覧会です



モロークスノキ建築設計が設計者として、フリーダ・エスコベド・スタジオがデザインアソシエイトとして手掛ける、フランス・パリの「ポンピドゥー・センター」の改修計画です。また、AIAライフ・デザイナーズがエンジニアとして参画しています。
ピアノ+ロジャースが1977年に完成させた文化施設を改修する計画です。既存の価値観とコンセプトを尊重しつつ、変化した時代と調和する建築を志向しています。設計者は、この建築の原設計者であるレンゾ・ピアノも審査員として参加したコンペティションで選ばれました。そして、5年間の休館を経て2030年の竣工を予定しています。
こちらはリードアーキテクトのモロークスノキ建築設計によるステートメントの翻訳です
設立以来、ポンピドゥー・センターは実験的なスペースであることに努めており、適切な存在であり続けるために常に自らを改革し、新しいアイデアを刺激し、個々の訪問者の体験を、個人と集団の記憶の両方に栄養を与えるユニークな発見のプロセスとして組み立てています。
今回の改修は、プロジェクトの創設理念のいくつかに再びつながる機会となります。コンセプト・アプローチの基礎となる4つの主要軸は、この魅力的な空間を、すべての来訪者とスタッフの期待に応えられるような豊かな体験のできる空間に変えることを目的としています。
物理的および視覚的な多孔性
この介入の主要な側面は、さまざまなプログラム間の視覚的および物理的なつながりを確立することにより、ポンピドゥーセンターの初期のヴィジョンの寛大さを再発見し、強化することを目指しています。新たな要素が、空間同士だけでなく、目の前の都市環境に対しても開かれたものにします。光は空間の奥深くまで入り込み、小道をより魅力的で歓迎的な方法で際立たせます。建物の中心部に都市を拡張することは、このプロジェクトの核心的な意図のひとつです。
進路の明確化
この設計案は、明確で読みやすいレイアウト原則を確立するために、空間構成の合理化と単純化を目的としている。直感的に識別可能な選択肢を提供する流動的な経路が、すべての人、特に初めての訪問者の体験を促進する枠組みが作られます。これらの道筋をたどることも、そこから外れることも、望むままに選択できます。ポンピドゥー・センターが構想されたとき、スピード、アニメーション、情報伝達といった概念が進歩を象徴していました。今日、パラダイムは逆転しています。情報過多、注意力の分断、スクリーンタイムによる孤立に直面しているポンピドゥー・センターは、媒介、人的交流、身体的体験が中心となる空間を提供しているのです。空間は、幅広い観客に芸術と知識を浸透させることができる、生き生きとした創造的な側面をよりよく展開するために、より高い流用の自由と集中する機会を与えなければなりません。
空間の活性化と再認識
通路を明確にし、空間の透明性を強化することで、訪問者はセンター全体を探索する機会を得ることができ、これが公衆によるより良い利用と、以前は活用されていなかったエリアの利用増加に寄与しています。空間が物理的にも視覚的にも解放され、新たな可能性が見えてきます。それは、その成功のための活性化に必要な条件を作り出すことです。それは、プログラムの収束、多様なレイアウト、観客の混在、アクセスしやすいスペース、横断的な視覚的関係です。このような物理的、視覚的、知的な関係は、あらゆるレベルで明確化されており、建物の創造的なプラットフォームとしての性格を回復するのに役立っています。
聴竹居などの、京都の住宅建築を訪問してるテレビ番組「訪ねてみたい京の名邸 -限定公開の住宅遺産-」のオンライン版です。常盤貴子と歴史家の中川理が出演しています。2024年6月に公開されたもの。
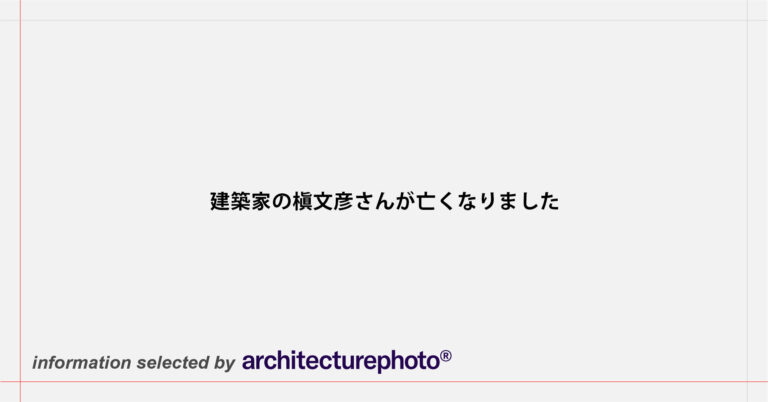
SHARE 建築家の槇文彦さんが亡くなりました
建築家の槇文彦さんが亡くなりました。95歳でした。
ご冥福をお祈りいたします。
以下のように様々なマスメディアが報じています。
- NHK:世界的建築家 槇文彦さん死去 95歳 幕張メッセなど設計
- 朝日新聞:建築家の槇文彦さんが死去 挑んだモダニズム建築の日本への着地
- 読売新聞:プリツカー建築賞を受賞の建築家・槇文彦さん死去、95歳…代官山のヒルサイドテラス設計
- 産経新聞:世界的建築家の槇文彦さん死去 95歳 世界文化賞受賞、幕張メッセなど手掛ける
- 日本経済新聞:槙文彦さんが死去 建築家、幕張メッセなど設計
- 中日新聞:世界的建築家の槇文彦さん死去 95歳、名古屋大豊田講堂や幕張メッセなど手掛ける
- 時事通信:槇文彦さん死去、95歳=世界的建築家、文化功労者
- FNN:建築家・槇文彦さん(95)死去 代官山のヒルサイドテラスや幕張メッセなど設計し世界文化賞も受賞
- The Japan Times:Renowned Japanese architect Fumihiko Maki dies at 95
大阪・関西万博の、若手建築家が設計を手掛ける全20施設のパース画像とコンセプトが公開されています。
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会は、若手建築家による2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)会場内の「休憩所」「ギャラリー※1」「展示施設※2」「ポップアップステージ※3」「サテライトスタジオ※4」「トイレ」計20施設の設計業務が完了しましたので、各施設概要、設計コンセプト及びイメージパースを公開します。
20施設の公募については、1970年開催の日本万国博覧会(大阪万博)を担当した若手建築家が、その後著名な建築家となったように、大阪・関西万博においても若い世代の活躍、飛躍のきっかけとなるよう、将来が期待される若手建築家を対象に行ったものです。
「多様でありながら、ひとつ」という会場デザインコンセプトの下、SDGs(持続可能な開発目標)達成につながる、意欲的かつ大胆な提案により、会場内に個性豊かで魅力的な博覧会施設を創出していきます。
※1・・・アート、アニメ、ファッション等の催事、各種展示会、フォーラム等の開催を想定した施設。
※2・・・「未来の暮らし(食・文化・ヘルスケア)」が体験できる『フューチャーライフエクスペリエンス)』と、「未来への行動」が体験できる『TEAM EXPOパビリオン』で行われる事業について、それぞれ発表・展示を想定した施設。
※3・・・音楽、トークイベント、お祭り等のイベント実施を想定した小規模ステージ広場。
※4・・・放送局の番組中継・収録用スタジオ。
リンク先は公式サイトが公開しているPDFファイルです。
藤森照信のデザインで完成した、滋賀・北之庄町のバス停待合所の写真が5枚、滋賀県のサイトに掲載されています。藤森による建築があるラ コリーナ近江八幡の最寄りのバス停の様です。
BIGのビャルケ・インゲルスが、自身が設計している瀬戸内海(広島県)の佐木島のヴィラについて解説している動画です。NOT A HOTELの為に設計している建築です。
世界的建築家ビャルケ・インゲルス率いるBIGが瀬戸内海に浮かぶ離島・佐木島を舞台にデザインするのは、日本の風土と伝統建築、そして“角度”にインスパイアされた3つのヴィラ。

世田谷美術館での展覧会「民藝 MINGEI ― 美は暮らしのなかにある」の入場チケットを抽選で5組10名様にプレゼントいたします。
民藝について“衣・食・住”をテーマにひも解き、暮らしで用いられてきた品々を多数展示します。また、国内外の職人による民藝の品等を取り揃えた特設ショップも開設されます。
会期は、2024年4月24日~2024年6月30日。展覧会の公式ページはこちら。入場チケットプレゼント企画の応募締切は、2024年5月20日(月)13時まで(お申込みにはGoogleアカウントが必要になります)。こちらのフォームからご応募ください。厳正な抽選を行い当選された方にはメールにてご連絡いたします(メール送付を当選発表にかえさせていただきます)。
約100年前に思想家・柳宗悦が説いた民衆的工藝、「民藝」。日々の生活のなかにある美を慈しみ、素材や作り手に思いを寄せる、この「民藝」のコンセプトはいま改めて必要とされ、私たちの暮らしに身近なものとなりつつあります。
本展では、民藝について「衣・食・住」をテーマにひも解き、暮らしで用いられてきた美しい民藝の品々約150件を展示します。また、いまに続く民藝の産地を訪ね、そこで働く作り手と、受け継がれている手仕事も紹介します。
さらには、2022年夏までセレクトショップBEAMSのディレクターとして長く活躍し、現在の民藝ブームに大きな役割を果たしてきたテリー・エリス/北村恵子(MOGI Folk Art ディレクター)による、現代のライフスタイルと民藝を融合したインスタレーションも見どころのひとつとなるでしょう。
柳が説いた生活のなかの美、民藝とは何か―そのひろがりと今、そしてこれからを展望する展覧会です。
以下に、写真と詳細な情報を掲載します。
熊谷・石上純也・IAO竹田・アクト環境・ピーエス三菱・野村建設JVによる「徳島文化芸術ホール(仮称)」の実施設計概要が公開されています。平面図・立面図・パースなどを掲載しています。リンク先は徳島県のサイトにアップされたPDFファイルです。アーキテクチャーフォトでは、基本設計時のパースも特集記事として紹介しています。
旧徳島市立文化センター跡地等を計画地とする「徳島文化芸術ホール(仮称)」について、実施設計の成果を概要版としてとりまとめました。内容は、施設構成、平面図、立面図、パース図などとなっています。

平田晃久建築設計事務所のデザイン監修で、原宿駅旧駅舎跡地に商業施設が建設されます。設計者は、JR東日本建築設計です、また、旧駅舎の外観の再現も実施され、2026年冬の竣工を予定しているとのこと。
原宿駅旧駅舎跡地開発の工事着手について
・原宿駅旧駅舎跡地開発について、5月末頃から本体工事に着手いたします。
・本開発は、原宿のまちの玄関口において、100年近く地域のみなさまに愛されてきた旧駅舎の外観を再現しながら商業施設として整備するものです。
・Beyond Station構想の一環として、「時とつながる」「まちとつながる」「文化とつながる」という3つの「つながる」をコンセプトとし、原宿エリア全体の賑わいに寄与することを目指してまいります。
以下の画像は拡大して閲覧できます。

内藤廣建築設計事務所が内装設計を手掛けた、東京・銀座の店舗「TORAYA GINZA」がオープンしています。
旧「とらや 銀座店」の店舗は1947年より店舗を構えてきた。複合ビルへの建て替えに伴い、ビルの4階に新店舗として、この「TORAYA GINZA」をリニューアルオープンした。内装を手掛けているのは、これまでも日本各地のとらやの店舗を手掛けてきた内藤廣である。
今回の店舗では、吹抜のテラス席が空間のポイントとなっている。またテラス席に加えて、職人が目の前で和菓子をつくり提供するカウンター席もある。そのほがソファー席、奥座敷のような個室など様々なタイプの客席も用意されている。壁には鈍く輝く瓦タイルが使用され、空間の音にもこだわっているとのこと。
明治以降、多くの「日本初」が生まれ、やがて流行の発信源となった街「銀座」。
情報の発信地である一方で、老舗店舗や歴史的な建築が軒を連ねる、新しさと伝統が共存する街です。1947年、とらや 銀座店は生まれました。
そして2024年、国内外を問わず、年齢層もさまざまな人が行き交う銀座で、
とらやの菓子の新たな一面を体験できる店としてリニューアルオープンいたします。
以下に、その他の写真と空間の解説テキストを掲載します。