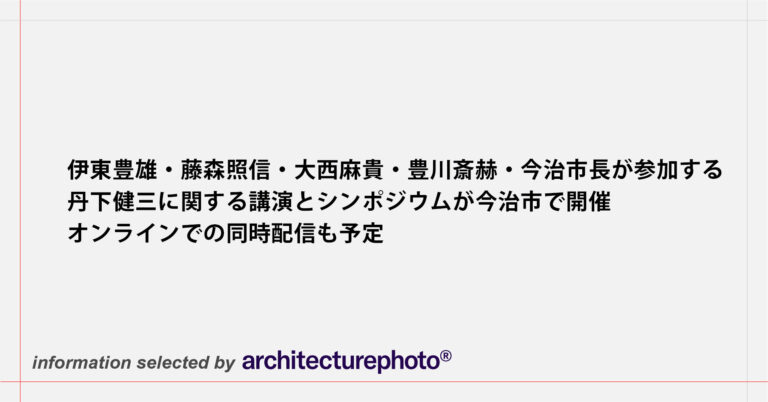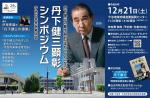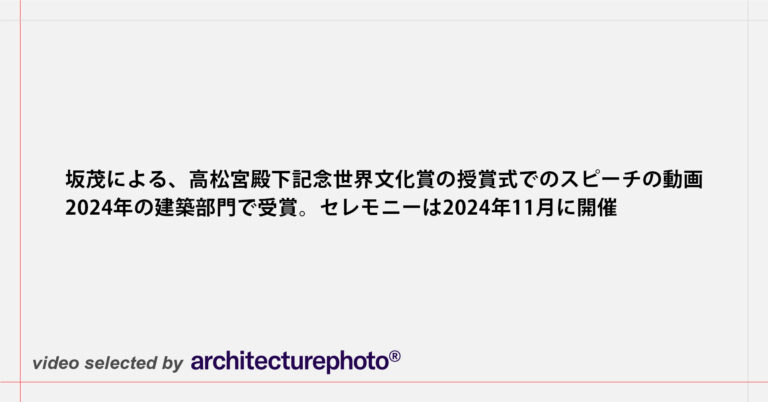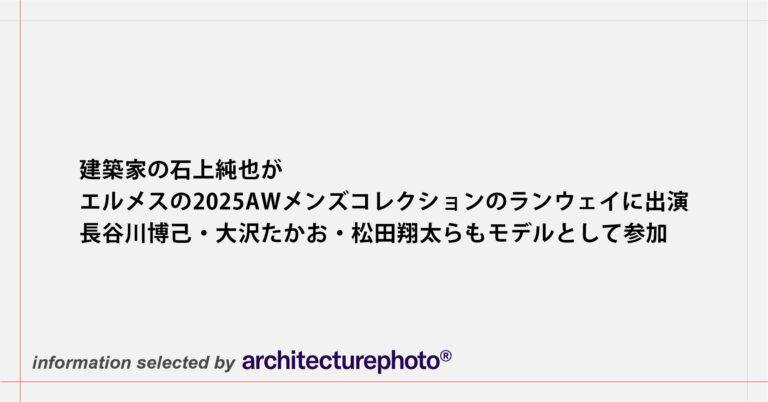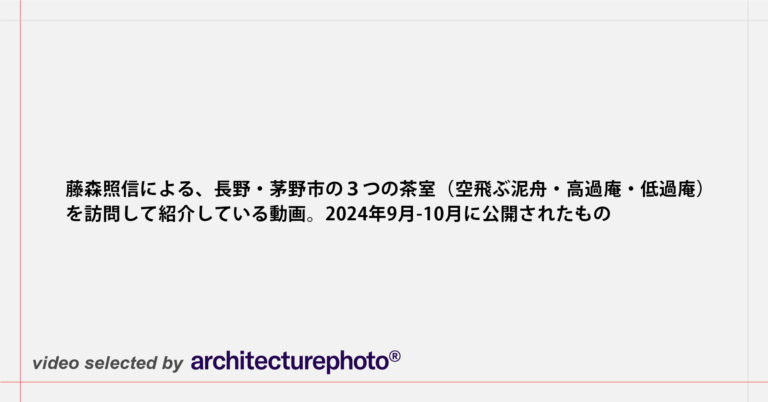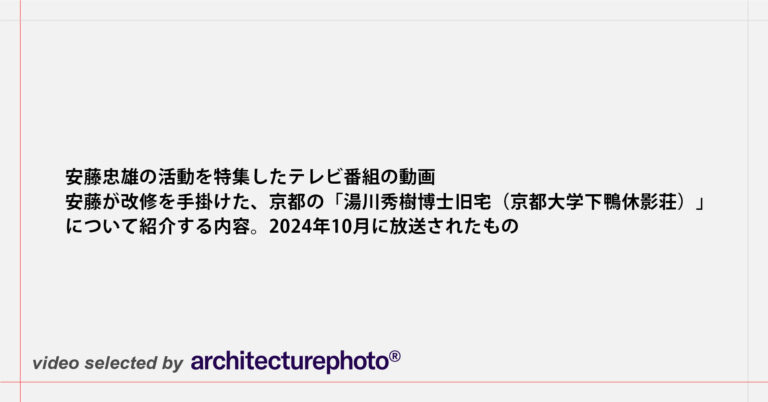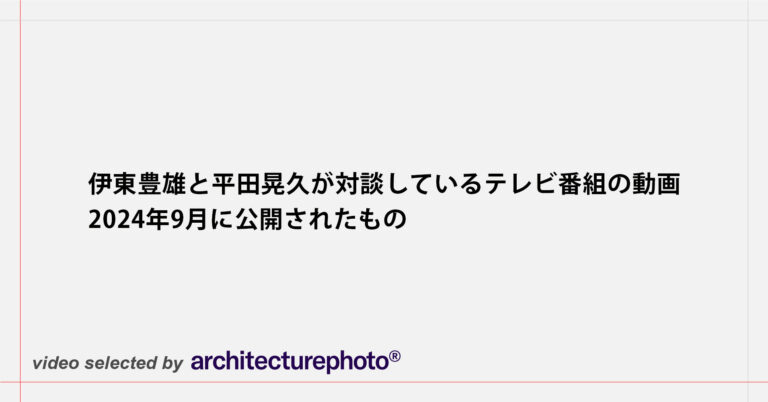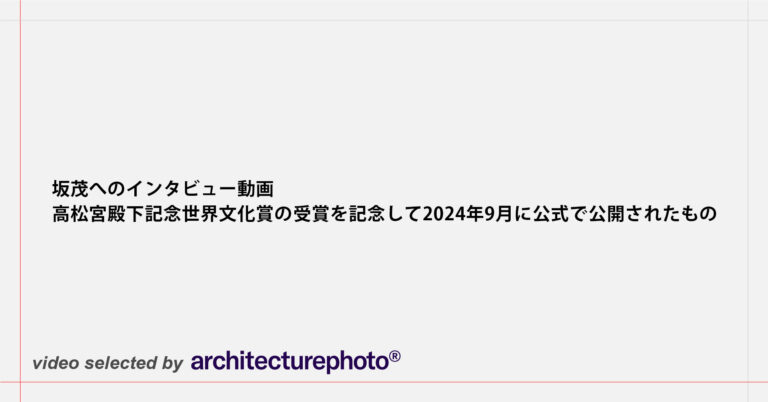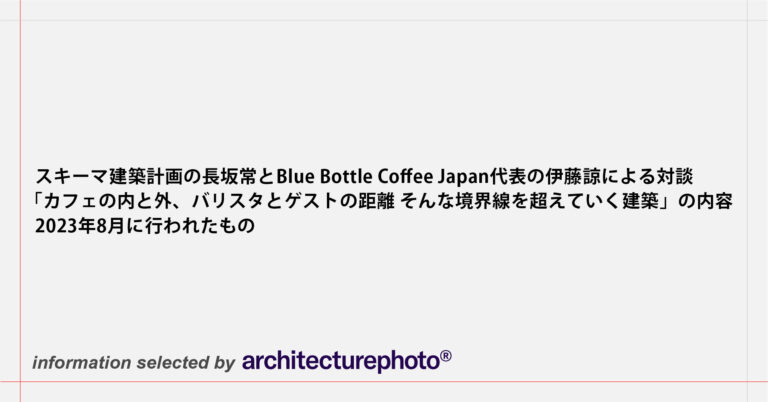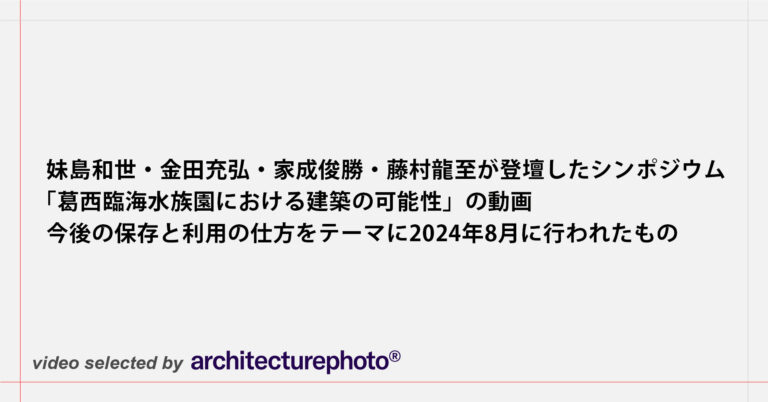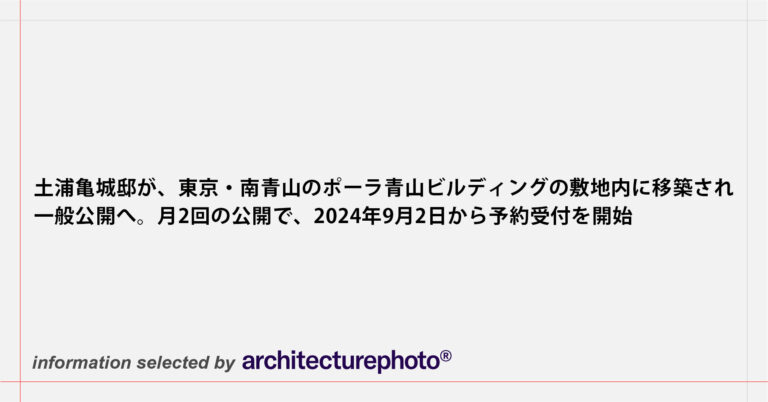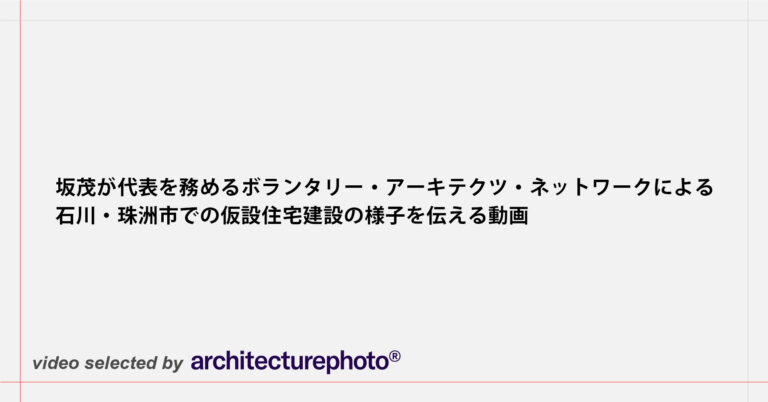culture archive
坂茂による、高松宮殿下記念世界文化賞の授賞式でのスピーチの動画です。2024年の建築部門で受賞していました。セレモニーは2024年11月に開催されました。受賞に際して、坂の業績をまとめたページはこちら。


隈研吾による、2つのクリスマスツリー「木漏れ日」と「木組み」です。
隈がデザインした虎ノ門と銀座のホテルで公開されます。建築家は、サステイナブルをテーマとし、小さな木のユニットを積み上げるデザインを考案しました。また、シーズン終了後は家具に転用されれます。
「木漏れ日」は東京エディション銀座にて2024年11月19日から、「木組み」は東京エディション虎ノ門にて2024年11月20日より公開されます。
隈研吾によるコメント
2020年にオープンした東京エディション虎ノ門と、2024年にオープンした東京エディション銀座のロビーに、クリスマスシーズンを華やかに彩る、木でできたツリーをデザインしました。どちらのツリーも、小さな木のユニットを積み上げて作り、それぞれの街の特色を表現します。また、複数の樹種を使うことで森の循環・育成に貢献します。クリスマスシーズンが終わった後も、ツリーのユニットは家具に転用され、違う場所に生まれかわります。そんなサステナブルで、永遠を生きるクリスマスツリーが生まれます。

SHARE 東孝光による「塔の家」(1966) と 伊東豊雄による「花小金井の家」(1983) の建築ツアーが開催。妹島和世の監修でアートウィーク東京の一環として実施
- 日程
- 2024年11月8日(金)・11月9日(土)


東孝光による「塔の家」(1966) と 伊東豊雄による「花小金井の家」(1983) の建築ツアーが開催されます。妹島和世の監修でアートウィーク東京の一環として実施されるものです。開催日は、2024年11月8日・9日(要事前申込)。申込ページはこちら。
SANAA 妹島和世監修による建築ツアー
「TOKYO HOUSE TOUR」は、東京の街に佇む名建築を巡る建築ツアー。コースの監修を務めるのは2004年ヴェネチアビエンナーレ国際建築展 金獅子賞、2010年プリツカー賞などの受賞歴をもつ建築ユニット「SANAA」の共同設立者であり、2022年からは東京都庭園美術館館長を務める建築家・妹島和世です。
1回目のテストケースとして実施される今回は、建築家・東孝光が1966年に設計した東京都心の住宅「塔の家」と、建築家・伊東豊雄が1983年に設計した東京郊外の住宅「花小金井の家」を訪ねます。
妹島和世によるコメント
現在の東京には素晴らしい小住宅が多く存在しています。それらは戦後、個人事業として設計を営む建築家の設計によって建てられた庶民の家です。そうした小住宅群は、戦後の東京の暮らしをいまに伝える貴重な財産でありながら、同時に日本近代建築史の中で公共建築とともに存在感を示し、日本の近代建築を象徴する存在として世界で高く評価されてきました。住宅建築がこれほど多く集まる街は、世界的に見ても東京以外にありません。
しかし現在、高齢化をはじめとする様々な理由により、そうした建築物の維持が難しくなってきています。例えば、ヨーロッパでは戦後に建てられた住宅建築の多くは集合住宅であり、それらは地方自治体によって保存されながら現在も大切に使われていますが、日本の小住宅群はすべて民間で作られたものであるために、その保存と継承の困難さが現実的に大きな問題になっているのです。そこで、そうした小住宅に新たな使い方を与え、それらを東京の、そして日本の財産として継承し、みんなで守っていけたら良いのではないかと考え、このプログラムを企画するに至りました。
今回のツアーはその1回目のテストケースとして、建築とその保存継承、そして東京の暮らし全般に関心のある方たちを対象に、東京都心に建つ住宅と、まだ自然が残る郊外に建つ住宅のふたつを取り上げます。
詳細な情報は以下に掲載します。
建築家の石上純也が、エルメスの2025AWメンズコレクションのランウェイに出演しています。長谷川博己・大沢たかお・松田翔太らもモデルとして参加したようです。VOGUEのサイトにはレポート記事も掲載されています。リンク先のfashionsnapのサイトに写真が1枚掲載されています。石上は、2010年にもヨウジヤマモトのコレクションにモデルとして出演していました。また、同じく建築家の中山英之が2016年にエルメスのランウェイに出演しています。



鎌倉市の新庁舎等基本設計プロポーザルで、日建設計が最優秀者に選定されています。
計画案のコンセプトは「ひとつながりの未来の庁舎『鎌倉ONE』」です。また提案のイメージも公開されました。その他の応募者には、石本建築事務所 横浜事務所、内藤廣・松田平田設計共同企業体、隈研吾建築都市設計事務所・梓設計共同体が名を連ねていました。
※提案書の画像も追記しました(2024/10/24)
市と共に、新庁舎の基本設計を進める事業者(人・チーム)を選定するため、令和6年(2024年)9月1日(日曜日)に「新庁舎等基本設計者等選定審査会」を開催し、一次審査を通過した4者の提案について、二次審査(プレゼンテーションを含む)を実施した結果、総合的に高い評価を得た「株式会社日建設計」を最優秀提案者に決定しました。
以下に、その他の画像と審査公表を掲載します。
安藤忠雄の活動を特集したテレビ番組の動画です。安藤が改修を手掛けた、京都の「湯川秀樹博士旧宅(京都大学下鴨休影荘)」について紹介する内容です。2024年10月に放送されたもの。施設の概要が京都大学のページに掲載されています。年数回の一般公開も予定されているとのこと。

石上純也が設計した「house & restaurant maison owl」の一般宿泊予約が開始されています。山口県宇部市にある、2024年日本建築学会作品賞を受賞した建築です。1日1組限定で全館貸切が可能となります。
「house & restaurant maison owl(メゾンアウル)」(所在地:山口県宇部市、オーナーシェフ・平田基憲)は2022年春に開業し、これまで招待制でゲストをお招きしておりました。この度、10月1日(火)より、1日1組限定の「suite stay experience(スイートステイエクスペリエンス)」を一部、一般向けに予約開始することをお知らせいたします。
1日1組限定の全館貸切のため、ご利用のお客様には完全プライベートな時間をゆったりとお過ごしいただけます。
「suite stay experience」概要
■料金:700,000円(税別)/1泊・1組2名様
■プラン内容:本プランには2名様分の以下の料金が含まれております。
[1] アコモデーションエクスペリエンス(ご宿泊・ご朝食)
・お部屋の広さ:2LDK
・寝室:2部屋(ダブルベッド1台ずつ)
・チェックイン:16時から/チェックアウト:翌日11時まで[2] スペシャルダイニングエクスペリエンス
オーナー平田のおすすめする、素材を感じるお食事とシャンパーニュから始まり、食後酒まで全てのお料理にワインをマリアージュ。■ご予約について:1日1組2名様でのご予約を、半年先まで承ります。
■詳細およびご予約:公式サイトよりご確認ください。
・house & restaurant maison owl公式サイト:https://maison-owl.com/
※本プラン以外の全てのダイニングエクスペリエンス、およびアコモデーションエクスペリエンスはインビテーション制です。
※不定期で公式インスタグラムにて一般のご予約をお受けしております。
・公式Instagram:https://www.instagram.com/okcs_maison_owl/
※その他お問い合わせは下記メールアドレスよりお問い合わせください。
・E-mail:owlinfo@okcs.co.jp
以下にその他の写真も掲載します。
坂茂へのインタビュー動画です。高松宮殿下記念世界文化賞(第35回 2024年度)の受賞を記念して2024年9月に公式で公開されたもの。
スキーマ建築計画の長坂常とBlue Bottle Coffee Japan代表の伊藤諒による対談「カフェの内と外、バリスタとゲストの距離 そんな境界線を超えていく建築」が公開されています。スキーマが手掛けたブルーボトルコーヒーのプロジェクトの背景について色々と語られています。「ブルーボトルコーヒー 豊洲パークカフェ」の開店に合わせて2023年8月に行われたもの。
土浦亀城邸が、東京・南青山のポーラ青山ビルディングの敷地内に移築され一般公開へ。月2回の公開で、2024年9月2日11時10時から予約受付を開始するそうです(※2024/7/30 時間を訂正しました)。こちらのウェブサイトに移築前の土浦亀城邸の写真と藤森照信が執筆したテキストが掲載されています。
坂茂が代表を務めるボランタリー・アーキテクツ・ネットワークが行っている、石川・珠洲市での仮設住宅建設の様子を伝える動画です。能登半島地震の被災者支援の一環として行われているものです。