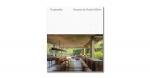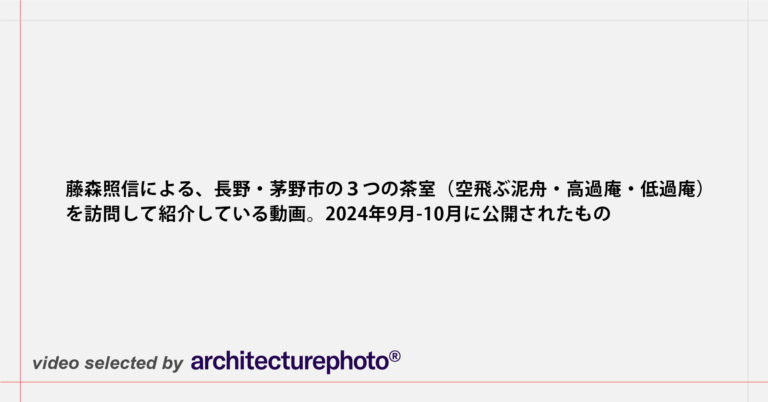MADによる、アメリカ・デンバーの「ワン・リバー・ノース」。都市の中心部に建つ低層部に商業施設も備えた集合住宅。都市生活の再考を目指し、地域の特徴的な環境を参照した“亀裂“のような空間を備えた建築を考案。外と内の空間を融合させて自然と建築の境界も曖昧にする 外観、西側から見上げる photo©Parrish Ruiz De Velasco MADによる、アメリカ・デンバーの「ワン・リバー・ノース」。都市の中心部に建つ低層部に商業施設も備えた集合住宅。都市生活の再考を目指し、地域の特徴的な環境を参照した“亀裂“のような空間を備えた建築を考案。外と内の空間を融合させて自然と建築の境界も曖昧にする 外観、北西側から見る、夜景 photo©Iwan Baan MADによる、アメリカ・デンバーの「ワン・リバー・ノース」。都市の中心部に建つ低層部に商業施設も備えた集合住宅。都市生活の再考を目指し、地域の特徴的な環境を参照した“亀裂“のような空間を備えた建築を考案。外と内の空間を融合させて自然と建築の境界も曖昧にする 外観、北西側から「キャニオントレイル」を見る、夜景 photo©Parrish Ruiz De Velasco MADによる、アメリカ・デンバーの「ワン・リバー・ノース」。都市の中心部に建つ低層部に商業施設も備えた集合住宅。都市生活の再考を目指し、地域の特徴的な環境を参照した“亀裂“のような空間を備えた建築を考案。外と内の空間を融合させて自然と建築の境界も曖昧にする 「キャニオントレイル」 photo©Iwan Baan MAD が設計した、アメリカ・デンバーの「ワン・リバー・ノース」です。
こちらはリリーステキストの翻訳です
マー・ヤンソン / MADアーキテクツが「ワン・リバー・ノース」を発表。デンバーの中心における裂け目のような峡谷。
コロラド州デンバーのリバーノースアート地区(RiNo)の中心近くに位置する新しい複合施設、ワン・リバー・ノース(ORN)の16階建てガラス張りのファサードを、自然の地形が刻み込んだような亀裂が走っています。
単なる集合住宅ではなく、ワン・リバー・ノースは、居住者がまるで山歩きをしているかのように縦方向に歩き回れるランドスケープです。MADのプリンシパルアーキテクトのマー・ヤンソンは述べています。「建物の中にいながら、まるで自然の風景の中にいるような気分になります。まるで峡谷の中に住んでいるような気分になるのです」
居住者が7階から10階まで建物のキャニオントレイルを移動する間、コロラドの丘陵地帯と峡谷の生態系から着想をえて厳選された環境に浸ることができます。道案内となるのは下の通りから聞こえる滝の水音です。ワン・リバー・ノースで、MADは、自然体験を現代建築に統合することで、都市生活を再考しようとしています。没入型の生活体験を創り出すことで、コミュニティを育成し、住民同士や自然界とのつながりを強化します。
この革新的なアプローチは、デンバーという都市の環境条件に対応したものです。デンバーは、都市部を囲む険しい山々や深い峡谷で知られています。市内では、リバーノース・アート地区(RiNo)が最近、目覚ましい変貌を遂げています。かつては工業の中心地でしたが、その後、クリエイター、アーティスト、アウトドア愛好家が集まる活気のある中心地へと変貌を遂げ、彼らが一体となってコロラドの創造性と活動的な文化を活性化しています。
ワン・リバー・ノースは、デンバーの高密度都市型住宅に対するニーズに応えると同時に、安全で歩きやすい近隣地域における健康と利便性を重視したライフスタイルの拡大を提供しています。MADのデザインは、探検、幸福感、そして自然とのつながりを奨励することで、その都市の活発な文化を反映しています。これにより、その都市の住民は、自分たちの周囲や互いとのつながりを強めることができます。
この建物は、16階建てで187戸の賃貸住宅があり、周囲の景観や街並みにシームレスに溶け込む約840㎡の地上階の商業スペースを備えています。外装材や植栽が室内に流れ込み、屋内と屋外のつながりを増強しています。
キャニオンの柔らかな表面は、自然浸食から着想を得て、スロットキャニオンを想起させるようにデザインされた4層からなるアメニティ空間です。この空間は、建物の塊のクリーンで幾何学的なラインと対照的なものとなるよう、MADによって設計されました。この施設には、約1,200㎡を超える造園されたテラスがあり、まるで空間に浮かんで見えます。このテラスからは、この街で最も素晴らしい景色のいくつかを楽しむことができ、また、水辺の要素が、居住者と自然環境との強い結びつきを育んでいます。ファサードを貫く峡谷のようなストラクチャーは、屋内と屋外の空間を融合させ、自然と建築の境界を曖昧にすることで、没入感のある自然な体験を生み出しています。