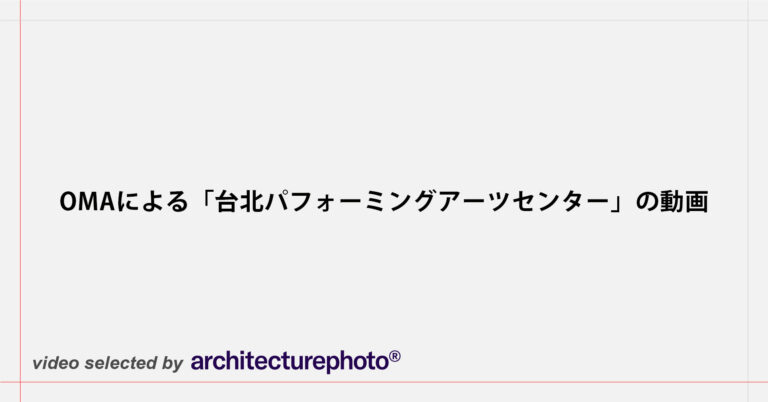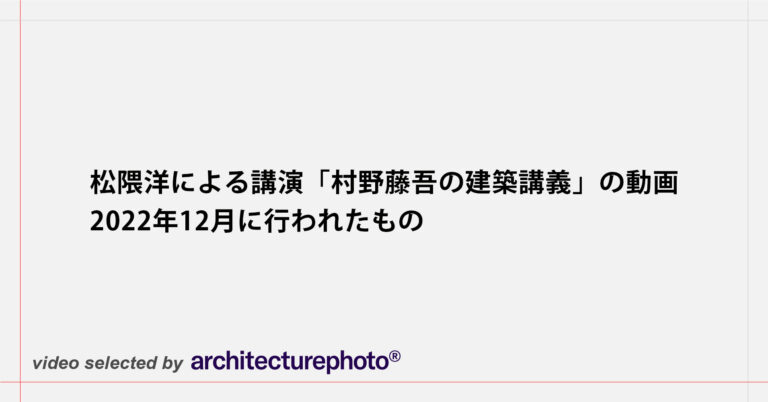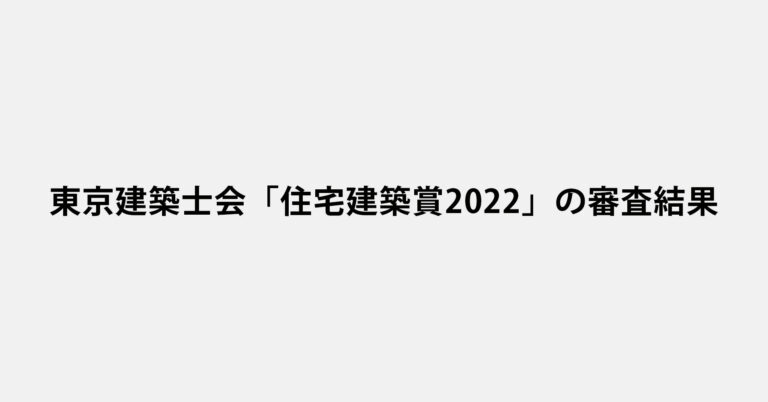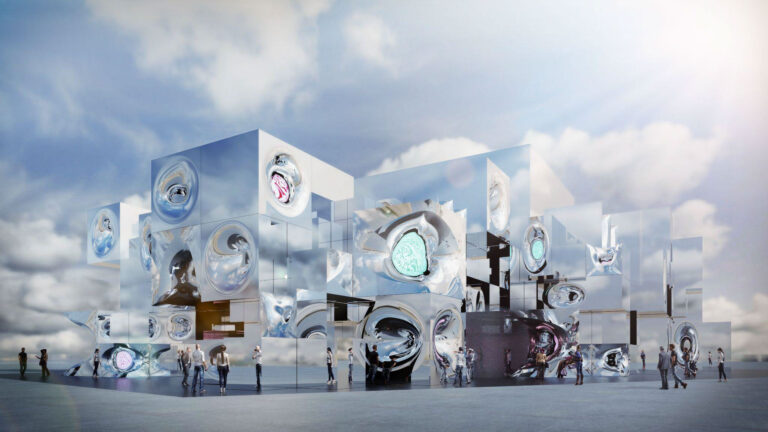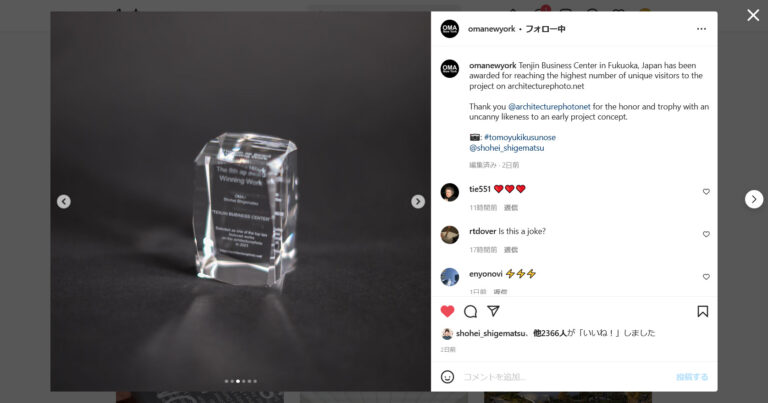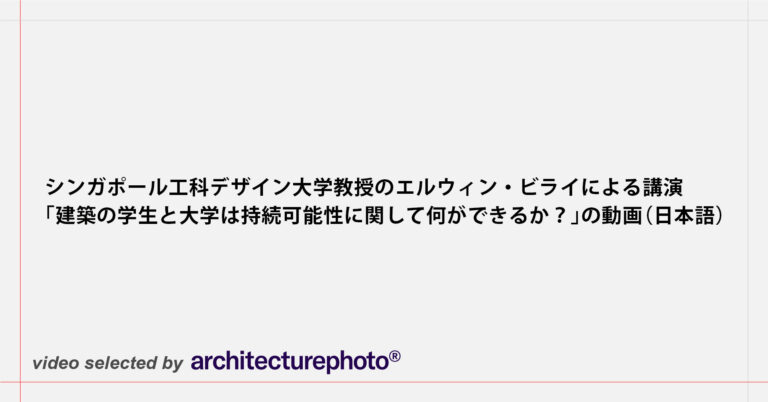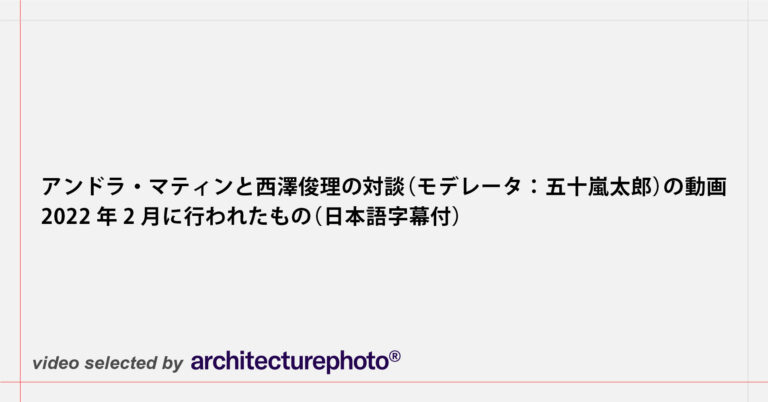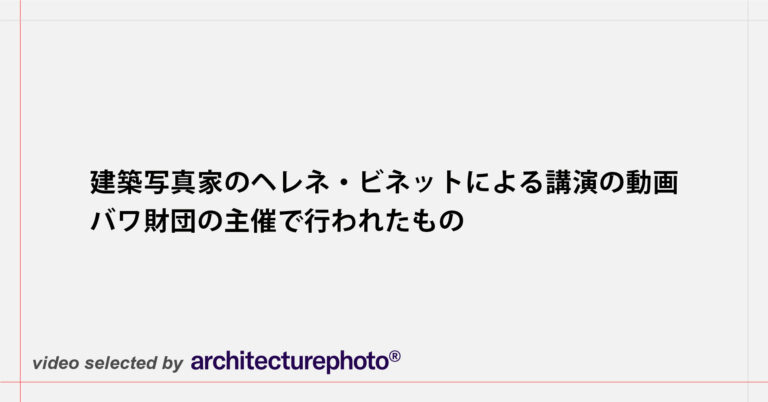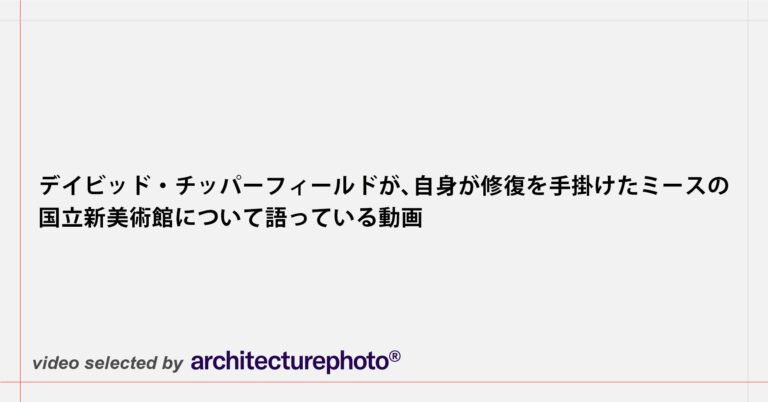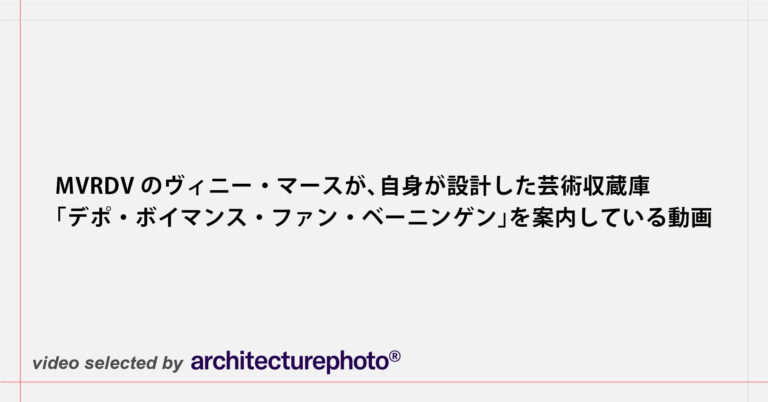OMA / レム・コールハース+デイヴィッド・ジャーノッテンの設計で完成した「台北パフォーミングアーツセンター」の動画です。写真や図版は、こちらのページで多数公開しています。
以下は、リリーステキストの翻訳の一部です。
OMA / レム・コールハース+デイヴィッド・ジャーノッテン設計の台北パフォーミングアーツセンターが竣工しました。台北の活気ある士林夜市に位置するこのコンパクトで柔軟な空間は、舞台芸術の新たな可能性を生み出す場となります。無料でアクセスできるパブリック・ループは、大衆を建物の中に招き入れ、劇場のさまざまな側面を体験させます。
建物は、球状の800席のグローブ・プレイハウス、1,500席のグランド・シアター、800席のブルー・ボックスが中央のキューブに差し込まれた構造になっています。このキューブには、3つの劇場のステージ、バックステージ、サポートスペースが収容されており、グランドシアターとブルーボックスを連結してスーパーシアターとして、工場並みの巨大な空間で、思いもよらないパフォーマンスを実現することができるのです。グローブ・プレイハウスは、ユニークなプロセニアムを持ち、舞台構成の実験が可能です。
中央のキューブは地面から持ち上げられ、景観の良い広場になります。そこから、3つの劇場の内部を見ることができるポータルウィンドウを備えたパブリック・ループが、通常は隠されている舞台芸術制作のためのインフラと空間を貫いています。
創設者のレム・コールハースは言います。
「劇場は非常に長い伝統を持っています。現代の劇場は、保守的な内部運営方針で画一化されつつあるように見受けられます。私たちは、劇場の歴史に貢献したいのです。ここ台北では、3つの客席を特殊な方法で組み合わせることができました。この建築が、劇場でできることを拡張するという意味で、どのような影響を与えるのかに興味があります」