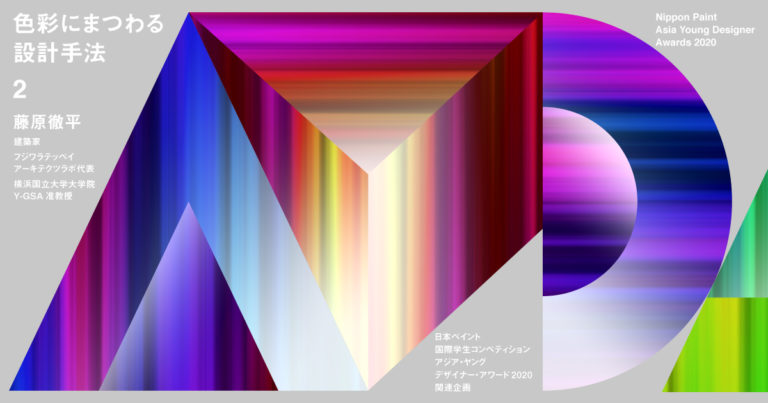日本ペイント×architecturephotoコラボレーション企画 “色彩にまつわる設計手法” / 第2回 藤原徹平・後編 「色と建築」
日本ペイント×architecturephotoコラボレーション企画 “色彩にまつわる設計手法” / 第2回 藤原徹平・後編 「色と建築」
本記事は学生国際コンペ「AYDA2020」を主催する「日本ペイント」と建築ウェブメディア「architecturephoto」のコラボレーションによる特別連載企画です。4人の建築家・デザイナー・色彩計画家による、「色」についてのエッセイを読者の皆様にお届けします。第2回目は建築家の藤原徹平氏に色彩をめぐる思考について綴っていただきました。
色と建築
text:藤原徹平
以下の写真はクリックで拡大します

日本ペイント×architecturephotoコラボレーション企画 “色彩にまつわる設計手法” / 第2回 藤原徹平・後編 「色と建築」Cuadra San Cristóbal(Luis Barragán,1968) photo courtesy of Kentaro Yamazaki
大学に入って建築を学び始めた頃、いつも何も聞かず思い付きで出張土産を買ってくる父が、色鉛筆セットを買ってきてくれたことがある。60色くらいそろった本格的なもので、それまで大学生協で買った12色セットを使っていたから、とても嬉しかった。しかしカラフルな色鉛筆セットを手にしたものの、私が学生時代に設計した建築はコンクリートとか木材とかガラスとかビニールとか、素材がむき出しになったものばかりで、建築に色をつけたことは一度もなかった。
19世紀半ば頃に始まるモダニズム建築には、それ以前の建築の在り方に比べいくつか際立った特徴がある。その1つが色彩に関するもので「白を基調とし、場合により黒や灰色を用い、あるいは材料の生地をそのまま表わす」と簡潔に定義することができる(※1)。つまりモダニズム建築とは、もっぱら白く塗るか、黒く塗るか、グレーに塗るかであり、でなければ素材のままという建築だ。学生時代に、素材を荒々しくむき出しにすることで、モダニズム建築の堅苦しさに抵抗していたつもりだったものが、俯瞰してみればそれもまさにモダニズム建築の一種だったということになる。
色について考えていくとき、考えれば考えるほど、色のことが捉えられなくなる。よく考えてみると、これは面白いことだ。生物的な仕組みからいえば、人は光の波を錐体で感じ、脳で色を認識するが、その最終的な段階に至るまでの間にも、複数の複雑で随時的な情報変換のプロセスがある。決して入力と結果というような単純な処理ではない。そのプロセスに少しの変化があることによっても、色の認識はうつろいでゆく。感じることへの集中により生じる色のうつろいを、茶室などで経験した人もいるかもしれない。
色を感じるということは、光の波の性質を通じ人が世界を微細に感じ分けているということだが、それはあくまで人が色という認識でとらえた世界の姿であり、真の世界はおそらく別の姿をしているはずだ。しかし人はそれをとらえることはできない。人は自身の感覚器官でとらえたものからしか世界を認識できないし、あらゆる物理法則も人が感じて認識できるものが思考の基盤になっている。その意味では、色彩学は物理学を生んだ母なる存在といえる。
ダヴィッド・カッツ(David Katz:1884-1953)という心理学者が人の色の感じ方を研究し、9つのモードに整理したが、その1つに「面色(film color)」というものがある。「面色(film color)」とは、主に青空のように、定位性や表面のテクスチャをはっきり知覚することができない色の見え方である。人は空によって自分たちの世界が包まれているように感じ分けているが、他の生物がそのように感じ分けているかは、まったくわからない。しかし人は空によって世界が包まれているという感じ分けができたことで、昼と夜の不思議さに気づき、その結果、天体運動の法則や他の天体の存在、宇宙の存在について認識するに至った。もしも「面色(film color)」の感じ分けを人ができなかったとしたら、こうした世界認識そのものが不可能だったのかもしれない。