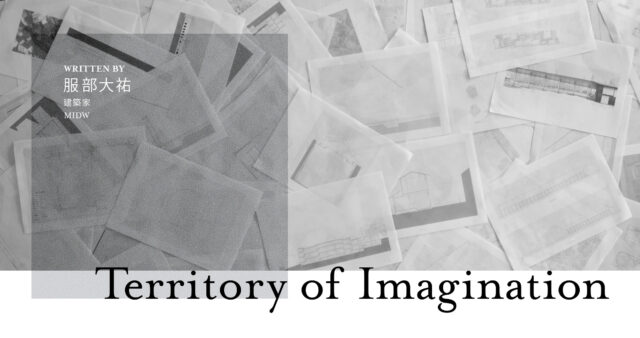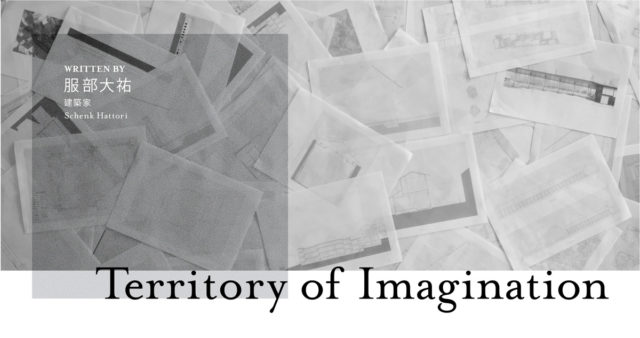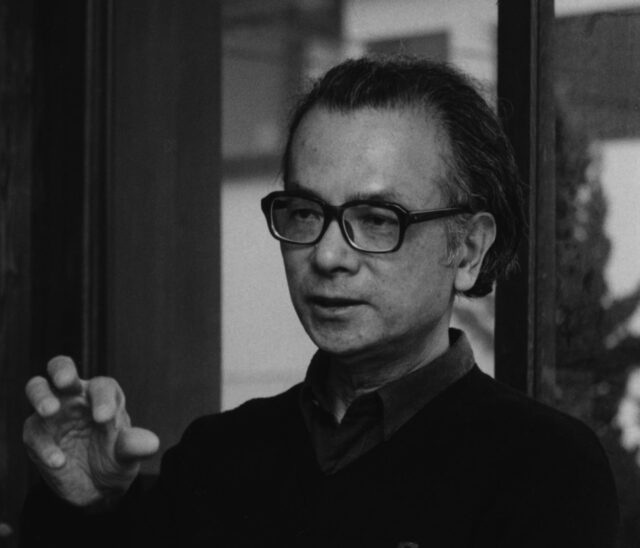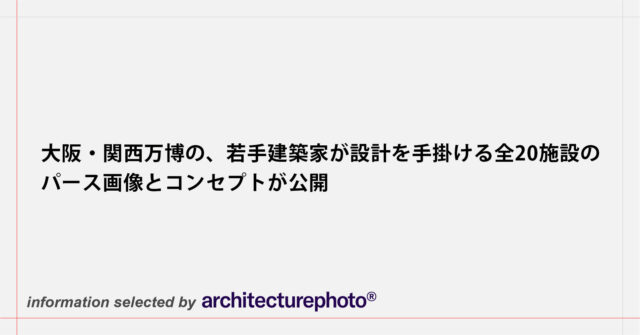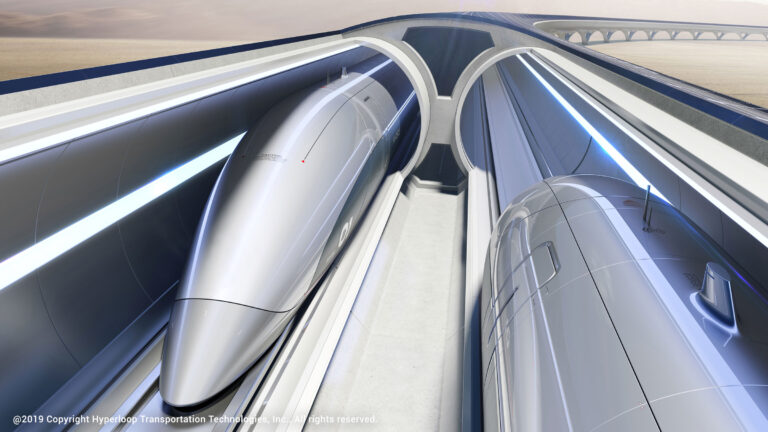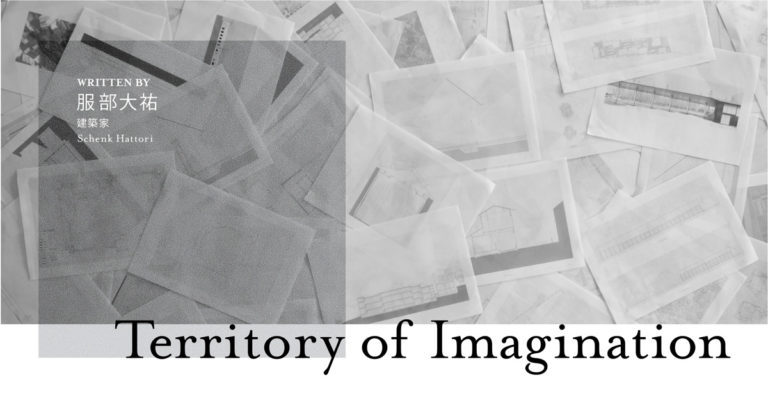
SHARE 服部大祐による連載エッセイ“Territory of Imagination” 第2回「メンドリジオでの学びとSchenk Hattoriでの近作」

メンドリジオでの学びとSchenk Hattoriでの近作
2008年に大学を卒業した後、イタリア国境にほど近いスイスのメンドリジオという田舎街に留学しました。
当初は3年程で帰るつもりでいましたが、気がつくとちょうど10年ヨーロッパで生活をしていました。その間にベルギーで事務所を始めたこともあり、日本に帰国してからも頻繁にあちらに行く生活が続いていたのですが、去年はコロナ禍の影響で再三渡航が中止となり、本当に久しぶりに1年中日本国内に居る年となりました。
こんな状況で当時のことを回想すると、割と最近のことだったはずなのに、なんだか随分昔の出来事だったような気がしてきます。そういうわけで、今回のエッセイでは、薄れゆく記憶が完全に消える前に僕が通っていたメンドリジオ建築アカデミーについて、そしてコロナ禍で進めていたプロジェクトについて書きたいと思います。
アトリエ・サージソン
僕がメンドリジオに留学を決めた理由はごくシンプルで、様々な国の第一線で活躍している建築家が何人もこの学校で教鞭を執っていたからです。「ここしかない」と思いポートフォリオを送り、周囲の助力もあり無事入学が認められました。メンドリジオはイタリア語圏に位置するので、授業は当然イタリア語で行われます。ちんぷんかんぷんな講義はほどほどに、文字通り四六時中アトリエ(※日本でいう設計製図課題)での作業に没頭する毎日を送りました。
そこまで集中出来たのは、メンドリジオが何の娯楽もない田舎街だったことや、家族のサポートを受けて留学させて貰っている気負いなどもあったとは思いますが、何よりも、本当に設計課題が面白かったからだと回想します。アトリエは選択制で、各アトリエ課題はそれぞれ建築家である教授の個性を思い切り反映した内容になっており、アトリエが変われば考え方も、アウトプットの形式も、評価の基準もまるで変わります。なので、毎学期新鮮な気持ちで取り組むことが出来るのです。
教授の個性は様々ですが、ヴァレリオ・オルジャッティの言う「アイデア」や、クイントス・ミラーの言う「参照」「メモリー」などについては、既に様々なメディアでも言及されている話なので、ここではサージソン・ベイツを共同主宰するジョナタン・サージソンについて少し説明します。
ロンドンとチューリッヒを拠点に活動している設計事務所サージソン・ベイツは、作品集も多く出版され、最近ではヨーロッパを中心に数々の巨大コンペで勝利しています。しかしその割には日本で取り上げられる頻度は少なく知名度も今ひとつのように感じます。思うにその理由は、彼らの作品が一見すると「地味」だから。
以下の写真はクリックで拡大します

学期始めの敷地調査を兼ねたアトリエトリップも、サージソンのアトリエは他の建築家のものと比べると随分と地味で、毎日延々と敷地エリアを歩いて回るというものでした。トリップ後の最初の課題も、旅行中に街で訪れたなんの変哲も無い建物のファサードを、レンガ一つ一つまで正確にドローイングさせられるといった非常な地味なものです。
以下の写真はクリックで拡大します

そんなアトリエ・サージソンですが、前回のエッセイで書いた設計における始まりの作業としての「とにかくそこにあるものを注意深く観察する」ことは、まさにこのアトリエの特徴の一つだったと言えます。
結論から言うと、実際は興味深いことをやっていたりするにも関わらず、サージソン・ベイツの作品が「地味」な印象を放つのは、この「注意深い観察」から生まれる設計上の操作が非常に繊細であるがゆえに、ぱっと見では周囲に馴染みすぎて特徴のない建物のように感じられるからです。そして、この「地味」さこそが、実は彼らがロンドンやスイスのみならず、世界各国で仕事を勝ち取っている理由の一端だとも思うのです。
アトリエでのサージソンとのやりとりの中で、一つ強く記憶に残っている出来事があります。ロンドンの小学校設計の課題を取っていた時のこと。学期終盤のテーブルクリティークの際に、1/20スケールの模型を使い、レンガ造の教室群とRC造の回廊による構成を説明していたのですが、じっと模型を覗き込んでいたサージソンがこう言いました。「軽やかな回廊とマッシブな教室群の対比関係に違和感があるので、いっそのこと全部同じ素材、似たような構造リズムで作った方がいいんじゃないかな。」
それではコンセプトが台無しだと食い下がる僕に対し、しばらく考えていたサージソンは、「コンセプトって何だろう、そんなに大事なものなのかな。私はただ、君の模型を見て素直に自分が感じ取ったことを述べたまでだよ。」とだけ説明してくれました。その返答に納得が行かず悶々としながら、後日とりあえず自分の目で確認しようと、言われた通りに模型を作り直して覗き込んでみました。「あれ、確かにこっちの方がずっといい空間だ!」と感じた時の、ちょっとしたショックと驚きの感覚は今でもよく覚えています。
以下の写真はクリックで拡大します

これは、アトリエ・サージソンだけでなく、メンドリジオの多くのアトリエに共通しているのですが、毎週のテーブルクリティークと最終講評も、基本的には図面と模型のみ、必要に応じて1、2枚のパースが求められます。そこにコンセプトダイアグラムのようなものはほとんど出番がありません。これは、模型や図面で表現されないもの、つまり空間に翻訳されない概念は、結局建築としては意味がない、といった態度の表れなのです。
個人的にも、模型や図面ですら見落とされるくらい繊細な空間的操作が、いかに僕らの知覚に作用しているか、といった事柄に興味を持っているので、そういう側面で見れば、僕もサージソンのように「地味な建築」に心惹かれる設計者の一人なのかも知れません。
無視されていた微地形を顕在化する
現在に話を戻しましょう。今、世の中は色々大変なことになっていますが、僕は元々在宅勤務だったこともあり、さほど影響を受けることもなく、ほとんど通常通り過ごしています。
仕事に関して起きた唯一の大きな問題は、アントワープの文化施設deSingelで予定されていた僕らの展示会(Schenk Hattoriとsugiberry、二事務所の合同展示)が、再三の延期を乗り越えてなんとか開催には漕ぎ着けたものの、ロックダウンの影響でほぼ誰にも見られることなく閉幕を迎えるという事態になってしまったことです。
そういうわけで、幻の展示会、という形になってしまいました。その展覧会の内容というのは、皮肉なことにも、当初展示のアイデアを出し合う中で、「建築なんだから、実際の空間体験をしてもらうのが一番分かりやすいだろう」という話をして、施設内のいずれかの場所に、作品の紹介や会期中のレクチャーイベントに使用するためのパビリオンを作るというものでした。
以下の写真はクリックで拡大します

展示施設=「場所」、数ヶ月の会期=「時間」でしか作り得ない空間・建築体験とはどういったものかと考え、施設の中庭に、地面に半分埋め込む形のパビリオンを作ることにしました。見切り発車でとりあえず穴を掘ったところ、展示予算をほとんど使い切ってしまいました。
困り果て、「そもそも予算が少なすぎるんだ。」と開き直る僕らに対し、さすがはアントワープの誇る展示会場deSingel、過去の展示やイベントに使用された廃材が大量にストックされている地下室に案内され、「ここにあるものは全てタダで使っていいよ。どうせ捨てるし。」と提案してくれました。
以下の写真はクリックで拡大します


演劇のステージバックとして使用された、建築材料としては脆弱な木製パネルを、彫り込んだ地面に差し込み、隣り合うパネル同士の端部を重ね合わせて留め付けていくことで、グラつきながらも辛うじて自立する壁面を作ります。屋根面にも同じ木製パネルを同様に留め付けることで、建物としての最低限の強度を確保します。屋根の防水には、石上純也展で使用されたビニールの床材を転用し、別の建築展で制作された版築ブロックを乗せて固定しました。
以下の写真はクリックで拡大します

人の感覚は本当に面白くて、例えば床・地面に僅かな傾斜があった場合、それが建物の内部だとすごく気になったり、「欠陥住宅だ」というような話になったりするのに、それが外部で、自然の一部として認識するだけで、途端に「概ね平坦」、といったようなものすごく大雑把な捉え方に変わります。
今回の敷地も、中庭中央に向かって下がる僅かな傾斜がついていたのですが、何もない状態だと歩いていてもほとんど気付かない程度で、実際のところ既存の施設図面には表現されておらず、いわば無いものとして無視され続けていました。
その傾斜が、中庭を横断する細長いパビリオンの水平性との対比によって初めて顕在化され、人々の意識上に立ち現れます。傾斜はパビリオン内部にも取り込まれ、端に向かうに従って地面が僅かに上がってゆき、両端では人の通れない高さにまで天井高が絞られることで、パビリオンの内外を規定しています。外部においては、中庭の中央部分、地面レベルが最も低くなっている場所に向かう方向性が生まれ、ちょうど円形劇場のような野外空間が出来上がります。ここではパビリオンの外壁が投影壁面となり、展示会関連のレクチャーイベントなどが行われる予定でした。
以下の写真はクリックで拡大します


基礎が無く直接土に触れているので、地面から生え出たような、この場所に強く根ざした存在としての印象を与えるパビリオンですが、やはり最低限以下の仕様による限界は如実に現れます。数ヶ月の間、外部環境に晒され、徐々に劣化してゆき、ついには形状を保つことが難しくなるパビリオンの存在は、この「場所」、この「時間」でしか有り得ない生の体験を強く印象付けます。
以下の写真はクリックで拡大します

均質性の中に歪みを内包するグリッドシステム
メンドリジオに留学する更に前、僕は慶應義塾湘南藤沢キャンパス(SFC)で建築を学んでいました。2017年の帰国後に、SFCの教授から「キャンパス拡張計画の一部を卒業生有志に設計させたいのだけど、参加してみたら」とお声掛けいただき、進めてきたプロジェクトが最近ようやく完成しました(設計:アーキスコープ+miCo.+POINT+Schenk Hattori+Sho Kurokawa architects)。
以下の写真はクリックで拡大します

SFCは24時間型キャンパスなのですが、例外の一部研究室を除き、必ずしも宿泊に適した環境が整っているわけではなく、年々学生のキャンパス滞在時間が減ってきている、という現状があるようです。
環境改善を図り、学生にはより積極的にキャンパスを使い倒してもらいたい、と始まったのがこの滞在型教育施設群のプロジェクトだったようで、そのうちの最後の一棟を卒業生が主宰する複数事務所の協働で設計することになりました。
コスト上の制約や既設棟との関係から、まずは木造であること、そして30人程度の学生が宿泊兼作業場として使うことが想定されていました。
驚いたことに、その具体的な使われ方については「運用が始まってから、学生が自分たちで考え、発見し、更に手を加えていく」という、自由というか放任というか、なんともSFCらしい方針だけが示されていました。
可変性と経済性を備え、ある程度のスケールを超える一室空間について考える場合、木造在来工法であれば均等グリッドを敷くところから設計を始めることが一般的だと思います。
このプロジェクトでも、全体計画における“使い方を限定しないフレキシブルな学びの場“という構想を踏まえ、壁で仕切られていない大きな空間を用意するために、グリッド状の柱による平面構成を採用しました。
また、そうして出来上がる空間の中に場所毎の性格の違いを生み出す際、間仕切りや家具といった副次的な要素にそれを委ねるのではなく、最初に設定するグリッドのシステム自体に微小な方向性や性格の変化を持たせることが出来ないか、ということを考えながら設計を進めていきました。
以下の写真はクリックで拡大します

まず、敷地形状から導かれた緩やかに湾曲するグリッドを設定し、グリッドの交点に柱を置いてゆきます。2m間隔の列柱は、グリッドの歪みよって僅かに異なる性質を持った場の連続を作り出します。さらに、床の高さを操作して室内に人工的な地形を作り、上階に建物正面の外部広場と繋がる大きなワークスペース、下階に寝室や水回りといった最低限の機能を納めます。このワークスペースに具体的な用途は定められておらず、使い手は、グリッドの歪みによって変化していく空間や、場所ごとの天井高の違い、窓からの距離などを元に、自らの感覚に従って自分の居心地が良いと感じる場を発見してゆきます。
以下の写真はクリックで拡大します

ここで、難しかったのが、グリッドを歪ませながら、如何に経済性を担保するかという点。
例えば、オフセットにより同心円上の曲線でグリッドを設定すると、柱間の距離は少しずつ変化していってしまうので、それを繋ぐ全ての梁が微妙に異なる長さになってしまいます。そうなると、施工の負担は一気に膨れ上がるので、大幅コスト増に繋がることが想定されました。そもそもグリッドシステムの採用には経済的な側面もあったので、湾曲グリッドによってコスト増になっては本末転倒です。
そのため、幾何学上の操作によって全ての柱間距離がぴったり2mになるように調整し、また、柱梁の接合部を数種類のタイプに統一することで、部材の均一性と施工の単純化を計りました。また、等間隔で立ち並ぶ柱の各面には溝スリットと穴を設け、柱間にホワイトボードを取り付けたり、ハンモックを吊るしたりと、使い手が自ら空間をカスタマイズいくための手掛かりを用意しました。
以下の写真はクリックで拡大します


周辺のコンテクストやプログラムといった与件に過度な依存をせず、自律する建築のシステムが建物内外の体験の繋がりを予見させ、そして使い手の創作の拠り所となる、そんな空間構成を目指しました。
既にあるモノを見つめ、未だ見えない風景を作る
最近釣りをするのですが、目に見えない水中の世界に対して、一本の細い糸で勝負を挑む、というのが、なんとも好奇心を掻き立てます。よく言われることですが、目の前の大物を釣ろうと糸を垂らしても、闇雲に竿を振って遠くまで飛ばしても、魚が食いつくことは無いけれど、海底の形状や潮の流れといった複雑な与件を読んで魚の居場所を予測すると、狙った獲物を釣り上げることが出来るらしいです(僕は、闇雲に投げて釣れず、綺麗な夕日に満足して「次こそは」と帰る人間ですが)。
例えが悪い気もしますが、建築設計においても、常に様々な事柄や情報が膨大な量の与件として存在しています。それらの中から、信じられるモノとそうでは無いモノを選別していき、設計の根拠となり得る確たるモノを探り当て、それに対する適した解答を与えることができた時、そこに現れる新しい風景はある種の必然性を獲得するはずです。あるいは、その場所において適切な空間的・時間的連続性と言い換えられるかもしれません。
僕がアトリエ・サージソンで学んだ、既にあるモノに対する「一見地味にも思える注意深い観察」という行為は、deSingelの水平なパビリオンが中庭の「無視されていた地形」を可視化したり、SFC滞在棟の湾曲グリッドが木造在来工法の慣習的な「均等グリッド」に変化を与えたりといった形でSchenk Hattoriでの実践に反映されています。そしてこれらの例は、その場所で見過ごされていた、あるいは未だなかった体験の可能性を取り出し、具現化するための試みと言えます。
新しい建築が何かしらの具体的な必然性を持って立ち現れることで、その体験もまた、何かしらの道筋で場所に接続し、訪れる人はその建築の存在をすんなり受け入れることが出来るようになるのです。そうすることで初めて、余計な思考に妨害されることなく感覚的に空間を体験することが可能になるのではないでしょうか。
服部大祐
1985年 横浜生まれ。2008年 慶應義塾大学環境情報学部, 神奈川 – 学部卒業。2012年 Accademia di Architettura, Mendrisio (CH) – 修士課程修了。2014年 Schenk Hattori, Antwerp (BE) / 京都 – 共同主宰。2014-15年 University Antwerp (BE) – ワークショップ講師。2016-17年 Academie van Bouwkunst, Rotterdam (NL) – 非常勤講師。2019年- 慶應義塾大学環境情報学部, 神奈川 – 非常勤講師。
■連載エッセイ“Territory of Imagination”