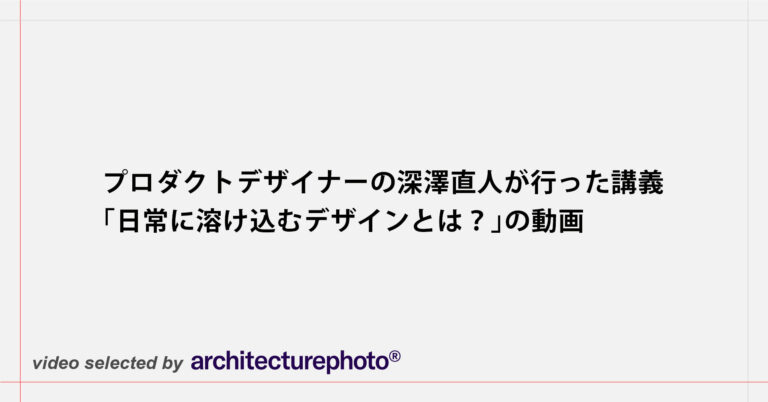SHARE 【シリーズ・建築思索360°】第4回 長坂常が語る“武蔵野美術大学16号館”と“建築思索”

「建築思索360°」は「360度カメラ RICOH THETA(リコーシータ)」と建築ウェブメディア「architecturephoto®」のコラボレーションによる特別連載企画です。現代社会のなかで、建築家として様々な試行錯誤を行い印象的な作品をつくる4組の建築家に、その作品と背景にある思索についてインタビューを行い、同時に建築・建設業界で新しいツールとして注目されているRICOH THETA活用の可能性についてもお聞きしました。さらに建築作品をRICOH THETA を用いた360度空間のバーチャルツアー「RICOH360 Tours」でもご紹介します。
建築家・デザイナーの長坂常率いるスキーマ建築計画が内装設計を担当した「武蔵野美術大学16号館」は、利用者である学生自身が作業スペースをつくり出す、長坂曰く「自走する建築」。その空間は、プラスターボードや足場用単管など剥き出しの素材が特徴的であり、学生たちが自然とものをつくりたくなる創作意欲を引き出す空間だ。この作品と、出世作ともいえる「Sayama Flat」を中心に紹介しつつ、長坂が考えるデザインと言葉の重要な関係についても語ってもらった。
※このインタビューは感染症予防の対策に配慮しながら実施・収録されました。
「自走する建築」=「武蔵野美術大学16号館」
以下の写真はクリックで拡大します

360度カメラRICOH THETA Z1で撮影・現像した画像データを埋め込み表示した、RICOH360 Toursの「武蔵野美術大学16号館」バーチャルツアー。画像内の矢印をタップすることで、空間を移動することができます。
──2021年3月に竣工した「武蔵野美術大学16号館」(以下「ムサビ16号館」)のコンセプトイメージについて長坂さんは「半建築」、「自走する建築」と説明されています。改めてこの建築について紹介していただけますでしょうか。
長坂:「ムサビ16号館」は、武蔵野美術大学の工芸工業デザイン学科と大学院造形構想研究科の学生の一部が、木材や金属を加工する作業場やデジタル作業を行う工房としてつくられた校舎です。
そもそもは将来のキャンパス計画までのつなぎとして使われる、言うなれば仮校舎の計画です。ただこれまでも仮校舎が20年ぐらい使われることがよくあったらしく、ならばローコストながらきちんとつくろうということで、プレハブメーカーの大和リースが建築本体を設計施工し、我われは内装設計とサインなどのデザイン監修を担当しました。

長坂:設計にあたって、まず既存の校舎を訪れ、雑然とした中で自分のアジトをつくっている様子が面白く印象に残りました。そこから自分の学生時代を思い出しました。当時うわべのデザインはいいから自分のつくったものが一番かっこよく見える、そしてつくりやすい場所を欲していたんです。そこで、学生たちが自分でつくる校舎という意味で「半建築」、「自走する建築」というイメージに辿り着きました。
具体的には、平面に設定したグリッド上に天井から穴のあいたレースウェイを吊り、その穴に先端を差し込んで立てる、足場用単管を転用したポールを用意しました。ポール同士の間にDIYで合板のパネルをはめれば壁になります。
レースウェイには配線ダクトを併走させ、個別にオンオフ可能なスマートライトや移動可能なリールコンセントを取り付けることによって、目的にあった空間の増減が簡単にできます。
他にもハンドリフターで移動できる棚やロッカー、つくり替えと積み重ねが可能な作業台など、学生たちが主体的に作業スペースをつくれる仕組みを用意しました。
これらのアイデアは、よく行っていたパリで見た光景がもとになっています。
というのも、パリが歴史的な建物に一切触れずに都市に豊かなアクティビティを生んでいるのが不思議で、観察したことがあるんです。すると、ベンチをハンドリフターで自由に動かしたり、マルシェのテント用ポールを立てる穴をあらかじめ地面に開けたりしていることに気付きました。
そこで、2017年の京都市立芸術大学移転設計プロポーザルでこの仕組みを元にしたアイデアを提案し、翌年の2018年にはHAY TOKYOという店舗のデザインで実現することができました。そして3年後、さらに踏み込んだ形で「ムサビ16号館」ができたというわけです。
360度カメラRICOH THETA Z1で撮影・現像した「武蔵野美術大学16号館」1階の360度画像。竣工約10カ月後。
以下の写真はクリックで拡大します











360度カメラRICOH THETA Z1で撮影・現像した「武蔵野美術大学16号館」1階の360度画像。竣工約10カ月後。
──実際に足を運ぶと、段ボールや木材といった学生が使う材料があふれた時に違和感がない空間としてつくられていることが実感できます。このような光景をある程度予測されていたのでしょうか。
長坂:いえ、必ずしも見えていたわけではありません。たぶん僕が設計できたのは、かつて学生だった頃、同じような環境で勉強していたからでしょう。もともと美術館よりつくる現場の方が面白いと思っていますから。
アトリエではゴミにしか見えないものがホワイトキューブに持っていくと突然作品に変身することは知っていますが、あくまで僕にとって宝物がある場所は、つくっている現場です。見せ方が決まったものよりまだ定まらないものの方が、インスピレーションが湧いてワクワクします。
それに、たとえ失敗することがあっても、できるまで不安な方が、うまくいった時に感動します。そういうプロジェクトこそ一番面白いんです。
答えが見えるのは、前例があるからです。「こうしたらうまくいく」というものは、途中でルーティンになって、退屈になってしまいます。
新たなデザイナーが育つ環境のデザイン
──実際に校舎を使ってみた学生からのリアクションはありましたか。
長坂:DESIGNART TOKYO 2021という都内で一斉に開催されたデザインイベントにムサビの学生が出展していたので見に行ったら、すごく嬉しそうに「楽しんで使わせてもらってます」と言ってくれました。16号館から生み出されたものを展示していて、こちらも嬉しかったですね。展示の内容も良かったです。
最初にこんな校舎をつくろうと考えた工芸工業デザイン学科の山中一宏教授のヴィジョンが校舎だけではなく学生にも伝わっているようです。
──そこまで建築が影響を与えているとしたら、すごいことですよね。長坂さんは今回新たなデザイナーが育つ仕組みというか、環境をデザインしたとも言えるわけですね。
長坂:そこまでは想像していませんでした。山中先生はもしかしたら想像していたのかもしれませんが。
振り返れば、僕らは2007年にセルフビルドでつくったHAPPAという事務所兼ギャラリーで活動を始め、TOKYO DESIGNERS WEEKやDESIGNTIDE TOKYOに出展した世代です。二俣公一、松澤 剛、藤城成貴といった人たちと同世代です。
その後の世代でコンセプトプロダクト、アートプロダクトをやろうとする子たちが見当たらないと思っていたら、同世代の山中先生が育て始めていたというわけです。
ただし当の学生たちは今ごろ「どうやって食っていくの」「騙された」と思っているかもしれません(笑)。それほど未開のジャンルで先輩がいないし、事業として成立していない。プロダクトのアートピース的な活動は、日本では全然育っていないのが実情です。
──量産プロダクトしかないということですか?
長坂:プロダクトデザイナーを目指す人は大体企業に行きますから。
でもようやく出始めてきたので、期待しています。
建築とデザインの領域を横断する
──長坂さんご自身が社会に出られた頃は、どのような状況だったのでしょう。
長坂:僕らが20代の頃はみんな「40代、50代は新人だ」「お前らはこれから地獄のように働くんだ」と言われるのが当たり前でした(笑)。そんなこと言われたらたじろぎますよね。
これは何とかしなければ、と思っているときに射してきた微かな光が、インテンショナリーズやクラインダイサムアーキテクツ、塚本由晴さん、片山正通さんといった、20代、30代で起業した建築家・デザイナーでした。
片山さんの展示を目黒の家具屋さんに見に行ったり、インテンショナリーズには同級生が入っていたから一緒に現場仕事を手伝わせてもらったりしながら、彼らの背中を見て、「こうやっていけば道が開けるかな」と思ったものです。
──先人がいたということですね。
長坂:それまでは絶対あり得ない枠だったのに彼らが横でつながって、作品も面白かったので、「この人たちに続くとしたら、独立しかないだろう」と勘違いしてしまいました(笑)。
案の定、独立した当初はやることがなくて、当時オランダで始まっていたドローグデザインの本を読んではスケッチに描き写す日々でした。
そんな憧れのデザイナーたちが何年か後に、HAPPAでドローグ展をしてくれて、オランダのロイドホテルのディレクターだったスザンヌ・オクセナーにも会えました。よりダッチデザインに近寄っていった結果、僕らもミラノサローネで発表する機会をもらえたんです。
そう考えると、今のムサビの学生たちの活動は、たまたま僕たちが引っ張った路線の延長上にいるのかもしれません。
──道を切り拓いていった建築家の系譜となっているのかもしれませんね。
長坂:もっとも、建築家の枠があるのは「ミラノサローネ」というより「ヴェネツィア・ビエンナーレ」でしょう。
ともかく、建築とデザインの領域を横断しているのが自分たちらしさであり、外側から環境をつくる側であると同時に環境の中でものをつくる側でもあると思っています。
「引く」だけで再構成するデザイン=「Sayama Flat」
──「Sayama Flat」(2008年、埼玉県狭山市)もリノベーションの文脈ですごい価値転換を起こした作品ですよね。
長坂:確かに、そういう自負はあります。
この建築は、築38年の典型的なnLDK型社宅を賃貸マンションに用途変更したリノベーションです。問題は工事費が一室あたり100万円程度という厳しい条件でした。
いちいち図面や模型を作成していたらとても予算に合わないので、まず4室をセルフビルドでつくり、その結果を見てもらい了解を得てから、残りの部屋も同じ方法でリノベーションするという手順を踏みました。
セルフビルドで不要な壁を取り除いて明るくしてみると、それだけでもかっこよくなることが分かり、そこから新規に足すことはしない、「引く」だけで再構成するデザインを思いついたわけです。
どういうことかと言うと、かつては壁で隔たれていた既存のもの同士が壁を取り除き新たに向かい合うことで、不思議にも美しく見えるんです。しかも、空間に異物を受け入れる許容力が増すというか、何がやってきても空間の一部として成立する、ある意味おおらかな空間になりました。
以下の写真はクリックで拡大します

長坂:できあがってみて、自分としてはかっこいいと思うものの、発表したら何と言われるか怖くて思案に暮れたのを覚えています。
そこで、一か八かドイツのバウハウス・アワード2008に応募したところ、たまたまローコスト建築がテーマで2位に入賞できました。日本人が自分たちの生活を背景にしながら見ると、どうしてもズレがあるというか、想像が追いついていかないところですが、外国人は無責任に楽しめたのでしょう。
一方、入居者の募集では、住人が自分で改修してもいいというルールをつくったところ、全国から変わり者が集まってすぐに埋まってしまいました。ただ残念ながら、後々転売され、普通のマンションに改修されてしまったようです。
──それだけ問題作だったんですね。古いものと新しいものを対比させるデザインが一般化したのは「Sayama Flat」以後じゃないでしょうか。
長坂:そう思います。僕らは勢いに乗ってリノベーションを続けましたが、スラブが剥き出しの天井を見たクライアントから「こんなところじゃ寝られない」と怒られることも度々ありました。そのせいか2009年に奥沢の家ができた後は商業系の仕事が続き、住宅の仕事はしばらく来ませんでした。
それがふとした時に住宅設計の依頼メールが来て、「作品集の『B面がA面にかわるとき』(鹿島出版会)を読んで感激しました」と書かれてあるんです。どんな人が来るのかと思えば普通の夫婦だったので驚きました。
自分が言っていることは間違っていないと確信するものの、世の中も変わったと思ったものです。それが「鳩ケ谷の家」(2015年、埼玉県川口市)のクライアントでした。
「まかない家具」とB面の魅力について
──建築やデザインの領域でも、既存の流れやルールを踏襲するアプローチは多いように思います。もちろんそれは手段のひとつですが、一方で長坂さんは果敢にルールチェンジを試みているように見えるんです。「まかない家具」もそのような印象を受けました。
長坂:「まかない家具」とは、現場で大工さんなど職方の人たちが端材などあり合わせの材料で手間をかけずにつくっている家具を僕らなりに言い表した名称です。
角材を相欠きで組んでベニヤをのせた作業台や道具置き場など、人に見せるためにつくっているわけではないので、機能的かつ必要最低限な加工が実に素っ気なくて、逆に気になり出しました。
海外の現場でも似たものを見かけますが、コストの考え方やその場にある材料が違うので、国ごとに様子が違います。それがまた面白くて、中国とか韓国で見かけるたびに撮っていた写真を家具チームのスタッフに見せ、「これ何て言うんだと思う?」と聞いたら「まかない家具じゃないですか」という答えが返ってきました。
以下の写真はクリックで拡大します

長坂:その言葉がスコンと入ってきて、自分たちなりにつくり、事務所の1階で展示したのが2020年10月の「まかない家具展」です。このネーミングがなければ、家具のジャンルとして立ち上げないままスルーしたかもしれません。
だから、必ずしも新しいことを提示しているわけではありません。設計者だったら現場で「あの家具いいな」と思っているはずだけど、誰も言わなかったということだと思います。
「Sayama Flat」も同様です。
たぶん藝大生だったら知っているというか、僕らが学生だった頃は谷中のボロい木賃アパートで何も言われないから天井を壊して、押し入れを壊して、自分のアジトをつくっていました。これがどんなきれいなアパートよりもかっこいいのはみんな知っていましたから。
そのくせ卒業したら、よそゆきのきれいな仕事をするので世の中には認知されず、たまたま僕が作品だと言ったから新しいと言われただけなんです。
伊東豊雄さんの事務所に行って独立した中山英之だって知っていたはずですから。
──確か、不動産会社の社長さんが「HAPPA」を見て「こういう感じがいいんだよね」「これかっこいいじゃない」と言って依頼してきたのが「Sayama Flat」の始まりだったと聞きました。作品集『B面がA面にかわるとき』でいうところのB面の魅力を象徴するエピソードですね。
長坂:そうですね。当時は妹島和世さんも小川晋一さんも白い建築ばかり設計されていたので、「HAPPA」のようなデザインは許されないと思っていました。馬場正尊さんのリノベーションも全部真っ白でしたから、自分もその流れに乗ってよそゆきの仕事をしていました。
それが「HAPPA」は自分が使う場所を初めてデザインすることになって、予算に限りがあるし、心から必要だと思うことだけを正直にやらざるを得なかった。でもそれを「Sayama Flat」のオーナーは気に入ってくれたんです。
でも今だって、何でもかんでも好き勝手にやっているわけではありません。よそゆきの仕事も当然していますよ。
短い言葉で説明できないとデザインにならない

──長坂さんは「半建築」、「自走する建築」、「まかない家具」と、短い言葉でデザインを説明されます。長いコンセプトで語るよりも一瞬の言葉で撃ち抜こうと意識しているのでしょうか。
長坂:言葉を使うのはそれほど得意ではありません。でも説明とデザインが一致していることが大事だと、よく言っています。しかも、100字か200字ぐらいで言い当てられないとデザインになりません。
──デザインにならない、というのはどういうことですか。
長坂:たとえば「『引く』だけで再構成するデザイン」と説明できなければ「Sayama Flat」は成立しませんでした。
DESCENTE BLANCの一連の店舗デザインで言うと、「在庫を取りに行かないでその場で上から在庫が降りてきたら、お客さんが逃げなくていいよね」と。この説明ができて初めて昇降式のハンガーが降りてくるアイデアが実現するんです。
的確に求めているものを言えるとそれが形になるし、できあがりが分かりやすいですから。
──プロジェクトの過程でもそういった言葉が見つかることが判断基準になるのでしょうか。
長坂:そうですね。複雑でなく、できるだけシンプルに、ここが面白い、ここが新しい、と言い当てられないと、延々と悶々とします。
僕がよく言う「知の更新」と同じで、それが分かった瞬間にデザインが生まれると思っています。「何かいい感じだよね」とか「爽やかだね」としか言いようのない、雰囲気だけの作品はつくりたくありません。
若い頃に憧れたダッチデザインもものすごく分かりやすくて、何を意図してつくっているかがかなり明確です。ドローグデザインなんてまさにそうです。その影響があるのかもしれません。
「見えない開発」=「ARARIO Tapdong project」
──「D&DEPARTMENT JEJU by ARARIO」(2020年、韓国済州島)をはじめとする済州島の開発プロジェクト「ARARIO Tapdong project」では「見えない開発」という言葉を使われていますね。
長坂:この言葉が見つかるまでは悩みました。ナガオカケンメイという手強い大先輩とのコミュニケーションから物事が決まっていく中で、どうやって説明していいのか全然分からない。しかもクライアントであるARARIOのキム・チャンイル会長からは「これもお願いしたい」「あれもお願いしたい」とリクエストが次々に飛んでくるわけです。
ポイントは街に点在する3~4戸の建物をつなぎ止めるルールであり、この街を変えていくきっかけをつくらなければいけないと思っていました。
ちょうどその頃、たまたま大学の設計課題の講評会に参加したところ、ある学生が大久保の辺りを敷地に設定したプロジェクトを発表していました。それは4箇所ぐらい敷地が離れた建物を改修する設定で、模型ではそのコンセプトが全然見えなくて先生たちに「これじゃ駄目だよ」言われていました。
僕としては、体験したらきっと面白いだろうけど、どう言えば援護射撃になるだろうと考えた瞬間、まさに自分が悩んでいることと一緒だと気づきました。
だったら、見えないことをそのまま言えないかと思って「見えない開発」という言葉をつくったんです。「開発」をつけたら「見えない」もいい言葉になるなと。
以下の写真はクリックで拡大します


──逆説的なものが接続されているから、意外性があってインパクトがありますね。
長坂:そもそもこのプロジェクトが面白いのは、ほとんど人がいない街だったので物件ごとの価格がとても安く、日本の開発業者ならまとめて開発しそうなところを、あえて数件づつ手に入れては改修するという点にあります。とはいえ3~4戸を同時に改修するとなると、やはり街に対するステイトメントを表明する必要がありました。
それが「見えない開発」という言葉になったことで、道がパッと開けたんです。
外から見えないのが逆にいいのだから、頑張って色を変えなくてもいい。実際はD&DEPARTMENTの外壁に結構手が入っていたりしますが。
──計画の指針が竣工した後もキャッチコピーのようになっているのが面白いですね。
長坂:はい。ある土地でくすぶっている問題は大体よそでも起こっているので、そこをうまく言い当てられると、別の場所にもつながっていくものです。
「Sayama Flat」以降、肩ひじ張らずに考えてもいいと知って、いたってどこにでもある問題に対応するようになりました。大げさに考えず、身の丈で物事を整理していくと、実はそれほど難しくないのだなと。
──長坂さんは本当に体感して分かる形で答えを出してくださるので、いよいよ街づくりに本格的に携わるというので、すごくワクワクして見守っている人が多いと思います。
長坂:ありがとうございます。
コロナ禍になって以来、本当に手を動かしてものをつくっています。「まかない家具」もそうですし、事務所の改修もそうです。直接手を動かしながら得た実感を他者に提示できるところまで落とし込むことを、常に意識しています。
建築なら何となく煙に巻いたままうやむやにできても、家具は幅広い層の人たちが使うという良し悪しがわかりやすいものだから、はっきりと評価されてしまいます。街も一緒なので、とてもやりがいのある仕事だと思っています。
「顔のない建築」をどう伝えるか
──「ムサビ16号館」について、現在の使われ方に建築的意味があることをどうにかして伝えようと腐心されていると聞きました。
長坂:その辺は結構ジレンマで、たとえば「桑原商店」(2018年、東京都品川区)という酒屋のデザインや「ムサビ16号館」は、海外ではなかなか受け入れられません。
──ヴィジュアル的にということでしょうか。
長坂:僕らが伝え方を分かっていないんだと思うんです。
たとえば「Blue Bottle Coffee Kyoto Café」(2018年、京都市左京区)や「LIM, loji」(2021年、大阪市中央区)というヘアサロンのリノベーションを僕は「顔のある建築」と言っていて、文脈的に評価が得られやすい。
でも、「ムサビ16号館」のような、いわば「顔のない建築」は1枚や2枚の写真で「面白いね」とは分かってもらえません。竣工したてで写真を撮っても、その面白さは伝わらないんです。
以下の写真はクリックで拡大します


──新しいことを伝えるには、伝え方の開発もセットでないといけないんですね。
長坂:そうです。「半建築」という言葉も非常に伝わりにくい。
ただ中国のような同じ漢字を使っている人たちには何とか通じます。その辺りの限界はよく分かっていますが、どうやって突破したらいいか悩んでいる最中です。
ウェブサイトは何で伝えるのか
──スキーマ建築計画のウェブサイト(http://schemata.jp/)は、各プロジェクトの写真や図面、テキストをDropboxでダウンロードでき、何かに使ったら報告すればいいというスタイルが日本の建築家としては実に先駆的です。今、海外の設計事務所、たとえばMVRDVもそのスタイルに移行していますよね。
長坂:表現者という立場に自覚がある人であればあるほど、伝え方は大事です。
「いいものをつくっているから何とかなる」ではなく、しかも僕みたいに泥臭い活動の仕方だと、全部セルフプロデュースでやらないといけません。
今でもウェブサイトのあり方はこれでいいのか、すごく悩みます。本当に写真なのか、何で伝えたらいいのかと考えているところです。
──最近Instagramに制作プロセスの動画を投稿しだしたのはそういう理由でしたか。
長坂:本当につくっている様子を見せないと伝わらないことがありますから。使ったことがなかったアプリの使い方を覚えて自分でつくっています。
東京の水辺空間を豊かにしよう
──動画でSUPに興じる様子も撮られていますね。
長坂:ヴェネツィアでも神田川でも乗りました。都内では前例がなく水上のルールがないので、どこでも乗れます。もちろん私有地を横断すると問題になるし「この航路は並走しないでください」とは言われます。
ただ東京では着水する場所を見つけるのが難しいので、相当リサーチが必要です。
──その話も、長坂さんらしいですね。
長坂:僕らは、ただの川遊びでは終わらせません。将来的には、海か川のプロジェクトを実現したいですね。
リサーチする中で気づいたのですが、時代の変遷で水辺の捉え方が変わっているようです。
神田川辺りは、かつて相当水が汚かったからか全部ビルが水辺に背を向けているのに対して、東京湾ではベイエリアという言葉があるように、建物が水辺の方を向いています。
ヴェネツィアの建物であれば、みんな川に向けた視線をちゃんと意識してつくっていますから、水辺の空間は豊かです。
都内の川も今はきれいになりつつありますから、現状は変えられるはずです。
特に墨田区のように川が張り巡らされているエリアは、川のルートを使えば、かなりいろいろなところに行けます。
可能性はいっぱいあるので、もったいないと思います。
スタッフのキャラクターを活かしたフレキシブルな事務所運営
──長坂さんは小規模の事務所から活動を始めて、少しずつスタッフが増えてきたとうかがっています。今はどのようなスタイルで事務所を運営されているのでしょうか。
長坂:今は正社員がトータルで25人ぐらいいます。そのうち設計スタッフが20人ぐらいです。
以前は設計スタッフを幾つかのチームに分けて仕事を割り振っていました。それが2015年頃からBlue Bottle Coffeeの店舗デザインなど仕事が増えたタイミングでチームのリーダー格が1人辞めることになり、後釜が見つからなかったので、仕方なくいったんバラして個々のプロジェクトに応じて担当を決めていました。しかし2020年辺りから人数が多くて対応しきれなくなったので、再びチーム制を復活させました。
ただどのチームにも同じルールを適用すると不具合が出ることが次第に分かってきました。
僕1人ですべてのプロジェクトについてお金の処理も含めて一から面倒を見るわけにはいかず、しかもスタッフやチームの特性によって僕が立ち入る度合いを変える必要があるので、個々の意向や特性を考えて「この人はここまでやるけどこの人はここまで」というラインを見極めるようにしています。よってチームの人数も、6人、3人、2人、1人といった具合に偏っています。
──スタッフの個性を見出しつつそこに長坂さんが関わっていくという仕組みがスキーマの創造性の原動力になっているのでしょうか。
長坂:自分のつくりたいものだけをつくるのであれば小さい組織の方がやりやすいのは確かです。しかし規模が大きくて面白い仕事もありますから、それにはある程度の人数がいないと対応できません。
具体的に何人が適切なのかは何とも言えませんが、時代が変わるなかで多様な状態を受け入れていかないと、もはや頑丈な奴らだけがやっていける時代ではありません。
よく例に出すのですが、突出して強いキャラクターがいる『ドラゴンボール』ではなく、多種多様なキャラクターが集まった『ONE PIECE』のような組織がいいのではないかと。
それをどうすれば実現できるか、いつも悩んでいます。
──長坂さんの役割は、スケッチを所員に渡して図面を描かせるようなトップダウンではなく、チーム運営の状況と作品としてのクオリティを同時にチェックするわけですね。
長坂:そうです。今や全部ひっくるめて一つの作品ですから。単純に巨匠をスタッフみんなで支えますという時代はさすがに終わりでしょう。
──チーム制をさらに推し進めた場合、長坂常という名前は作品のクレジットに出続けるのでしょうか。
ちなみに西田司さんのオンデザインパートナーズでは担当者の名前を全部出すようにしているようです。
長坂:西田さんは上手にやられていると思います。もともとチームで出発したからできるのでしょうか。
我われもクレジットに担当者の名前を入れようかと考えたりしますが、ほぼほぼ一人で始めた事務所なので、そう簡単には決められません。当然ながら建築の設計には責任が伴うので、事務所を代表して責任を取れる人間の名前を入れる必要がありますから。
──もはや長坂さんがブランドなので、併記するパートナーもブランド化して、その名前で仕事が得られる状況が望ましいのでしょうか。
長坂:客観的にどうあったら面白いのでしょう。僕は単純に好きなことをやりたいだけで、組織の面倒を全部見るのがしんどいのは確かです。どなたかにご指導いただきたいところです(笑)。
──スタッフの独立についてはどうお考えですか。独立したいなら、させてあげた方が本人にとって幸せな気がする反面、独立しないで共同設計者として一緒にいてもらう方が、その人にとっても事務所にとってもいい場合があります。
たとえば、以前の青木淳さんの事務所は、スタッフ1人が1物件を担当するスタイルをとり在籍4年で卒業する仕組みを構築していて建築業界では広く知られていましたよね。そこには、新陳代謝して新しいものができるという意図もあったようです。一方、OMAではOMA/重松象平という表記の仕方をして組織の一員である重松さんを前面に出しています。
長坂:スタッフにとって独立のメリットは、やはり自分で責任を持てることです。
しかもリフレッシュというか、軌道修正を図るいい機会になります。
ただし時代的にみて、今のスタッフが全員独立した後でスキーマと同じような組織を構えられるとは限りません。いざ独立した後で「やはり組織にいた方が良かった」と思わなければいいのですけどね。
OMAのように組織が大きくて、一つひとつのプロジェクトの規模も大きければ、デザイナーがそれなりに責任をとりつつ自由に動くことも可能なのですが。その辺りをどうすればいいのか、まだ模索中です。
360度カメラRICOH THETAを設計者が使いこなすには
──長坂さんやスタッフのみなさんは360度カメラRICOH THETA(リコー シータ)が建築設計の現場においてどのような可能性を持っているとお考えでしょうか。(株)リコーTHETA マーケティング担当の平川さんと一緒にお聞きしたいと思います。
平川:現在の「ムサビ16号館」の様子をバーチャルツアーでご覧になっていかがですか。
長坂:学生さんが使い倒している様子が、リアルですね(笑)。
平川:THETAは建設DXの分野でもここ数年かなり広く使われるようになり、施工中の現場で撮った360度写真によって関係者間における進捗状況の共有化に役立てていただいています。
ところで、コロナ禍で海外の現場に行くことが難しいなか、先日お話しいただいた韓国の「見えない開発」が引き続き進行中とうかがいました。どのように進められていらっしゃいますか。
宮下(スキーマ建築計画):コロナ禍で海外に行くことが難しくなり、この1年間以上は韓国の現場に直接確認に行くことができなくなりました。そのため、ミーティングは全部オンラインです。月に1回オンラインでミーティングの場を設け、週に1回は韓国の施工会社に進捗状況のレポートを提出してもらい、社内でチェックしたものを送り返して反映してもらうというペースです。
ただ複雑な調整が必要な場合は現場に行くことも検討します。
平川:現在THETAを、韓国側の現場でも使い始めていただいていると伺いました。
宮下:韓国側の施工会社に、THETAで撮影した現場の360度画像を共有してもらうよう、依頼しています。そのまま360度画像のデータで共有してもらうか、現場の図面と画像を紐づけたかたちで共有可能なツールの活用(RICOH360 Projects)を検討しています。
以下の写真はクリックで拡大します



平川:THETAを活用していただいている建築業界の方からは、通常のカメラの撮影だと後で取りこぼしに気が付くことが多々あるので、360度カメラを現調時や施工中の現場の確認時に併用しているという声を伺っています。現場が遠隔地でなかなか足を運べない状況でプロジェクトを進めるのは大変だと思いますが、日頃どのように対処されているのでしょうか。
長坂:おっしゃる通り、設計図面を描く過程では均等に考えていても、写真を撮り忘れる場面が往々にしてあります。
怖いのは、情報が足りていない時に限って、間違いに気付かないということです。実際、9月にミラノサローネで出品するために久しぶりに行ったら、現場で想定と食い違っていることが相当ありました。
リノベーションも一緒で、一通り撮ったり実測したりしているつもりでも、どこかで偏って見ているのでしょう。実測した内容を図面に起こす段階で抜けに気づくことがあります。
それに対して360度カメラは、頭の中で平面図に引いたグリッド線に従って等ピッチで撮る感覚に近いのかもしれません。
宮下:確かに現場調査や現場管理には便利そうですね。
長坂:現場監督が気になっているディテールの写真ばかり送られてきても困りますから。
おそらく360度カメラが補えることは多いと思います。さらには現場だから得られるイマジネーションやアイデアを、カメラを通して得られたら、なお素晴らしいですね。
長坂:もしTHETAで撮影したときに、その場の360度の空間を測量できたら本当に助かります。そこまで精度が高くなくても、最初の現場調査でSketchUpで絵が描けるくらいの寸法を取ることができたら、画期的ですね。
平川:そのようなお声は多くいただいています。最近海外などでは、THETAを活用して360度の測量に活用するようなシステムも見かけるようになりました。
長坂:面白い使い方として、たとえば模型の中に入ってぐるっと見回したりできませんか。
平川:模型がカメラを入れられる大きさであれば撮れます。
長坂:僕は個人的に美術館など見せるための場所よりも、つくっている場に興味があります。そういう場ってゴミと作品が混在していて、解釈次第でゴミが作品になるかもしれないし、つくり掛けのものから未来を想像させてくれたり、多様に想像を広げてくれて、個人的には大好きなのです。
その点からしたら、この360度カメラで16号館内をヴァーチャルツアーし、ゴミと思って見ていたものに突然フォーカスされ、それが作品のように見え出し、あたかも美術館のようにそれを鑑賞できたり。時に模型を見つけ、そこに近づき、さらに中に入ることでリアルにその場を体験できたりしたら、リアル空間と模型空間、作品とゴミの間を行き来できて、とても面白い体験ができそうですよね。
──一瞬でアイデアの話につながるのが、さすが長坂さんですね。
長坂:日々新たなアイデアを模索しながら楽しんでいるので。
平川:確かに楽しそうです。そのような使い方で言いますと、THETAで撮影した360度画像を、より立体的な3Dバーチャル空間の制作に活用される事例も増えています。
空間に携わる業界の方には今後もいろいろな場面で活用していただきたいと思っております。貴重なお話をどうもありがとうございました。
(企画・インタビュー:後藤連平・矢野優美子/文章構成:矢野優美子・中村謙太郎)
長坂常(ながさか じょう)
1998年東京藝術大学卒業後スタジオを立ち上げ、のちにスキーマ建築計画に改称。2007年にシェアオフィス「HAPPA」を設立。家具から建築まで幅広く手掛け、1/1のスケールを意識した設計を行う。国内外でジャンルを問わず活動の場を広げている。
■建築概要
武蔵野美術大学 16号館
設計:長坂常/スキーマ建築計画
建築施工:大和リース
内装施工:TANK
サイン計画協力:Village
用途:教育施設
所在地:東京都小平市小川町1-736
構造:鉄骨造 地上3階建
建築面積:1178㎡
延床面積:3444㎡
竣工:2021年3月
■シリーズ・建築思索360°のアーカイブ