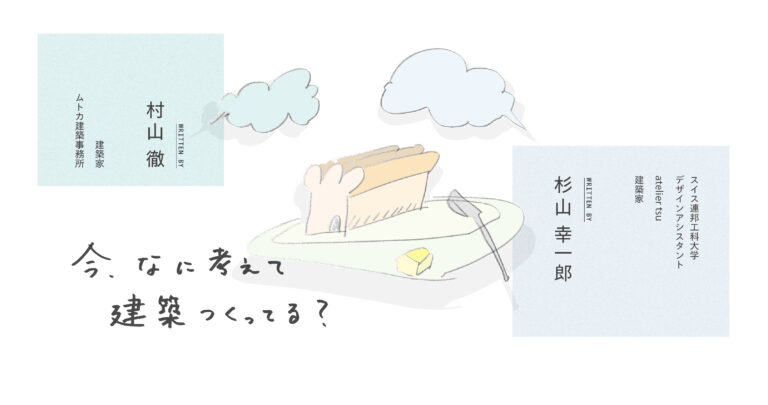SHARE DDAAとSOUP DESIGN Architectureによる、長崎・波佐見町の「HIROPPA」。企業が立ち上げた広場・店舗・カフェからなる施設で、“自然な賑わいが生まれる場”の要望に対して様々に解釈可能な“地面”をデザイン、特殊なランドスケープも組み合わせ“原っぱ”と“遊園地”の両立を試みる




元木大輔 / DDAAと土井伸朗 / SOUP DESIGN Architectureによる、長崎・波佐見町の、複合施設「HIROPPA」。企業が立ち上げた広場・店舗・カフェからなる施設で、“自然な賑わいが生まれる場”の要望に対して様々に解釈可能な“地面”をデザイン、特殊なランドスケープも組み合わせ“原っぱ”と“遊園地”の両立を試みました。施設の公式サイトはこちら。
ヒロッパは、長崎県波佐見町で磁器を企画製造する企業・マルヒロが立ち上げた、広さ4,000平方メートルほどの施設。いただいたオーダーは、「県外から訪れる焼物ファンだけでなく、地元の住民や子どもたちも集まるような、自然な賑わいが生まれる場をつくりたい」というものだった。「ヒロッパ」という最高な名前をつけたのはマルヒロの方々だったが、「広場」や「原っぱ」のような響きもあって、この空間にぴったりなように感じた。まさに「原っぱ」の考え方でこの施設をデザインしていきたいと思ったのを覚えている。
ヒロッパでは、こうした「遊園地」的なつくられ方のあまりよくない側面を避け、なんとかして遊具の新しい形式を発明できないかと試行錯誤した。しかし結局、安全基準のために、最終的にはお決まりの遊具に収束してしまった。
そこで、新しい遊具を考えるのは一旦ストップして、できるだけ根源的な状況から考え直してみることにした。たとえば、すべり台をつくるのであれば、「滑ると楽しい」という本質的で根源的なコンセプトないし気づきからスタートする。そこから、「滑る」を何か別の状況で再現できないかと考える。遊びとは遊具の形によって決められた行為ではなく、「目的もないのに楽しい」という事実を発見した時に生まれるものだったはずだ。
最終的に僕たちがデザインしたのは、遊具というよりも「地面」そのものだった。人が腰かけたり、滑ったりするための「きっかけ」を地面に与えてみたのだ。たとえば、土を盛って斜面をつくりつつ、その上部に日陰をつくるためのパーゴラ(植物を絡ませられる日陰棚)も設置する。傾斜地を下ったところには、廃品の陶器を細かく砕いた砂を敷き詰め、砂遊びができるビーチを設けた。浅く水を貯めれば波打ち際のようなじゃぶじゃぶ池もつくれるし、夏には水をたくさん貯めて水遊びもできる。
「地面の操作」というアイデアに至った経緯としては、遊具の制作費が思いのほか高く、土の移動だけで済むやり方がコスト上とても有利だったという現実的な事情もありつつ、「遊具のある公園」よりももう少しプリミティブな広場を考えてみたいと思ったことが大きい。地形に様々な特徴を与えることで、広場そのものに対して、様々に解釈可能な「原っぱ」として質を持たせたいと思ったのだ。
HIROPPAの広場
以下の写真はクリックで拡大します













建築家によるテキスト
僕たちが興味をもっているのは「いかに多様な使い方ができる未完成品=いい原っぱをつくれるか」ということだ。可能なら、そこにプロダクトとしての完成度、つまり「いい遊園地」性も求めたい。ただの「原っぱ」だと、利用者がばらばらに遊んでいるだけで全体性が乏しくなってしまう。やはり、何らかの体験の質をデザインするような作為がそこにはあって欲しい。「いい遊園地」の役割は、「原っぱ」の参加可能性に導かれた人々にとってのロールモデルとして機能することだと思う。とはいえ、それが「原っぱ」のよさである自由を阻害するものであってはならない。そのバランスをいかに取るかが、これからの課題になる。
そんなことを考えながら取り組んだプロジェクトが、広場、店舗、カフェで構成された複合施設「ヒロッパ」の総合計画だ。ヒロッパは、長崎県波佐見町で磁器を企画製造する企業・マルヒロが立ち上げた、広さ4,000平方メートルほどの施設。いただいたオーダーは、「県外から訪れる焼物ファンだけでなく、地元の住民や子どもたちも集まるような、自然な賑わいが生まれる場をつくりたい」というものだった。「ヒロッパ」という最高な名前をつけたのはマルヒロの方々だったが、「広場」や「原っぱ」のような響きもあって、この空間にぴったりなように感じた。まさに「原っぱ」の考え方でこの施設をデザインしていきたいと思ったのを覚えている。
とはいえ、プロジェクト開始当初から「原っぱ」的につくろうと思えていたわけではなく、遠回りのスタディもたくさん行った。最初は「原っぱ」ではなく、公園と遊具をつくろうとしてしまったのだ。
なぜ公園と遊具ではだめなのか。すでに批判され尽くしているきらいもあるが、現代の多くの公園には、注意書きの書かれた看板がいくつも立てられている。コンセプチュアル・アートかなと思うほどに、ほとんどすべての行為が禁止されている公園も存在する。また、公園に置かれる遊具にも様々な制約が課せられていて、事故が起こるたびに業界内で新たな安全基準が設けられている。危険と判断された遊具は撤去され、次につくられる公園や広場では採用されなくなっていってしまうのだ。この安全基準においては、ブランコは「揺動系遊具」、シーソーは「上下動系遊具」といったように、遊具はカテゴリーで分類されている。柵はこうしましょう、金具はこれを使いましょうといった制限もカテゴリーごとに定められる。こうして「この遊具はこのように遊ぶ」というルールが先行して決められてしまうと、遊びは形骸化して画一的なものになってしまう。なのでヒロッパでは、こうした「遊園地」的なつくられ方のあまりよくない側面を避け、なんとかして遊具の新しい形式を発明できないかと試行錯誤した。しかし結局、安全基準のために、最終的にはお決まりの遊具に収束してしまった。
そこで、新しい遊具を考えるのは一旦ストップして、できるだけ根源的な状況から考え直してみることにした。たとえば、すべり台をつくるのであれば、「滑ると楽しい」という本質的で根源的なコンセプトないし気づきからスタートする。そこから、「滑る」を何か別の状況で再現できないかと考える。遊びとは遊具の形によって決められた行為ではなく、「目的もないのに楽しい」という事実を発見した時に生まれるものだったはずだ。
最終的に僕たちがデザインしたのは、遊具というよりも「地面」そのものだった。人が腰かけたり、滑ったりするための「きっかけ」を地面に与えてみたのだ。たとえば、土を盛って斜面をつくりつつ、その上部に日陰をつくるためのパーゴラ(植物を絡ませられる日陰棚)も設置する。傾斜地を下ったところには、廃品の陶器を細かく砕いた砂を敷き詰め、砂遊びができるビーチを設けた。浅く水を貯めれば波打ち際のようなじゃぶじゃぶ池もつくれるし、夏には水をたくさん貯めて水遊びもできる。
「地面の操作」というアイデアに至った経緯としては、遊具の制作費が思いのほか高く、土の移動だけで済むやり方がコスト上とても有利だったという現実的な事情もありつつ、「遊具のある公園」よりももう少しプリミティブな広場を考えてみたいと思ったことが大きい。地形に様々な特徴を与えることで、広場そのものに対して、様々に解釈可能な「原っぱ」として質を持たせたいと思ったのだ。
また一方、風景を引いてみた時には、不自然に直線的な稜線や、グラデーション状に機能が変わる斜面、ベンチとして使える真っ赤な三角形の穴など、自然の中ではあり得ない特殊なランドスケープが浮かび上がるようにデザインしている。この部分については、「遊園地」的なデザインも意識した。ヒロッパ自体もまだ完成というわけではなく、現代進行形のプロジェクトで、今後も様々な使い方や施設が追加されていく計画がある。竣工して完成ではなく、ここからまた変化していくことを前提にしており、増改築にも対応可能なつくりになっている。この点はアアルトの分散型規格化に大いに影響を受けており、つまりヒロッパは、ここまでに議論してきたような内容をすべて詰め込んだプロジェクトともいえるだろう。
これからのプロジェクトにおいても、「遊園地」と「原っぱ」を両立するようなあり方を探していきたい。言い換えれば、プラットフォームかコンテンツかどちらかだけを設計するのではなく、どちらもつくりたいということだ。みんながおのおの好き勝手に過ごしているのに、全体性が失われていない状態。高い質が確保されているのに、参加可能性が残されている状態。要するに、Stool 60のような状態を目指したい。
『元木大輔/ DDAA LAB Hackanility of the Stoo スツールの改変可能性』より抜粋
■概要
施主:マルヒロ
所在地:長崎県波佐見町
用途:広場
建築設計:DDAA / SOUP DESIGN Architecture
プロジェクトチーム:元木大輔 / 村井陸 (DDAA) / 土井伸朗 (SOUP DESIGN Architecture)
構造設計:yasuhirokaneda STRUCTURE
施工:上山建設、西海園芸
構造:木造
敷地面積:3947.99m²
延床面積:2727.96m²
竣工:2021年8月
撮影:長谷川健太
HIROPPAの建築(店舗・カフェ)
以下の写真はクリックで拡大します













建築家によるテキスト
完成しない、ということに興味がある。建築に限らず、プロダクトからランドスケープまで、竣工や完成をピークとするのではなく、その後の更新や参加可能性が残されていることで、変化や様々なノイズを受け入れることのできるおおらかな質に魅力を感じている。プロジェクトの完成度は重視しつつも、完成してしまうことでプロジェクトが元々持っていた可能性がひとつの価値観に収束してしまうことなく、オープンに広がっていく可能性を残してデザインできないだろうか。
昨年、モダニズムのマスターピースの一つ、アルヴァ・アアルトがデザインしたStool 60をもう一度「未完成品」ととらえなおし、小さなテーブルやキャスターを付けたり、高さの調節などの機能や役割を追加する100パターンのアイデアを発表した。Stool 60に代表されるモダニズムのデザインは、最大公約数的にできているけれど、決して万能ではない。この「Hackability of the Stool」 (スツールの改変可能性)というプロジェクトは、その最大公約数なデザインの過程で削ぎ落とされてしまった、多様で、ニッチで、ささやかな機能を付加していくものだ。モダニズムや大量生産品の良いところはキープしたまま、地域差や個人差といった変数を加え、多様性を担保することはできないか。これは、モダニズムが席巻した後の均質化した世界を生きる僕たちにとっては、とりわけ切実な問題に感じている。100パターン以上の多様な改変を許容してくれるStool 60のように、人々に多様なアクティビティを促し、オープンエンドな参加可能性が担保されている魅力的な空間やプロダクトは設計可能なのか、という関心に基づいて設計したのが、このHIROPPAとおうちというプロジェクトだ。
地場産業を公園から盛り上げる
江戸時代から陶磁器づくりが盛んで、現在も住民の約3割が焼き物づくりに関わるという長崎県波佐見町。この地域を代表する企業であり、陶磁器の企画・販売を手がける「マルヒロ」より、複合施設的な店舗の設計依頼があった。興味を惹かれたのは、彼らのプランに「公園」が含まれていたことだった。遠方から訪れる焼き物ファンだけでなく、地場産業を支える地域の人々も自然に集まり、波佐見焼やさまざまな文化を身近に感じられる場をつくりたい。それを実現できるのは、単一の目的しか持たない店舗や博物館ではなく、多様な目的を受け入れられる寛容さをもった「公園」なのではないか。マルヒロのそんな考えに強く共感した。
厳密にいえば、私企業がつくる空間は「公園」ではない。それでも老若男女誰でも自由に入れて思い思いに過ごせる開かれたあり方や、地域のためにつくられているという公共性はまさに「公園」の持つ性質といえる。そんな場所で生まれる何かが、めぐりめぐって地域や地場産業を盛り上げ、後継者不足や売上の減少といった課題の風向きを変えるかもしれない。
「地面」を多様に解釈する
マルヒロからのオーダーを空間に落とし込み、多様な目的を受け入れられる寛容さをもつ空間の質を作るべく、あらゆるレイヤーにおいて「オープンエンド」な設計を試みている。HIROPPAは店舗やカフェ、キオスクとトイレからなる「建築」と敷地の大半を占める「広場」、そして両者をつなぐ中間項の「パーゴラ」から構成されている。どのエリアについても、「利用者の過ごし方や場の使われ方」、「場の雰囲気や空間の質」、「構法や構造」にかんして、特定の機能やコンセプトに集約されない開かれた状態をキープしたい。
広場については、たとえば、すべり台をつくるのであれば、「滑ると楽しい」という本質的で根源的なコンセプトからスタートする。そこから、「滑る」を何か別の状況で再現できないかと考える。遊びとは遊具の形によって決められた行為ではなく、「目的もないのに楽しい」という事実を発見した時に生まれるものだったはずだ。最終的に僕たちがデザインしたのは、遊具というよりも「地面」そのものだった。人が腰かけたり、滑ったりするための「きっかけ」を地面に与える。たとえば、土を盛って斜面をつくり、その上部に日陰をつくるためのパーゴラを設置する。傾斜地の下には、廃品の陶器を細かく砕いた砂を敷き詰め、砂遊びができるビーチになっている。浅く水を貯めれば波打ち際のようなじゃぶじゃぶ池もつくれるし、夏には水をたくさん貯めて水遊びもできる。「地面の操作」というアイデアに至った経緯としては、遊具の制作費が思いのほか高く、土の移動だけで済むやり方がコスト上とても有利だったという現実的な事情もあるのだが、「遊具のある公園」よりももう少しプリミティブな広場を考えてみたいと思ったことが大きい。地形に様々な特徴を与えることで、広場そのものに対して、様々に解釈可能な「原っぱ」的な質を持たせたいと思ったのだ。
内と外をつなぐパーゴラ
店舗とカフェについては、まず広場と建築をつなぐ中間領域としてのパーゴラを中心に考えていった。パーゴラはHIROPPA全体のエントランス、カフェと広場をつなぐような形で配置されているほか、広場の高台にも設けられている。
広場は日陰が少なく、日差しの強い日は大人にとってはつらい。しかし、そこで単なる日よけや建物をつくってしまうと、大人がそこから出なくなることは容易に想像できる。そこで日よけとして、子どもと大人のスペースをほどよく混在させられる「建物未満」のパーゴラを高台に設置することにした。パーゴラの中には桜などの季節を感じる樹種を植えており、木々が成長することで木漏れ日を楽しめる日陰のスペースになる。パーゴラの2階部分には子どもたちが遊べるハンモックを設けており、壁にシーツなどをかぶせればイベント時にプロジェクターで映像を投影することもできる。
エントランス付近については特に、中と外の境界や仕上げの範囲を丁寧にずらすことで、パーゴラと建築の境界が曖昧になり、連続性が生まれるようにデザインした。カフェのカウンターはそのまま広場に延び、テラス席のテーブルになっている。テラスの地面には陶石(磁器になる前の石)が敷き詰められ、それがそのままカフェカウンター周辺の床にも敷き込まれている。さらに、外と同じように、その床に直接植物を植えた。カフェスペースのカウンター周辺は、テントを間柱に直付けしている。テントのジッパーを開け放つと、サッシがないことで架構だけのパーゴラのような佇まいになる。また、屋根もパーゴラに折半屋根を乗せただけのつくりにすることで、明確な内外の境界をつくらないように納めた。
構法もオープンエンドに
パーゴラと建築は、つくり方についても在来工法に拠らず、DIYの延長のような技術的にも開かれた構法を構造家とともに考えた。構造材はプレカットをせず直線カットのみで加工し、材どうしを沿わせて止めるだけのつくりにしている。在来工法のように仕口の加工がなく、シンプルな加工のみで特殊な技術も必要としない。また、パーゴラには、パッションフルーツやキウイといったつる性植物を植えている。生長とともにパーゴラ屋根のルーバー状の垂木につるが絡まり、やがて実もなる予定だ。将来梁や柱が腐食した場合も、ボルトやビスを外すだけで架構を1本単位で交換することができる。
内装についても同様、空調用のスパイラルダクトを使った台やオフィスの床材に用いられるOAフロアを転用した什器は既製品のモジュールでできているため、必要に応じて簡単に縮小や拡張ができる。二期、三期と拡張を続けていく予定のHIROPPA、そのカフェが最終的に「オープンエンド」と名付けられたのは、可変性をもたせたいという思想の象徴といえるかもしれない。また、「公園」をつくるというアプローチは波佐見町に限らず、全国のどこにでも応用できる。このアイデア自体がいわばオープンエンドに広がっていき、日本各地によい公園が増えていったら面白い。
(新建築2022年3月号のためのテキストより抜粋)
■概要
施主:マルヒロ
所在地:長崎県波佐見町
用途:店舗・カフェ
建築設計:DDAA / SOUP DESIGN Architecture
プロジェクトチーム:元木大輔 / 村井陸 (DDAA) / 土井伸朗 (SOUP DESIGN Architecture)
構造設計:yasuhirokaneda STRUCTURE
施工:上山建設、西海園芸
構造:木造
延床面積:288m²
竣工:2021年8月
撮影:長谷川健太
「人工芝クッション」と「△ハイスツール」
以下の写真はクリックで拡大します





■概要
人工芝のクッション
用途:クッション
デザイン:DDAA LAB
プロジェクトチーム:元木大輔 / 村井陸
完成年月:2019年9月
Photo:長谷川健太
───
△Stool
用途:クッション
デザイン:DDAA LAB
プロジェクトチーム:元木大輔 / 村井陸
完成年月:2021年8月
Photo:長谷川健太