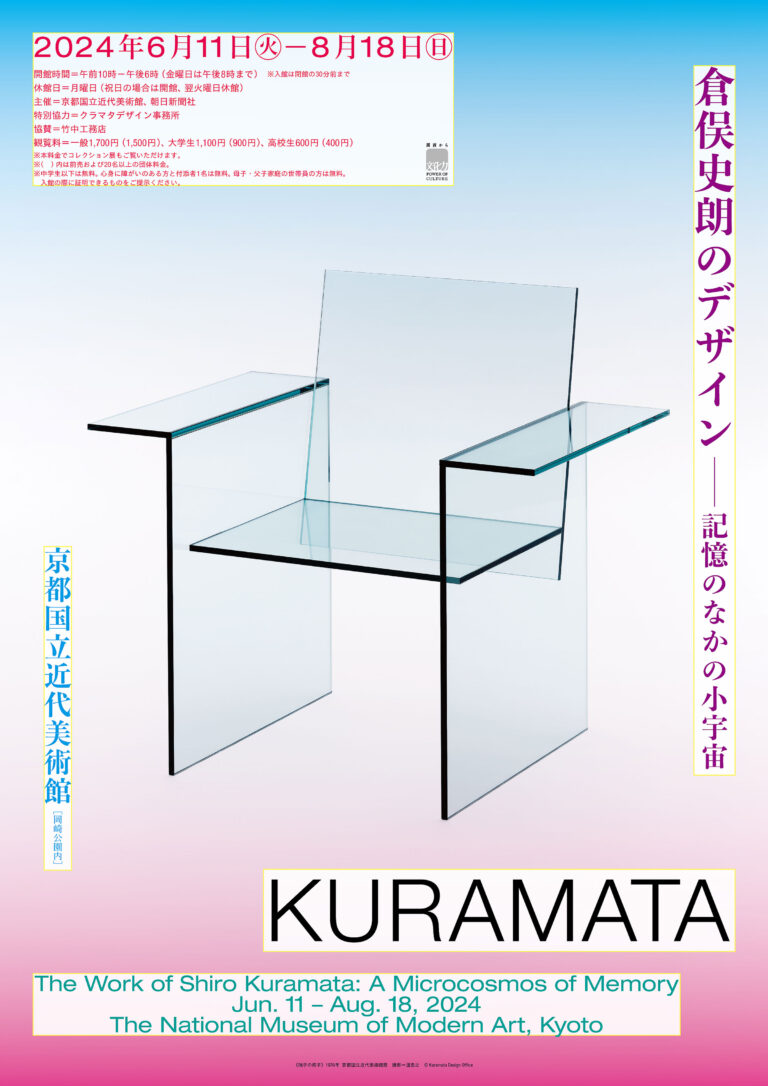森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る外観、南側より見る。 photo©西川公朗
森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る外観、南側より見る。 photo©西川公朗
 森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る2階、階段からダイニングルームを見る。 photo©西川公朗
森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る2階、階段からダイニングルームを見る。 photo©西川公朗
 森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る3階、ベッドルーム、テラス側からを見る。 photo©西川公朗
森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る3階、ベッドルーム、テラス側からを見る。 photo©西川公朗
森田悠紀建築設計事務所が設計した、東京の「春日の家」です。
見晴らしの良い坂道沿いの敷地での計画です。建築家は、“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案しました。また、“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作りました。
神田川から小石川台地へと上る長い坂道の中腹に計画地はある。北側隣地は敷地より3m高く、南側隣地は敷地より3m低い雛壇状の場所である。建主からは眺望の良さを活かした家にしたいとの要望があった。
周辺には高低差が作る特徴的な街並みが散見され、擁壁に沿った坂道や階段を登り切ると、新たな視点や眺望が開けるという空間体験が印象的であった。ここでの課題は、がけ条例によって必要とされるRC造の高さ3mの擁壁や、コンパクトな敷地にかかる3方向からの斜線制限という厳しい条件の中で必要面積をどう成立させるか、そしてどの様にこの場所ならではの建築を作ることが出来るかということであった。
がけ条例に対しては、基礎の一部を3mの高基礎として擁壁の機能を兼ねる形とし、外断熱とすることで室内に擁壁のコンクリートを表した。これは擁壁本来の目的である住まいを守るという役割を室内側に示したものである。ただ、通常の打ち放し仕上げでは大味になりすぎるため、型枠に布を貼って打設することで、繊細で湿度感のある土壁の様な素材感とした。
1階に水回りと寝室、2階に居間と食堂、3階に子供室を計画し、階段は斜線制限を避ける様に配置し、螺旋状に上階へと上る空間構成とした。2階へはRCの擁壁に沿うように階段を上り、その後方向を変え3階へ上がり切ると、眼下に街の風景が広がる。敷地の条件に向き合った結果、この街特有の空間体験を内部のシークエンスとして取り入れる形となった。
コンパクトな各階の面積に対して、この街の路地に見られる小規模な木造住宅の表情が作る、小さな空間に高い密度感が存在する親密な空気感を室内でも実現したいと考えた。同時に、端正なディテールやプロポーションは建主家族の雰囲気に合うだろうとも感じた。羽目板やフローリングなどの素材の単位を細分化し、ディテールを構成する要素も徒に線を消さず、むしろ必要な線を適切な形で存在させることで、この街の空気感と違和感なく繋がりを持った密実な空間を目指した。
以下の写真はクリックで拡大します

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る外観、南側より見る。 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る外観、エントランス部分を見る。 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る1階、エントランス photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る1階、エントランスのコンクリート壁の詳細 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る1階から2階への階段 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る1階から2階への階段 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る階段からリビングルーム側を見る。 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る2階、階段からダイニングルームを見る。 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る2階、デスクの詳細 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る2階、ダイニングルームからリビングルーム側を見る。 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る2階、ダイニングルームからリビングルームを見る。 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る2階、リビングルームを見る。 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る2階、リビングルームからダイニングルームを見る。 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る2階、キッチンとダイニングルーム photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る2階、ダイニングルームから開口部越しに外部を見る。 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作るダイニングテーブルの詳細 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る2階から3階への階段 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る3階、ベッドルーム photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る3階、ベッドルーム、テラス側からを見る。 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る3階、ベッドルームから開口部越しに外部を見る。 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る3階、ベッドルームの開口部周り詳細。 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る3階、テラスからの眺め。 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る1階、廊下からマスターベッドルームを見る。 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る内部建具の詳細 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る外観、南側より見る、夜景 photo©西川公朗

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る1階平面図 image©森田悠紀建築設計事務所

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る2階平面図 image©森田悠紀建築設計事務所

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る3階平面図 image©森田悠紀建築設計事務所

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る断面図 image©森田悠紀建築設計事務所

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作るスケッチ image©森田悠紀建築設計事務所

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る敷地周辺の街並み photo©森田悠紀建築設計事務所

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る敷地周辺の街並み photo©森田悠紀建築設計事務所

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る敷地周辺の街並み photo©森田悠紀建築設計事務所

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る敷地周辺の街並み photo©森田悠紀建築設計事務所

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る施工中の写真、型枠 photo©森田悠紀建築設計事務所

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る施工中の写真、打放壁のサンプル photo©森田悠紀建築設計事務所

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る施工中の写真、基礎施工の様子 photo©森田悠紀建築設計事務所

森田悠紀建築設計事務所による、東京の「春日の家」。見晴らしの良い坂道沿いの敷地。“この場所ならでは”の存在を求め、街特有の空間体験に通じる上階に登った先に“眺望が開ける”建築を考案。“必要な線を適切に存在させる”設計で地域の親密さとの繋がりも作る施工中の写真、基礎施工の様子 photo©森田悠紀建築設計事務所
以下、建築家によるテキストです。
神田川から小石川台地へと上る長い坂道の中腹に計画地はある。北側隣地は敷地より3m高く、南側隣地は敷地より3m低い雛壇状の場所である。建主からは眺望の良さを活かした家にしたいとの要望があった。
周辺には高低差が作る特徴的な街並みが散見され、擁壁に沿った坂道や階段を登り切ると、新たな視点や眺望が開けるという空間体験が印象的であった。ここでの課題は、がけ条例によって必要とされるRC造の高さ3mの擁壁や、コンパクトな敷地にかかる3方向からの斜線制限という厳しい条件の中で必要面積をどう成立させるか、そしてどの様にこの場所ならではの建築を作ることが出来るかということであった。
街特有の空間体験を取り込む高基礎と階段
がけ条例に対しては、基礎の一部を3mの高基礎として擁壁の機能を兼ねる形とし、外断熱とすることで室内に擁壁のコンクリートを表した。これは擁壁本来の目的である住まいを守るという役割を室内側に示したものである。ただ、通常の打ち放し仕上げでは大味になりすぎるため、型枠に布を貼って打設することで、繊細で湿度感のある土壁の様な素材感とした。
1階に水回りと寝室、2階に居間と食堂、3階に子供室を計画し、階段は斜線制限を避ける様に配置し、螺旋状に上階へと上る空間構成とした。2階へはRCの擁壁に沿うように階段を上り、その後方向を変え3階へ上がり切ると、眼下に街の風景が広がる。敷地の条件に向き合った結果、この街特有の空間体験を内部のシークエンスとして取り入れる形となった。
小さく密実な空間がもたらす親密さ
コンパクトな各階の面積に対して、この街の路地に見られる小規模な木造住宅の表情が作る、小さな空間に高い密度感が存在する親密な空気感を室内でも実現したいと考えた。同時に、端正なディテールやプロポーションは建主家族の雰囲気に合うだろうとも感じた。羽目板やフローリングなどの素材の単位を細分化し、ディテールを構成する要素も徒に線を消さず、むしろ必要な線を適切な形で存在させることで、この街の空気感と違和感なく繋がりを持った密実な空間を目指した。
坂道の景観の一部として
敷地が面する坂道は江戸時代から存在する歴史ある道で、この坂道を含む景観にふさわしい佇まいを心掛けた。外観はいくつかの小さなボリュームが組み合わさる形とした上で、ダイニングから坂道を捉えるように角度を振った出窓は、この家のささやかなキャラクターとして存在している。そして、この出窓は室内から眼下の街並みを眺めるためのものであると同時に、坂道のある景観の中において、ここが眺めの良い場所であり、人の生活の営みがあることを示している。
建主の暮らしが始まり、夕暮れ時に部屋に明かりが灯った姿を見た時、この住宅が坂道の景観の新たな一員となっていくことを実感した。
■建築概要
題名:春日の家
所在地:東京都
主用途:一戸建ての住宅
設計:株式会社森田悠紀建築設計事務所
施工:株式会社水雅
構造:木造
階数:地上3階
敷地面積:64.90㎡
建築面積:39.80㎡
延床面積:97.16㎡
設計:2021年1月~2022年12月
工事:2022年1月~2022年7月
竣工:2022年7月
写真:西川公朗
建材情報| 種別 | 使用箇所 | 商品名(メーカー名) | | 外装・壁 | 外壁 | 外壁[ジョリパット]
|
| 外装・屋根 | 屋根 | 屋根[ガルバリウム鋼板 縦ハゼ葺き]
|
| 内装・床 | 居室 床 | チークフローリング
UV塗装
|
| 内装・壁 | 居室 壁 | EP塗装
|
| 内装・天井 | 居室 天井 | EP塗装
|
※企業様による建材情報についてのご意見や「PR」のご相談はこちらから
※この情報は弊サイトや設計者が建材の性能等を保証するものではありません