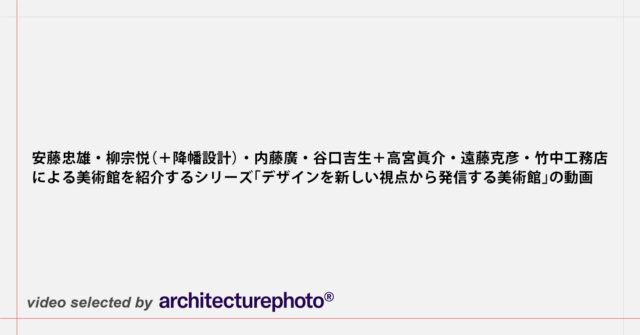元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、受付の横にあるラウンジ photo©Kenta Hasegawa
元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、受付の横にあるラウンジ photo©Kenta Hasegawa
 元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ワークスペース photo©Kenta Hasegawa
元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ワークスペース photo©Kenta Hasegawa
 元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる上階、プレゼンルーム photo©Kenta Hasegawa
元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる上階、プレゼンルーム photo©Kenta Hasegawa
 元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ラウンジ内の個室と家具 photo©Kenta Hasegawa
元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ラウンジ内の個室と家具 photo©Kenta Hasegawa
元木大輔 / DDAAが設計した、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」です。
新築ビルの二つの階での計画です。建築家は、現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向しました。そして、合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げました。
オフィスとはなんだろう。
コロナ禍を経て、オンラインミーティングやリモートワークがとても日常的になった。通信環境の充実によってどこでも仕事ができるようになり、家とオフィスの境界はあいまいになっていき、オフィスの存在意義や定義がどんどん難しくなっている。
家で仕事ができれば通勤時間はなくなり、より自由に時間を使えるようになる一方で、公私の境界が曖昧になりオンとオフの切り替えに悩まされる。人間関係のない気兼ねなさを謳歌する一方で、人とのコミュニケーションを切望する。人との繋がりや誰かに相談できる環境を求める人もいれば、1人で黙々と作業をしたい人もいる。音楽をかけたい人もいれば、耳栓をすることで集中力が増す人もいるし、明るい空間が好きな人もいれば、暗い方が良いという人もいる。
博報堂Gravityはファッション・ラグジュアリー・ライフスタイル業界に特化した広告会社である。
彼らの新しいオフィスを考える上で、「mingle」というキーワードがクライアントからあがった。mingleとは、一緒になる、出会って何かが生まれる、それぞれの特質を失わせない状態で混ぜ合わせる、一つにする…といった意味がある。できたてのカフェラテのように、いくつかの色がマーブル状に混在している状態を表す言葉としてぴったりだと思った。
今回のプロジェクトは新築ビルへのオフィス移転計画だ。移転先のビルは典型的なオフィスビルではあるものの、コロナ禍以降の考え方が色濃く反映されていて、柱裏のカーテンウォールが通風のために開閉することができ、各フロアにはテラスがあり、さらにほぼ4面から採光を得ることができ、窓の外からは皇居の緑が見える。この風通しと光環境の良さを活かして、様々な機能がグラデーション状に繋がっている状態をデザインしたいと考えた。
コロナ禍を経て通信環境の充実した現代にあって、わざわざ会社に行くのは、コミュニケーションの機会を増やすということと、家より充実した選択肢がある場所だからだ。そこで、まずは選択肢の充実を図るべく、オフィスでの過ごし方の可能性を羅列してみることにした。例えば下記のようなスペースだ。
・家のような個室で他人の視線を気にせず作業する
・誰かと共有した空間で作業する
・ちらかすことができる
・隣の作業を見ることができる
・キッチンでコーヒーやお茶を淹れる
・だらだらしたりリラックスしたりする
・足を伸ばす
・雑談する
・他のチームの活動を横目に見る
・喫煙所のような”裏”で休憩する
・大きなテーブルでディスカッションする
・大勢で集まってイベントを行う
・狭い場所に籠る…….
ここに並べた例はほんの一部だが、こうして出てきた選択肢を俯瞰して眺めると、個人とチーム、集中とリラックスの軸でまとめることができそうだと気づいた。これらの相反する環境をそれぞれ独立して配置するのではなく、大きなワンルームの中で互いに関係しながら機能するような状態を目指して平面計画をスタディした。
以下の写真はクリックで拡大します

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、受付の横にあるラウンジ photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、受付の横にあるラウンジ photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ラウンジ、家具の詳細 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ラウンジ内の個室と家具 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ラウンジから会議室を見る。 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、会議室 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、会議室 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、会議室 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、会議室、扉の詳細 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、会議室、テーブルの詳細 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、会議室、金具の詳細 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ワークスペース photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ワークスペース、セキュリティライン(OAシェルフ)の詳細 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ワークスペース、家具の詳細 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ワークスペース、家具の詳細 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ワークスペース、個室ブース photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ワークスペース、什器の詳細 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ワークスペースから「こたつエリア」側を見る。 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、「こたつエリア」 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、「こたつエリア」 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、「こたつエリア」、こたつの詳細 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ライブラリーエリア photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ライブラリーエリア photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、デザイナー席、家具の詳細 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ライブラリーエリア側から、キッチンとソファのあるスペースを見る。 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ソファのあるスペース photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ワークスペース photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ワークスペースからファミレススケールのブースを見る。 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ワークスペースからファミレススケールのブースを見る。 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ワークスペース、家具の詳細 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ワークスペース、家具の詳細 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ワークスペース、家具の詳細 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、ワークスペースから一人席側を見る。 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、一人席、間仕切りの詳細 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる下階、一人席 photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる上階、プレゼンルーム photo©Kenta Hasegawa

元木大輔 / DDAAによる、東京・千代田区のオフィス「HAKUHODO Gravity」。新築ビルの二つの階での計画。現代の労働環境に求められる“複雑な状況”に応える為、多様な選択肢が“相互に関係しながら機能”する空間を志向。合理性も考慮して既存のフロア材を転用した家具等で場を作り上げる上階、プレゼンルーム、家具の詳細 photo©Kenta Hasegawa
以下、建築家によるテキストです。
オフィスとはなんだろう。
コロナ禍を経て、オンラインミーティングやリモートワークがとても日常的になった。通信環境の充実によってどこでも仕事ができるようになり、家とオフィスの境界はあいまいになっていき、オフィスの存在意義や定義がどんどん難しくなっている。
家で仕事ができれば通勤時間はなくなり、より自由に時間を使えるようになる一方で、公私の境界が曖昧になりオンとオフの切り替えに悩まされる。人間関係のない気兼ねなさを謳歌する一方で、人とのコミュニケーションを切望する。人との繋がりや誰かに相談できる環境を求める人もいれば、1人で黙々と作業をしたい人もいる。音楽をかけたい人もいれば、耳栓をすることで集中力が増す人もいるし、明るい空間が好きな人もいれば、暗い方が良いという人もいる。
集中力は、時間帯や気分、体調によって多かれ少なかれ左右されるので、効率だけに特化した単一の環境が作業に適しているかというと、そうでもない。働く場所がひとつしかないと集中するための場所そのものに飽きてしまうので、気分を切り替えられる場所があった方が良い。とはいえ、働く環境を何箇所にも分散するのも難しい。
立場によっても求める環境は異なるだろう。監督者は、スタッフ全体を俯瞰してみる必要がある一方で、スタッフからすると常に見られている状況でパフォーマンスが発揮できるかといわれればそうでもない。リラックスして自由に振る舞いたいと思う一方で、適度の緊張感は必要だったりする。
つまり、社会の多様性は増すばかりで、オフィスで働くという時間はとても動的だ。この複雑な状況に対応できるように、オフィスを単一のコンセプトでまとめるのではなく、多くの選択肢の一部として外の場所も含めた大きなグラデーションで考えることはできないだろうか。
博報堂Gravityはファッション・ラグジュアリー・ライフスタイル業界に特化した広告会社である。
彼らの新しいオフィスを考える上で、「mingle」というキーワードがクライアントからあがった。mingleとは、一緒になる、出会って何かが生まれる、それぞれの特質を失わせない状態で混ぜ合わせる、一つにする…といった意味がある。できたてのカフェラテのように、いくつかの色がマーブル状に混在している状態を表す言葉としてぴったりだと思った。
今回のプロジェクトは新築ビルへのオフィス移転計画だ。移転先のビルは典型的なオフィスビルではあるものの、コロナ禍以降の考え方が色濃く反映されていて、柱裏のカーテンウォールが通風のために開閉することができ、各フロアにはテラスがあり、さらにほぼ4面から採光を得ることができ、窓の外からは皇居の緑が見える。この風通しと光環境の良さを活かして、様々な機能がグラデーション状に繋がっている状態をデザインしたいと考えた。
コロナ禍を経て通信環境の充実した現代にあって、わざわざ会社に行くのは、コミュニケーションの機会を増やすということと、家より充実した選択肢がある場所だからだ。そこで、まずは選択肢の充実を図るべく、オフィスでの過ごし方の可能性を羅列してみることにした。例えば下記のようなスペースだ。
・家のような個室で他人の視線を気にせず作業する
・誰かと共有した空間で作業する
・ちらかすことができる
・隣の作業を見ることができる
・キッチンでコーヒーやお茶を淹れる
・だらだらしたりリラックスしたりする
・足を伸ばす
・雑談する
・他のチームの活動を横目に見る
・喫煙所のような“裏”で休憩する
・大きなテーブルでディスカッションする
・大勢で集まってイベントを行う
・狭い場所に籠る…….
ここに並べた例はほんの一部だが、こうして出てきた選択肢を俯瞰して眺めると、個人とチーム、集中とリラックスの軸でまとめることができそうだと気づいた。これらの相反する環境をそれぞれ独立して配置するのではなく、大きなワンルームの中で互いに関係しながら機能するような状態を目指して平面計画をスタディした。
さらに、新築の計画であったために、B工事と呼ばれるビル側の工事を計画の最初期に決定する必要があった。
なので、間仕切りを最小限にすることでB工事のボリュームを少なくして、残りは家具で対応することを考えた。内装の寿命は建築に比べるととても短命で転用可能性が少ない。将来のことを考えても、できるだけ内装工事を少なくして、家具で空間を構成することは理にかなっている。なによりB工事は得てしてコストがとんでもなく高いのだ。
まず、できるだけ大きなワンルームが確保できるラウンジと執務スペースの配置をスタディし、エレベーターを降りてすぐにラウンジ、そのラウンジを取り囲むようにコの字の執務スペースを配置した。ラウンジは誰でも入ることができ、ラウンジと執務スペースの間にはどちらからも出入りができるセキュリティラインを兼ねたミーティングスペースを設けている。
執務スペースをコの字型にしたのは、個人⇔チーム、集中⇔リラックスという両極の環境を隣り合わせにならずに、ひとつづきの空間とするためだ。コの字の東側を個人が集中できるエリア、西側をチームでリラックスして過ごせるエリアとして、それらが中心に向かってグラデーションに変化していくように考えた。
コの字の東側は、個人の固定席ではあるが、小さな席の集合ではなく、大きなテーブルをシェアしている状態が良いと思った。さらに、テーブルを有機的なかたちにして植栽を配置することで視線が交差しない工夫をしている。一方の西側は、チームでリラックスして過ごせる場所だ。
フリーアドレスのデスクを中心にいくつかの違う性格の機能を分散して配置しているが、東側と西側で大きく印象が違わないように、有機的な大きなデスクを中心に組み立てる。こちらも、視線が交わらないように簡易的なパーテーションの役割を果たす植栽を植えている。
繰り返すが、オフィスとは複雑な状態の産物だ。混ざりたいが邪魔されたくない。個人の気分や性格によって、居場所を選びつつもコミュニケーションのひだのようなものは残しておきたい。そこで、ライブラリーやキッチン、ロッカー、個室といった、多くの人が使う固定の機能を、できるだけ分散して配置することで、ある特定の人だけしか行かないエリアをつくらないようにした。
例えば、管理者側の席のそばに集中できる特等席の個室を配置することで、お互いの交流を促している。ライブラリールームのような部屋をつくるのではなく、フリーアドレスデスクエリアの壁面いっぱいに本棚をつくり、自然と人の足が向くようにする。キッチンは、給湯室のように横並びで洗い物をするのではなく、数人で対面で会話をしながら水道を使うことができるように、360度どこからでも使えるように水栓に工夫をしている。
さらに、このオフィスビルは、窓からたくさんの緑が見えるとても良い環境なので、窓際にいくつかの特等席をつくることにした。固定席に座る人だけでなく、特等席を求めてさまざまな人がここを通過し、会話のきっかけとなると良い。たとえば、カーテンウォールのマリオンのピッチで、極めて小さな漫画喫茶スケールの個室ブースを配置している。窓の外へ視線が抜けるので、とても狭いが贅沢な個室ブースだ。
また、ファミレススケールの最大4人で使えるブースは、座ると壁によって誰とも視線が交差しない高さにパーテーションの寸法を調整している。皇居の方向に開けた見晴らしのいいコーナーにはこたつ席をつくった。こたつは、ランチの時間や業務終了後に、自然と人が集まってきてコミュニケーションのきっかけになる装置として機能することを期待しつつ、足を伸ばして仕事ができる環境を提供する。
オフィスビルの合理性
このプロジェクトを考える上で、オフィスとは何か、働くとは何かという問いの他に、もう一つ重要なテーマがあった。オフィスビルというビルディングタイプだ。オフィスビルは働くというアフォーダンスが極端に強い。当然といえば当然なのだけれど、効率を優先し、とてもシステマチックにできている。
床は500mm角のOAフロアが敷き詰められ、床下に電気やLANなどの配線を通すことでどの席にも簡単に通線が可能で、部分的に剥がしやすく、足音のしにくいタイルカーペットによって仕上げられる。天井の600mm角のシステム天井には、空調と照明、防災関係の設備がグリッド状に並べられ、将来の間仕切りを変更する際には、必要な部分を入れ替えることで、比較的簡易に対応できるようになっている。
このシステムはとにかくよくできている一方で、画一的でステレオタイプなオフィスの風景をつくってしまう。家具を持ってくれば内装工事をせずに、すぐに入居できるという利点があるが、想定外のリクエストに対しては柔軟なシステムとは言い難い。
さらに、不動産的な慣習として、原状回復義務というものがある。最低限の設備を整えた状態で退去することで、次に借りた企業がなるべく早く業務を開始できる、いわばゼロ地点を決めるための慣習だ。この慣習は、オフィスビルのシステムとよく似ていて、システムとしてはよくできている一方で、個別解やイレギュラーには酷く相性が悪い。
既存のインテリアから大きく変えようとすると、前の借り主によって原状回復したばかりのOAフロアやシステム天井、タイルカーペットを、捨てるところからスタートすることになってしまうのだ。
システム自体はよくできていると感心する一方で、今回は画一的なオフィスの風景をつくることも求められていないし、このもったいないとしか言いようのない循環に加担するのもどうも釈然としないが、ゼロから仕組みを考えるのも違和感がある。そこで、オフィスや不動産のシステムを最大限利用しつつ、そのシステムをハックするようなデザインを考えることにしたのだった。
まず、既存の仕上げとして発注が予定されていたタイルカーペットの発注をストップしてもらう。OAフロアは捨てることなく素材として見つめ直すことで、様々な家具に転用することを考えた。とにかくできるだけ捨てない、ゴミや資源の無駄にならないようなあり方だ。具体的には、ラウンジエリアの床に貼ってあったOAフロアを家具に転用した。ラウンジエリアのソファ、ラウンジと執務スペースを繋ぐパーテーション、執務スペースのこたつの小上がりなどに既に現場にあったOAフロアを転用してデザインしている。
樹脂の什器
今回の計画では、とにかくたくさんの家具をデザインした。引き出しのつまみや、扉の取っ手に始まり、間仕切り、フック、キャビネット、デスク、チェア…これは僕たちDDAAのこだわりというか特徴でもあるのだけど、塗装による色合わせをせずに、できるだけ既製品やマテリアルの色だけを使って全体を構成している。
ファッション・ラグジュアリー・ライフスタイル業界に特化した広告会社なので、個室ブースの入り口のロープや、把手に使ったMA1の生地など、ファッションの文脈で使われることの多いマテリアルを選定した。
今回唯一塗料を使っているのが樹脂の什器だ。できれば「Gravity」と「Mingle」を象徴するようなものが作れると良いと思った。この3段のシェルフの上部2段には穴が空いており、そこから数色の顔料が自然に混ざった樹脂が下に垂れることで2、3段目は重力に任せて表情ができあがる。つまり「Gravity」によって様々な色が「Mingle」している什器だ。
■建築概要
タイトル:HAKUHODO Gravity
クライアント:博報堂Gravity
所在地:東京都千代田区
用途:オフィス
設計:DDAA 担当/元木大輔、萬藤大雅、滝実彩喜
内装施工:JPDH、竹中工務店
特注家具制作:JPDH、E&Y Co., LTD.、SET UP、GroovySeams
───
こたつ布団
ディレクション:三好良
デザイン:Hyewon Shin
───
陶器フック
企画:有限会社マルヒロ
製造:重山陶器
───
特殊塗装:中村塗装工業所
テキスタイル:Onder de Linde、パシフィックハウステクスタイル
植栽:SOLSO
延床面積:1,512.49m²
完成年月:2023年6月
撮影:Kenta Hasegawa