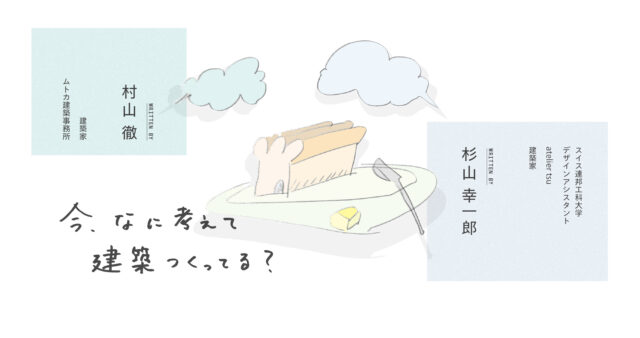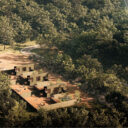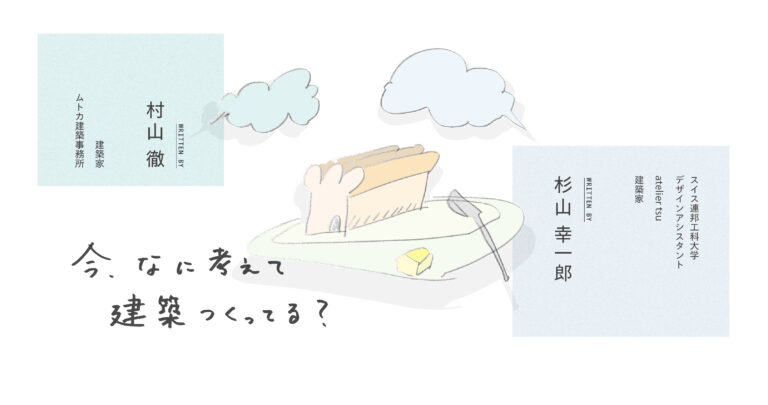
SHARE 村山徹と杉山幸一郎による連載エッセイ ”今、なに考えて建築つくってる?” 第5回「素材と仕上げ」

「今、なに考えて建築つくってる?」は、建築家の村山徹と杉山幸一郎によるリレー形式のエッセイ連載です。彼ら自身が、切実に向き合っている問題や、実践者だからこその気づきや思考を読者の皆さんと共有したいと思い企画されました。この企画のはじまりや趣旨については第0回「イントロダクション」にて紹介しています。今まさに建築人生の真っただ中にいる二人の紡ぐ言葉を通して、改めてこの時代に建築に取り組むという事を再考して頂ければ幸いです。
(アーキテクチャーフォト編集部)
第5回 素材と仕上げ
こんにちは、ムトカの村山です。気づけば前回の杉山くんの「構造と工法」から1年以上経ってしまいました。反省ですね…… ここから飛ばしていきたいと思います。
前回の杉山くんから「素材へのリスペクトについて、どう考えてますか?」との質問がありました。日本の意匠教育では素材から建築を考える視点はあまり重視していませんよね。
空間構成やプログラムの新しさに目がいき、何の素材でできているか、仕上げがどうなっているかということはあまり議論されません。現代では新建材がたくさん開発され、実務においてもそれらをカタログから選ぶことが設計になっている現状があったりするので、素材を深く考える機会がほとんどないのではないでしょうか。
主に乾式となる新建材は、湿式のように現場の職人の腕で出来が左右されるものではなく、プラモデルのように組み立てるだけで出来てしまうことから、素材に対する思考がなくなってしまうのだと思います。昔に比べると今はこうした乾式仕上げで出来ている建築が多く、時間とコストが掛かる湿式をやる機会が減っています。
僕はできるだけ湿式で建築をつくることを心がけています。コストがなく新建材を使わざる追えない状況下でも如何に建材の素材感を出すかを考えたりします。そうすると自ずと杉山くんの言うところの「素材へのリスペクト」が出てくると思います。この石はこういう特性があるから展示台に使えるとか、この木は硬いからコンクリートと並べてもおかしくないとか、素材の特性を見極めながら建築をつくる。
そんなことを考えていたら今回のテーマ「素材と仕上げ」で書くべきことが浮かび上がってきました。

素材から建築を考える醍醐味
自分で言うのもなんですが、昔から変わった素材を使うことが好きで色々試していた方でした。思い起こせば学生時代、今は岐阜市立女子大で教えておられる畑中久美子さんをリーダーに、大学校内に版築造の実験小屋をつくったことがありました。
近くの工事現場の残土をもらい、残土には大小の石が混入しておりそのまま使うことができなかったので、ふるいにかけて石を取り除き、凝固剤の石灰も海で貝殻をもらい焼成してつくったりしました。何から何まで手作りでつくった版築小屋は、どの面(仕上げ)も異なる表情があって素材と仕上げから考える建築の楽しさを体感した出来事でした。
そしてその後の修士研究で美術館を研究したこともあってか、青木淳建築計画事務所に入って土の展示室を堤案した「青森県立美術館」(2006年)を担当するというミラクル(笑)。
また、所員時代に担当した住宅「m」(2012年)では、土木で使われることが多い超高強度コンクリート(最近の使用例で言えば、ゲーリーの「ルイ・ヴィトン ファンデーション」の三次曲面の外壁が有名)を使ってルーバーをつくったり、広葉樹のMDFを使って壁をつくったりと、あまり使われない素材を積極的に使ってきました。
これらの経験から言えるのは、素材からも建築を考えることができるし、素材ありきでの建築づくりにはロマンがあるということです。

色々と綴ってきましたが、第1回目のエッセイにも書いたようにコストやレギュレーションの問題から、最近では新しい素材を開発したり使ったりできる機会が少なくなりました。コンプライアンス社会になってしまった現代では、誰も新しい試みをやりたがらない。
昔はメーカーに電話して「こんな使い方したい」と伝えると「やったことないです」と言われることが喜びで、「誰もやったことない素材の使い方を発明できるかも!」と意気込んでいましたが、最近では即「やったことない」=「やらない」という判断になり、素材での冒険が出来にくい状況になっています。
もちろん、責任問題があるのでメーカーがやりたがらないのも理解できるのですが……
さらに、建築雑誌やWebで建築作品を見ていても、ほとんどの外壁は窯業系サイディングか波板鋼板、内壁は合板素地、構造現しといった、素材は選べず、言い方は悪いかもしれませんが“仕上げなし”、といった状況です。もちろん窯業系サイディングや波板鋼板は仕上げではありますが、もはや選択肢がなく消去法でそうせざるを得ないということが多く、仕上げを施したとは言えないのではないでしょうか。
では、こういった状況のなかでどう素材と仕上げを使いつつおもしろい建築をつくっていけばいいか?を、まずは商業インテリアと建築の比較から考えていきたいと思います。
「演出的仕上げ」と「建築的仕上げ」
新しくできた建築がどうしてもメディアに取り上げられる機会が多くなる昨今ですが、それだけ(今だけ)を見てしまうと仕上げの経年変化といった時間的要素が抜け落ちてしまいがちです。また、新しいその状態だけを見て建築の良し悪しを判断してしまうのは時期尚早だという考えもあります。なので、僕は仕上げにおいて時間が組み込まれているかをポイントに見るようにしています。そしてそのなかで「演出的仕上げ」か「建築的仕上げ」かを意識して見るようにしています。
例えば、近年はインテリアデザイナーの主戦場だった商業インテリアに建築家が携わることが多くなりました。商業インテリアのテーマのひとつは、売上が上がる空間をつくることです。如何にお客さんにお金を落としてもらえるかが問われるので、簡単に言えば“今を詰め込んだ流行りの空間”にして高揚感を与えることが重要になります。つまり時間の概念を省き古くならならない「演出的仕上げ」が求められる世界線です。
00年代あたりだと片山さんのワンダーウォール、森田さんのグラマラスなど、本物のいい素材を使って演出的仕上げができた時代もありましたが、最近ではコストとレギュレーションもあって、エイジングを掛けた木材や木目調シート、大理石のようなタイルと言った偽物が使われることが多くなってきました。
商業インテリアは長くて10年保てばいいという論理があります。
不特定多数が訪れる場所なので耐久性という意味でも真っ当な手段だと言えますし、商業インテリアは内部しか存在しないため、外壁や地面の仕上げに必要な耐候性が必要ないということもあると言えます。
偽物の素材であることは悪いことではないですが、デザインの持続可能性が考慮される時代になったこともあり、そろそろ消費主義のデザイン思考を再考する必要があるように思います。
一方で、演出的ではなく耐候性や耐久性を兼ね備えた仕上げとして「建築的仕上げ」があります。
建築的であることは耐候性などもありますが、素材に時間を組み込んでいるか否かにその違いがあります。商業インテリアの10年と違って建築は30年、長くて50年~100年と言ったスパンで物事を考える必要があるため、素材の経年変化を想定することになります。木材は茶色から灰色に変化する、塗装は剥がれる、大理石は黄変すると言った素材の特性を加味して、数十年先の姿を想像しながら仕上げを施していくのが建築的仕上げです。
時間を組み込むと自ずとの素材そのものの特性を考慮した仕上げを考えることになります。これはおそらく、建築には外部があることで耐候性と耐久性が必然的に求められることがあるからだと思いますが、それが建築家の強みでもありますし、この思考力が好まれたことも、建築家が商業インテリアで台頭してきた一因ではないでしょうか。
特に中村竜治さんが設計した「JINS京都寺町通店」は、商業インテリアにも関わらず、内装工事でテナント内にコンクリートを打設して仕上げるといった今まで誰も考えつかなかった(やりたくてもやれなかった)驚きの手法が実践されており、度肝を抜かれました。これは僕が思いつく商業インテリア作品の中で一番強烈な建築的仕上げです。そしてこの作品が商業インテリアにも関わらずJIA建築新人賞作品に選ばれているというのも納得です。

商業インテリアに並走してリノベーションも建築家の仕事の主戦場になっている現代では、建築的仕上げにもいくつかバリエーションが出てきています。建築家の岩元真明さんが建築同人誌『ねもは003』(発行: 2012年8月)での論考「仕上、無仕上、未仕上、脱仕上」は、近年の日本のリノベーションにおける仕上げの変遷を見事に言い当てています。
ここでは、コルビュジエ、ラカトン、ゲーリー、そして日本のスキーマ建築計画を引き合いに出しながら、仕上げがないことを白で表現したモダニズムの無仕上げ、仕上げをしない下地の状態で留めた未仕上げ、仕上げを剥ぎ取った脱仕上げの流れを説明し、現代日本においてスキーマ建築計画が先頭に立って実践していると書かれています。
スキーマの仕上げはこれまで建築家が実践してきた時間の組み込み方とは違い、時間をそのまま受け入れるのではなく操作している点が特異なところです。商業インテリアにおいてのスキーマの戦略は、演出的仕上げではなく建築的仕上げとして時間を組み込みながらも、時間を止める、戻す、遅延させるといった操作を行うことで空間を演出しているといえばいいでしょうか。
こう言った意味でも彼らは特別な存在だと言えます。さらに、脱仕上げのラフな表層をつくりながらも同時にラグジュアリー感を演出するツヤのある表層を加えることで短絡的なラフさに陥らないようにしている点にも唸らせられます。

青森県立美術館の土とレンガ
ここではじめに話した版築と美術館の研究が縁となって担当した「青森県立美術館」の仕上げについてお話したいと思います。
竣工から10年経った時に、時間が経過することで見えてきた素材と仕上げについての、当時は考えもしなかった気づきがありました。


青森県立美術館はトレンチを掘って上向きに凸凹になった土の地面に下向きに凸凹になった白い箱を被せ、その凸凹の隙間を土の展示室、白い箱のなかをホワイトキューブの展示室とする構成になっています。ここでは土の壁はハンチク(版築風吹付仕上げ)で仕上げています。
当初は本物の版築で壁をつくる計画でしたが、何万平米もある壁を版築で仕上げることは現実的ではなく(大学時代に版築を実践していた身からしてもいくら人海戦術でやっても不可能だと思いました)、擁壁などで使われるショットクリートに近い工法で土にセメントを混ぜたものをコンクリート下地に吹き付けて版築風に仕上げることになりました。
一方で白い箱の内部では展示壁としての機能を考えてプラスターボード+塗装で仕上げていますが、外壁は耐久性と耐候性を考慮してレンガを白く塗装した仕上げとしています。このレンガはタイルではなくホンモノのレンガ4万個を手積みで積んだ上にローラーで塗装しています。
塗装は、通常の目地と伸縮目地の色の違いを隠蔽する意味や、透水性のあるレンガを保護する役割など多くの理由からきていますが、意匠的には土の壁と白い壁がスケールを凌駕して対等にあること、その拮抗した平衡状態をつくりだすことを意図しています。
竣工当時は、土の茶と壁の白がまさに拮抗した状態でした。しかし約20年経った今では、外壁のレンガはところどころ塗装が剥がれて風化しています。一方で、土は風化せずほとんど当時のままの状態を保っています。塗装のレンガは、見る人によっては劣化していると感じるかもしれませんが、僕は良い感じに風化して味が出ていると感じました。しかし土の壁はところどころエフロしているものの、変に綺麗で時間の経過を感じさせないことに違和感を覚えました。
この感覚はこうして20年経った姿を見てはじめて得たものでしたが、これはつまり、レンガは建築的仕上げで土は演出的仕上げだったということになります。そして、建築的仕上げと演出的仕上げを同居させると時間の流れにズレが生じて建築の在り方と空間に歪みが起きることに気付かされました。それ以降、時間をどう扱うか、この仕上げは建築的仕上げか?演出的仕上げか?を意識するようになりました。
そのような視点で仕上げを見ていくと、最近の仕上げは演出的仕上げに傾向しているように感じます。〇〇風、〇〇な感じといった雰囲気重視な仕上げです。日本の建築や都市は時間を考慮しない、今を重要視する方向に加速しているようです。ですが、やはり建築家として建築の持続性を考えていくと、できるだけ時間を組み込んだ建築的仕上げを考えていきたいと思っています。
オーバーホールインヨコハマでの実践
次は、自邸である「オーバーホールインヨコハマ」(2023年)について書きたいと思います。
この作品は50年経って繁茂した中庭の緑が印象的なヴィンテージマンションの住戸リノベーションです。
とにかく建築と環境が素晴らしく、特に50年という時間がつくりあげた中庭の緑は、なくなってはいけない、守り続けなくてはいけないと感じるものでした。といったことから、どうすれば価値あるこの建築と環境を守りずっとここにあり続けられるかをテーマに設計を進めていくことにしました。

自邸なので普通だとどうしても自分たちの好みが出てしまいますが、この素晴らしい建築と環境をレファレンスして設計していくことで、誰もがいいと思える、住んでみたいと思える、ニュートラルなデザインにすることで、未来にこの空間が存在し続けることができるのではと考えました。つまりクライアントを施主である自分たちではなくこの建築と環境自身に置き換えた、ということです。
レンガ、スタッコ仕上げの外壁塗装、ブラウンガラスといった竣工から50年経っても変わらずあった素材や、竣工時から変わってしまったリビングのカーペット、突板張りの間仕切り壁といったモダンリビングの内装まで、昔の図面や文献を元に、この建築を徹底的にレファレンスしていきました。
具体的には、以前のリフォームでカーペットからフローリングに変わっていたリビングの床をウールカーペットに戻したり、突板張りの間仕切り壁を踏襲して新たに加えた間仕切り壁の仕上げを突板にしたり、カーテンは外壁スタッコ仕上げに似せたクラッシュ仕上げにしたり。キッチンの壁面タイルは既存の建物に使われている数種類のレンガタイルの色をサンプリングし、それらに合わせて水野製陶園さんにピンク地に薄い白の釉薬を載せた上に鉄粉を振りかけたオリジナルタイルを製作してもらったりと、もともと50年前の原設計からこの仕上げだったのではないかと感じられるように仕上げていきました。



唯一、自分たちの好みでサニタリーのカウンターとトイレの床に廃ガラス入りテラゾを使いました。これは倉俣史朗さんが40年前にデザインした「スターピース」というテラゾのオマージュで、当時スターピースを製作したテラゾ会社にお願いし、ガラスも当時仕入れていたガラス工場に廃ガラスを買いに行き、まったく同じレシピで再現しました。
ただ、製作された1980年から40年経っていたことでベースとなる尖った石の採石場が閉山していたので代わりに丸い石に変更したり、廃ガラスの色が時代の流行りで淡いものが多くなったりと、時間が経ったことでどうしても変わってしまうものはありましたが、それも時代性であり時間を組み込むことで起こった出来事でした。

時間を組み込んだ「本仕上げ」
オーバーホールインヨコハマは、前述した無仕上げ、未仕上げ、脱仕上げの先に何があるかということを考えさせられたプロジェクトでした。と言うのも、脱仕上げは、時間を組み込んだ建築的仕上げではあるものの、時間を、止める、戻す、遅延させると言った時間の流れを断絶する手法であり、その先がありません。
建築の持続性を考えるならば、時間とどう繋げるかが重要です。であるならば、時間に寄り添い、本物の素材を使い、経年変化を楽しみ、性能も上げるように仕上げる、「本仕上げ」(本物の仕上げ、本当の仕上げ)を徹底的にやってみよう、そう思ったのでした。本仕上げとは、時間を組み込んだ他に揺るぎがないほどにその建築にあった仕上げのことを指しています。
ともすれば、無仕上げ以前の「仕上げ」に戻ったように思われるかもしれませんが、未仕上げ、脱仕上げで仕上げとなる表層と建築の構成(構造)が一度分離した状態になったと考えると、そこからもう一度その建築にあった本当の仕上げを思考するという意味で「仕上げ」と「本仕上げ」は別の手立てになるのではないでしょうか。
そして、仕上げが否応なくクローズアップされるリノベーションやインテリアデザインを経ることで、新築や大きな建築の仕上げがどう変わっていくかに繋がっていくはずですし、さらにその先に新しい建築の姿があるように思っています。
オーバーホールインヨコハマは竣工からまだ1年しか経っていないので結果はわかりませんが、コストやレギュレーションに左右されず、前述した本仕上げを実践していくことでいい建築をつくり残していければと思っています。
村山徹
1978年大阪府生まれ。2004年神戸芸術工科大学大学院修了。2004-2012年青木淳建築計画事務所勤務。2010年ムトカ建築事務所共同設立。現在、関東学院大学研究助手。主な作品に「ペインターハウス」、「小山登美夫ギャラリー」、「天井の楕円」、「WOTA office project」など。
連載エッセイ:今、なに考えて建築つくってる?