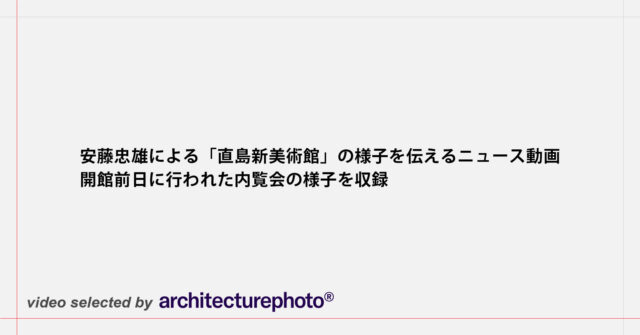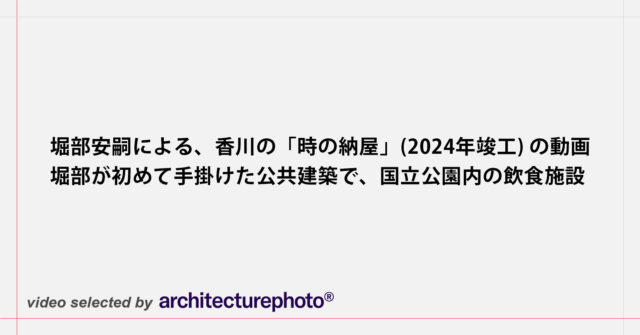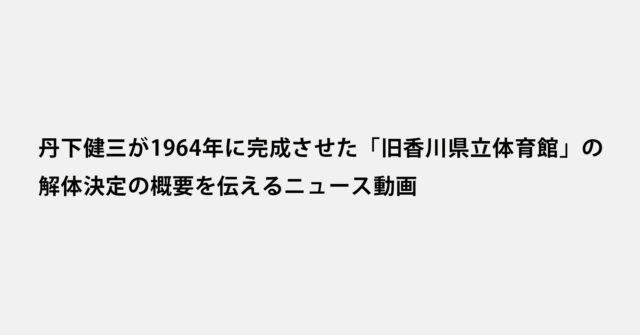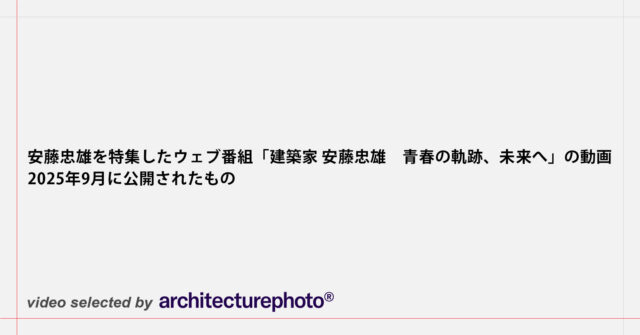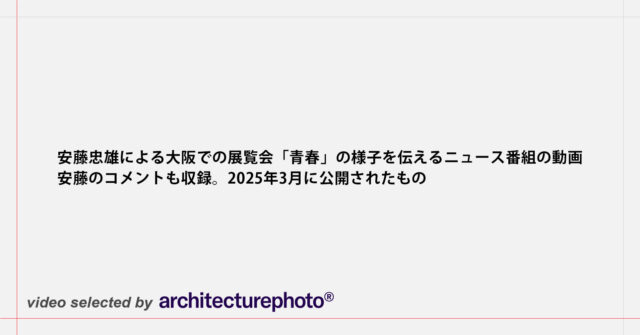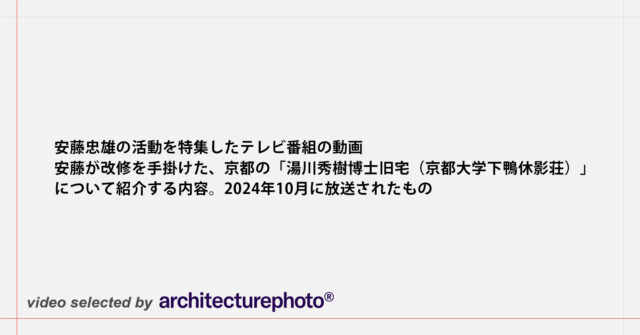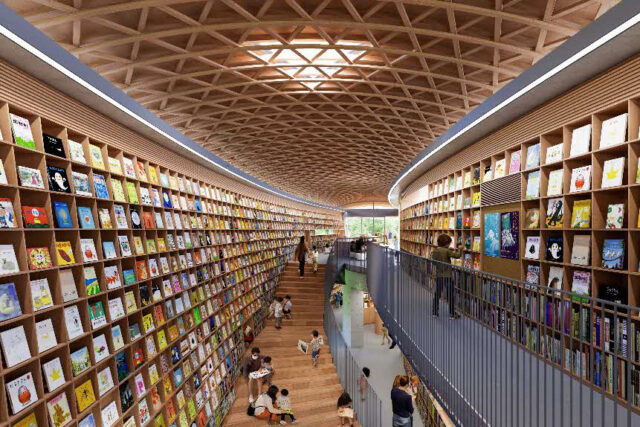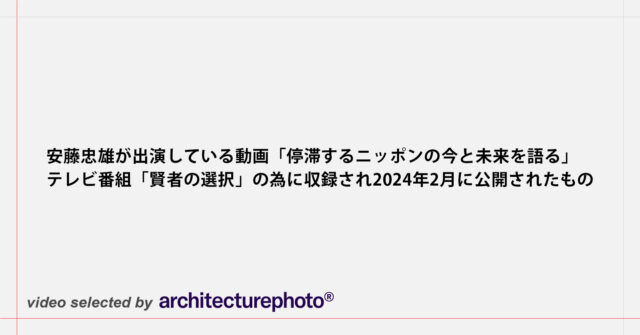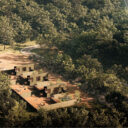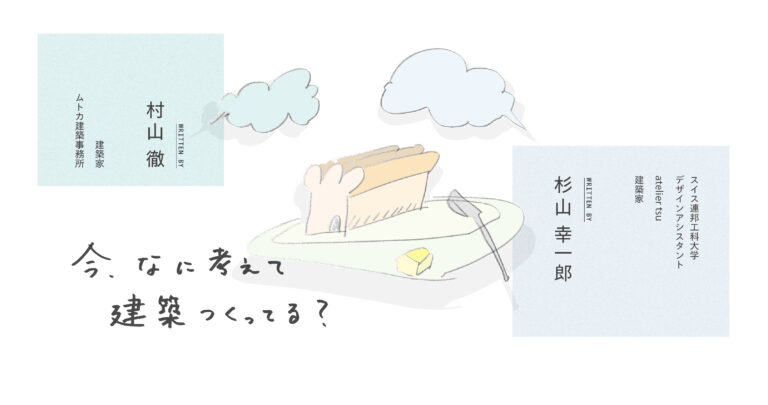村山徹と杉山幸一郎による連載エッセイ ”今、なに考えて建築つくってる?” 第5回「素材と仕上げ」
村山徹と杉山幸一郎による連載エッセイ ”今、なに考えて建築つくってる?” 第5回「素材と仕上げ」
「今、なに考えて建築つくってる?」は、建築家の村山徹と杉山幸一郎によるリレー形式のエッセイ連載です。彼ら自身が、切実に向き合っている問題や、実践者だからこその気づきや思考を読者の皆さんと共有したいと思い企画されました。この企画のはじまりや趣旨については第0回「イントロダクション」にて紹介しています。今まさに建築人生の真っただ中にいる二人の紡ぐ言葉を通して、改めてこの時代に建築に取り組むという事を再考して頂ければ幸いです。
(アーキテクチャーフォト編集部)
第5回 素材と仕上げ
text:村山徹
こんにちは、ムトカの村山です。気づけば前回の杉山くんの「構造と工法」から1年以上経ってしまいました。反省ですね…… ここから飛ばしていきたいと思います。
前回の杉山くんから「素材へのリスペクトについて、どう考えてますか?」との質問がありました。日本の意匠教育では素材から建築を考える視点はあまり重視していませんよね。
空間構成やプログラムの新しさに目がいき、何の素材でできているか、仕上げがどうなっているかということはあまり議論されません。現代では新建材がたくさん開発され、実務においてもそれらをカタログから選ぶことが設計になっている現状があったりするので、素材を深く考える機会がほとんどないのではないでしょうか。
主に乾式となる新建材は、湿式のように現場の職人の腕で出来が左右されるものではなく、プラモデルのように組み立てるだけで出来てしまうことから、素材に対する思考がなくなってしまうのだと思います。昔に比べると今はこうした乾式仕上げで出来ている建築が多く、時間とコストが掛かる湿式をやる機会が減っています。
僕はできるだけ湿式で建築をつくることを心がけています。コストがなく新建材を使わざる追えない状況下でも如何に建材の素材感を出すかを考えたりします。そうすると自ずと杉山くんの言うところの「素材へのリスペクト」が出てくると思います。この石はこういう特性があるから展示台に使えるとか、この木は硬いからコンクリートと並べてもおかしくないとか、素材の特性を見極めながら建築をつくる。
そんなことを考えていたら今回のテーマ「素材と仕上げ」で書くべきことが浮かび上がってきました。
 村山徹と杉山幸一郎による連載エッセイ ”今、なに考えて建築つくってる?” 第5回「素材と仕上げ」visvimのプロジェクトで使った素材のサンプル photo©村山徹
村山徹と杉山幸一郎による連載エッセイ ”今、なに考えて建築つくってる?” 第5回「素材と仕上げ」visvimのプロジェクトで使った素材のサンプル photo©村山徹
素材から建築を考える醍醐味
自分で言うのもなんですが、昔から変わった素材を使うことが好きで色々試していた方でした。思い起こせば学生時代、今は岐阜市立女子大で教えておられる畑中久美子さんをリーダーに、大学校内に版築造の実験小屋をつくったことがありました。
近くの工事現場の残土をもらい、残土には大小の石が混入しておりそのまま使うことができなかったので、ふるいにかけて石を取り除き、凝固剤の石灰も海で貝殻をもらい焼成してつくったりしました。何から何まで手作りでつくった版築小屋は、どの面(仕上げ)も異なる表情があって素材と仕上げから考える建築の楽しさを体感した出来事でした。
そしてその後の修士研究で美術館を研究したこともあってか、青木淳建築計画事務所に入って土の展示室を堤案した「青森県立美術館」(2006年)を担当するというミラクル(笑)。
また、所員時代に担当した住宅「m」(2012年)では、土木で使われることが多い超高強度コンクリート(最近の使用例で言えば、ゲーリーの「ルイ・ヴィトン ファンデーション」の三次曲面の外壁が有名)を使ってルーバーをつくったり、広葉樹のMDFを使って壁をつくったりと、あまり使われない素材を積極的に使ってきました。
これらの経験から言えるのは、素材からも建築を考えることができるし、素材ありきでの建築づくりにはロマンがあるということです。
 村山徹と杉山幸一郎による連載エッセイ ”今、なに考えて建築つくってる?” 第5回「素材と仕上げ」超高強度コンクリートでつくった厚さ10mmのルーバー photo©村山徹
村山徹と杉山幸一郎による連載エッセイ ”今、なに考えて建築つくってる?” 第5回「素材と仕上げ」超高強度コンクリートでつくった厚さ10mmのルーバー photo©村山徹
色々と綴ってきましたが、第1回目のエッセイにも書いたようにコストやレギュレーションの問題から、最近では新しい素材を開発したり使ったりできる機会が少なくなりました。コンプライアンス社会になってしまった現代では、誰も新しい試みをやりたがらない。
昔はメーカーに電話して「こんな使い方したい」と伝えると「やったことないです」と言われることが喜びで、「誰もやったことない素材の使い方を発明できるかも!」と意気込んでいましたが、最近では即「やったことない」=「やらない」という判断になり、素材での冒険が出来にくい状況になっています。
もちろん、責任問題があるのでメーカーがやりたがらないのも理解できるのですが……
さらに、建築雑誌やWebで建築作品を見ていても、ほとんどの外壁は窯業系サイディングか波板鋼板、内壁は合板素地、構造現しといった、素材は選べず、言い方は悪いかもしれませんが“仕上げなし”、といった状況です。もちろん窯業系サイディングや波板鋼板は仕上げではありますが、もはや選択肢がなく消去法でそうせざるを得ないということが多く、仕上げを施したとは言えないのではないでしょうか。
では、こういった状況のなかでどう素材と仕上げを使いつつおもしろい建築をつくっていけばいいか?を、まずは商業インテリアと建築の比較から考えていきたいと思います。