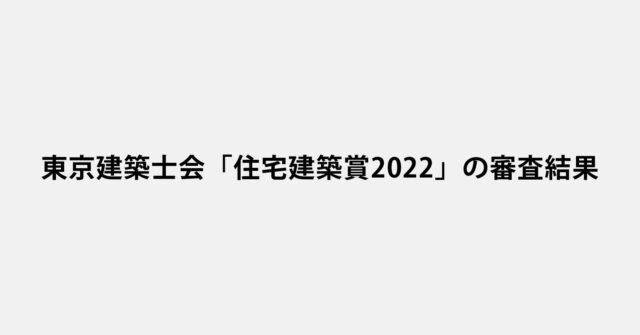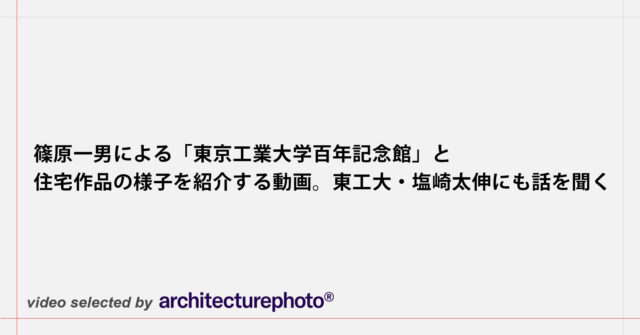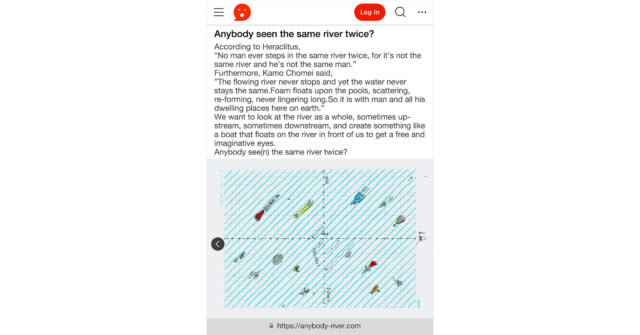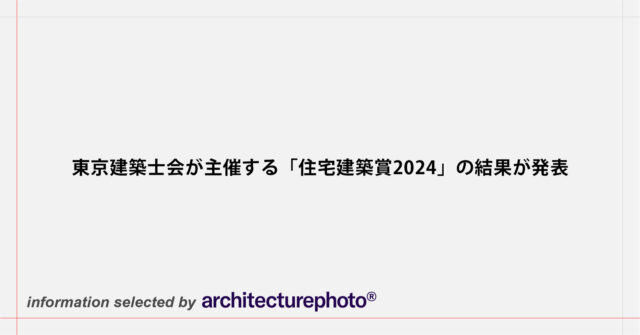SHARE 塩崎太伸による論考「y/g──近接した可能世界群としての建築、あるいはフィクショナリティと世界の複数性について」。湯浅良介が設計してGottinghamが撮影した住宅“LIGHTS”を訪問して執筆

建築設計事務所「アトリエコ」を共同主宰し、東京科学大学(前・東京工業大学)でも教鞭をとる塩崎太伸による論考を掲載します。湯浅良介が設計してGottinghamが撮影した住宅“LIGHTS”を訪問して執筆されました。湯浅良介による、埼玉・狭山市の住宅「LIGHTS」は、アーキテクチャーフォトでも特集記事として紹介しています。
y/g──近接した可能世界群としての建築、あるいはフィクショナリティと世界の複数性について
白い灯台のような家である。灯台の光は白よりも白い、それがたとえ少し霞んだ色の光源であっても漆黒の闇の海からは、ただただ、とてつもなく白く映るのだろう。なので、最初は光(lights)という名づけの白い家を訪れて訪問記を書けばよいのだと思って引き受けたのだけれど、どうやら違う。どうやらフレーミングの外(あるいは内)にいる人間によって映されたこの白い家の表象をも含めて活字にして欲しいとのことだった。
その(とりあえず)ふたりをyとgと呼んでみる。
時系列でいうと、yはこの家の「前」にイメージをつくっている。
ドローイングにはふしぶしで豊かなカタチが登場する。消えてはまた別のカタチが生まれ、チカチカと明滅するそれらのカタチは、建築家同族の目によれば、いろいろな要望やコストバランスの中で削除・脱色されながら整理されてきたのだろうと読みとれる。当然いくつかのカタチは意識的に残されている。整理の過程で壁・天井そして床は、目地のリズムとプロポーションと幾何学と、そして力学的な力の流れと隠れた架構モジュールと、さらには流通する既成品の寸法と数とを、取り込み参照し合ってそれらの関係性がちょうど比率として成立するところでバランスを取っている。けれどそうした過程の調整は、この家の表象としてはこの際どうでもよい。
gはこの家の「後」にイメージをつくっている。
現像された表象には不思議な光の穴がある。それ自身もフレームを持ってフレームの外を暗示するようなその白い光は、フレームの外への行手を阻むかのように手前にスケールを誇示するテーブルセットが置かれている。おそらくgは、入れ子につづくこのフレームの繰り返しのどこか途中に揺蕩って、この住宅という舞台のなかのイメージを眺めて取り出そうとしている。エレベーターで言えば階と階の間の存在しないはずの途中階や、アリスで言えば鏡のコチラとアチラの間の空間。そうしたフィクショナルな境界空間(ルビ:リミナル・スペース)に半ば自分から閉じ込められに行っているようにも見える。なので表象側にも表象の裏側にもgのその姿は見えない。けれどそこに、いることは確かだという不思議な状況がある。
以下の写真はクリックで拡大します

少し記憶の話を挟む。
この家には二又階段がある。宮殿にあるような階段。他にもいろいろな部分があるのだけれどおそらくこの階段がロクスとしてもっとも強い。ロクスというのは記憶術における記憶を重ねる建築的な部位のことである。かってローマ時代、弁論を記憶するための器が建築だった。そして時代を経て大航海時代、海の向こうの未だ見ぬユートピア世界から集まってくる膨大な動植物や珍品たちへの名づけと博物学整理のために、記憶術士は空想上の建築を設計する。記憶のための多くのロクスを備えた空間はきっと、悠久の時間の中で豊饒な記憶を携えて光で満たされたに違いない。岬に佇む灯台のように、記憶の光で満ちた建築とはどんなカタチで満ちいくか。この住宅はそうした意味で、さまざまな記憶に、あるいは複数の世界に、生まれ変わる可能体としてのロクスをもった建築として見ることができそうに思う。それは同時に、そのロクスが別物に置き換わった“ありえたる建築”やその先の可能世界をも想起させる。
いま、ロクスをL、その集合としての建築をA、建築を含む絡まりとしてのわたしたちがいる世界をWとすると、□A(スクウェアA)は線的な時間の中で必然の結果としてつくりあげられた建築を示し、◇A(ダイアモンドA)はロクスが自在に入れ替わる可能体の集合としての建築と位置づけられる。□Aはどちらかといえば演繹的な作業(deduction)の末にできあがり、◇Aは帰納的、さらには仮説的な作業(induction、abduction)の末にふわふわと漂う建築である。建築家・原広司はかって、◇A(ダイアモンド・アーキテクチャー)の様相実在にこれからの建築を想像したのであるが、どちらかといえば大陸の哲学思想が蔓延してきた日本の建築界隈でその行末をフォローできていたものはどれほどいたのであろうか。いま、□Aと◇Aとのあわいの場には、~を否定記号として次の式が成立する。
□A=~{◇~A} ◇A=~{□~A} ※
□Aは容易に◇Aと置き換わる。そしてもちろんその逆も。それは、シュルレアリストが気づいた現実と超現実の連続、あるいはハイゼンベルクたちが気づいた量子の動きの不確定性とも近似している。
以下の写真はクリックで拡大します

ところでyという字とgという字は、その図像として、急いで書いたらほとんどどちらがどちらか分からないくらいによく似ている記号なので、その記号を入れ替えて読んでもらって構わない。というより、この際だから積極的に入れ替えた可能世界を考えてみてほしい。時間も逆行させて。ひょっとするとgがこの家の前にイメージをつくっていたならば。この家の記憶は入れ子のように反転してゆく。あの階段に座っていたのははたして、いつか見たあの人だったのかもしれないという可能世界に瞬時に飛んでみることができる。ともするとyがこの家の後にイメージをつくっていたとすると。さらにいうならば、イメージの置き換えは記憶の置き換えと裏表なのであるから、いま、この文章を書いているわたしやあるいは、この文章を読んでいるあなたが、yやgになることも考えうるというところで、この家も、あなたやわたしがいまいる場所も、理解すべきなのだとおもう。
わたしがいるここに、いつかのだれかが置き換わることを前提として、その空間の名づけも時間と共に入れ替わることを許容すると、どんなに自由がひらけてくることか。
記憶のロクスは建築の部位に限らない。それは目地のリズムのように住宅全体に広がる物でもよいであろうし、名前や色や光でもよい。
以下の写真はクリックで拡大します

ドアを開けて住宅に入る。住宅を訪れるときはとても気を使う。住宅にとってわたしはまだ他者だ。その他者が埃を持ち込むわけにはいかないから、靴の泥は敷地の手前で落とし、せめて上着は外で脱ぐ。声をその空間に落として良いかも慎重になる。しかしそれでも、もしこの家に自分が住んでいたらと置き換えを夢想できる、そんな家に遭遇するときがある。置き換えができるということは「いつかのだれか」の記憶を知ることができるということでもある。家のなかに居ながら、そのフレームの外からこの家を見ることでもある。いま、共保有という言葉をつかえば、その空間をたしかに、クライアントを差し置いていつかのだれかと保有できてしまっているような感覚で、別の可能世界にその住空間をずらす感覚といえるかもしれない。そうなれたとき、この住宅の複数の記憶とわたしの複数の記憶が交差できたように思える。
※□A、◇Aなどは分析哲学における様相論理を示す記号式。
参考文献:デイヴィッド・ルイス『世界の複数性について』名古屋大学出版会、2016
塩崎太伸
1976年生まれ。建築家。アトリエコ共同主宰。東京科学大学(前・東京工業大学)建築学系准教授。東京工業大学理工学研究科修了、2001-2002年オランダ・デルフト工科大学。 2009年東京工業大学・博士(工学)取得。2016年より現職。建築制作に《tom tit toque》、《菊名貝塚の住宅》(SDレビュー、住宅建築賞、東京建築賞など)、《上池袋の住宅》、《五平柱の住宅》(Japan Wood Design Award 2020)など。著書・編著に、『空間の名づけ──Aと非Aの重なり』(NTT出版)、『建築論辞典』(共著、日本建築学会)、『応答「漂うモダニズム」』(共著、左右社)、『JA93 Kazuo Shinohara』(新建築社)など。