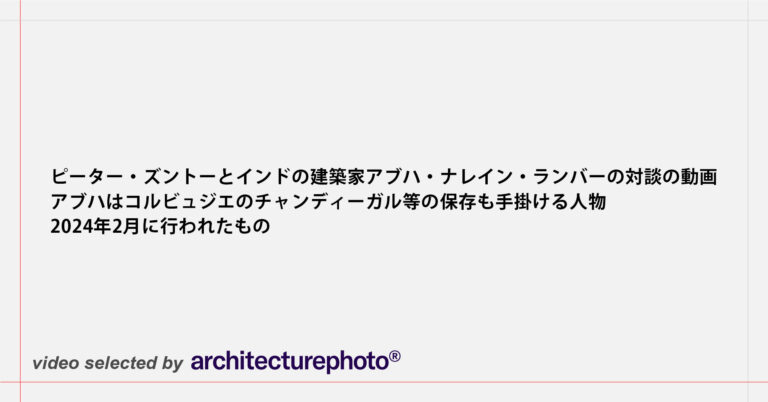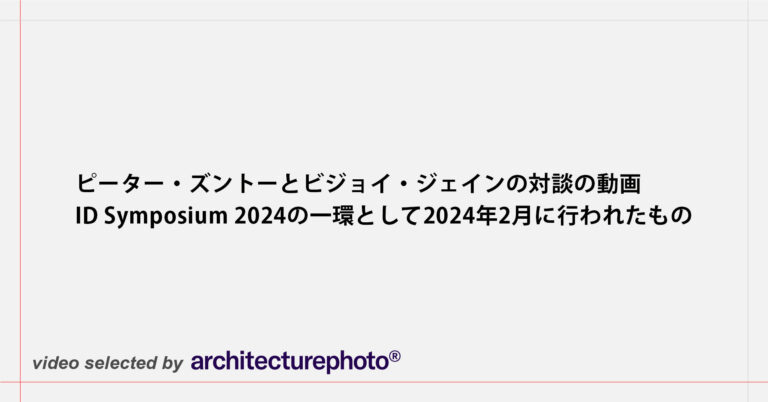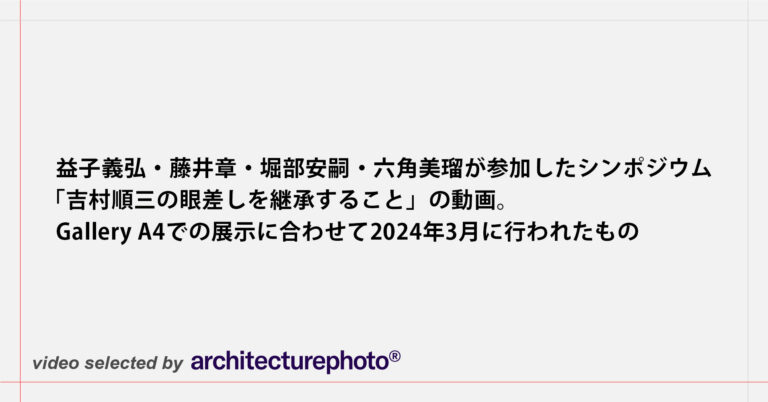ピーター・ズントーとインドの建築家アブハ・ナレイン・ランバー(Abha Narain Lambah)の対談の動画です。アブハはコルビュジエのチャンディーガル等の保存も手掛ける人物。2024年2月に行われたもの。
architecture archive
ピーター・ズントーとスタジオ・ムンバイのビジョイ・ジェインの対談の動画です。India Deaseig Symposium 2024の一環として2024年2月6日に行われたものです。内容は、彼らの個人的な体験からプロとしての学び、そして若い建築家に対する洞察まで多岐に渡る。
益子義弘(建築家、東京藝術大学名誉教授)・藤井章(建築家、吉村順三設計事務所元所員)・堀部安嗣(建築家)・六角美瑠(建築家、神奈川大学教授)が参加したシンポジウム「吉村順三の眼差しを継承すること」の動画です。Gallery A4での展示に合わせて2024年3月6日に行われたもの。2024年5月7日18:00までの期間限定公開です。


連勇太朗が代表理事を務め、“新たな住環境モデル”の発明を目指す「CHAr」の、設計スタッフ(2024年新卒・既卒・経験者)募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
【わたしたちについて】
NPO法人CHAr一級建築士事務所は、「つながりを育む、まちをつくる」をビジョンに掲げ、デザイン・建築設計・まちづくりを軸としながら、自社サービスの運営を通じて多様なアクターと協働しながらプロジェクトを進めている組織です。
人/時間/空間を再び繋ぎ合わせ、新たな価値観と想像力によって、21世紀の社会に求められるネットワークを創造することを目指しています。現代における住環境には住宅や家といったビルディングタイプに限定されず、地域社会やコミュニティまで含めた包括的な視点から住環境モデルの大胆な構想と再編が求められています。CHArは小さな手すりの改修から、大きな都市の計画まで、スケールや領域を横断しながら次の時代に求められる新たな住環境モデルを発明し、実装することをミッションとします。
これまでは改修設計や利活用提案・コンサルティング・自社事業の運営が中心でしたが、それぞれの事業・協働者が成長し、これまでよりも規模の大きい設計案件や地方の案件・ユニークな案件が増えてきています。一方でほんの小さな変化で空間の質が変容するようなミクロなデザインのクオリティも追求しています。
また建築設計だけにとどまらず、企画提案・プログラム提案・プログラム開発・事業モデル開発など、多岐にわたる業務を横断しながらプロジェクトを進めています。


プロジェクト規模の拡大が進む「チームラボアーキテクツ」の、建築及び内装の設計スタッフ(経験者・既卒・2024年新卒)と バックオフィス募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
チームラボアーキテクツでは、プロジェクト規模の拡大にともない、私たちのチームに参加してくれる建築設計実務経験者、内装設計実務経験者、既卒、新卒、バックオフィス担当者を募集します。
私たちはデジタル社会に向けた心地よい空間を目指し世界中で空間設計をおこなっております。
よく知られているプロジェクトとしてはチームラボと共同で制作するデジタルアートが体験できる美術館があります。
その中では、アート空間はもちろん、カフェやショップ、休憩するための家具にいたるまですべてをデザインしています。東京では麻布台ヒルズの中に最近オープンしましたので、ぜひご体験ください。また、デジタルを直接利用するものばかりではなく、社会がどんどん変化する中で、それに対応できる心を養う場所として、子供の学び場をデザインしています。それらの空間の建築から内装にいたるまでを担当してもらうのが仕事になります。
多くの案件は自社が運営することが多いので、我々の仕事は建物、内部のアート作品が完成したら終了ではなく、その後の作品のアップデートまで含めた完成のない空間です。異なる職能の人と共同で、受託ではなく当事者として継続して関わっていくことに特徴があると思います。
世界中で仕事がしたい人、受託ではなく当事者として継続して関わっていきたい人、誰も見たことがない新しい空間が作りたい人、ぜひご連絡ください!



OSTR / 太田翔+武井良祐が設計した、大阪市の「大阪サウナDESSE」です。
都心のビルの中に計画された温浴施設です。建築家は、閉鎖的な状況で“日常の延長”としての空間を目指し、多様な動線がある“庭のような建築”を志向しました。そして、異なる特徴を持つ7つのサウナをフロアに点在させて“川的な風景”で繋げました。施設の場所はこちら(Google Map)。
心斎橋商店街に面した元ボーリング場の11階建てビルの4階に、サウナを中心とした温浴施設を作るプロジェクトです。
テナントビルによる制約も多く、屋外空間もない閉鎖的なコンテクストの中で、「日常の延長」としてのサウナにするために、人それぞれで多様な動線が生まれる「庭のような建築」を考えました。
2つの浴室の中には、7つのサウナ、2つの風呂・4つの水風呂、外気を感じられる休憩スペース、はなれのような黙浴スペースで構成されています。7つあるサウナは、風景を切り取る大きな窓があるサウナ、川に直接飛び込めるサウナ、土手に寝転ぶようなベンチがあるサウナなど、庭との距離がそれぞれ違うサウナを作っています。
風呂や水風呂や掛け湯は、かつてこの場所に流れていた長堀川のように、連続した水系として浴室全体を横断します。川によって対岸が生まれ、橋や飛石が置かれ、川に浮かぶ小屋や土手など、川的な風景が立ち上がります。「庭のような建築」に呼応するように、さまざまなランドスケープが感じられるようにしています。
2つの浴室は桟橋部分の扉によって1室空間にもなります。この浴室とは別に、グループで貸し切れるサウナもあります。ラウンジは使い方を規定しすぎないように、床の段差のみで構成しています。どの順番でサウナをめぐるか考えたり、好きなところに腰かけたりテーブルとして使ったりと自ら場所を探すことは、まちの体験とも連続します。


愛知を拠点に建築等の撮影を手掛け、雑誌社にも多数依頼される「トロロスタジオ」の、フォトグラファー(未経験者も可)募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
愛知を拠点に建築や美術の撮影をしている「トロロスタジオ」が、フォトグラファー(経験者・未経験者可・既卒・2024年新卒)を募集中
【トロロスタジオについて】
トロロスタジオは、建築文化、芸術文化を深く愛する “ 記録係集団 ” です。
建築・美術・舞台・プロダクトの 写真・動画を撮影しています。
撮影を通じて、微力ながら文化の発展に貢献したいと考えています。私たちは現在3名で活動しているチームです。それぞれに得意分野を持って、全国各地で撮影しています。月に一度はBOGという名前の勉強会をして、お互いの知見を高めあっています。
田島ナナ
中村マユ
谷川ヒロシ私たちはニシヤマナガヤというシェアスペースに事務所を構えています。1Fには、花屋さん、珈琲屋さん、焼き菓子屋さん、2Fには私達の事務所のほか、建築設計事務所、キッチン設計事務所、そして色々な教室が開催されるレンタルスペースがあります。ここを訪れる多様な人達と交流することで、視野を広げることができる環境です。
【代表 谷川ヒロシについて】
学生時代に友人らと共に空間デザインの事務所を開始。シーラカンスアンドアソシエイツ等を経て2007年に独立。その後病気になり3年半くらい病室か寝室で過ごす。リハビリと思っていた建築や美術の記録が楽しくなってしまい現在に至る。建築/美術バカ。来世では必ず建築家か芸術家になる予定。私が本格的に写真を始めたのは40歳の時です。初めは月に1、2件しか撮影依頼がなかったのですが、徐々に建築や美術の分野で活躍されている方々からもお声がけ頂けるようになりました。頼もしいメンバーが増え、チームでしか成し得ない仕事もできるようになってきました。建築や美術の分野で新しい世界を見せてくれる方々に、微力ながら貢献できることに喜びを感じています。




丹羽隆志アーキテクツが設計した、ベトナムの飲食店「矢澤ハノイ」です。
歴史あるヴィラを改修した焼肉の店です。建築家は、調理に用いられる“鉄”に着目し、鉄で彩った空間が連続して風景となる建築を志向しました。そして、地域で普及する“鋳物”で店名を参照した“紋章”を作ってスクリーン等の様々な場所に用いました。店舗の場所はこちら(Google Map)。
焼肉という料理の面白さは生肉が鉄板で調理されることで状態が変化する様を楽しむことである。
焼肉レストランヤザワは食材とともに、肉を焼く機械、特に鉄板、鉄網へのこだわりが強く、それがクオリティへと直結している。ハノイに新しくできる彼らのレストランを考えるにあたりこの鉄という素材に着目することで、食の風景から空間までを通したオリジナルな場をつくれるよう考えた。
鉄自身が変化すること、鉄によって変化するものを対比させたり融合させる。鋳物、弁柄、鉄棒、鉄板などと、鉄によって彩られた空間によって表現されたシーンが連続する風景をつくり、もの、ひと、空間がインタラクティブに交わる場を作る。
敷地はハノイの街を代表するような改修と増築を重ねたフレンチヴィラ。様々な形で鉄の持つ力を与えて改修を行い、新旧のコントラストをつくり出す計画である。
鋳物はフレンチコロニアル時代から一般的にハノイで使われる材料・構法として発展してきた。
本プロジェクトではそのポテンシャルを活かして、オリジナルのアイアンスクリーンを製作した。レストランの頭文字Yを用いた135×125mmの鋳物のエンブレムをつくり立体的に編み込むように溶接して組み合わせた。
三次元の曲面をもつエンブレムは、3Dプリンターで作製したモックアップを型にローカルの製作工場で鋳鉄にて量産製作した。このエンブレムは照明やテーブルの天板、店のロゴマーク、ワインショーケースにも敷衍して利用することで店のアイデンティティをあらゆるシーンで表現した。


集合住宅や住宅などを手掛け、より大規模な建築へのチャレンジも進める「川辺直哉建築設計事務所」の、設計スタッフ(2024年新卒・既卒・経験者)募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
株式会社川辺直哉建築設計事務所 設計スタッフ募集
現在、集合住宅、住宅をはじめ、別荘、宿泊施設、テナントビル等のプロジェクトが進行中です。
海外では、カンボジアでサービスアパートの設計監理、病院建築の設計監修、住宅や内装設計を行い、国内でも広島の子ども施設、新潟の特別養護老ホームなど、福祉関連施設の設計監理にも取り組んできました。沖縄や逗子などでも積極的に別荘建築の提案を行い、プロジェクトも現在進行中しています。その中でも住宅と集合住宅の件数は多く、特に集合住宅は弊社の強みでもあり、クライアントと事業立案の段階からご一緒していますので、将来このような仕事に関わりを持ちたい方には、有益な職場環境です。
これまで、能力や熱意に応じて1年目からプロジェクトの担当者として、企画立案・基本設計・実施設計から現場監理まで一貫して携わってもらいました。経験年数によらずプロジェクトを担当してもらうので、当然責任も生じますが、努力や取り組み次第で成長を感じられると思います。
今後はこれまで手掛けていないプログラムや規模の建築にもチャレンジしていきたいので、一緒に議論に加わってくれる設計スタッフを募集します。



桑原淳司建築設計事務所が設計した、大阪・豊中市の住戸改修「豊中の家」です。
閑静な住宅地にある集合住宅の中での計画です。建築家は、“上質で洗練された空間”の要望に、様々な種類の“素材”や“照明”の使い方に注力する設計を志向しました。また、既存サッシの内側に設けた造作建具は上質さと共に機能性も向上させています。
大阪府豊中市の閑静な住宅地に建つ5階建てマンションの改修。
「上質で洗練された空間を作りたい」とのご要望を頂きました。
玄関に入って一番最初に見えるのは、和室の入り口に備えられた簾虫籠(すむしこ)と呼ばれる、竹を細く(幅4mm)割ってつくった格子を無数に使用した障子です。閉塞感のあった玄関すぐの廊下に坪庭のような光が差し込むスペースが欲しいとの要望で設置しました。
玄関から左右に展開する廊下の天井面にはダウンライトの設置を避け、スリット状の間接照明を端から全体に通すことでシンプルで美しく仕上がりました。足元のマイクロフットライトは実用性と照明のアクセントとしてリズムを崩さないよう等間隔に設置しています。壁と天井には珪藻土を採用し、壁に施したハケ引きの表情が間接照明に照らし出され、シンプルな廊下に暖かな手触りを持たせています。
LDKや寝室、書斎の既存アルミサッシの内側には、壁をふかした上で造作の引き戸と調光ロールスクリーンを取り付けました。これにより断熱や遮光、防音性能の向上に加え、既存アルミサッシを視界から消すことで木や土の素材に囲まれた、より上質な住空間とすることができました。




神出顕徳 / 3411 STUDIOが設計した、和歌山市の「神前の家族葬会館」です。
幹線道路が交差する角の敷地です。建築家は、情報化社会での“建築形態”を考慮し、街のスケールとの“整合性”も意図した量塊を二分割する建築を考案しました。また、内部では精度の高い“お見送り”の場として“木架構が連続”する空間を作りました。
県道が交差する角地を敷地とした葬儀会館の計画。敷地西側にはJR和歌山駅と貴志駅を結ぶ私鉄が走っており交通量が多い場所である。このように、和歌山市内の家族葬会館が建つ場所は、マーケティングを優先し比較的交通量が多い道路に面する傾向がある。
葬儀は、故人の最期を偲ぶセレモニーであるとともに、御見送りという過程を通して参列者が故人と向き合い、自分の人生にも想いを巡らす節目の時間と場所であるように思われる。そこに価値を見出し、我々は大切な者の死を迎えた時、葬儀という形をもって故人と別れを告げながら、自身の過去を回顧し、未来を想像するのであろう。
内部の空間について。
家族葬は親族のみで行われるケースがほとんどで、前時代的で派手な葬儀とは異なる。故人とのこれまでを回顧し、お見送りをする場としての精度が求められている。街に対して。
1ヶ月の多くは、葬儀が行われずボリュームとして街に存在する。市内で見かける葬儀会館はいわゆる家形のロードサイドショップで躊躇なく看板等が立ち並ぶ。日常的に利用しない葬儀会館から放たれるその異様さに以前から違和感を感じていた。情報化社会となり、広告塔等による集客が終わりを迎える今日、葬儀会館の建築形態は、益々環境との対話により生み出されるものであるべきではないだろうかと考えた。


デザインを通して“豊かで楽しい社会づくり”に貢献する「ALA INC.」の、設計スタッフ(2024年新卒・既卒・経験者)と 事務職募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
現在、下記の設計スタッフ、事務スタッフの募集をしています。
別荘、ホテル、集会場、共同住宅、アートプロジェクト、開発のマスタープラン、リノベーション等のプロジェクトが進行中です。
事務所は代官山蔦屋書店の近くにあり華やかな環境にあります。昼食・カフェ費用の補助の他、芸術鑑賞の費用全額負担やマッサージ・スパ費用の補助もあります。デザインが大好きな方募集しております!興味のある方は是非ご連絡ください!
【代表プロフィール】
梅澤竜也
1982年東京都生まれ。2008年隈研吾建築都市設計事務所入社。
海外プロジェクトやアートプロジェクトを主に担当。設計室長を経て、独立。
2017年に ALA INC. 設立、主宰。【代表メッセージ】
私たちはデザインを通して、豊かで楽しい社会づくりに貢献したいと思っています。
具体的にはホテル、ショップ、 レストラン、住宅、工場、エリア開発から家具やアートなど幅広いスケールで取り組んでいます。
そんな多彩なプロジェクトを通じ、日々新たな出会いや価値の発見に喜びを感じながら、それを1つひとつの形にしています。
楽しんで一緒に活動してくださる方のご応募をお待ちしています。

重松象平が「2023毎日デザイン賞」を受賞しています。
クリスチャン・ディオール展の空間デザインや、虎ノ門ヒルズステーションタワーの建築デザインで評価されました。
毎日デザイン賞とは
グラフィックやインテリア、クラフト、ファッション、建築など、あらゆるデザイン活動で、年間を通じて優れた作品を制作、発表し、デザイン界に大きく寄与した個人、グループ、団体を顕彰する賞です。(主催・毎日新聞社)
1955年に毎日産業デザイン賞として創設され、デザインの多様化を背景に76年に毎日デザイン賞と名称を変更した後も我が国のデザインの活性化とともに歩み続けています。国際的、文化的な賞として高い評価を受けています。
選考委員(50音順・敬称略)
齋藤精一(パノラマティクス主宰)/柴田文江(プロダクトデザイナー)/須藤玲子(テキスタイルデザイナー)/永井一史(アートディレクター)/保坂健二朗(滋賀県立美術館ディレクター(館長)
重松氏はニューヨークを拠点に世界各地で活躍している、今最も注目される建築家の一人。
2022年12月から翌年5月に日本で開催された「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展では、その空間デザインを担当。日本の地域性を反映させ、ディオールの世界観を読み解いた幻想的でダイナミックな空間は没入感に満ち、多くの人々を魅了して絶大な人気を博した。
また、「虎ノ門ヒルズステーションタワー」(23年10月開業)では、建築デザインを担当し、メトロ新駅直結の駅前広場が一体的に作られ、地下2階から3層にわたっての吹き抜けの大空間や、タワーの最上階にはホールやギャラリーを備えた情報発信拠点「TOKYO NODE」を設けるなど、都市再生の新しいかたちを壮大なスケールで実現した。
現在も「江戸東京博物館」の空間デザインなど複数のプロジェクトが進行中で、今後の活躍にますます期待が高まる。
以下に、評価の対象となった作品の写真も掲載します。


下町の雑司が谷を拠点に楽しく活動する「アトリエマナ」の、設計スタッフ(既卒・経験者・2024年新卒)募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
「アトリエマナ」では、一緒に働いて頂けるデザインスタッフを募集しています。
一級建築士事務所アトリエマナ(代表:河内真菜)は、「住宅地で別荘暮らし」をテーマに、身体に関する建築の環境造りを手がけています。五感で感じられる空間を大切にし、光や風、陰影などを巧みに取り込みながら美しく居心地の良い「居場所」づくりを心がけ、子育てや食事など、日々の生活の基盤となる空間をお客様と一緒に語らいながら設計していくことを大切にしています。
暮らしの基盤となる豊かで安らげる住環境のデザイン。
非日常を実現するVillaの建築空間。
保育園や幼稚園な、学童施設などの、子供の成長を促す環境つくり。
差別化できるデザーナーズマンション。スタッフが、好きな仕事を選択し、クライアント様の要望を「カタチ」にすることから、内装デザイン、家具デザイン、素材の選定、照明計画、環境デザイン、実施デザイン、現場監理まで一貫してクライアント様とともに造り上げるお仕事です。
デザインが好きで、いろいろなシーンを共感でき、共に働ける方を歓迎しております。雑司が谷は、漫画家の手塚さんや多くの文豪が在籍した歴史ある下町です。
また、多くの学校が隣接し、全国の若い世代から高齢者までが仲良く暮らす町です。
駅も4線利用でき、首都高の出入り口も3箇所と、東西南北どこにでも行ける便利な下町です。
見上げると高層ビル、一歩踏み入れると八百屋さんなどのある環境。
都心でありながらとても暮らしやすい穴場?な環境で建築デザインの仕事を手がけています。
事務所は、設計事務所などのデザイン事務所もいくつか入っている、SOHO可能なマンションです。
アトリエはメゾネットタイプの少し変わったプランで、アットホームな職場雰囲気です。「ハタラキ方について」
設計が好きで長く勤めたい方は、事務所にとっては大切なパートナーと考えています。アトリエの運営や職場環境ついて共に考えを相談し、大切に育てています。長く勤め、育休などを活用し、小さな子供を育てながら、好きな設計を長く続けているアトリエスタッフも在籍しています。独立を志す方もデザインの提案からお引き渡しまで丁寧に業務に携わることで、5年から8年程度でスキルをみにつけることが出来る環境を整えています。最初は小規模な案件から無理なく取り組み、コミュニケーションをとりながら丁寧に続ける事で、様々な規模構造の物件まで携われるようになります。資格を取得することも設計者として必要と考え、働きながら学べる業務体制を整えています。
仕事だけでなく、暮らしを大切にすることも設計者として大切な要素です。
自分の生きがいをみつけながら、いろいろな働き方をサポートする業務体制です。とてもアットホームな設計事務所で、アトリエマ見学なども実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。




高塚陽介 / TYdo architectsが設計した、静岡・磐田市の「西町の住宅」です。
祭典が盛んな地区での計画です。建築家は、祭り仲間で話し合える場を持つ住居との要望に、人が集まる“半屋外リビング”と“家族リビング”を備えた建築を考案しました。そして、二つの居間の間に中庭を設けて必要に応じて空間の分節も可能にしました。
静岡県の西部地方、磐田市の中心駅にほど近い住宅街の中にある、地域の集会所的な機能をもった木造二階建の住宅です。
駅から北に向かう駅前通りを中心に東側は再開発計画が完了し新しい街区へと生まれ変わったが、反対に西側街区は現在の車社会の感覚にはそぐわない幅員の道路と古い住宅、店舗が今も残るという対照的な街区内に当該敷地はある。
家族構成は夫婦と子ども二人。
地域の祭典に関する活動が活発な地区ということもあり、祭典準備期間中はもちろんのこと通年で祭典関連の会合が行われるコミュニティが深い地区でもある。通常会合は、会所や地区内の店舗で行われるものであるが、二次会やマンネリ防止で場所を変えて集まることもあるようで、施主からは、家族のプライバシーを守りつつも突発的な会合の場所として提供が出来る場を住宅内に組み込むことが求められた。
会合といっても所謂親睦の場でもあることから夕方から深夜までと開催される時間幅が長い。そこで会所としても利用できる半屋外のリビング兼駐車場を設け、中庭を介して家族リビングを配置する計画とし、ブラインドの操作で半屋外リビング+中庭や家族リビング+中庭、半屋外リビング+中庭+家族リビングとその時々に必要な空間に分節して使用できる配置計画とした。
さらにその招き入れ可能な空間から完全プライベートな空間までを4つのレイヤーに分割し、それを箱として積み重ねる形状とすることでこの住宅の印象的な意匠になっている。



勝野大樹 / 勝野建築事務所が設計した、長野・上伊那郡の「ハウスKA」です。
かつての典型的な間取りの住居を改修する計画です。建築家は、日照の良い場に“お座敷”が位置する既存に対し、平面構成の基準を“接客”から“家族”へと変更する設計を志向しました。そして、元座敷を欄間等を再活用した“開放的雰囲気”のLDKに転用しました。
祖父の世代が建てた住宅を、孫の世代が将来にわたり住み継いでいけるようにするため、大規模なリノベーション工事を行いました。
既存の住宅の間取りは、南向きの日当たりのいちばんいい場所に「接客」のための三間続きのお座敷が配置されている一方で、北側の薄暗く寒い場所に「家族」が日常的に使用する居間や台所が配置されている、ひと昔前によくみられた間取りのものでした。
設計においては、お座敷をLDKへと変更することで、明るく暖かい場所で「家族」の日常が営まれるようにし、かつての「接客」を基準にした間取りから、「家族」の生活を基準にした間取りへと変更を行いました。
またその際には、和室の特徴でもある「空間の連続性と視覚的な広がりによる伸びやかな開放的雰囲気」が残るよう、LDKは既存の障子や襖を取り払った一室空間としながらも、既存の欄間などを積極的に再利用することで、連なりながらも緩やかに区切られている、どことなく和室のしつらえを感じられるような空間を目指しました。