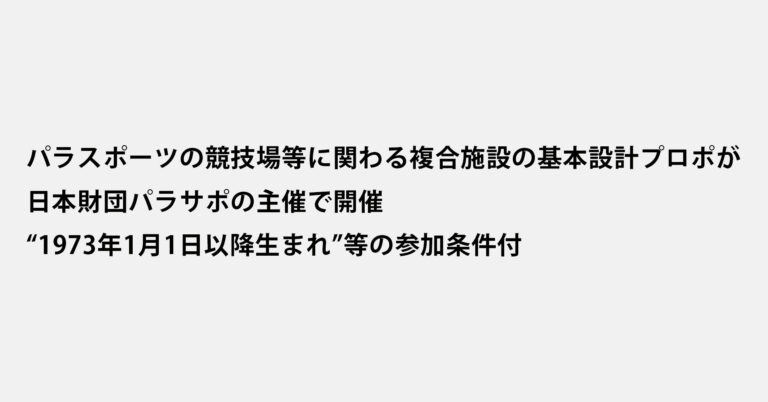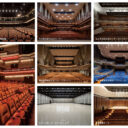ベネチア・ビエンナーレで金獅子賞を受賞した建築家らが率いる「waiwai」の、ドバイ及び東京での 設計スタッフ(2023年新卒・既卒・経験者)とアルバイト募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
waiwaiは、山雄和真とWael Al Awarの2人のパートナーが率いる、東京とドバイを拠点とする建築設計事務所です。
東京とドバイを拠点としながら、日本国内をはじめ、中東・アジア・アフリカの様々な国や地域において幅広い設計・デザイン業務を手がけています。一昨年のベネチア・ビエンナーレ国際建築展では、弊社パートナーがキュレーションしたUAE館が、最高賞である金獅子賞を受賞しました。単なる設計事務所の枠を超えて様々な活動を行っており、国際的に高い評価を得ています。現在進行中のプロジェクトに、数万㎡規模の美術館・アートギャラリーやホテル、大規模住宅地開発、数千㎡規模のホテル・ヴィラ/別荘・商業施設・福祉施設・リノベーション等々、多種多様なプロジェクトが動いています。
まだまだ若い事務所ですが、比較的大規模な民間の建築プロジェクトが複数同時に動いていることが特徴です。
クライアントや協働する関係者も国内外多様な人々と日々関わっており、チームメンバー全員が前線に立ちますので、組織設計では手に入れることのできない経験が得られるはずです。デザインの面においては、ひとつひとつのプロジェクトが真に求めているものを様々な角度から分析し、「そこにしかない物語」を構築することによって、関係者全員の意思共有を図るとともに、その都度全く異なったデザインを行うことを信条としています。
昨年度より、会社規模の一層の発展を目指した組織改編を行っています。中東地域を中心とする海外プロジェクトにおいても、日本チームとドバイチーム双方で携わり、すべてのチームメンバーが、国内外双方のプロジェクトに関わる機会を作っていきます。
本年は、この新たな体制づくりを見据えた新規メンバーを募集したいと思い、大きく2通りのキャリアパスを想定した募集方法としました。詳細は以下の[勤務地]の欄をご確認下さい。日本人として海外で、あるいは海外と活躍する、私たちwaiwaiでしか得ることのできない経験を元に他にないチームを共に作り上げていく仲間を募集します。
大きな視点で様々なプロジェクトに共に挑戦してくれる方の応募をお待ちしています。