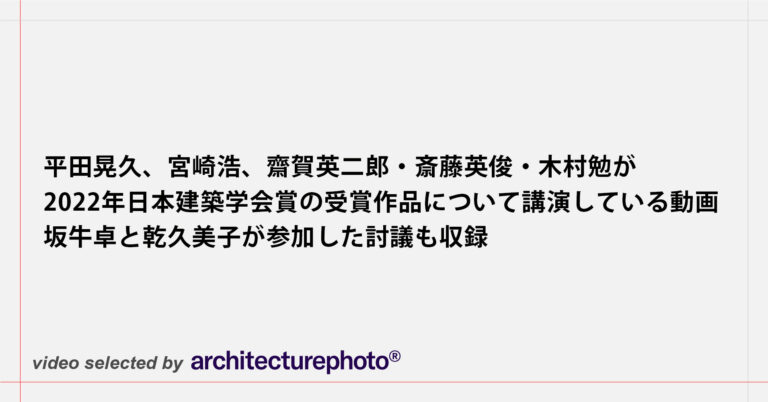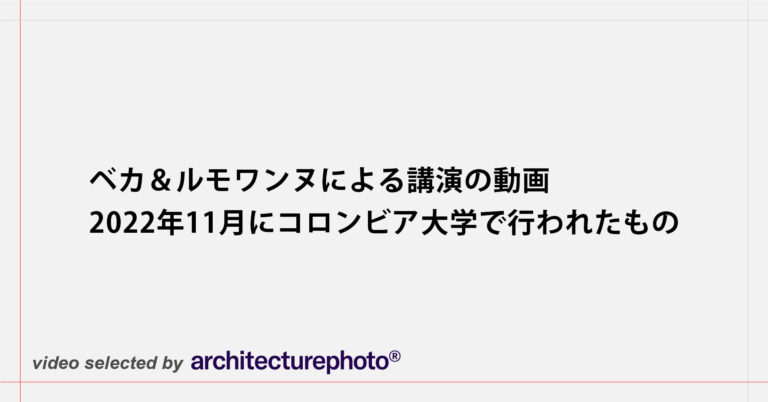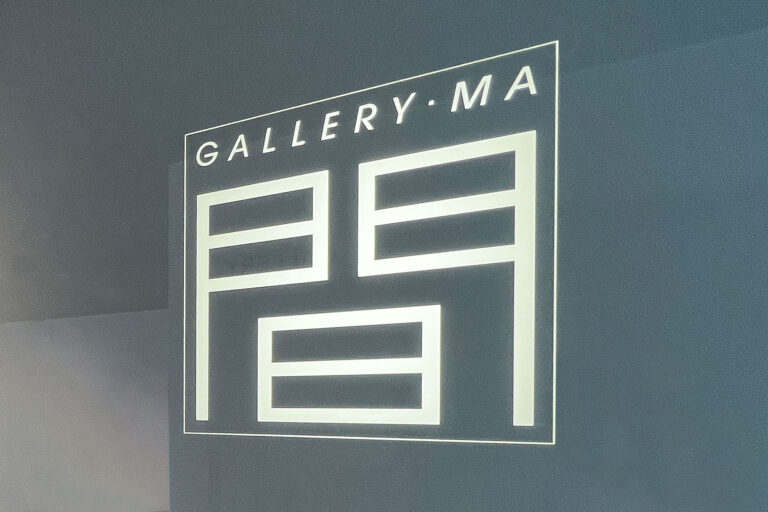湯浅良介による、富山・氷見市の住宅改修「となりはランデヴー」。移住した施主と機能や在り方を数年話し合い計画。街の奥行きとなる“秘密”の生成を求め、“落書き”の様な断熱建具を考案し開口に設置。シェードやデスクは“秘密の中身”の意味も重ねて設計 photo©白井晴幸 湯浅良介による、富山・氷見市の住宅改修「となりはランデヴー」。移住した施主と機能や在り方を数年話し合い計画。街の奥行きとなる“秘密”の生成を求め、“落書き”の様な断熱建具を考案し開口に設置。シェードやデスクは“秘密の中身”の意味も重ねて設計 photo©白井晴幸 湯浅良介による、富山・氷見市の住宅改修「となりはランデヴー」。移住した施主と機能や在り方を数年話し合い計画。街の奥行きとなる“秘密”の生成を求め、“落書き”の様な断熱建具を考案し開口に設置。シェードやデスクは“秘密の中身”の意味も重ねて設計 photo©白井晴幸 湯浅良介 が設計した、富山・氷見市の住宅改修「となりはランデヴー」です。
施主は氷見の海沿いに4階建のビルを購入し、その3階に住みながら宿やギャラリー、カフェとして改修し生活を営んでいた。そのとなりの一軒家も空き家だったため、何かに使えるかもしれないとしばらくして入手した。しかし何年も使われていない空き家だったことで内部は痛み、冬は寒く夏は暑く、そのままではとても利用できるものではなかった。
とりあえず不要なものは取り払って断熱材でパッキングしてほしい、というのが施主からの最初の依頼で2020年のことだった。この場所が何になるかも決まっていないため、仕上げも後から考えることになり、とりあえず不燃のボードで断熱材をおさえ、仕上げはパテ処理でとめておいた。
施主がこの家を購入してから、ここにどんな機能をもたせるか、どんな場所にするかを話し合ってきた。その話し合いは2年にも及ぶが、過疎化が進む氷見の街に越して2人きりで事業を始めた彼らにとって、どう生きていくか、どういう場所にするか、どういう街だったらよいかは地続きだったのだと思う。
この一軒家は海の目の前、交差点に面した角地にある。つまり、目立つ場所にある。ここを通り過ぎる人がここを見た時、何か違和感を与えられるものとすること、その違和感が街に秘密を生み出すこと、この時点で僕が提案したことはそれくらいだった。秘密は街の奥行きとなり、この場所を人の意識の向く場所とすること、それによりまだ何でもないこの家にある種のベールをかぶすことをこの段階での目標とした。
2021年下旬になってようやく使い方の目処がたった。施主からの要望は、1階を住居、2階を書斎にしたいというものだった。
1階の戸棚は廊下と住居スペースの間仕切りを兼ね、さらに接道する道路からの走行音を軽減する遮音壁と外気温の影響を軽減する断熱層のような役割を果たしている。2階は数人がデスクワークに使え打合せもその場でできるような大きなデスクと、その上部に卓上と空間全体を照らすシェードランプを設えた。