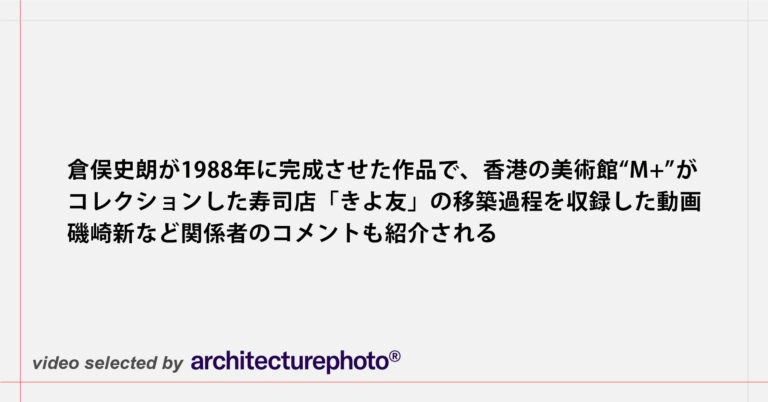スノヘッタによる、アメリカ・ニューヨークの、宿泊施設と学習センター「Cornell Tech Hotel and Education Center」。2棟別の建物として同時に計画、効率最適化のためバックサービスを共有するよう考慮され、建物形状とファサードの素材によりこの都市にふさわしい存在感を設計しています。
こちらはリリーステキストの翻訳
スノヘッタがニューヨークのコーネル・テック・キャンパスに2棟のビルを竣工
このビルは、ニューヨークの起業家精神に満ちた新しい住処を創造します
スノヘッタは、ニューヨークのコーネル・テック・キャンパスの玄関口となるよう設計された、独立して運営される2つの建物、グラデュエイト・ルーズベルト・アイランド・ホテルとベライゾン・エグゼクティブ・エデュケーション・センターを発表しました。2棟の建物は植栽されたエントリープラザで結ばれ、学術会議、授業、エグゼクティブプログラムに対応した柔軟なスペースと、宿泊客や島を訪れる人々のための宿泊・飲食オプションが結ばれています。この2つのビルが一体となって、ニューヨークの起業家精神が息づく新たな拠点となるのです。
中庭で結ばれた2棟の建物
スノヘッタは、約3390㎡のビジネスコンファレンスセンターの全体設計と、196室のホテルタワーのファサードデザインを担当しました。キャンパスに到着すると、まず18階建てのホテルタワーが目に入ります。その柔らかな曲面は、きらめくダブルハイトのアルミニウム製ファサードパネルで包まれています。V字型の柱は、共有の中庭に面した1階のバーへの入り口を示し、この入り口から1階の外周に沿って連続する軒裏は、最終的にベライゾン・エグゼクティブ・エデュケーション・センターに通じています。このカンファレンスセンターは、4階建てのキャンパスの中にあり、ホテルタワーのメタリックパネルを補完するように、垂直方向に木のルーバーで包まれています。この2つの建物は、中庭と蛇行した軒裏によって物理的につながっており、それぞれが太陽光を受けて反射し、視覚的にも互いに作用し合っています。基壇部には透明なガラスパネルが設置され、内部の集会スペースと隣接する中庭や景観を視覚的につなぎ、キャンパスのメインエントランスから建物内まで、そして最終的には建物を通しての眺望を広げています。
スノヘッタのディレクター兼シニアアーキテクトであるマイケル・コットンは、次のように説明しています。
「当初から、2つの建物を同時に設計するというユニークな経験でした。それぞれのプログラム、それぞれのクライアントに特徴的な表現が必要でしたが、最終的に建物は連携し、コーネル工科大学の大きなキャンパスの中に統合されます。設計を進めるうちに、共有の中庭を包む統一された基壇を作ることが、2つのプロジェクトをまとめる最善の方法であることがわかりました。高くて細いホテルは、公共空間を利用して、それに比べて低くて柔らかいベライゾン・エグゼクティブ・エデュケーション・センターとつながっているのです。」