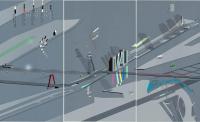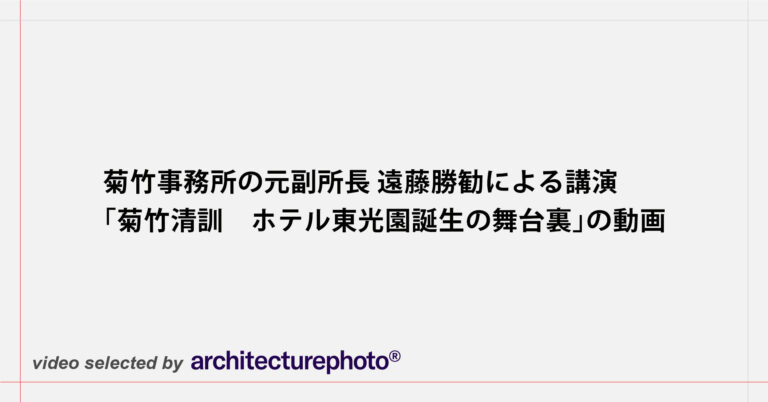MVRDVが計画している、ロンドンのハイドパーク脇に仮設で作られる丘のような構築物「Marble Arch Hill」。市議会の依頼でこの地域の関心を高めるために建設される image courtesy of MVRDV
MVRDVが計画している、ロンドンのハイドパーク脇に仮設で作られる丘のような構築物「Marble Arch Hill」。市議会の依頼でこの地域の関心を高めるために建設される image courtesy of MVRDV
 MVRDVが計画している、ロンドンのハイドパーク脇に仮設で作られる丘のような構築物「Marble Arch Hill」。市議会の依頼でこの地域の関心を高めるために建設される image courtesy of MVRDV
MVRDVが計画している、ロンドンのハイドパーク脇に仮設で作られる丘のような構築物「Marble Arch Hill」。市議会の依頼でこの地域の関心を高めるために建設される image courtesy of MVRDV
 MVRDVが計画している、ロンドンのハイドパーク脇に仮設で作られる丘のような構築物「Marble Arch Hill」。市議会の依頼でこの地域の関心を高めるために建設される image courtesy of MVRDV
MVRDVが計画している、ロンドンのハイドパーク脇に仮設で作られる丘のような構築物「Marble Arch Hill」。市議会の依頼でこの地域の関心を高めるために建設される image courtesy of MVRDV
MVRDVが計画している、イギリス・ロンドンのハイドパーク脇に仮設で作られる丘のような構築物「Marble Arch Hill」です。市議会の依頼でこの地域の関心を高めるために建設されるのだそう。
以下はプロジェクトの要約・抜粋です
MVRDVは、ロンドンのマーブル・アーチに隣接する仮設の「Marble Arch Hill」を発表しました。足場構造をベースにし、地上レベルをくり抜いた山である「Marble Arch Hill」は、オックスフォード・ストリートとハイド・パークの間のつながりを再定義し、公園とマーブル・アーチを見渡せる貴重な景色を訪問者に提供します。
ヨーロッパで最も賑やかなショッピングストリートであるオックスフォード・ストリートは、Covid-19の影響で特に打撃を受けています。通りのスペースを多様化させる計画が進行中ですが、これらの変更には数年の歳月がかかるでしょう。その頃には、ロンドンがパンデミックによって課された条件から浮上している可能性があるので、短期的に、ウェストミンスター市議会は、この地域に新たな関心を生み出すために仮設を利用しようとしていました。
MVRDVのこのインスタレーションの提案は、この場所の歴史からインスピレーションを得ています。マーブル・アーチはかつてハイドパークの角をマークしていましたが、1960年代には新しい道路が追加され、アーチは公園の他の部分から切り離されて、島のようになってしまいました。MVRDVのデザインは、芝生と木々の公園のような風景を導入し、ハイドパークのこの再現された一角を「持ち上げる」ことで、高さ25メートルの壮大なビューポイントを作りだし、オックスフォードストリートと公園の景観、そしてマーブルアーチ自体の新しい視点を訪問者に提供します。
「Marble Arch Hill」は、1本の連続したルートで体験することができます。訪問者は、丘の南側の斜面を登っていきビューポイントまで登り、丘の中心部にある大きなホールに降りていきます。ホールからの出口は、丘の角に設けられた切り欠かれた場所にあり、またマーブル・アーチからの距離が撮られています。このようにして、訪問者はマーブル・アーチを複数の視点から見ることができ、これまで当たり前と思っていたものを新たな視点で見ることができるようになります。
MVRDVの創設パートナーであるヴィニー・マースは語ります。
「このプロジェクトは、ロンドンの非常に認知度の高い場所に衝撃を与える素晴らしい機会です。ここは矛盾に満ちた場所であり、私達のデザインはそれを強調しています。このランドスケープの要素を加えることで、マーブル・アーチの都市レイアウトについての批評を行い、敷地の歴史に目を向けることで、この地域の未来についての解説を行います。公園を拡大し、角に持ち上げる。『Marble Arch Hill』は、オックスフォード・ストリートとマーブル・アーチを介した公園とのつながりを強化します。この一時的な追加は、1960年代の過ちを元に戻し、そのつながりを修復するために街を鼓舞するのに役立つでしょうか?」
「Marble Arch Hill」は、芝の上層部が成長するために必要な合板と土の層を支える足場構造を基礎に使用しています。戦略的なポイントとして、樹木を収容する大きなプランターを保持するために構造が適応されています。MVRDVは2016年にロッテルダムで行った「Stairs to Kriterion」のインスタレーションで仮設足場構造の変容の可能性を示し、一方、山のコンセプトはハイドパークの近くにあるサーペンタイン・パビリオンの2004年の提案(MVRDVの設計で建設される予定だった)を思い起こさせます。このデザインは、博物館が実現できなかったサーペンタイン・パビリオンの唯一のイテレーションであり、「Marble Arch Hill」では、この野心的なアイデアがついに実現することになります。
持続可能性は「Marble Arch Hill」の設計において重要な考慮事項です。一時的な構造物として、それが取り除かれたときに可能な限りほとんど廃棄物を生み出さないことを保証することは非常に重要です。従って設計は再利用を念頭に置いて作成されます。足場の構造はもちろん分解して再利用することができ、最上層を構成する要素である木、土、草のすべては、近くの庭や公園で利用されます。
「Marble Arch Hill」は2021年7月にオープンし、冬の閉館日は今後決定される予定です。