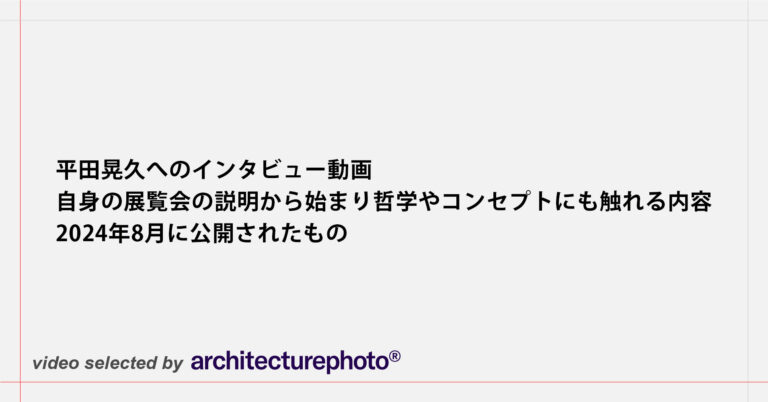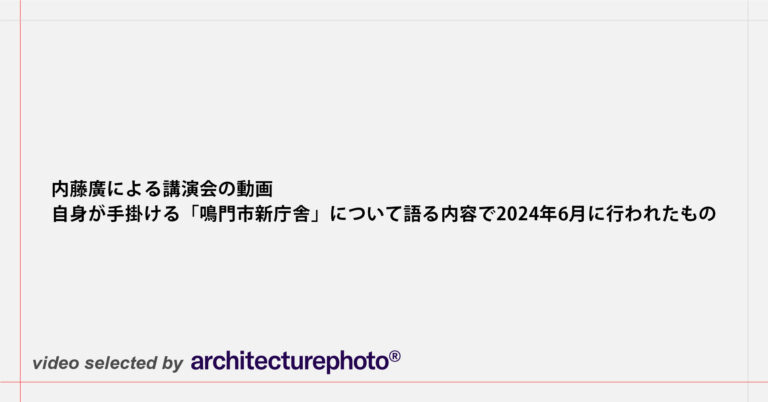長坂常 / スキーマ建築計画による、東京・世田谷区のオフィス「JAKUETS TOKYO MATSUBARA」。全国に支店のある企業の東京事務所の改修。会社全体の未来を考慮し、本社と全支店の関係を“双方向かつネットワーク型”とし“交流を繋ぐ”設計を志向。各地の職場同士を巨大モニターで常時接続する労働空間を考案2階、オフィス "Untitled (The Lined Office in Matsubara #639)", 2024 © Gottingham Image courtesy of Jakuets, Schemata Architects and Studio Xxingham photo©Gottingham
長坂常 / スキーマ建築計画による、東京・世田谷区のオフィス「JAKUETS TOKYO MATSUBARA」。全国に支店のある企業の東京事務所の改修。会社全体の未来を考慮し、本社と全支店の関係を“双方向かつネットワーク型”とし“交流を繋ぐ”設計を志向。各地の職場同士を巨大モニターで常時接続する労働空間を考案2階、オフィス "Untitled (The Lined Office in Matsubara #639)", 2024 © Gottingham Image courtesy of Jakuets, Schemata Architects and Studio Xxingham photo©Gottingham
 長坂常 / スキーマ建築計画による、東京・世田谷区のオフィス「JAKUETS TOKYO MATSUBARA」。全国に支店のある企業の東京事務所の改修。会社全体の未来を考慮し、本社と全支店の関係を“双方向かつネットワーク型”とし“交流を繋ぐ”設計を志向。各地の職場同士を巨大モニターで常時接続する労働空間を考案4階、オフィス、モニター側を見る。 "Untitled (The Lined Office in Matsubara #690)", 2024 © Gottingham Image courtesy of Jakuets, Schemata Architects and Studio Xxingham photo©Gottingham
長坂常 / スキーマ建築計画による、東京・世田谷区のオフィス「JAKUETS TOKYO MATSUBARA」。全国に支店のある企業の東京事務所の改修。会社全体の未来を考慮し、本社と全支店の関係を“双方向かつネットワーク型”とし“交流を繋ぐ”設計を志向。各地の職場同士を巨大モニターで常時接続する労働空間を考案4階、オフィス、モニター側を見る。 "Untitled (The Lined Office in Matsubara #690)", 2024 © Gottingham Image courtesy of Jakuets, Schemata Architects and Studio Xxingham photo©Gottingham
 長坂常 / スキーマ建築計画による、東京・世田谷区のオフィス「JAKUETS TOKYO MATSUBARA」。全国に支店のある企業の東京事務所の改修。会社全体の未来を考慮し、本社と全支店の関係を“双方向かつネットワーク型”とし“交流を繋ぐ”設計を志向。各地の職場同士を巨大モニターで常時接続する労働空間を考案5階、ストック、模型机側を見る "Untitled (The Lined Office in Matsubara #361)", 2024 © Gottingham Image courtesy of Jakuets, Schemata Architects and Studio Xxingham photo©Gottingham
長坂常 / スキーマ建築計画による、東京・世田谷区のオフィス「JAKUETS TOKYO MATSUBARA」。全国に支店のある企業の東京事務所の改修。会社全体の未来を考慮し、本社と全支店の関係を“双方向かつネットワーク型”とし“交流を繋ぐ”設計を志向。各地の職場同士を巨大モニターで常時接続する労働空間を考案5階、ストック、模型机側を見る "Untitled (The Lined Office in Matsubara #361)", 2024 © Gottingham Image courtesy of Jakuets, Schemata Architects and Studio Xxingham photo©Gottingham
 長坂常 / スキーマ建築計画による、東京・世田谷区のオフィス「JAKUETS TOKYO MATSUBARA」。全国に支店のある企業の東京事務所の改修。会社全体の未来を考慮し、本社と全支店の関係を“双方向かつネットワーク型”とし“交流を繋ぐ”設計を志向。各地の職場同士を巨大モニターで常時接続する労働空間を考案7階、ミーティング、フリースペースから会議室を見る。 "Untitled (The Lined Office in Matsubara #31)", 2024 © Gottingham Image courtesy of Jakuets, Schemata Architects and Studio Xxingham photo©Gottingham
長坂常 / スキーマ建築計画による、東京・世田谷区のオフィス「JAKUETS TOKYO MATSUBARA」。全国に支店のある企業の東京事務所の改修。会社全体の未来を考慮し、本社と全支店の関係を“双方向かつネットワーク型”とし“交流を繋ぐ”設計を志向。各地の職場同士を巨大モニターで常時接続する労働空間を考案7階、ミーティング、フリースペースから会議室を見る。 "Untitled (The Lined Office in Matsubara #31)", 2024 © Gottingham Image courtesy of Jakuets, Schemata Architects and Studio Xxingham photo©Gottingham
長坂常 / スキーマ建築計画が設計した、東京・世田谷区のオフィス「JAKUETS TOKYO MATSUBARA」です。
全国に支店のある企業の東京事務所の改修計画です。建築家は、会社全体の未来を考慮し、本社と全支店の関係を“双方向かつネットワーク型”とし“交流を繋ぐ”設計を志向しました。そして、各地の職場同士を巨大モニターで常時接続する労働空間を考案しました。施主企業の公式サイトはこちら。
JAKUETSは福井県敦賀市に本社を構え、遊具や教具などの企画・開発から製造・販売・メンテナンス、幼稚園・保育園や公園の設計から街づくり事業まで、教育に関わる多種多様な事業を展開する全国に67もの支店をもつ会社である。
その東京支店の改修にあたり、我々はこの1支店にとどまらず、本社および67支店の未来を考えた計画を行なった。
これまで全国の支店は各地域の顧客のニーズや事情に応えるべく、支店に在庫をストックし商品の現物を持ち運ぶような地域に根ざした営業スタイルで事業に取り組んできた。こうした1対1のコミュニケーションの分厚さで顧客の信頼を得てきたが、顧客層やニーズの多様化に加え、情報環境・物流が整った今では地域に縛られる必要性がなくなり、各支店は倉庫と社宅の空間を多くの地域でストックとして抱えることになった。
社内的には全国規模の市場をもちそこで培われたノウハウがあるにもかかわらず、地域で閉じたコミュニケーションにとどまり、さまざまな事業から集まる多様なニーズを部署間で共有する機会も気薄だった。それでも本社と67支店の結びつきは強いため、本計画ではその関係を双方向かつネットワーク型で結び全国のコミュニケーションをつなぎ合わせることで、JAKUETS本来の分厚さを未来に向けてより強固なものにしたいと考えた。
そのネットワークを実現するアイデアとして、約100インチのモニターをオフィスに置くこととした。そのモニターが別の支店にも配備されオフィス空間が常に画面に映し出されることで、全身が映り目線が合うスケール1:1のリアルなコミュニケーションをリアルタイムで行うことを考えた。しかしモニターに取り付けられるカメラの視野角には限りがあり、フロアの矩形と直行してモニターを置くとどうしても死角が生まれてしまう。
カメラが空間全体をカバーでき、かつどこにいてもモニターが見えるようにするには、フロアの角から斜め45°に角度を振って置くことが最も効率的である。その結果モニターがオフィスレイアウトの基準となり、その他の家具なども建築に対して斜め45°に配置されることになった。