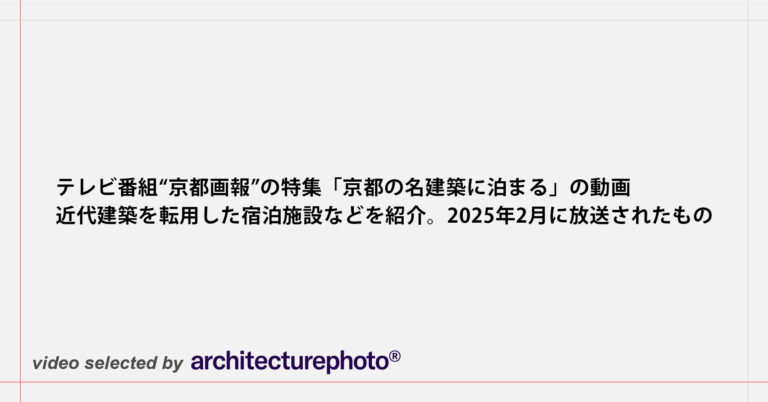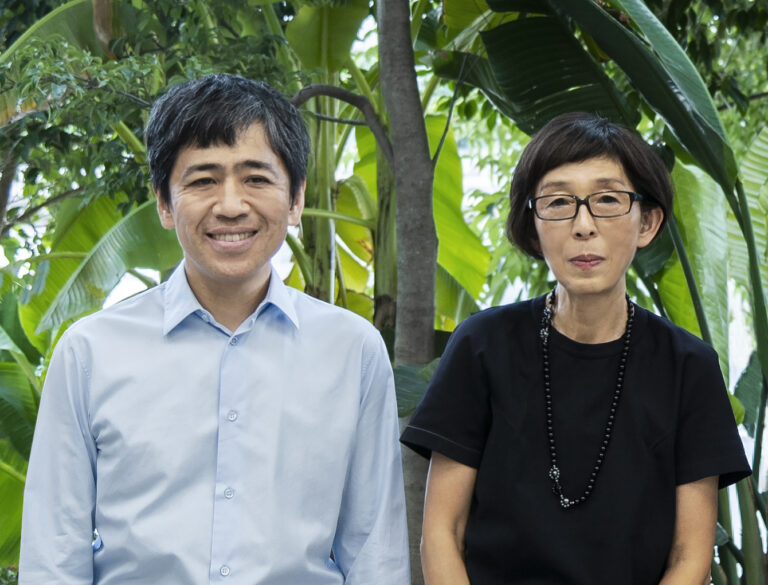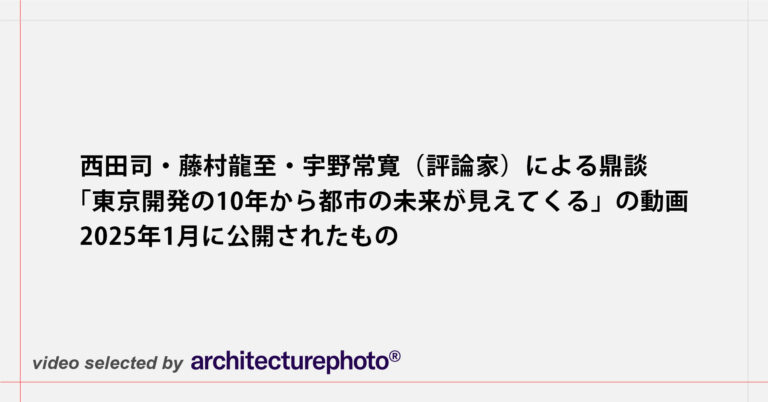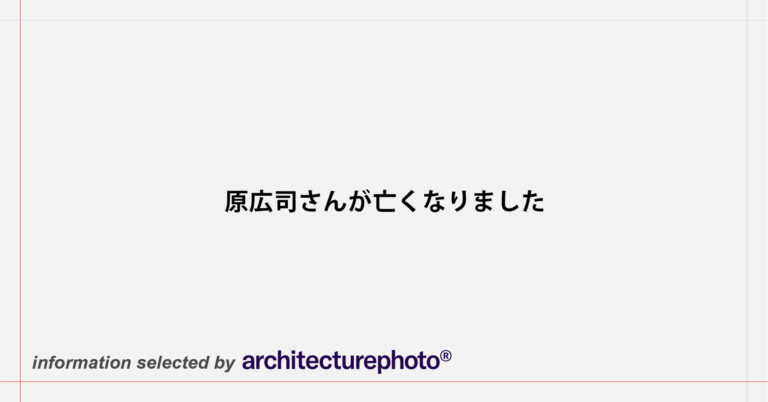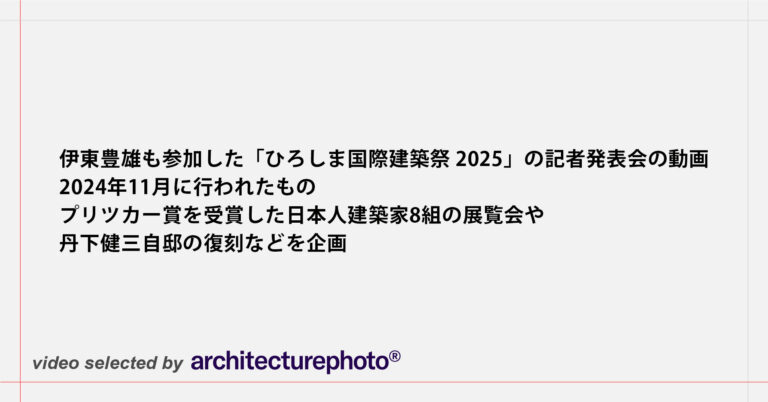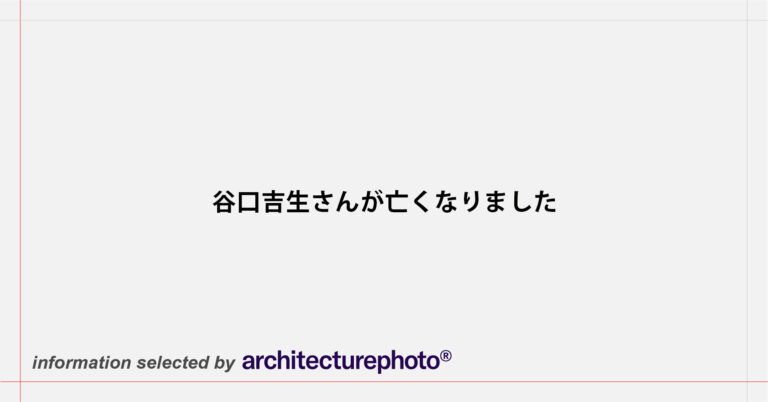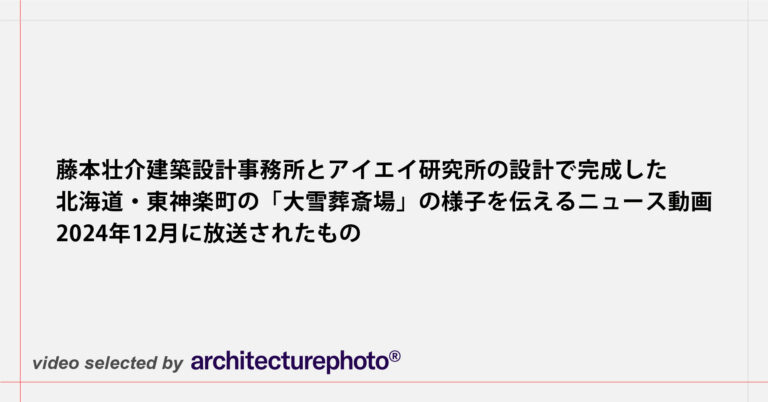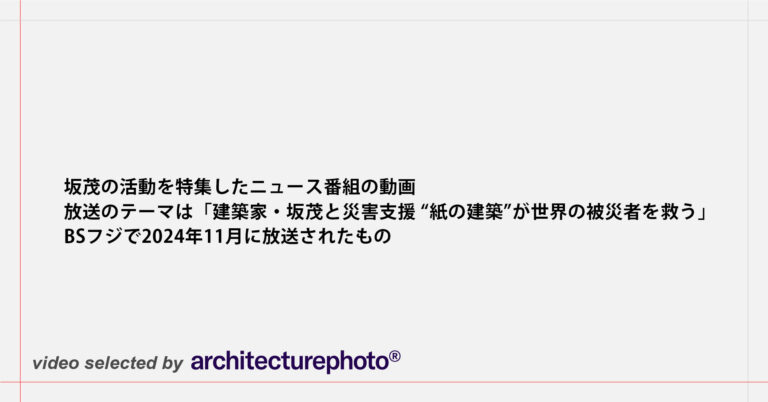MVRDVとNACOによる、チェコ・プラハの空港の拡張計画「The Czech Lanterns」です。
国内最大の空港施設の増築と新築です。建築家は、場所の感覚を備えた安らぎを与える存在を求め、国の衛星画像を施したガラス張りの外観で“ランタン”の様に発光する建築を考案しました。また、持続可能性も考慮して将来の拡張が可能な柔軟な空間を作ります。
こちらはリリーステキストの翻訳です(文責:アーキテクチャーフォト)
※リリース資料の公開は2025年2月ですが、テキスト自体の公開は2023年10月のようです
チェコのランタン:MVRDVとNACOがヴァーツラフ・ハヴェル・プラハ空港の柔軟な拡張設計をデザイン
MVRDVとNACO(オランダ空港コンサルタント)は、プラハおよびチェコ共和国最大の空港であるヴァーツラフ・ハヴェル・プラハ空港の3つの新しい建物の設計コンペで勝利を収めました。このデザインでは、空港ターミナル1を拡張し、空港のセキュリティエリアの主要なセキュリティ施設、ビジネスラウンジとVIPラウンジ、そしてヘリポートのための新しい建物が追加されます。空港環状道路の反対側には、ホテル、会議センター、駐車場を備えた別の建物が予定されています。これらの持続可能なハイブリッド構造は、将来の拡張や再編成にも容易に対応できる柔軟性を空港に提供します。一方、外観は、チェコ共和国の衛星画像を照明で照らし、プログラム可能な状態で「覆う」ことで、3つの「チェコ・ランターン」を形成し、新しい空港大通りを定義し、遠方からの訪問者を歓迎します。
この3つの建物は一体となって、飛行機で到着する乗客、あるいは車、タクシー、バスで空港に向かう乗客のいずれにとっても、到着時に最初に目にする空港の要素となります。ターミナル1の拡張工事自体は、既存の出発ホールを東側に2段階で拡張するもので、第1段階では、セキュリティチェックなどの乗客対応エリアが追加されます。4つの支持コアと大きな無柱スパンに基づくテーブル状のハイブリッド構造アプローチが、新しい建物の柔軟な基盤を形成します。構造の一部にはコンクリートと鉄骨が必要ですが、軽量中空コンクリート床を接着集成材梁で支えることで、構造物の炭素排出量を削減しています。
空港ループと滑走路の両方に正面を持つ2棟の空港ターミナル拡張ビルは、可能な限り透明性を高める設計となっており、ビル越しに反対側を直接見通すことができます。建物の間の中庭には、地元の植物が密に植えられ、セキュリティエリアの両側にはうっそうとした森のような景観が現れます。
第1段階では、セキュリティプロセスがシームレスになるように設計されています。垂直離着陸機用ポートへのアクセス、ビジネスラウンジ、VIPラウンジは1階に配置されており、セキュリティエリアにレベルの変化や不透明なバリアがないようにしています。これはつまり、旅行者の目的である滑走路が常に視界に入っていることを意味します。建物の両側に広がる自然の景色と相まって、これにより、空港内での旅行者の移動によるストレスを最小限に抑えることができます。
第2期の建物は、セキュリティ拡張部分と「双子」のように、同様の規模と構造原理で提案されています。設計チームは、この建物が滑走路に直接面していることが、空港の拡張が進む将来において非常に価値のあるものになると考えました。シンプルかつ柔軟なレイアウトにより、この建物エリアは将来的に空港の取扱いエリアの一部分へと容易に転換することができ、コストがかかるうえ持続不可能な再建プロセスを回避することができます。
建物は、チェコ共和国の緑色の衛星画像に「覆われている」ような状態で、内部の屋根と天井の両方にその画像が見えます。外観では、このプリントガラスに太陽光発電機能が組み込まれており、建物で使用するエネルギーの一部を生成します。また、建物にはプログラム可能な照明要素が組み込まれており、国内のさまざまな最新の出来事に関する情報を発信できるようになっています。このプリントガラスは、建物の特徴的な外観を提供するだけでなく、戦略的なポイントで日射を低減することで、プロジェクトの持続可能性を高めます。