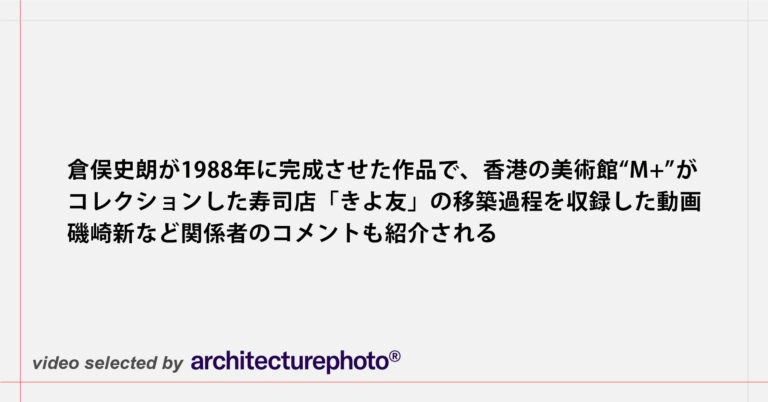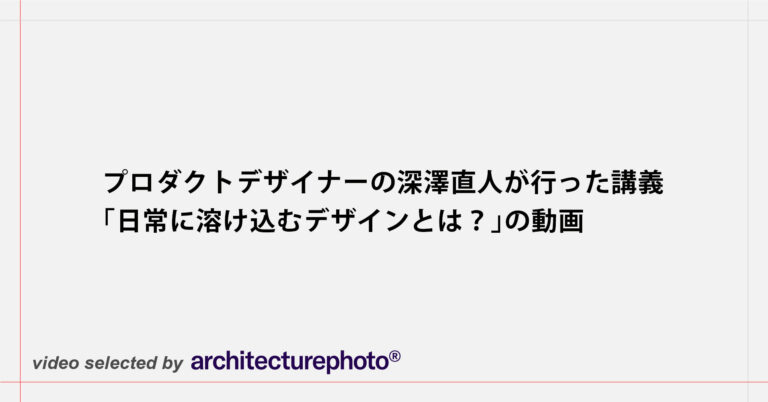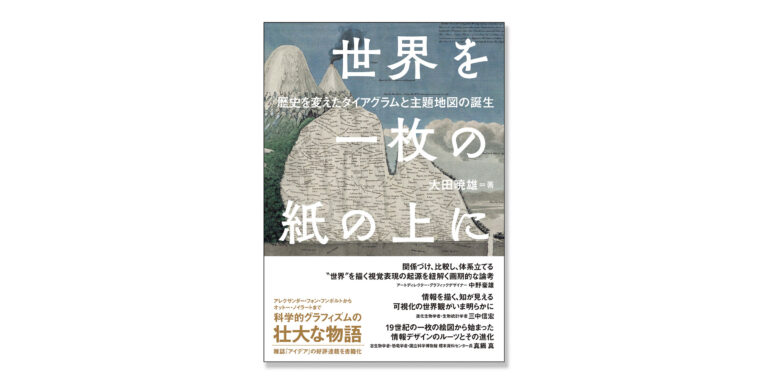スノヘッタによる、ノルウェー・オスロの、ノーベル平和センター前に設置された彫刻「The Best Weapon」です。ネルソン・マンデラの歴史的言葉“最高の武器は座って話すこと”に由来する作品名をもち、弧のデザインが人々を引き寄せ対話を促すことを意図、加えて環境に優しいアルミで造られています。
こちらはリリーステキストの抄訳です
この彫刻は、対話と平和的な会話を促すためにスノヘッタがデザインし、ハイドロ社とヴェストレ社とのパートナーシップで制作されました。
ベンチとしても機能するこのインスタレーションは、ネルソン・マンデラの歴史的な言葉「最高の武器は、座って話すことだ」にちなんで「The Best Weapon」と名付けられています。ネルソン・マンデラ氏の妥協、対話、思いやりといった人道的な理想と、他のノーベル平和賞受賞者、そして平和のための効果的な解決策を見つけるために人々を結集させた努力に敬意を表するものである。
ノーベル平和センターから委託された「The Best Weapon」は、2019年7月のネルソン・マンデラ・デーにニューヨークの国連本部の外に初めて設置されました。このたび、オスロのノーベル平和センター外の新しい恒久的な場所に移設されました。
重力を利用して人々を引き寄せる
スノヘッタのプロダクトデザイン・ディレクターであるマリウス・マイキングは説明します。
「ベンチの最も低い位置で地面に接する部分円形のデザインは、ベンチに座る人々を緩やかな弧で引き寄せ、その後、対話をさりげなく促します。」
このインスタレーションには、ハイドロ社のアルマイトが使用されています。このアルミニウムは、温室効果ガスの排出量が業界平均より大幅に少ない、世界で最も環境に優しい素材です。ベンチの表面を美しく仕上げるだけでなく、アルマイト加工は高い耐腐食性と傷からの保護機能を備えています。ヴェストレ社では、完全にカーボンニュートラルなプロセスで生産されています。ビーズブラストとプレディストレスを施した頑丈な素材は、ベンチの寿命を保証し、今後長年にわたって外交と対話を促進します。