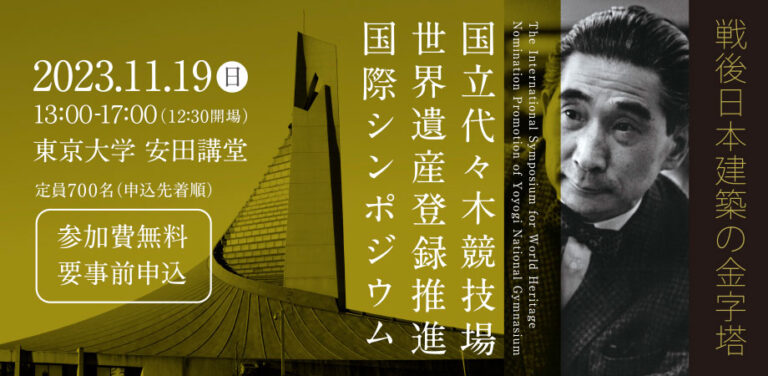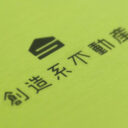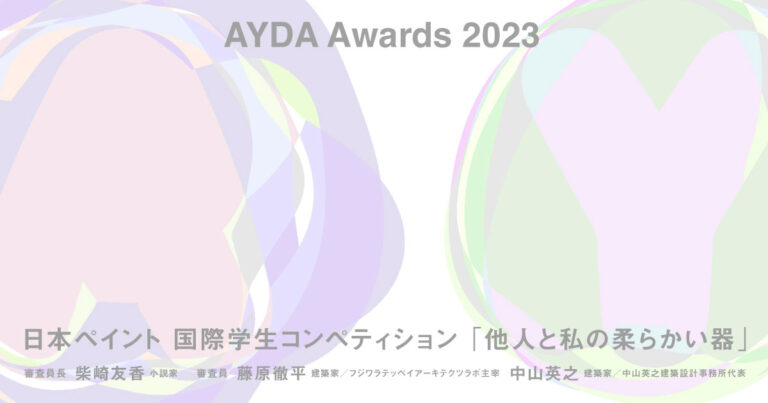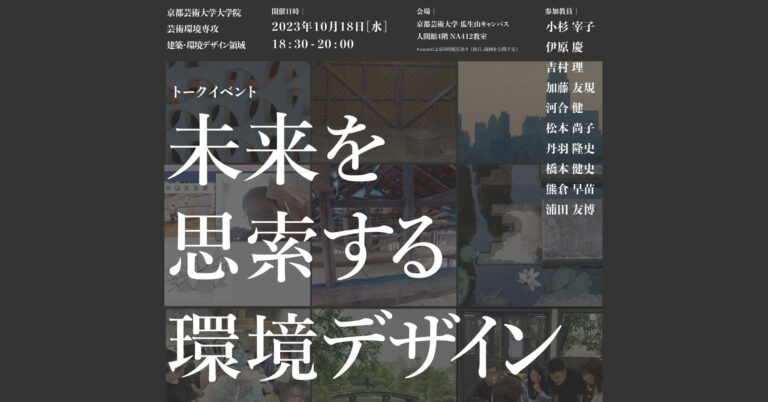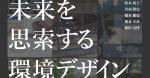別荘をメインとして、全国のリゾート建築を専門的に手掛ける「エムズ・アーキテクツ」の、設計スタッフ(2024年新卒・既卒・経験者)と秘書兼広報募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
私たちは、別荘をはじめとするリゾート建築を設計する設計事務所です。
リゾート建築は人生を豊かにする建築ですが、必要不可欠な建築ではありません。
だからこそ、夢のあるデザインが求められます。建築が好きで、夢や目標を共有できるスタッフを募集します。
好きな気持ちさえあれば、スキル、経験は仕事を通じて着実に身につくと考えます。
弊社の仕事を通じて、建築家、設計者としてのキャリアを育てたいと思います。①デザインを大切にしたリゾート建築
どういった案件で設計の仕事に携わるか、これは仕事の楽しさ、魅力につながると考えます。②1軒の別荘を設計できる能力を身につける
部分的な仕事をするのではなく、一通り全ての知識をつけてもらいたい。
キャリアを築く上で、一番大切で近道だと考えます。③スタッフそれぞれの個人の能力、経験、目標、希望に合わせて
意欲のある方にはチャンス、機会をつくります。
経験が少ない、若しくはまだ自身のない方には易しいところから無理せず、段階を踏んでスキルアップしていきます。④新しいツールの活用
最近導入したものとして、ドローンやVRを活用したプレゼン、3Dプリンタを活用した模型製作があります。
新しいツールはどんどん取り入れていきたいと考えております。⑤仕事を楽しむことが一番大切
弊社の設計している別荘とは、人生を楽しむためのもの。
夢のある作品づくりを、楽しんで仕事をしてもらいたいと思っています。