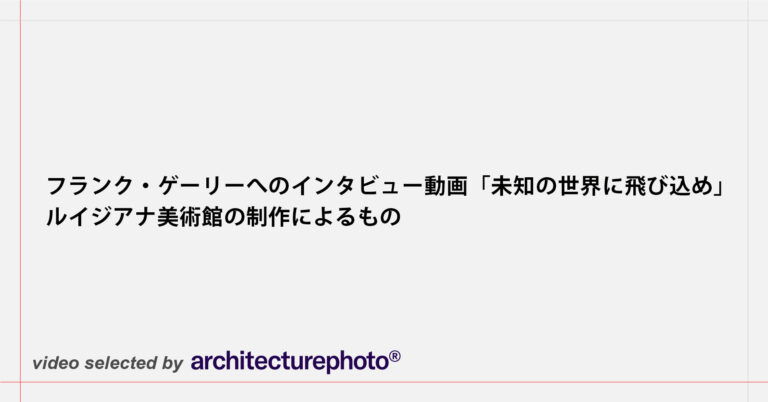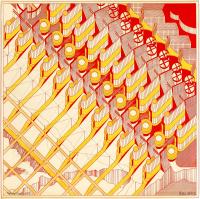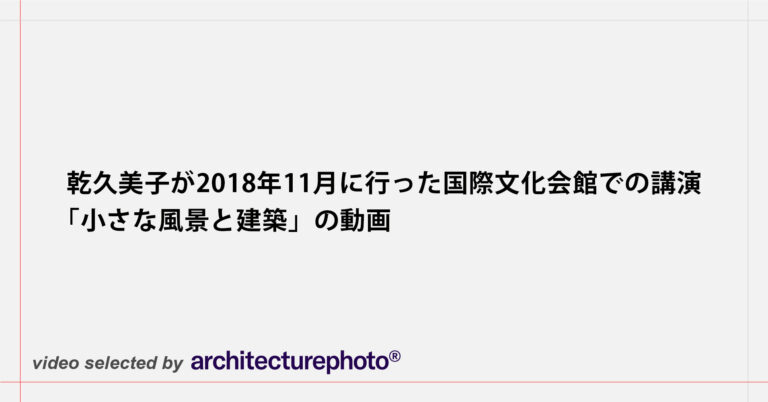リナ・ボ・バルディが1951年に完成させたブラジルの自邸「ガラスの家」の横に、ソル・カマチョ(sol camacho)設計のパヴィリオンが完成したそうで写真とアクソメが8枚、designboomに掲載されています。ガラスの家の写真はこちらで閲覧可能です。
remarkable archive
ヘルツォーグ&ド・ムーロンが、スイスのルガーノ湖畔に完成させた8戸が連続するヴィラ「castagnola」の写真が14枚、designboomに掲載されています。2017年に竣工していたようです。
乾久美子建築設計事務所が設計した宮崎の「延岡市駅前複合施設 エンクロス」を、設計担当者が解説している動画です。
動画制作者のブログにも建物の写真が数枚掲載されています。延岡観光協会のウェブサイトにも写真がたくさん掲載されています。施設のコンセプトが公式サイトにも掲載されています。
フランク・ゲーリーへの、ルイジアナ美術館によるインタビュー動画「未知の世界に飛び込め」が公開されています。約35分の動画です。
デイビッド・チッパーフィールドのウェブサイトに、中国・安吉県の「浙江自然博物館」の写真と図面が12枚掲載されています。
ジョン・ポーソンがドイツ・ウンターリーツハイムに完成させた、丸太を積み上げて作られた細長いプロポーションの内部空間が特徴的なチャペル「Wooden Chapel」の写真が6枚掲載されています。開口部にはサッシ等はなくプリミティブな印象の建物です。リンク先ページの写真をクリックするとスライドショーが閲覧できます。
アンドラ・マティンが設計した、インドネシア・ジャカルタの、水庭とそこに面する居場所の関係のデザインが秀逸な住宅「AW Residence」の写真と図面が35枚、archdailyに掲載されています。
余談ですがアンドラ・マティンはinstagramを活用していて、彼が訪問した世界中の建築の写真などがストーリーに投稿されるので見ていて面白いです。
西沢立衛の設計で建設が進められている、チリの建築プロジェクト「オチョアルクーボ」の為の住宅の写真がinstagramに投稿されていました。この建築プロジェクトには2014年時点では石上純也・平田晃久・アトリエワン・隈研吾も参加することが公開されていて、こちらのページにはその他の建築家の計画案を含む124枚の画像が掲載されています。建築プロジェクトの公式サイトはこちら。

RCRの、ギャラリー間で始まった建築展「夢のジオグラフィー」の会場写真が、japan-architects.comに掲載されています
RCRアーキテクツの、ギャラリー間で始まった建築展「夢のジオグラフィー」の会場写真が24枚、japan-architects.comに掲載されています。会期は2019年3月24日まで。
以下は、展覧会公式の概要です。
ラファエル・アランダ、カルマ・ピジェム、ラモン・ヴィラルタによって1988年に設立されたRCRアーキテクツ(以下、RCR)は、常に3人で対話を重ね、カタルーニャの土地に根差しながら詩情豊かな建築を生み出してきました。こうした彼らの活動が評価され、2017年にはプリツカー建築賞初の3人による同時受賞という快挙を成し遂げました。
本展ではRCRのこれまでの歩みに加え、「夢」をテーマに彼ら自身がカタルーニャ地方ガロッチャで進めている「ラ・ヴィラ」プロジェクトを紹介します。RCRは、広大な敷地に研究施設や工房、宿泊施設、パビリオンなどを配した「ラ・ヴィラ」において、人びとが集い、ともに学び、自然を空間として体感してもらうことで、知覚することそのものを学ぶ研究の場を実現しようとしています。
そのなかのひとつである「紙のパビリオン」は、RCRが長年にわたり影響を受けてきた日本文化との架け橋となるプロジェクトで、奈良県吉野町の人びとと協力し、吉野の木材を用いながら、RCR独自の世界観を表現しています。「紙のパビリオン」の構造体の一部分や、吉野をめぐる旅を追ったドキュメンタリー映像、RCRの手によるドローイングなど多彩な展示を通じ、RCRアーキテクツが長い時間をかけて実現しようとしている「夢のジオグラフィー」の一端をぜひ体感してください。
乾久美子が2018年11月に行った講演「小さな風景と建築」(モデレーター:藤村龍至・小林正美)の動画です。国際文化会館で行われたものです。
OMAが改修を手掛けた、中国・北京の「ウレンス現代美術センター(Ullens Center for Contemporary Art)」の写真などが8枚、architects newspaperに掲載されています。
ディーラー・スコフィディオ+レンフロが計画を公開した、ロンドンの捻じれたピラミッドのような外観形状が特徴的なコンサートホール「Centre for Music」のCG動画です。こちらのページで画像も閲覧できます。
島田陽が設計した「宮本町の住居」の、島田と施主のインタビューも収録した高クオリティな動画です。中国のメディア・一条の制作です。日本語で語られていて英語字幕付き。この作品はアーキテクチャーフォトでも特集記事として紹介していますので併せてどうぞ。
西澤徹夫建築事務所・タカバンスタジオ設計共同体がプロポで選定され設計を進めていた、青森の八戸市新美術館の実施設計概要版が公開されています。2017年3月にプロポの結果が公開されました。こちらでファイナリストの提案も閲覧できます。10+1websiteには、設計者の西澤と浅子にコンセプトを聞いた記事(2017年7月公開)があるので併せてどうぞ。
八戸市新美術館の実施設計業務が完了しましたので、その概要をお知らせいたします。(via city.hachinohe.aomori.jp)
青木淳に建築を志すキッカケや学生時代のエピソード等を聞いている、YGSAの学生によるインタビューが公開されています。