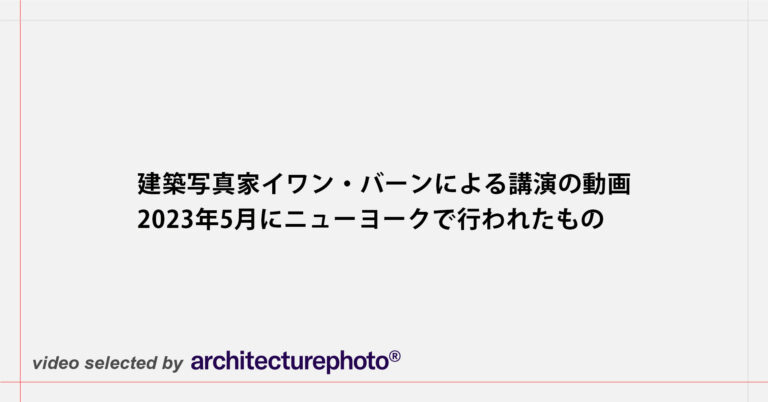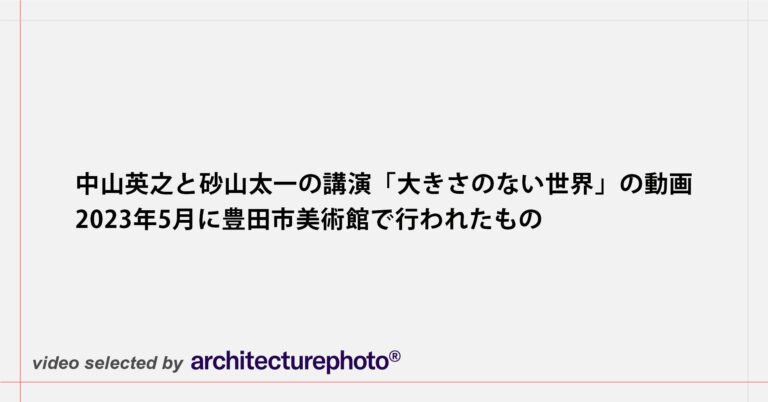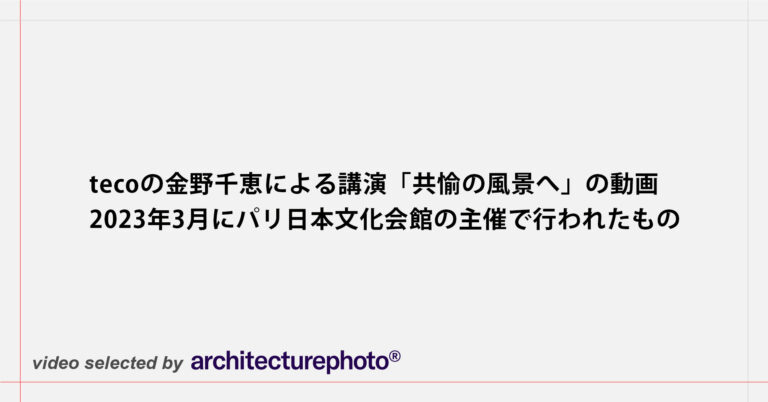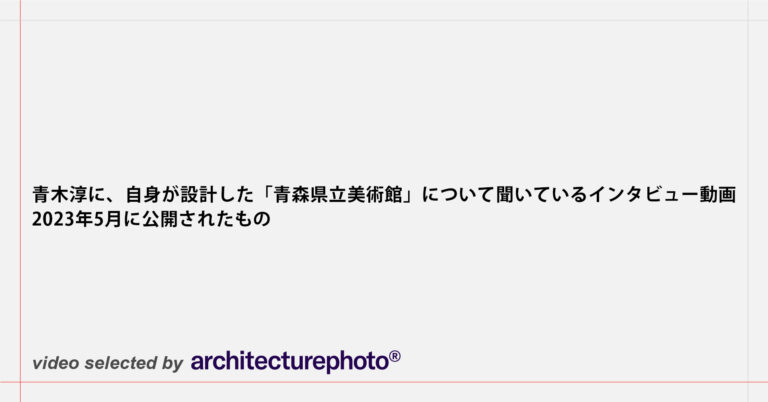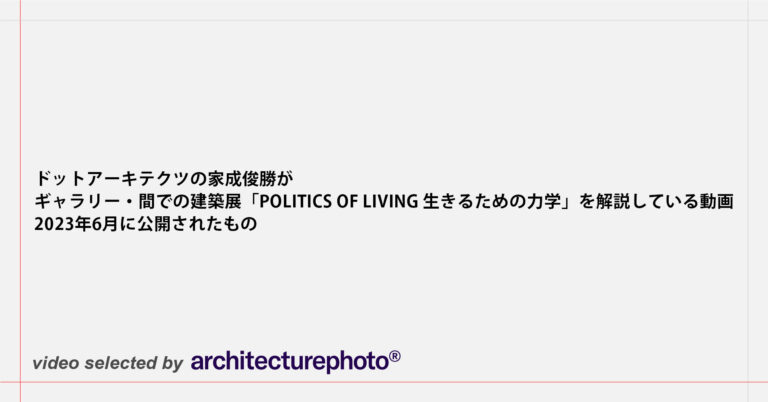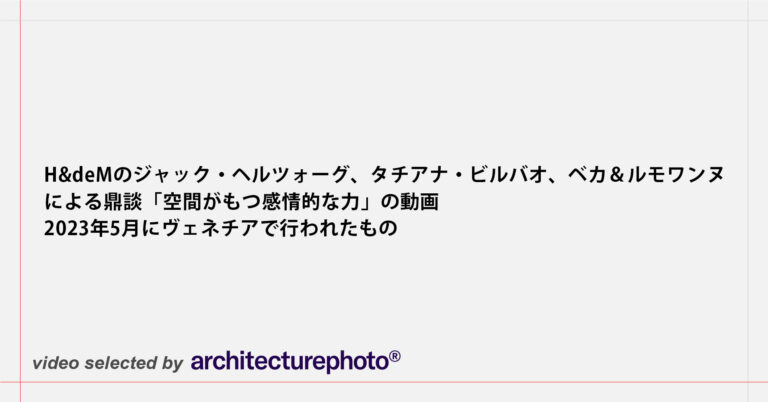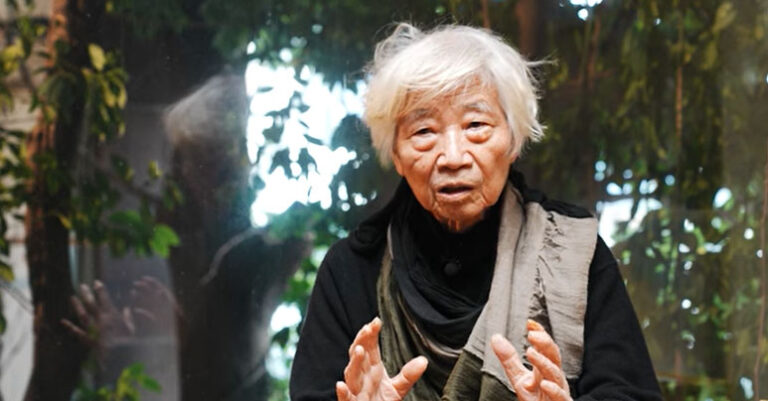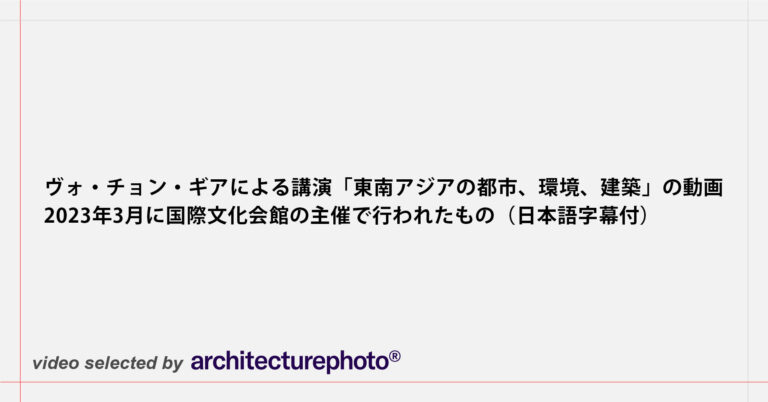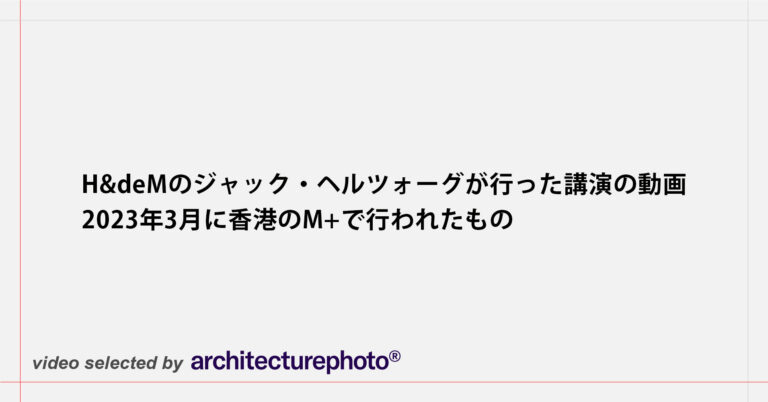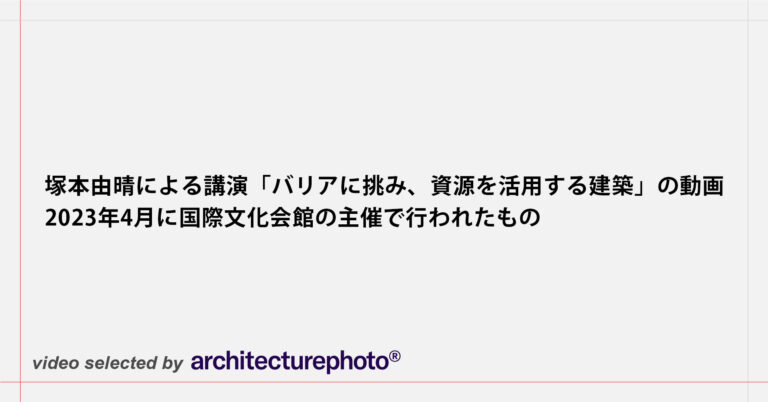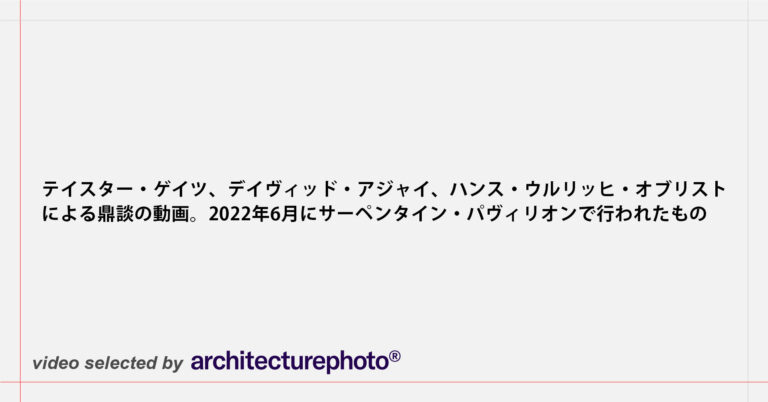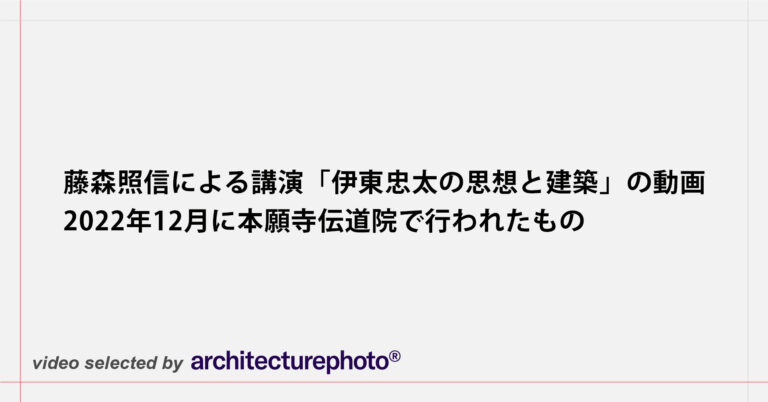建築写真家イワン・バーンによる講演の動画です。2023年5月19日にニューヨークのデザインイベント「NYCxDESIGN」で行われたものです。
(翻訳)
イワン・バーンは、今日の建築と都市デザインにおける代表的な写真家の一人です。 彼の写真は世界的な巨大都市の成長を記録し、ヘルツォーク&ド・ムーロン、レム・コールハース、ザハ・ハディドなど著名な現代建築家の建物を描いています。このオランダ人写真家による初の大規模な回顧展が、2023年秋にヴィトラ・デザイン・ミュージアムで開催されます。バーンの生き生きとしたリアリズムは、人々と建築環境との関係に焦点を当てています。その視野の広さにより、バーンの作品は人間建築の幅広いパノラマを提供しています。それは、建築と都市デザインの実存的な重要性を印象的に示しているのです。(原文)
Iwan Baan is one of today’s leading photographers of architecture and urban design. His images document the growth of global megacities and portray buildings by prominent contemporary architects including Herzog & de Meuron, Rem Koolhaas, and Zaha Hadid. The first large retrospective of the Dutch photographer’s work will open at the Vitra Design Museum in autumn 2023. Baan’s vibrant realism puts the focus on people and their relationship to the built environment.
Thanks to the great scope of his vision, Baan’s works offer a broad panorama of human building that impressively demonstrates the existential importance of architecture and urban design.