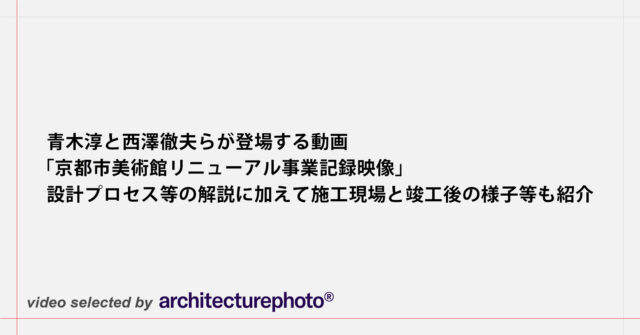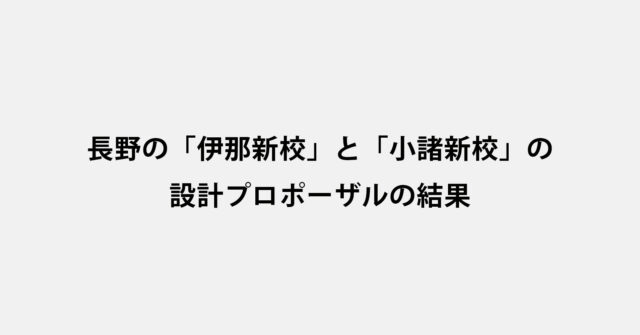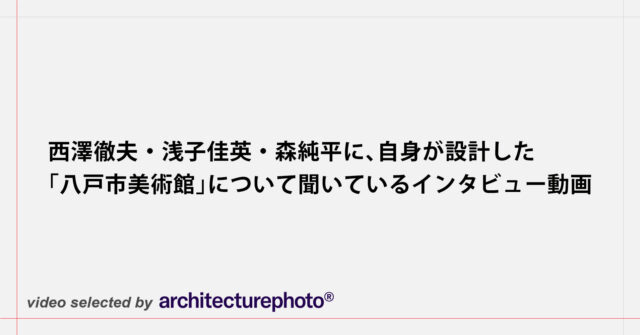SHARE “建築と今” / no.0007「西澤徹夫」
「建築と今」は、2003年のはじまりから、常に建築の「今」に注目し続けてきたメディアarchitecturephoto®が考案したプロジェクトです。様々な分野の建築関係者の皆さんに、3つの「今」考えていることを伺いご紹介していきます。それは同時代を生きる我々にとって貴重な学びになるのは勿論、アーカイブされていく内容は歴史となりその時代性や社会性をも映す貴重な資料にもなるはずです。

西澤徹夫(にしざわ てつお)
1974年京都府生まれ。2000年東京芸術大学修士課程修了後、2000-2006年青木淳建築計画事務所勤務。ルイヴィトン銀座店、青森県立美術館 基本・実施設計・監理を担当し、2007年に西澤徹夫建築事務所開設。2011〜2013年東京芸術大学教育研究助手。東京芸術大学、日本女子大学非常勤講師。主な受賞歴:2020年京都建築賞、AACA賞、2021年毎日芸術賞。主な作品:東京国立近代美術館所蔵品ギャラリーリニューアル、京都市美術館(青木淳と協働)、八戸市新美術館(浅子佳英、森純平と協働)ほか、展覧会の会場デザイン多数。
URL:https://tezzonishizawa.com/
今、手掛けている「仕事」を通して考えていることを教えてください。
昨年は京都市美術館が改修と増築を経てリニューアルオープンしました。
本館は二軸対称、帝冠様式の重厚な建物で、およそ現代において美術館を新築しようとするときには決して採用しないような強い形式を持っています。まずはこの本館の保存修復が起点にはなるので、何を決めるにもまず本館の意匠ありきになるのですが、ではすべてが本館の意匠に沿わせられるかというとそうはなりません。
例えば新しいエントランスであるガラスリボンは、プロポーションや大きさにおいて本館ファサードに(こう言ってよければ)調和するように腐心しましたが、そもそも本館が持っていた意匠ではないし、また、ガラスリボンのデザインがうまくいったからと言って中央ホールに新設した螺旋階段とは意匠的な繋がりは全くありません。
螺旋階段は中央ホール(旧大陳列室)との調和を優先して考えてあるし、それでさえ本来なかった材料や納まりを採用せざるを得ません。ガラス屋根を掛けた北中庭のスチール部分は、白では強すぎるのでタイルに寄せてややグリーンを入れていますが、それが新館の東山キューブの塗装色と関連しているかと言えば、していません。
しかし、厳密なデザインの繋がりはなくとも、どこかひとつを決めると常にそれとのバランスを考えて次の要素を抑えめにしたり太めにしたり、といったふうに決めていきました。
この作業中、これはとてもニュートラルさに関わることだと思っていました。
ひとつひとつの判断は、客観的な正解であるわけではなく、本館はもとより決定したデザインも無機質でも無彩色でも無個性でもないので、もちろん一般的な意味でのニュートラルではありません。むしろ出どころがバラバラな条件を、局所的に丁寧に解決しようとすれば当然の帰結として霧散してしまう各要素を、それらが独立しているとも言えるし全体としてバランスをとっているとも言えるような関係性のなかで成立させることが、手続きとしても出来上がったものとしても何かとても自然な状態に思えたのです。
恣意性のカタマリのような部分が、全体としてみれば「まあそれはそうかもしれない」と思わせるような全体性のあり方、もしくは共同作業におけるこのバランスの共有の仕方、その結果、スタイルとしてのニュートラルではなく「つくること」と「つくられたもの」に共に内在するニュートラルさのようなものが、とても気になっています。
今、読んでいる「文章」とそこから感じていることを教えてください。
ここ数年、アナキズム、というワードが頭をもたげていました。
ここでいうアナキズムは決してテロリズムや無政府主義を指す一般的な解釈ではありません。本来は階層秩序や国家支配なき協力関係、相互性を指す言葉です。むしろ原初的な共同体のあり方についての概念なのであり、an-archy、つまりなにか全体を統べるものへのアンチテーゼ、もしくは建築を指すarchi-tectureとほぼ対で考えることができるのではないか、というのが思いついたアイデアでした。
そこで手にとったのが、『実践 日々のアナキズム』と『可能なるアナキズム』でした。
特に前者には日常におけるルールの逸脱、反抗、サボり、不法占拠、常習欠勤といったささやかな抵抗、組織化されていない反乱が構造的変化に必要だと説きます。秩序に対する警戒を怠らず、時に秩序を「小さく」破ること、その先に国家に縛られない共同性の可能性や社会に潜む衝動の連帯の重要性を訴えるのです。と書くと、やはり破壊活動のように聞こえてしまうのですが、例示されているエピソードはどれもユーモアのあるものばかりで、つまりは、個々人のレベルにおいてなさなければならない部分と全体の関係についての絶え間ない問いこそが、わたしたちが本当の意味で近代化するために必要なことであると言っているようにも思えます。
近代とは、ひとりひとりが近代人となった前提で進んできた時代に過ぎないのであって、はたしてその前提は正しかったのだろうか、と問われているように思います。
今、印象に残っている「作品」とその理由を教えてください。
東京国立近代美術館で見たピーター・ドイグ展。
これまで画集の中のイメージを延々見てきたけれど、実物を見るのは始めてでした。まず驚いたのはサイズです。手前へスキージャンプする人物を描いた《オーリンMKIV Part 2》の下1/3は、奥行きのない黄緑色の、雪なのか芝なのか判別できないような薄塗りで、あまりにも表面に取っ掛かりがないのでずっと舐めるように見てしまう。
《ポート・オブ・スペインの雨(ホワイトオーク)》の画面の大半を占める黄色いブロックの壁は、その周囲に描かれているライオンや消えかかっている人物や灯台といった細かなモチーフが暗示するものを無いことにしてしまうような存在感で、目の行き場を失わせてしまう。
画面のなかにこんな「無意味な」色面を「大きく描く」ことの勇気ってすごいなと思います。そして意味を読み取ることを一旦保留にさせて、絵の具のカタマリだけがあるような表面に、見る者の目をどこまでも横滑りさせていく。我に返って、奥行きもサイズもない空間がもう一度画面を飛び出して体に迫ってくるのを経験すると、これはもうほとんど建築的なイリュージョンだな、と思うわけです。
実に豊かな色彩の戯れでありながら、そのなかに具象とも抽象とも言えないイメージが浮かびあがり、かつそれが空間を支配していく。それをそのように受容する人間の感覚とは一体なんなのか、どうしてそのような絵画と人間の応答が可能なのか、そしてこの事態を思考するということの繰り返しがまた、絵画経験となるのでした。