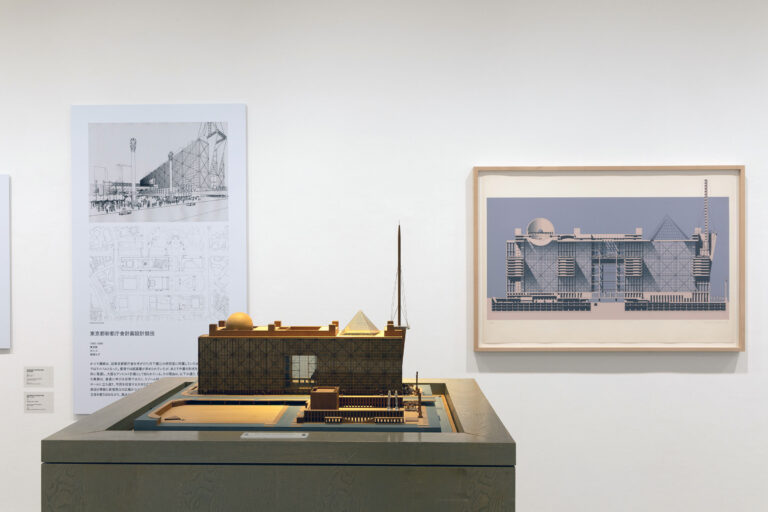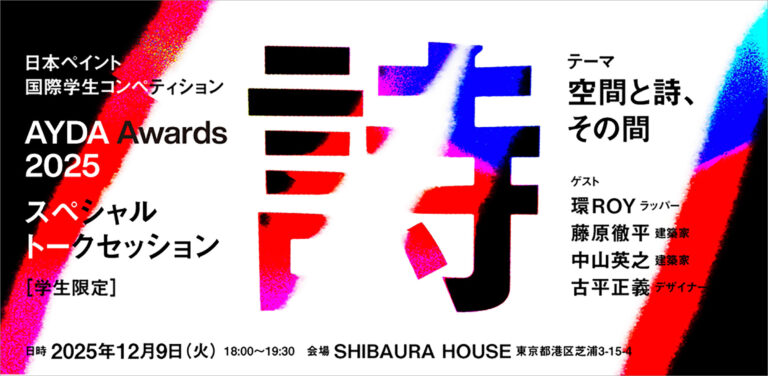青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 外観、西側の道路より見る。 photo©太田拓実 青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 1階、住宅部分、ダイニングからリビングを見る。 photo©太田拓実 青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 1階、住宅部分、リビングからダイニングとキッチンを見る。 photo©太田拓実 青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 2階、住宅部分、小屋裏から吹抜を見る。 photo©太田拓実 青柳創と青柳綾夏 が設計した、岩手の「金ケ崎の家」です。
この場所は、江戸時代からの武家屋敷群と、それらを囲う生垣が特徴的な街並みを形成する集落の中心「表小路」の突き当りに位置している。伝統的建造物群保存地区の規制がかかり、寄棟屋根で左官の真壁としなければ新築することが許されない。
間口は広いが奥行きが浅く、地域内では比較的狭い敷地において、外観規制の条件と要求された容積から南北に細長い建物外形がほぼ自動的に導き出された。武家屋敷風の外観を模すことは形骸とも思えたが、この集落にとっては街並みこそが重要な観光資源であり、県外から移住する建主にとっての集落に溶け込むための儀式的な側面もあったため、外観は街並みに馴染ませることを優先した。
一方で、建主や設計者の意思とは無関係に建物の外形が決まるということは、同時に内部に「空洞」を存在させてしまうという、奇妙な「反転」現象を起こしていることに気が付いた。先に空間があるという意味では改修に近いとも思えたが、それともどこか状況が異なる。改修対象の既存には空間に先行する構造体も合わせて存在するからだ。
つまりこの家は、通常の構造体が空間を形成していく設計・力学のプロセスとは異なり、先行する「空洞」の支え方を思考するという順序がまったく出鱈目の設計ということになる。このことに気が付いた時、新古典主義を代表するエティエンヌ・ルイ・ブーレーによる「ニュートン記念堂」の空洞が頭を過ぎった。ブーレーは建築の内部を宇宙へと「反転」させる巨大な装置を創造したが、この家は形式としての外観が「反転」して、内部に存在起源をもたない白昼夢のような空洞を生じさせているのである。
この空洞に相応しい逆説的な支え方を考えた際、空洞の暗がりの中から朧気に、繊細な柱群が浮かび上がる様を想像した。それは、いわゆる伝統的な古民家にあるはずの骨太で密な小屋組みの存在感が、極細の柱に集約され象徴化されるような様である。
以下の写真はクリックで拡大します
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 外観、西側より見る。 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 外観、西側の道路より見る。 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 外観、東側より見る。 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 1階、住宅部分、玄関側からリビングダイニング側を見る。 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 1階、住宅部分、ダイニングからリビングを見る。 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 1階、住宅部分、ダイニングからリビングを見る。 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 1階、住宅部分、リビングからダイニングとキッチンを見る。 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 1階、住宅部分、キッチン photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 1階、住宅部分、リビングから2階への階段を見る。 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 2階、住宅部分、小屋裏 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 2階、住宅部分、小屋裏 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 2階、住宅部分、小屋裏から吹抜を見る。 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 2階、住宅部分、小屋裏 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 2階、住宅部分、小屋裏から吹抜を見る。 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 外観、南側より店舗出入口を見る。 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 1階、店舗部分、広間から店舗出入口を見る。 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 1階、店舗部分、広間 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 1階、店舗部分、広間 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 1階、店舗部分、酵素風呂 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 外観、西側より見る。夜景 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 外観、西側より見る。夜景 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 2階、住宅部分、小屋裏。夜景 photo©太田拓実
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 1階平面図 image©青柳創+青柳綾夏
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 2階平面図 image©青柳創+青柳綾夏
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 断面図 image©青柳創+青柳綾夏
青柳創と青柳綾夏による、岩手の「金ケ崎の家」。寄棟屋根や左官真壁の採用が必須な地域。意思と無関係に“外形が決まる”状況に対し、通常と異なり“内部の空洞”の支え方を思考せざる負えない設計過程に着目。空洞を実態に変質させるべく極細列柱の構造体を考案 構造コンセプトモデル image©青柳創+青柳綾夏 以下、建築家によるテキストです。
反転の空洞 / 空間の反転
この場所は、江戸時代からの武家屋敷群と、それらを囲う生垣が特徴的な街並みを形成する集落の中心「表小路」の突き当りに位置している。伝統的建造物群保存地区の規制がかかり、寄棟屋根で左官の真壁としなければ新築することが許されない。
間口は広いが奥行きが浅く、地域内では比較的狭い敷地において、外観規制の条件と要求された容積から南北に細長い建物外形がほぼ自動的に導き出された。武家屋敷風の外観を模すことは形骸とも思えたが、この集落にとっては街並みこそが重要な観光資源であり、県外から移住する建主にとっての集落に溶け込むための儀式的な側面もあったため、外観は街並みに馴染ませることを優先した。
一方で、建主や設計者の意思とは無関係に建物の外形が決まるということは、同時に内部に「空洞」を存在させてしまうという、奇妙な「反転」現象を起こしていることに気が付いた。先に空間があるという意味では改修に近いとも思えたが、それともどこか状況が異なる。改修対象の既存には空間に先行する構造体も合わせて存在するからだ。
つまりこの家は、通常の構造体が空間を形成していく設計・力学のプロセスとは異なり、先行する「空洞」の支え方を思考するという順序がまったく出鱈目の設計ということになる。このことに気が付いた時、新古典主義を代表するエティエンヌ・ルイ・ブーレーによる「ニュートン記念堂」の空洞が頭を過ぎった。ブーレーは建築の内部を宇宙へと「反転」させる巨大な装置を創造したが、この家は形式としての外観が「反転」して、内部に存在起源をもたない白昼夢のような空洞を生じさせているのである。
この空洞に相応しい逆説的な支え方を考えた際、空洞の暗がりの中から朧気に、繊細な柱群が浮かび上がる様を想像した。それは、いわゆる伝統的な古民家にあるはずの骨太で密な小屋組みの存在感が、極細の柱に集約され象徴化されるような様である。
ここでの象徴化とは、古民家の太い大黒柱における蕩尽の意味合いとは異なり、手がかりがないと思われた虚無のような空洞内を暗中模索して掴んだ柱が、空洞を実態としての空間に変質させる瞬間を指す。
つまり、空間の実体化が「反転」して、建物の外形にも血を通わせる瞬間でもある。外部仕様のメッキを施された列柱は、このような内外の「反転性」を暗示させている。
外形を保持する小径の鉄骨柱(構造コンセプト)
大きな寄棟屋根が特徴的なこの建物は、外観から想像する通り内部に大きな小屋裏空間を有している。小屋裏には梁や束などの小屋組が密に配置される伝統木造の既視感に対し、「空洞」としての概念を体現すべく、小屋組の要素を極限まで減らすことにした。
まず、垂木・母屋・束を省略し、水平距離3640mmある棟木と軒桁の間に105×210の登梁を架け渡した。大きな屋根荷重を支える105×270の棟木は、5本の鉄骨柱で支持されている。鉄骨柱の断面は□-60x60x4.5、全長は約4600mm、細長比は200を超えている。細柱は桁の高さで木造部分に腕を出し座屈を拘束している。小屋組の存在感は極細の鉄骨柱に集約された。
水平力に対しては、屋根面を24mmの合板張りとして面剛性を確保するとともに、鉄骨柱・登梁・水平な小屋梁とでトラスを形成し、屋根から桁に直接力が流れるようにしている。
■建築概要
題名:金ケ崎の家