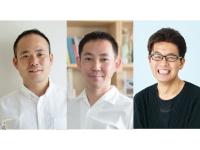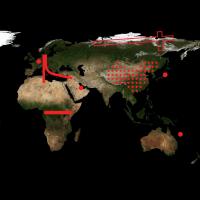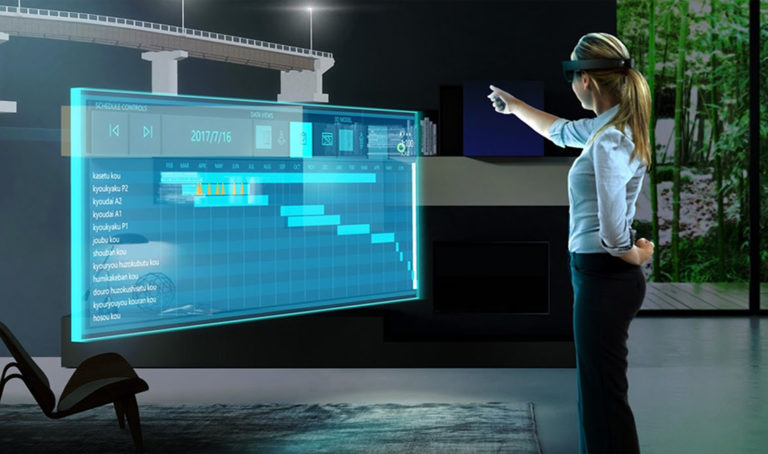内藤廣が設計した、神戸・六甲山に建つ「住居No.40」内のギャラリーで、アート展「有馬晋平展」が開催されます。会期は2019年11月2日~17日(正確な開催日は、2019年11月2日(土)、3日(日)、4日(祝・月)、8日(金)、9日(土)、10日(日)、16日(土)、17日(日) 計8日間)。会期中には内藤も参加するトークも開催されます(2019年11月9日、要予約)。建物写真はこちらで閲覧できます。
「住居No.40」は建築作品として発表された際の名前で、ギャラリーは「DOKI ROKKO」という名前で運営されているようです。
DOKI ROKKOは、内藤廣氏の設計による建築で、六甲山の頂近くに在ります。太古からそこにある遺跡を思わせるような錆び御影石の壁が 、木造のギャラリーや住居を抱いています。心安らかに周囲の美しい自然を感じられ、豊かな時間が流れる空間です。
建物内にあるギャラリーは一般社団法人文化振興ネットワークが運営しています。我々はその天井の美しい木組みに、人間が築き上げる文化的営みへの希望をみました。この場所で、人の心の根源に触れる文化の振興に寄与していきたいと願っています。どうぞこの機会に、懐かしくて新しい場所へ、お出かけください。
一般社団法人 文化振興ネットワークでは、11月2日(土)~11月17日(日)のうち<計8日間>の会期で神戸市六甲山にある「DOKI ROKKO」を会場とし、『有馬晋平展 「雲」』を開催いたします。
有馬氏は、オブジェ「スギコダマ」をはじめとした、杉の木をテーマに作品を制作する造形作家で、東京やパリなどにおいて、数々の個展や展覧会を行ってきました。
会場にたたずむ小さな「こだま」や大きな「こだま」を五感で感じてください。
11月9日(土)には、有馬氏とDOKI ROKKOの設計を手がけた建築家 内藤廣氏によるトークイベントも開催いたします。(詳細は後日配信いたします)
本展覧会は、現代美術家 安部泰輔氏をアドバイザーとして、また手仕事研究家 石田紀佳氏もチームのメンバーとしてお迎えし、有馬氏の作品を新たな視点で捉える展示構成となっています。