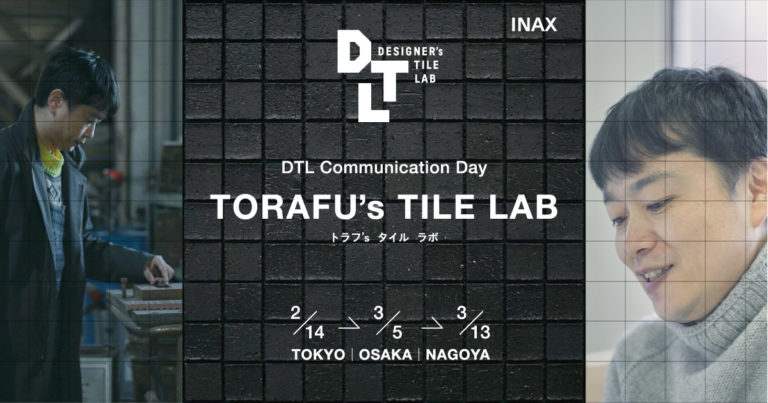建築家の青木淳との協働でも知られる、作家・杉戸洋の個展「cut and restrain」が小山登美夫ギャラリーで開催されています。会期は 2019年3月16日~4月13日(日月祝休)です。弊サイトでの過去の協同を取り上げたニュースはこちらで。
【本展、および出展作に関して】
前回、2017年の小山登美夫ギャラリーでの個展「frontispiece and end leaf チリと見返し」では、六本木の通常の展示スペースではなく、普段見せる事のない倉庫と、展示室と展示室の間のアプローチ部分を使用しました。その空間の壁色の差異や構造から本の「チリ」や「見返し」を着想し、その要素を分解。タイル作品の深みのある釉薬と配置のリズムを融合させ、観る人を驚かせる新たな空間を生み出しました。現在出展中の森美術館の「六本木クロッシング2019展:つないでみる」においては、杉戸は「2:3または2/3ということを考えながら構成を組んでいきました」と言います。
本展に関して、杉戸自身次のように述べています。
「そこ(前回の六本木、及び森美術館での展示)からさらに切り込みを加えて行くことで調整をして行こうと。単純に言うならば、静物画を描く場合モチーフが先に決まるのか後なのかわからないけれど、一旦全てどかして、まず下に来るものから見つめてみたいと思います。」
本展では新作を発表し、約3×2mのキャンバス2点と、それらを中心に小作品が加わります。普段制作で使用している素材、木枠とキャンバス地で、引っ張ったり緩めたり、作家が「テンションや撓みの言うとこを聞きながら」、貼り合わせた物を展示していきます。
【建築と作品が相互に作用し合う場:杉戸作品の世界観】
近年杉戸は、いわゆる「絵画」の枠にとどまらず、建築と作品が相互に作用し合う場を作り出し、新たな展示空間を生み出しています。
それはいわゆる「インスタレーション」とも違い、一つの作品にはそれぞれ独自の「空間」が構成され、作品と作品、作品と私たちのいる展示空間の間には、杉戸洋という作家の思考と入念なリサーチ、プロセス、時間、そして色彩と余白が幾十にも重なり合わされて、作品空間全体からまるで豊かな音楽のリズムや旋律が聴こえるかのようです。
東京都美術館学芸員の水田有子氏は、杉戸作品を次のように評しました。
「私たちがそこ(杉戸作品)に接したとき、どこか懐かしい感触が思いがけずよみがえることもあれば、考えても決して分からない深淵を覗き見ることもある。どんな絵であっても、それぞれが異なる尺度を持つ一つの空間だとすると、その違いや隔たりの中に自ら手を伸ばそうとする私たちの時間のなかにも、さまざまな感覚や思考や記憶や想像力が動き出す『のりしろ』が広がっているのかもしれない。』
(水田有子「『のりしろ』に広がる光と時間 杉戸洋の絵と空間をめぐって」、「とんぼとのりしろ」展覧会カタログ、東京都美術館、2017年)
鑑賞者は杉戸の世界観から、世界は一つの方向や視点ではなく、様々な角度から構築され変化し続けるものだということに改めて気づかされます。
そして、純粋に作品を見ることの楽しさ、喜び、そして新たな想像力を生み出す自由さも味わうことができるでしょう。 杉戸は、自らがとらえた現象世界の知覚を作品にあらわそうと真摯に探求し続けており、これからも、杉戸の表現への考察、実験は続けられます。
二度目の六本木の展示空間での個展、今回杉戸は空間にどのように向き合い、どのような作品世界を生み出すのでしょうか。ぜひご高覧ください。