
SHARE 震災復興支援活動関連企画「towards our ordinary life」についての伊藤達信によるテキスト「近くて遠い場所を想い続けること」

※これはarchitecturephoto.net 震災復興支援活動関連企画「towards our ordinary life」の関連記事です。
近くて遠い場所を想い続けること
東日本大震災の発生から早くも1年が経った。
被災者の方々は仮設住宅に移り、瓦礫は片づけられ、事態は次第に落ち着いていっているようにも見える。しかし、依然として問題は多く残されていて、被災地の人々が皆きちんと日常生活を送れるようになるのは、まだまだ先のことであると言わざるをえない。
また震災以降、原発の問題をはじめとして、現在の日本の社会がどれだけがんじがらめになってしまっているのかということを、わたしたちは嫌というほど思い知らされている。今なお続く混乱は、未だ解決の糸口を見つけられていない。そして、被災地では、元々地方都市が抱えていた問題がよりいっそうはっきりとしたかたちであぶり出されてきている。
震災は、建築にたずさわる人間の多くにとって、自分たちがこれまでどんなことをしてきたかを否応なしにあらためて考え直させられる契機になったのではないだろうか。わたしたちは、これから建築家がどうやって社会に関わっていくかということを今一度考えていく必要がある。それはもちろんただ与えられた条件のもとに、写真映りのよい建物を作ればいいというだけではないだろう。一見ネガティブなものをポジティブに捉え、何かを変えようという努力を続けていくこと。そして受け継いでいくべきところと変わるべきところとを冷静に見極め、ひとつひとつの事柄に対してきちんと対処していくこと。そういった姿勢によって、これまでより少しでもよい日常を作りあげていくことが可能になっていくのだと思う。
この企画では、顔の見える個人が建築をベースとしながらも、ただ単に目に見えるものを作ることだけにはこだわらず、そのつど目の前の状況に対して何をすべきかを見極めながら動いているプロジェクトに登場してもらおうと考えている。状況が刻一刻と変わっていく被災地においては、その場の状況に対して俊敏に反応できる瞬発力がつねに必要とされる。そして、現地に繰り返し足を運び、現地の人たちと直接向き合いながら活動していくことが求められる。彼らのやっていることは必ずしもすぐに全貌を理解できるものというわけではないかもしれない。けれども、彼らがその状況に入りこみ、媒介となることによってそれぞれの場所に確実に何らかの変化をもたらしている。それはあるとき突然なにかが劇的に変わってしまうというようなことではないが、その場の状況がよい方向へ進んでいくためのきっかけをちりばめていっているように思う。それぞれの活動によって、アプローチも規模もさまざまであるが、それが復興支援というものがいろんなかたちでありうるのだということを示してもいる。これから復興が進んでいくにつれ、どのような距離感で接していくかということについてはバランス感覚が求められる。ただ一方的な関係性を築いてしまうことは、双方にとって決してプラスにはならない。問題は一様ではないため、どうしてもひとつの考え方で全体をカバーしてしようとしても、こぼれ落ちてしまうものが出てくる。それらに目を向け、それぞれに見合ったやり方で働きかけること。そのようにしてマイノリティに対して敏感に反応し、きめ細やかなサポートを地道に続けていくことが求められているように思う。
こういった活動は性格上どうしても継続していくのが難しく、最初は勢いでやれたとしても、途中で問題が生じて頓挫してしまったものも多くある。それでもなお継続できている活動にはそれなりの理由があるし、またそれが知られることには意味があると思う。彼らに共通するのは、ただ善意だけでやっているというわけではなくて、あくまでも自分自身の問題として活動しているということだ。他人のためにやっているという気持ちがあれば、どこかで必ず負い目が出てきてしまう。決して言い逃れはせずに、いろんなことを全部含めてまるごと受け入れる覚悟ができていなければ、続けていくことはできないだろう。そしてその結果として、活動を通して得た経験を自らの日常生活にも反映させていっている。今被災地で起こっていることは決して他人事ではなくて、きっとどこかで自分たちにもつながっているという意識が、彼らにそれだけのことをさせているのだと思う。
直接被災していない人たちにとっても、被災地について想いをはせ、考えていくことは大切なことだ。時間が経つにつれ、どうしても意識が薄れていってしまう。そんな中で、これまでおこなわれてきた活動をふり返り、またこれから何をしていくべきなのかを考えるきっかけを見つけることができればと思う。これからじっくり時間をかけて新たな日常を築き上げていくために、まだまだ必要なことはたくさんあって、インパクトのある情報なしにでも、被災地に対しての想像力を失わずにいること。それはひいては自分たちの今の生活を見直し、変えていくことにもつながっていくのだと思う。

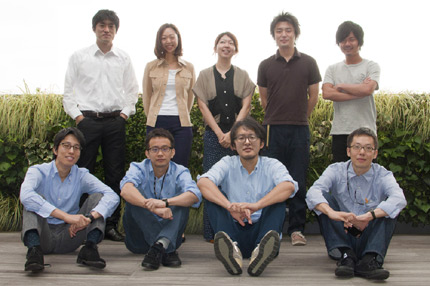




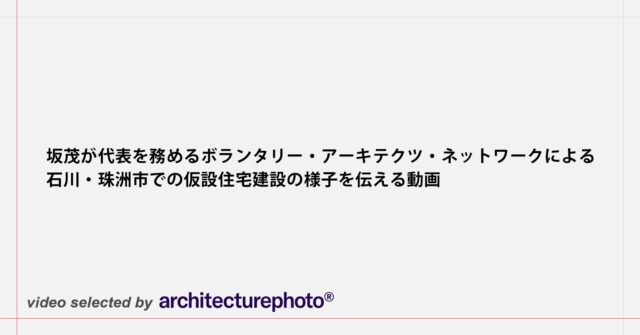
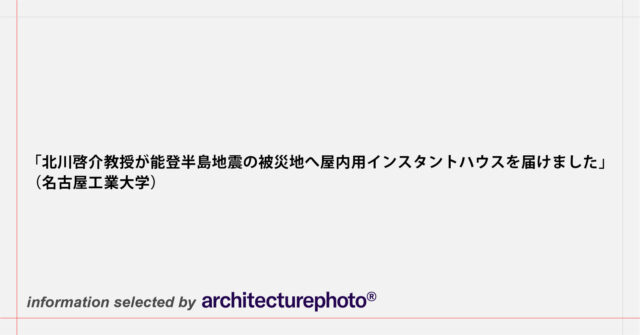
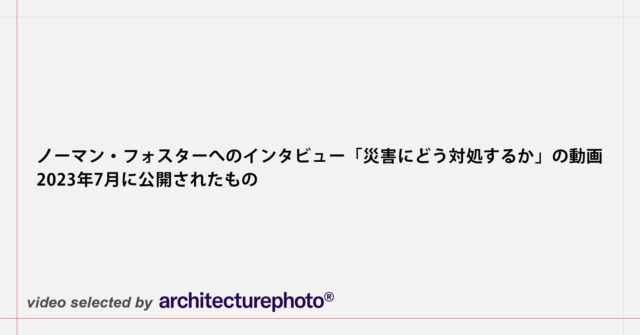


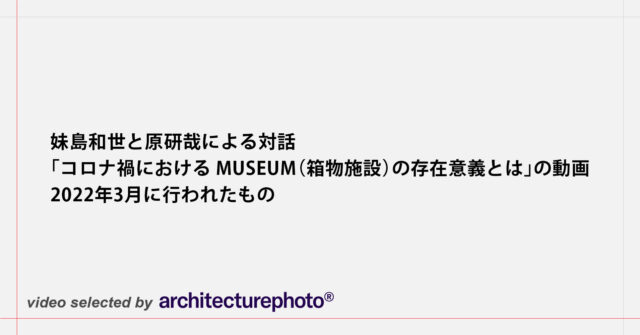

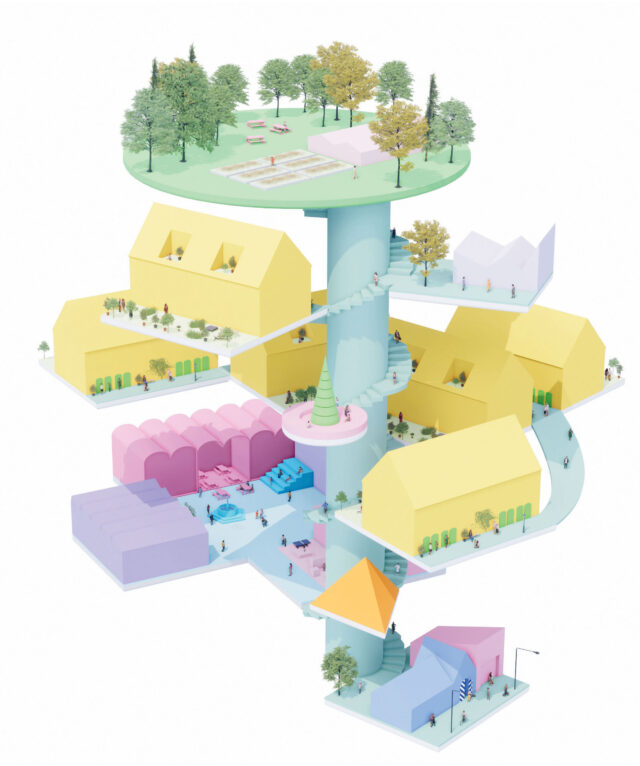

![サムネイル:アガ・カーン建築賞などを受賞しているシンガポールの建築家ユニット「WOHA」のレクチャーが京都工芸繊維大学で開催[2012/4/16]](/jp/woha.jpg)