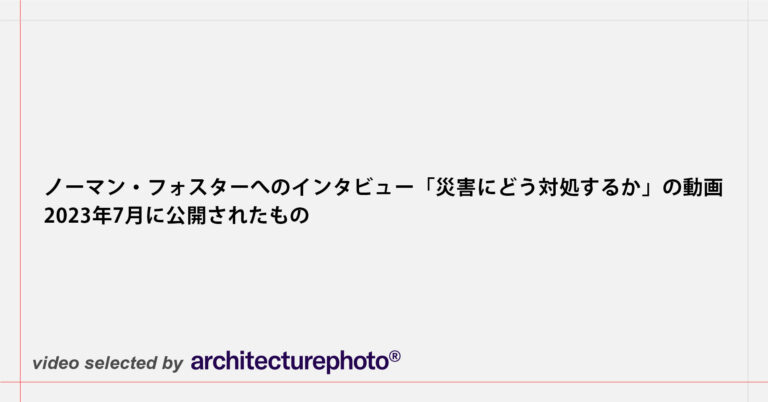企画・設計・施工の3部門が連携し、古い建物や空間を再生させる「株式会社LOOPLACE」の、設計スタッフ(経験者・既卒)募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
株式会社LOOPLACE(ループレイス)は、古い建物や空間を活かす、不動産再生カンパニーです。
築古ビル再生のセットアップオフィス「gran+シリーズ」をはじめ、役目を終えた場を壊さず、次の使い方を見出し、再び人が集まる場や空間を創造しています
私たちのビジョン「既存の場を、おもしろくする。」
老朽化した建物を壊さず、新たな付加価値をつくること、時代に取り残されてしまった建物に、一つでも多くの灯りを灯し人が集まる「場」をつくること。
不動産企画、デザイン設計、施工の3つの部門が連携し、物件取得から商品企画・設計デザイン、施工管理、売却、管理までを自社で手掛けることで、築古ビルの収益再生を行っています。
入居テナントのインサイトに寄り添う「はたらく場」の提供を通じて、新たに事業性を持ち、サスティナブル社会へ貢献することを目指し、商品化、設計施工を行っています。この度、事業拡大のため、デザイン設計職を募集します。
大手デベロッパーや不動産会社からの依頼を受けて行うオフィスビルリノベーションや、収益向上に伴うバリューアップ設計並びに、自社で仕入・企画・販売を行う築古ビル再生事業gran+(グラン・プラス)の設計企画について、設計者という立場からプロジェクトを推進する仲間を募集します。
【仕事の内容】
収益ビル(オフィスビル中心)の付加価値向上のためのコンセプト立案、デザイン提案・設計業務・設計監理・品質管理・工事進捗確認等。付加価値を高めるための内装デザインはもちろんのこと、遵法性・老朽化部分の修繕・各種設備関連等の改善や適正化に考慮しながらデザイン設計を進めます。場合によってはマーケテイング調査も行いながら、テナントニーズや地域性・収益性を含めたビルのポテンシャルを最大限まで高めていく視点で設計を行っていきます。
各プロジェクトは不動産仕入販売運営を担う部門や、商品企画・施工部門と連携を取りながら進めていくことが多く、各部署との連携や調整も行っていきます。gran+の実績を活かし、ビルオーナー様へ向けた事業も新たに進めており、ブランディング・築古再生事業強化に向けたコンサルティング事業の取組みも進めています。