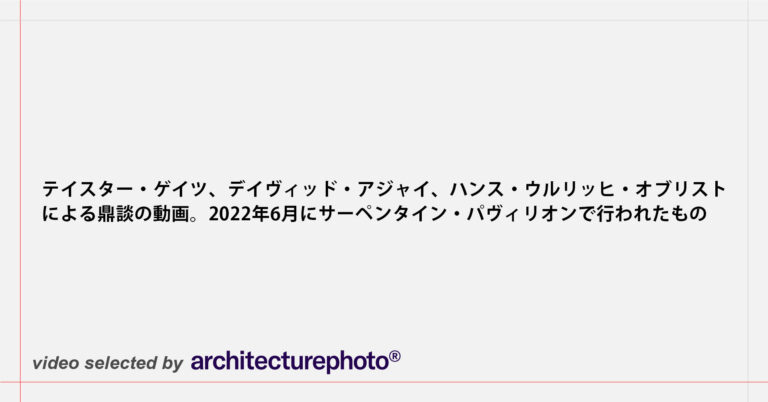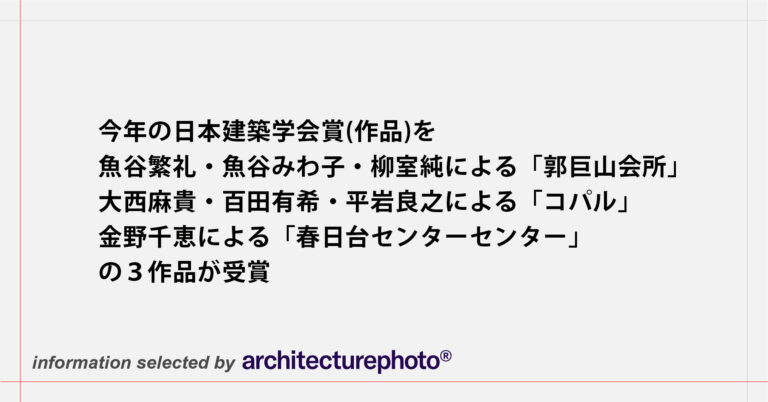宮城島崇人建築設計事務所が設計した、北海道・札幌市の住宅「Oプロジェクト」です。
公園に面する家の改修と増築です。建築家は、食に関わる施主の“ラボラトリー”となる建築を目指し、2本の柱でスラブを支え全方向に開放性を持つ“キッチン棟”を考案しました。そして、公園との新たな関係を作ると共に既存の内部環境も一変させる事を意図しました。
東京で食や料理に関する仕事をしていた施主は、育児休暇を北海道で過ごした際、豊かな自然のなかで新鮮な食材をシンプルに料理して楽しむ生活に感動して移住を決め、札幌市内の公園の一角にある、枠組壁工法の住宅(以下2×4住宅)を購入した。
2×4住宅は気密、断熱性能に優れることから道内に多く建つ。在宅でさまざまな仕事をする彼らは、料理を介したコミュニティづくりや食品開発などを行うための広いキッチンと仕事場、ライブラリーをもつ、開放的な食と生活に関するラボラトリーのような住宅を求めた。
公園に対して無関心に建つ、堅牢で均質な2×4住宅を開放的に改修するのは限界がある。
そこで、フェンスに囲まれた窮屈な庭の部分に、キッチン棟を増築することで、公園の開放性と2×4住宅の堅牢性を最大限に引き出し、総体として新しい環境を生み出すことを目指した。
軽い材料が高密にアッセンブルされた既存2×4住宅の躯体とは対比的に、重い材料で開放的な空間を生む躯体を増築することで、既存の環境を刺激しようと試みた。
屋上にリフトアップした菜園と、2×4住宅と公園の双方に対して程よい距離感をつくるために地面から1.2m浮かせた床スラブを、500mm角の2本のRC造の柱で支持する。2本の柱は2×4住宅と公園に対して中立するように並び、浮いた躯体は公園を敷地内に引き込む。異なる2つの環境を鼓舞する、住宅の増築のような、公園の増築のような、両義的な躯体である。
フリーになった外周部に腰壁と木製サッシを配した開放的なキッチン棟は、冬は躯体の熱容量と日射熱、夏は大きく開閉する窓と菜園の蔦植物がつくる日影によって快適に過ごすことができる。2×4住宅のダイニングに幅約4mの開口を設けて増築棟とつなぐと、公園の開放感と光が柔らかに入り込んで既存住宅の環境は一変し、どこにいても公園の樹木と空との一体感を感じられる、明るく落ち着いた空間となった。