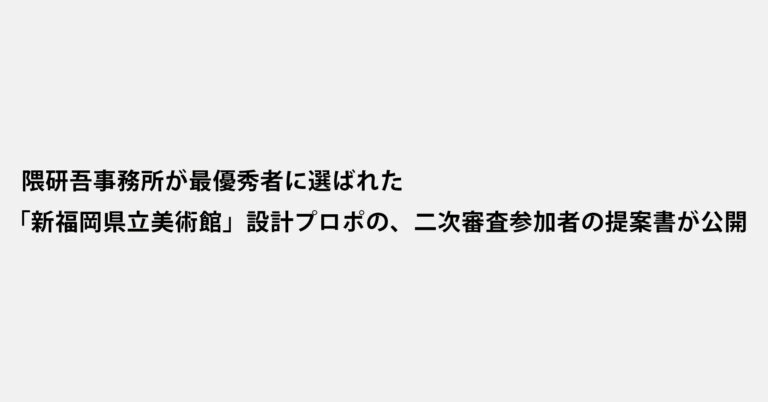ザハ・ハディド事務所による、リトアニア・ヴィリニュスの複合ビル。事務所や公共機能を内包した街の中心広場に隣接する建築。街の“新しい集いの場”となるよう、様々なレベルに勤労者や地域住民の為のテラスや広場を配置。省エネに加え建設段階や解体後の環境負荷軽減も考慮 ザハ・ハディド事務所による、リトアニア・ヴィリニュスの複合ビル。事務所や公共機能を内包した街の中心広場に隣接する建築。街の“新しい集いの場”となるよう、様々なレベルに勤労者や地域住民の為のテラスや広場を配置。省エネに加え建設段階や解体後の環境負荷軽減も考慮 image©Frontop ザハ・ハディド事務所による、リトアニア・ヴィリニュスの複合ビル。事務所や公共機能を内包した街の中心広場に隣接する建築。街の“新しい集いの場”となるよう、様々なレベルに勤労者や地域住民の為のテラスや広場を配置。省エネに加え建設段階や解体後の環境負荷軽減も考慮 image©Frontop ザハ・ハディド・アーキテクツ が設計して建設が始まる、リトアニア・ヴィリニュスの複合ビル「ビジネス・スタジアム・セントラル」です
こちらはリリーステキストの翻訳です
ビジネス・スタジアム・セントラルの計画が承認される
リトアニアのデベロッパー ハンナー社のためにザハ・ハディド・アーキテクツが設計したビジネス・スタジアム・セントラルが、ヴィリニュス市から承認されました。ビリニュス市の都市計画の中に組み込まれ、敷地に隣接する人気の高い公共広場と一体化したビジネス・スタジアム・セントラルは、街の新しい集いの場となることでしょう。
8階建てと9階建ての2つの低層タワーからなるこのセンターは、道路レベルで、中庭のアトリウムと2階分の公共施設によってつながっており、24,000㎡の広さのデザインは、5階でスカイブリッジによって2つのタワーをつないでいます。センターのファサードの曲線と片持ちのバルコニーは、街の中心部にある歴史的なゲディミナス城の塔に向けられています。
近隣の既存の市民建築のダイナミックな幾何学模様を再解釈したビジネス・スタジアム・セントラルのデザインには、11,750㎡のランドスケープテラス、ルーフガーデン、プラザが組み込まれ、マーサ・シュワルツのデザインによる公共広場に直接開かれています。カフェや レストラン、ショップが立ち並ぶアトリウムの中庭は、地域住民やオフィスワーカー、観光客に利用されます。エレベーターで最上階に上がると、2つのパブリックプール、サウナ、スチームルーム、サンデッキがあり、ヴィリニュスの歴史的な旧市街を一望することができます。
各タワーの中心階に配置されたフレキシブルなオフィススペースは、開発のライフサイクルを延長するために最大限の適応性を持つように設計されています。スタートアップから国際的な大企業まで、さまざまな企業に対応できるようサイズやレイアウトが異なるこれらのワークプレイスは、景観の良いルーフガーデンやテラスでつながっており、周囲の街の景色を眺めることができます。このセンターのガラス張りのファサードは、精密に制御された外部ルーバーを備え、ビジネス・スタジアム・セントラルのインテリアでは、温かみのある木材をベースにした素材に変化していきます。
ヴィリニュスの湿度の高い大陸性気候の中に位置し、毎年の太陽熱分析により、ファサードのルーバーとバルコニーの構成が決まり、夏の日射による直射を減らす一方で、寒い時期の太陽熱取得を最適化するようにしました。この外部遮光装置は、10月から4月にかけての太陽の低い位置(約38度)に合わせ、ヴィリニュスの夏の空で最も高い位置(151度)には垂直になるように設置されています。
サステイナブルな建築システムは、建設時のエンボディド・カーボンと運用時のエネルギー使用量を削減します。デジタル最適化デザインプロセスにより、構造体に必要な材料の量を最小限に抑え、プロジェクトのリサイクル率を高める調達システムと統合しています。インテリアに使用する木材は、認証された地元の供給源から調達し、配送距離を短縮するために確立されたプロジェクト全体の供給網の中に含まれることになります。すべての指定材料は、建物の運用期間終了後に解体して再利用できるように評価されています。