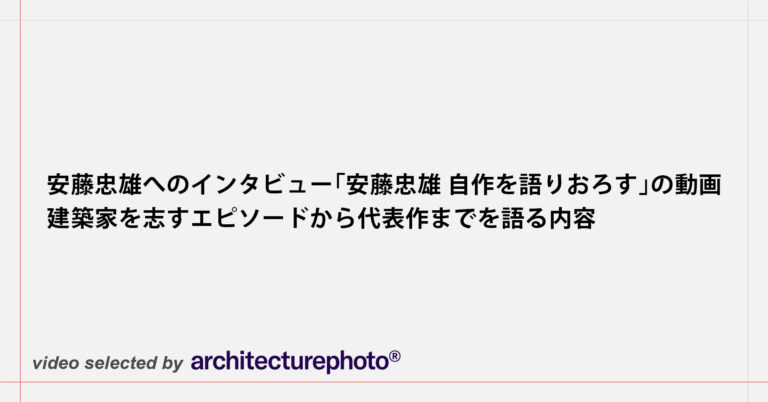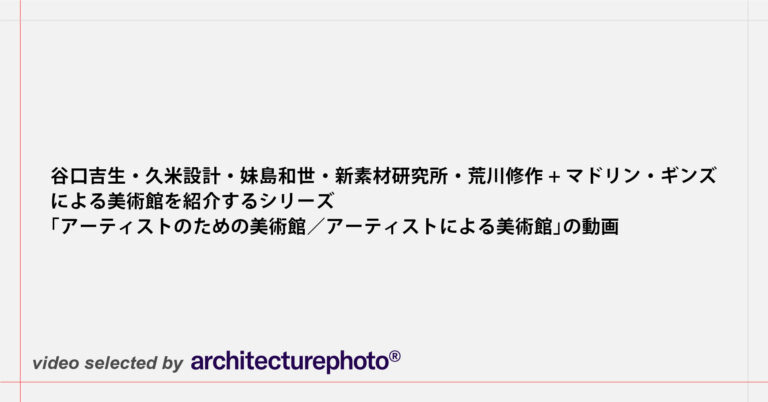小嶋伸也+小嶋綾香 / 小大建築設計事務所が設計した、中国・蘇州市の店舗「LIGHT MARK 蘇州」です。
新進ジュエリーブランドの為の内装計画です。建築家は、気軽に立ち寄れる空間を目指して、ケースへの商品陳列ではなく垂直のアクリル壁に展示する方法を考案しました。それにより、透明度と特別感のある閲覧状況を作り出す事を意図しました。
中国のジュエリーブランド「LIGHT MARK」のショップのデザインを担当しました。
LIGHT MARKは、設立から年月がそう経ってはいない新興ブランドでした。商品のラインナップもウェディングジュエリーだけでなく、カジュアルなシリーズまで取り扱うため、window shoppingの際にフラッと立ち寄ってみたくなるようなショップのデザインが求められました。
普通のアパレルショップはある程度お店の外からも販売している商品を見ることができるのですが、小さなジュエリーの場合1つ1つのデザインを店舗の外から感じることは難しい。また、一般的なジュエリーショップは煌びやかな内装を施され、ガラスケース越しに対応するスタッフが配置されている印象でした。それは高級な宝石を購入したいというような目的がはっきりとした方には相応しいスタイルですが、気軽にジュエリーを覗きに行くにはいささか敷居が高いように感じていました。
私たちはこの従来のジュエリーショップの展示方法が、ガラスケースの中にあるジュエリーを覗き込む点に注目しました。
什器の中で平置きになっているジュエリーは、踏み込んで覗き込むまでは正確なデザインがわからない。この課題に対してできる限り透明度の高い状態で垂直に展示ができないかと考え、デザインを試みました。