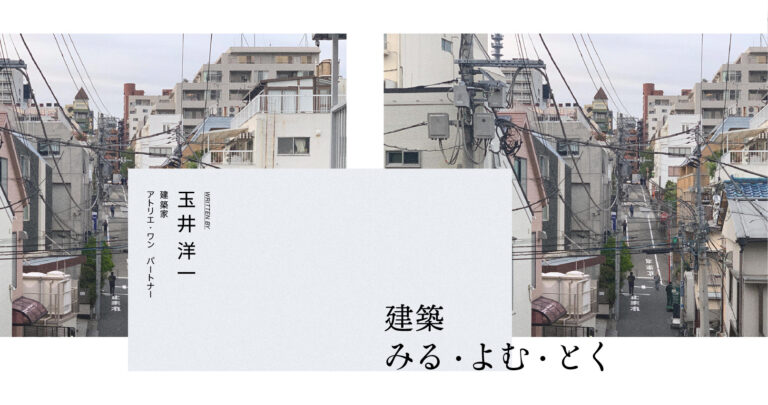藤本壮介の設計で完成した、ハンガリー・ブダペストの音楽施設「ハンガリー音楽の家(House of Hungarian Music)」の動画です。アーキテクチャーフォトでは2021年1月に建設現場の様子を特集記事として紹介しています。
architecture archive




今津康夫 / ninkipen!が設計した、奈良市の、照明器具メーカー“NEW LIGHT POTTERY”のオフィス兼ファクトリー「trophy」です。既存ペンシルビルを改修した施設で、小さな面積が積み重なる特徴を生かしフロア毎に用途と仕上げを変えた、ローカルで生まれ全国に広がる照明器具の製作発信拠点です。クライアントの公式サイトはこちら。
奈良を拠点とする照明器具メーカー、NEW LIGHT POTTERYのオフィス兼ファクトリーである。
周辺には江戸から明治にかけての町屋が多く立ち並ぶ「ならまち」に建つ5階建てのペンシルビルを改修した。
小さな面積が積み重なるビルの特徴を生かしてフロア毎に用途を変え、1階を荷解き場、2階にオフィスと作業場、3・4階は倉庫、5階をフォトスタジオとし、屋上にはデッキを敷きルーフトップテラスを設けた。
1階には階段を増設して動線を強化し、隣に浮かぶアルミの照明器具とシンクロするように側桁を溶融亜鉛メッキとした。2階は杉の棚板に合わせて躯体をアイボリーに塗装し、エントランスホールを兼ねたガラスの階段室にはネオンサインを掲げた。3・4階はスチール素地の支柱を効率よく並べ、5階はそれぞれの壁に異なった左官仕上げを与えることで、様々な印象の写真を取ることを可能とした。



フロリアン・ブッシュ建築設計事務所が設計した、静岡・伊東市の「伊豆高原のI邸」です。典型的な別荘用地と捉えた場所の茂みの中に建てられ、建築により風景を“濾過”し遠方の自然という資産を視界に取り込んだ、家族が週末を過ごす小さなシェルターとして設計された住宅です。
様々な用途を盛り込んだが故に、逃避するはずの日常生活のレプリカを作ってしまうという落とし穴に陥ることがしばしばあるが、このプロジェクトの意向は「都会の家族が週末を過ごすための小さなシェルター」という、立地同様にシンプルで慎ましいものだった。
この敷地を最初に訪れた時、なぜ景観について概要に触れられていなかったのかが分かった。事前分析から推測した通り、実際に茂みの奥深くに埋もれていた。それでも、それがこの別荘の重要な要素になり得るし、そうであるべきだと考えた。
急勾配の幅の狭い階段で道から敷地へのアクセスを確保。そこから家の中心部に据えた柱を旋回する螺旋階段を次々に登っていく形で家が展開する。この柱の行き着く先はパッと開かれたパラソルを彷彿させる屋根。
グラウンドレベルでは、屋内の床が、外の広々としたテラスとその先の庭へとつながっていく。家の中心の螺旋階段を登っていくと、途中で足を休めて寛ぐための場に出会す。天然の温泉が湧き出るお風呂場が唯一の閉じられたスペースだ。家全体は一つの空間で、それを取り囲む四つの壁には幾つもの窓が慎重に配置されている。



中川宏文 / O.F.D.A.と山本稜 / Spicy Architectsが設計した、山梨・富士吉田市の飲食店「喫茶檸檬」です。商店街活性化として計画され、運営者の地域資源と東京の創造性が混ざり合う場という思いに、人々の日常風景と非日常風景を引き立たせる舞台装置としての建築で応えようとする計画です。店舗の公式サイトはこちら。
喫茶檸檬は富士吉田市の、「富士吉田市本町通り活性化プロジェクト」としてつくられた。
富士山に日本一近いと言われる山梨県富士吉田市。市内の至るところから大迫力の富士山を望むことができ、中でも「富士山がきれいに見える商店街」として、富士吉田市本町通りはメディアからも注目されている。1000年以上続く繊維のまちとしても知られファッションブランドの産地として活気溢れるまちとして発展した。しかし、昭和50年代に入ると経済はグローバル化し、低廉な製品が国内に流通し衰退。通り自体は閑散とし空き家や空き店舗が増え、シャッター商店街と化しているのが現状だ。
本プロジェクトは、この本町通りを起点に地域の伝統産業を活用した事業と、地産地消を目指し地元の農作物を使用した運営を行い、空き家や空き店舗を活用し、内装のリノベーション、コンテンツ制作、PR力のあるクリエイターを誘致した長期運営を行い地域の更なる活性化を目的としたプロジェクトである。本プロジェクトを、地域の空き家等活用のモデルケースとしてPRすることで、新たな出店や移住、2拠点居住、ワーケーションの場所として、内外からのニーズや投資を増やしていくことで更なる地域の活性化を目指している。
同店を運営・プロデュースする、東京のデザイン事務所(株)れもんらいふは、富士吉田の資源と東京のクリエイティブが混ざり合う場所にしたいという思いがあった。
そこで我々は、ここに来る多様な人々の活動が街の日常の風景の一部として切り取られ、またある時には映画のワンシーンのような非日常の瞬間として映えるように、2つの舞台を設えることにした。



長坂常 / スキーマ建築計画が設計した、東京・銀座の、レストラン兼ショップ「ギンザ・イニット」です。。レトルト食品を食事として提供し販売もする店舗で、レトルトとの共通性をダイノックフィルムに見出し全面的に使用、内装制限もクリアしフィルムだからこその木目表現も追求されました。店舗の公式サイトはこちら。
非常食用に開発されたレトルト食品“IZAMESHI”の有料試食店、つまりレストラン兼ショップを設計させていただいた。2階ではアウトドア商品を販売する。
その商品特徴が多くの生活者のニーズに応えることから消費が大きく伸び、いまや一般の家庭では欠かせない食品のひとつとなっている。
ただ、それをレストランで出すことによって、ショップでその非常食は売れるが、レストランは繁盛するのか?と疑問に思ったが、それは今度は味勝負となるのであろう。すでにそれは新宿の姉妹店で証明済みでたくさんのお客さんで賑わう。味に信用があるとすると、誰が調理しても変わらない味になるのはむしろメリットになる。そして、よくよく考えてみると町にある多くのチェーン店がそのレトルトで料理を提供していることを思い出し、こんな鮮やかにその裏を見せて売りにしていくビジネスに感服させられた。
ふと思い出したのが、10年ほど前にタケオキクチのフラッグシップストアを渋谷で計画したとき、初めてあった時に武先生が「Aesop青山店素敵ですね。あの色まちまちの木の棚が好きです。一軒の家を壊した時に出てきた廃材で作ったんでしょ?面白いねえ」と言われながら「でも、代官山蔦屋も不思議と居心地がよく好きなんだよね。嘘だってわかっていてもあの木目が与える人への影響は大きく癒されるんだよね。長坂くんはどう思う?」って言われ、全く予想していなかった質問に面食らい答えを濁したことを覚えている。
それから、ことあるたびにその言葉を思い出すのだが、それを実作で実感することのできる機会がやってきた。レトルトとダイノックフィルムという二つの存在に共通項を感じダイノックフィルムをふんだんに使ったお店をここで計画した。



玉上貴人 / タカトタマガミデザインが設計した、東京・江東区の「つくりおき.jp 清澄白河キッチン休憩室」です。就業環境の快適化の為のスペースで、緊張感ある仕事から開放される“ひとやすみ”の空間を、円弧を重ねた柔らかな形状・有機的な左官仕上げ・天然木の使用によって生み出す計画です。クライアント企業の公式サイトはこちら。
「つくりおき.jp」は多忙な共働き子育て世代の家事負担を軽減する為に、専門の調理人が手作りした惣菜をデリバリーするサービスである。レシピは管理栄養士が監修しているという。開業以来ユーザー数を着実に伸ばし、配送対象エリアの拡大を計っている。
この休憩室は、開業以来最大規模の清澄白河キッチン新規開設において、就業環境をより快適にするとともにコーポレートブランディングの一環として計画されたものである。
キッチンでは天然由来のものを除き、保存料や添加物は使われず、徹底した衛生管理がなされる。この高度な調理環境の運用を可能にしているのが、緊張感を持って品質管理に努める従業員達である。その従業員達がシステマティックな厨房空間から開放される「ひとやすみ」の空間として、角のない包まれるような休憩室をデザインした。壁面仕上は有機的な職人の手跡が残るような左官とし、身体が触れる部位を天然木とすることで優しさのある表情と手触りを与えた。




五十嵐敏恭 / STUDIO COCHI ARCHITECTSが設計した、沖縄・南城市の「百名のゲストハウス」です。自然と暮らしの日常を感じる敷地に、4棟の宿泊室を分棟的に配置し建物までの小道を内部に引込むことで、集落と建築体験が連続する“暮らすように旅を楽しめる”施設が構想されました。
敷地は本島南部の海沿いの集落の外れにあり、森や畑に囲まれているため海への眺望はないが森や集落の中を通り緩やかに下る小道が海まで続いていたり、近くの畑では農作業の風景が見れたりと、自然豊かな環境と、ここで暮らす人々の日常を感じることができる。
建築は4棟のゲストルームとそれを繋ぐ共用部から構成されている。
各個室は敷地内にバラバラに配置され、プライベートな庭を持つ一つの住宅のように計画し、敷地の高低差に合わせて緩やかに傾斜した共用部は、敷地から海までの小道を建物内部へと引き込み、各個室と集落を繋いでいる。
また、共用部は内外の連続した半外部空間とし、壁の仕上げも集落内に点在する岩肌のような荒い仕上げとすることで集落での体験と建物での体験が連続し、集落の中で暮らしているような体験ができるのではないかと考えた。

SHARE ネリ&フーの、イタリア国立21世紀美術館での建築展「Traversing Thresholds」。施設に収蔵されるスカルパ作品と向き合い、内外と公私を調停する“閾値”の観点から読み解き、そのヴィジョンを再解釈して制作されたインスタレーション
- 日程
- 2021年11月19日(金)–2022年2月6日(日)



ネリ&フーの、イタリア国立21世紀美術館での建築展「Neri & Hu. Traversing Thresholds」。施設に収蔵されるスカルパ作品と向き合い、内外と公私を調停する“閾値”の観点から読み解き、そのヴィジョンを再解釈して制作されたインスタレーションが公開されています。会期は2022年2月6日まで。
こちらはリリーステキストの一部の翻訳
ドミティラ・ダルディ(Domitilla Dardi / MAXXIデザイン・キュレーター)がキュレーションするAlcantara-MAXXIプロジェクトは、2018年からスタジオ・ヴィジット形式に進化し、過去のマスターと現在のマスターが集まり、毎回招待されてMAXXI Architetturaコレクションの偉大な巨匠の作品を、アルカンターラ®を主要言語として解釈し、個人的解釈を提供するようになったのです。
2021年版では、ネリ&フーは、MAXXIに収蔵されている偉大な作家の一人と向き合います。カルロ・スカルパです。
上海を拠点とする建築デザインスタジオは、「Traversing Thresholds」によって、西洋と東洋の世界、感性と視覚の間に文化の架け橋を構築します。スカルパの解釈は、中国語の「jian」と日本語の「ma」の両方に存在する概念である「threshold」(「隙間」「空間」「間」と大別される)にあります。建築の世界では、この言葉は、内と外、公と私といった対照的な2つの空間環境の間の物理的な調停、あるいは閾値の状態を表すためによく使われるますが、この状態はイタリアの巨匠の空間通路に再び現れています。
リンドン・ネリはこう説明します「閾値の観点から見ると、この “jian”というアイデアは、空間として見ることもできるし、中間、あるいは時間のアイデアとして見ることもできます。」
「これは隙間の空間です。」とロサーナ・フーは付け加えます。「空間だけでなく、空間と時間の間、あるいは2つの構造的な部分の間にある抽象的な概念なのです。何かが満たされるのとは対照的に、空っぽであるという概念があり、音楽を作る音符の間の沈黙のようなものです。」
リンドン・ネリとロサーナ・フーがデザインしたインスタレーションは、スカルパのヴィジョンを、ディテールの発明、ソリッドとヴォイドの対話、素材の創造的な組み合わせという中心節において再解釈しています。
このインスタレーションの焦点は、スカルパの建築の6つの重要な通路を観察者に導くものです。ピボット・プレーン、侵食されたコーナー、挿入されたランドスケープ、フローティング・データム、スリット・ウィンドウ、オフ・アクシス。これらの要素は、完全なものからの引き算、素材間の対話、反重力サスペンション、プログレッシブな空間、構造軸のスライドなど、巨匠のいくつかの教訓に反映されています。ネリ&フーが解釈した建築の教えは、規則正しく交差する壁のメッシュを通して新しい空間を生み出し、6つの限界は訪問者に行動を促し、スカルパの源泉を明らかにする場となっています。
アルカンターラは、優れたデザインアイデアのための特別な「構成材料」であり、その汎用性、触感、エレガンスのあらゆる可能性をもって、この作品を過去と現在をつなぐ真の地点にしています。フルカラーのバリエーションで、あるいはエンボス加工やラミネート加工といった異なるテクスチャーで使用されるこの素材は、ネリ&フーがデザインする建築の礎となり、その生来の感覚的な魅力で人々を迎え入れます。
ドミティラ・ダルディは言います。
「ロサーナ・フーとリンドン・ネリは、MAXXI Architettura Archivesの中で最も貴重なカルロ・スカルパの作品に異なる視点を与えてくれました。」
「スカルパの作品に”胎動”として存在し、”閾値”というコンセプトを通して、旅や通路としての空間の感覚は、東洋のデザイン感覚へと開かれ、現代の建築家の解釈によって強化されています。」



空間構想+辻昌志建築設計事務所が設計した、東京・千代田区のテナントビル「内神田三丁目プロジェクト」です。環境に合わせるのでなく理想的な将来像を想定した建築設計という思想の下、低層部を街路から直接出入可能とし都市と立体的に繋げ、地域の人情的な界隈性をより濃密とすることが目指されました。
建築ができるときには、その周囲の環境は決まっています。だから、その環境に合わせて建築を設計する、というのはよく理解できます。しかし、時間の中での自分の立ち位置を少しスライドさせると、建築ができた後に、その周囲の環境も変わっていく、という見方ができるはずです。そうであるならば、まちがこう変わっていったらいいのに、という理想的なまちの将来像を予め想定して建築の設計をすることもできるはずです。
今でこそ広く知られるようになった、コーリン・ロウのコンテクスチュアリズムという1965年の言説は、本来、建築を文脈に合わせて設計するという意味ではなく、ある理想形をコンテクストに応じて変形させることにより、都市空間と建築形態を決定し、漸進的に都市全体を改変していく方法論として提唱されたものです。これは、都市の中ではたった1粒の建築でも、いつかは都市に大きな変化をもたらすきっかけとなれる、という前提にたっています。
将来、こうなったらいいな、というまちの姿をイメージし、そこにたどり着くための建築を設計する、というアプローチ。
建築はまちを変えることができる、願いにも似たモチベーションを建築に落とし込む方法論を模索しました。

建築家でありアトリエ・ワンのパートナーを務める玉井洋一は、日常の中にひっそりと存在する建築物に注目しSNSに投稿してきた。それは、誰に頼まれたわけでもなく、半ばライフワーク的に続けられてきた。一見すると写真と短い文章が掲載される何気ない投稿であるが、そこには、観察し、解釈し、文章化し他者に伝える、という建築家に求められる技術が凝縮されている。本連載ではそのアーカイブの中から、アーキテクチャーフォトがセレクトした投稿を玉井がリライトしたものを掲載する。何気ない風景から気づきを引き出し意味づける玉井の姿勢は、建築に関わる誰にとっても学びとなるはずだ。
(アーキテクチャーフォト編集部)
吹出口のひと言

外壁に沿わせた排気ダクトの吹出口の先端に、ステンレスの円板が貼られていた。
それはおそらく汚れやすいタイル面を油分や熱から保護するためだけれど、ステンレス板を四角ではなく丸にしたことはとても気が利いていた。吹出口だけにマンガの「吹き出し」か、とツッコミたくなったが、歩道の植栽や看板の書体などと相まって銀色に光る満月のような何とも言えない風情があった。
この排気ダクトは建物に入居するテナントの業態(たぶん飲食店)から事後的に必要になって渋々つけられたと推察される。しかしここでは単なる「対応」で終わらせずに外壁の汚れ防止や歩行者への気遣いなど複数の配慮が重ねられているのがとても良い。そういった何気ない工夫や知性は尊いもので見かけると得した気分になる。




ザハ・ハディド・アーキテクツによるキプロス・ニコシアの「エレフテリア広場」です。祭典や公共イベントの為の市民広場として計画され、敷地形状と機能配置から生まれた流動的な幾何学的形状をもち、旧市街と近代地区のコミュニティーの分断を解消し統一を提案するプロジェクトです。
こちらはリリーステキストの翻訳です
ニコシアのエレフテリア広場(Eleftheria Square)は、キプロス共和国大統領ニコス・アナスタシアデ(Nicos Anastasiade)とニコシア市長コンスタンティノス・ヨルカジス(Constantinos Yiorkadjis)によって落成式が行われました。式典には、EU委員のステラ・キリアキデス(Stella Kyriakides)も出席しました。
ザハ・ハディド・アーキテクツのデザインは、エレフテリア広場を街の主要な集いの場として確立し、分裂した首都をひとつにすることを意図した新しいつながりを生み出します。ニコシアは、ベネチア様式の巨大な要塞によって旧市街と近代的な地区が分断され、「グリーンライン」によって首都が2つのコミュニティーに分かれています。
ニコシアの中心部に位置するエレフテリア広場は、ベネチアン・ウォールと街を取り囲む空堀に隣接しています。中世に建設され、16世紀にベネチア人によって大規模に再建されたこの実質的な防御壁は、首都の最も古い部分の境界を定め、古代都市と壁の外の新しい地区とを分けています。
ザハ・ハディド・アーキテクツは、エレフテイラ広場を、首都再統一の触媒となる大規模な都市計画の初期段階として構想しています。デザインは、ヴェネチアン・ウォールの景観を損なわず、ニコシアのアイデンティティーの一部として定着させるとともに、空堀を開放して街を取り囲む環状公園としました。
以前はアクセスできなかった堀の部分を、新しい市民広場や庭園、ヤシの木が並ぶプロムナードなどに変えることで、堀は街を囲む「グリーンベルト」となることができるのです。ザハ・ハディド・アーキテクツのデザインは、堀の中の新しい公共空間を古代の城壁に沿って拡張し、ニコシアを囲むようにすることで、この分断された首都のコミュニティを再びつなげることを提案しています。


建築を根源から考え創る「株式会社 森下建築総研」の、設計スタッフ(新卒既卒・経験者)募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
設計スタッフを募集いたします。
新卒、経験者の方など、幅広く募集しています。建築を創るとき、なるべく根源から考えるように心がけています。
人の行為や意味、あらゆる事物のフローが建築を形作って行きますが、建築はある環境の中、時間軸の上に留まります。
次の時代を見据え、風化すること無くその場に存在しうる建築を創っていきたいと考えます。出来上がった建築とはそれを創ることに専念した人々の一つの答ですが、それは特定解ではなく、幾千通りの中から抽出された偶然とも言えるでしょう。唯、その偶然はそれを創る人の確信と信念に裏打ちされた物でないといけません。共に創造する人を募集します。
研究施設・ビル・公共施設・店舗に至るまで、新築・改修を問わず、企画・設計・監理・プロジェクト管理を行う一級建築士事務所です。また、建築に限らず環境デザイン・オブジェ・プロダクトデザイン・インテリア等、各種デザイン・制作も行っています。



安藤祐介建築空間研究所が設計した、愛媛・新居浜市の住宅「六光天井の家」です。家族の繋がりを大切にした平屋の要望に、共用部を中央配置し諸室を分散させ独立性も確保、自然採光を可能にする高窓の方角サイズ・ガラス種類・天井仕上げにより“光の異なる6つの空間”を生み出しました。安藤祐介は、安藤忠雄建築研究所出身の建築家です。
施主の要望は、家族のつながりを大切にできる木造平屋建て住宅であった。
平面計画は3×3のナイングリッドをベースにして、家族の共用空間を中央にワンルームで配置し、プライベートな諸室を周囲に分散させ、家族の一体感と個人の独立性確保の両立を図った。
フットプリントが大きくなる平屋建てでは、中心部への自然採光が課題となる。敷地にゆとりがあり、周辺高所からの視線を気にする必要がないことから、東西方向に3列並んだのこぎり屋根に南北に向かって開いた三角形の天窓を合計6か所設けた。
南側の窓からは、雄大な四国山地を臨むことができる。これらの三角窓に向かって登り天井を掛け、天井面を伝う自然光が室内深部まで拡散する構成とした。三角窓の室内側には、設備の納まりや収納スペース、また照明の架台を兼ねた内庇を設け、屋外からの直射光を遮り天井面へ向けて反射させ、まぶしさや暑さを軽減している。




古谷誠章+桔川卓也 / NASCAが設計した、東京・中野区の「実践学園中学・高等学校 共学館」です。街への活動のショーケースとなるべく考えられ、機能的役割も担うスクリーンによって一塊の建築としての佇まいを与えることで、記憶に残る個性的な姿の創出が目指されました。
実践学園は交通至便の都市部に立地する中高一貫の学校であり、12歳から18歳までの多様な教職員・生徒の皆さんが毎日通勤通学している。2011年竣工の自由学習館を設計した縁で、新しく山手通りに面した共学館の設計にも携わることとなった。
建築とは「人と人が出会う場所」をつくることというのが私たちのモットーであり、数多くの個性豊かな方々がここで出会い、共に学ぶことができるよう、この館内にいることが楽しく、どこにいても居心地の良さを感じてもらえるような建築のデザインを心がけた。
自由学習館が公園の緑に面した静謐な学びの空間であるとすれば、共学館は活発で賑やかに過ごすことのできる動きのある空間。表の多くの人々や車の往来に対して、いわば実践学園の活動のショーケースともなるものと考えて、ひとたびこの建築を見たらそれだけで記憶に残るような、個性的な姿を創り出したいと考えた。
建物の表の顔ともいえるアルミ製のルーバー・スクリーンは、様々な機能が積層するこの施設にひとまとまりの建築としての佇まいを与え、また、時に眩しい日射を遮り、交通騒音を緩和し、表を通る人からの視線を和らげる、いわば「格子戸」のような役割を果たしている。このルーバーの菱形は下層階では横長で密度が高く、上層の階へ行くに従って次第に縦長になり、密度がさがり見通しが良くなるよう変化させた。その変化がまた地上に近い階での騒音の減衰に役立ち、上の階での眺望の良さを生み出している。




五十嵐敏恭 / STUDIO COCHI ARCHITECTSが設計した、沖縄の住宅兼宿泊施設「今帰仁の家」です。快適な半屋外の空間をもちホテル運営も想定との要望に、緑化した大屋根下の開放的な広間と屋根を支える最小限の個室によって、通年で豊かな自然を享受できる建築が構想されました。
この住宅は沖縄県北部の山の中腹を開発して作られた住宅地の端にあり、北側に海を眺望する自然に囲まれた場所に建っている。
敷地は高台にあるため一年を通して風が良く通り、影のある所であれば真夏でも快適に過ごす事ができる。建主も風が抜ける影の空間の居心地の良さを知っており、自然の中での開放的な暮らしができる住宅を望まれ、特に昼夜を問わず外で過ごすことが好きなので快適な半屋外の空間をつくって欲しいことや、将来は海外との2拠点の生活を想定しているため1年の半分程度はホテルとして運営していきたいと要望された。
建物は緑化された大きな屋根の下の開放的な広間と屋根を支える最小限の室内化された個室からなり、半屋外の広間は深い影に覆われ一年を通して沖縄の豊かな自然を実感させてくれる。