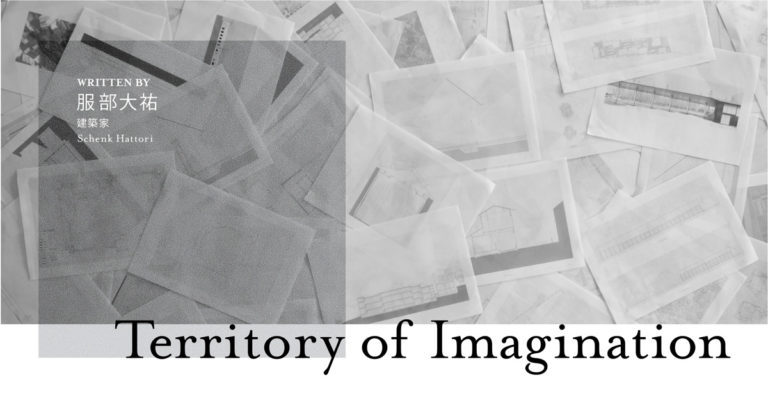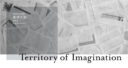 服部大祐による連載エッセイ“Territory of Imagination” 第1回「感覚に訴えかける建築をめざして」
服部大祐による連載エッセイ“Territory of Imagination” 第1回「感覚に訴えかける建築をめざして」
感覚に訴えかける建築をめざして
text:服部大祐
自己紹介 / アントワープと京都、二拠点で活動する設計事務所
大学でなんとなく始めた建築の勉強でしたが、設計課題に取り組み、色々な街や建物巡りをするうちに、自分の中で世界の見え方が拡張していくような感覚と共に、どんどん面白さや奥深さを感じるようになっていきました。その反面、アイデアコンペや学外の設計展を見るたびに、「このまま日本で勉強していたら建築が嫌いになる」という謎の危機感が大きくなり、半ば思いつきでスイスのメンドリジオという街に留学したのが2008年。
大学院の卒業といくつかの国での実務経験を経て、これまた夜更けの酔いと思いつきで設計事務所Schenk Hattoriを開設したのが2014年の春。相方のスティーブンと二人、スイスからベルギーのアントワープという街へ移りましたが、当初はなにも仕事が無いので、昼間からカフェでビールを飲みながらブラジルW杯を観る毎日でした。
いくつかのコンペに勝ち仕事もある程度増え「じゃあ日本でもやってみよう」と帰国したのが2017年の秋。
しばらく東京で過ごしたのち、今年2020年の春、京都に引っ越しました。
京都が寝静まる頃、アントワープで日中の仕事を終えた相方とビール片手にオンラインで話す、というのが事務所の日常。ある意味、このコロナ時代を何年も先取る形で、遠隔でのコラボレーションを継続してきました。(ただし二人ともアナログ人間なので、未だにzoomとか上手く使えません。)
違いを上げればキリがないですが、コンパクトなスケール感や、かつての繁栄を色濃く残す街並み、川と運河が一つのアイデンティティである点など、どことなく似ているこの二つの街を拠点に設計活動を行なっています。
以下の写真はクリックで拡大します

服部大祐による連載エッセイ“Territory of Imagination” 第1回「感覚に訴えかける建築をめざして」2014年当時のアントワープ事務所。 photo©服部大祐
ふたつの試み
今回与えられた連載という機会を通して、ふたつのことを試みたいと考えています。
ひとつは、僕らのこれまでの経験を紹介すること。
僕もスティーブンも、いくつかの異なる文化圏で建築教育を受け、実務の経験を積んだのち、一緒に独立しました。それからは、ベルギーやスイス、日本での設計活動や、ベルギーやオランダ、日本での建築教育に携わっています。これだけ小規模な事務所でありながら、全く異なる文化圏で多拠点的に活動を行なっている例はさほど多くないと思います。その中で見えてきた建築文化や制度、また建築家の働き方の違いなどを紹介していきます。
ふたつ目の試みは、今までの設計活動における自分たちの価値感を言語化するということ。これまで、そのような作業をほとんど行って来ませんでしたが、この機会にある仮説を設定し、その検証・展望という流れに沿って自分たちの取り組みを書き記してみます。
これまでSchenk Hattoriとして実践してきた活動は、建築理論的なバックボーンに貫かれたものでも、特定の社会的なコンテクストに応えようとしたものでもありません。
全く異なるバックボーンを持つ僕ら二人が、外国の大学で出会い、偶然にも共通した類の興味を持っていたことから意気投合し、一緒に事務所を設立し、その興味を実社会の中で検証するための手段として、建築を作ってきました。
そうした実践を通してなんとなく見えてきたひとつの仮説を設定してみたいと思います。
それは、<「感覚に訴えかける建築」は組み立てることができる>というものです。
「感覚に訴えかける建築」というと、生々しいざらっとした手触りや、ぼんやりとした仄暗さを思い浮かべるのは自分だけではないと思います。
あるいはボッロミーニの建築のように幾何学の重複が織りなす躍動感、ル・トロネ修道院のようにストイックなマッスが持つ重厚感、ローマのパンテオンのように圧倒的な架構と光が作り出す神秘性、廃墟の持つ哀愁や物々しさ。
そこには人の手の動きによって捏ねられ作られたような作家性、あるいは長い時の経過と共に物質がもちうる物語性も関係しているかもしれません。