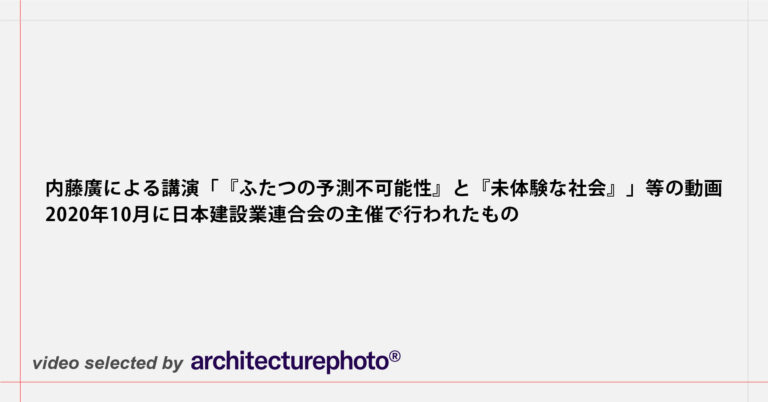伊礼智へのインタビュー「風の心地よさと開口部がもたらす暮らしの豊かさ」が、LIXILのウェブサイトに掲載されています。
architecture archive
辻琢磨による論考「世界とは視点を変えてみれば一本の木の切断面にすぎない」が、LIXILのウェブサイトに掲載されています。
浅子佳英による3組の建築家によるシェアハウスの今を取材したレポート「シェアハウスのその後」の中編が公開されています。成瀬・猪熊建築設計事務所が設計して2013年に完成した名古屋のシェアハウス「LT城西」を訪問して、運営者に話を聞いています。篠原聡子 / 空間研究所+内村綾乃 / A studioによる「SHAREyaraicho」(2012)を取り上げた前編はこちら。


膜業界のリーディングカンパニー「太陽工業株式会社」の、新規部署“デザイン戦略室”での建築デザイナー募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
膜業界のリーディングカンパニー、太陽工業株式会社がデザイン部署を立ち上げ。
自社デザイン提案力の向上とストリームライン化を共に推進する建築デザイナーを募集!大型膜構造物製造における世界シェアトップ企業として「膜の可能性」に挑戦し続ける—。それが私たち太陽工業の使命です。
東京ドームをはじめとするスポーツ施設、大学、鉄道の駅など、皆さんの知っている建築物にも数多く当社の膜構造技術が用いられています。■強み:
当社の強みは、圧倒的な信頼力とブランド力です。高い品質、技術力、納期厳守、という3つを長年積み重ねてきたことで、他社が追随できない程のクライアントとの信頼力を勝ち取り、またそれが当社のブランドとなっています。また、事業としては「膜」という素材は変幻自在に扱うことができる為、ビジネスフィールドも無限に広がる可能性があります。現在当社が展開する製品や商品開発のフィールドも、海底から宇宙まで用途は広がっており、発想力と実行力を駆使することで多くの事業展開が見込まれることも、事業の強みとなります。
■現在の太陽工業:
創業100年を2年後に迎える今、業績が好調であるからこそ、現在を改革のチャンスと捉え、全社で経営改革「Mak Ake」を実行しています。
目的としては、時代の変化に柔軟に対応し、既存事業の拡大とともに、新しい事業を創出できる強い企業体質を実現したいと考えています。その為に、経営マネジメント、ピープルマネジメントの仕組み自体を大きく変えている、真っ只中です。
世の中とクライアントに大きなインパクトを与えられる、発想豊かな会社であることと、また当社の作品、製品にてクライアントに問題解決方法を提供できる会社になることを目標としています。【代表的な膜構造建築物】
東京駅八重洲口グランルーフ、西武ドーム(天井)、埼玉スタジアム(天井)、味の素スタジアム(天井)、阪神競馬場(観客席シェード部分)、大阪ユニバーサルシティ駅、新豊洲Brilliaランニングスタジアム、Medina Haram Piazza Shading Umbrellas(Saudi Arabia)、Denver International Airport(USA)、Shanghai International Circuit(CHINA)、SouthAfrica FIFA World Cup Stadium(SouthAfrica)、LODZ TRAMSTATION(Poland) 等新規事業の創出を目指す動きとして、「膜」に関わる事業、デザイン、空間、運営の提案をクライアントに直接行う新規部署、デザイン戦略室が2021年1月に立ち上がります。
その参画メンバーとして、建築プロジェクトの企画、設計、ビジュアライゼーションを担う建築デザイナーを募集します。部内のプロジェクトメンバー、他部署、外部異業種との連携と積極的なコミュニケーションをしながら、太陽工業の新しい空間デザイン提案を共に構築していきます。



佐野文彦 / Fumihiko Sano Studioが設計した、京都市の、市指定文化財を改修した飲食店「ダンデライオン・チョコレート京都東山一念坂店」です。店舗の公式サイトはこちら。
この物件は高台寺近くの一念坂と呼ばれる、古くからの京都の風情が残り落ち着いた雰囲気を持った通りに建っている。建物は京都市指定の文化財となっており、建物の外観は歴史を感じさせるものだ。しかし内部は数年前に大規模な増改築がされており、元の姿をうかがい知ることができない状態だった。
私はこの建物が以前は持っていたであろう京町屋の雰囲気を取り戻させつつ、このチョコレートブランド発祥の地、サンフランシスコらしさをどこか感じるラフで心地よい開放的な空間を作ることを目指した。
日本建築は寺社仏閣などの特殊なものを除いて主たる素材は杉だ。天井板をはじめ鴨居、柱、長押、廻縁、障子、欄間など日本建築を構成する多くの部材に杉が使われている。
クラフトチョコレートと吉野杉という厳選された自然の無垢な素材を使ったものづくりには親和性があると考え、杉を空間を作っていく素材の中心に据えた。ほとんどのオリジナルの内部意匠は失われてしまっていたが京町屋だったはずのこの空間を、まるで元々ここにあったかのように、空間に溶け込むようデザインを進めていった。



二俣公一 / ケース・リアルが設計した、福岡市の、ブティック・ギャラリー「ヨーガンレール+ババグーリ博多店」です。店舗の公式サイトはこちら。
区画は、その二面を大きなガラスウィンドウで囲われた路面店で、ほぼ長方形のシンプルな箱型の空間であった。そのため、天然素材にこだわったものづくりを行うブランドのイメージには既存空間の無機質さや単調さを崩し、もう少し柔らかさをもつ空間にするのが良いと考えた。
そこで計画では、大きな曲線を描く壁を奥行き方向に連ねてレイアウトし、店舗の中に連続的で切れ目のない、おおらかな二つのシーンが生まれるようにした。ブランドイメージにインスプレーションを得てグリーンとした壁は鉄骨で下地を組み、左官によって強固な分厚い壁で形成している。



小木野貴光+小木野仁美 / 小木野貴光アトリエが設計した、神奈川・伊勢原市の「木と光、六角形の看護施設」です。
身障者が穏やかな看護生活をおくる為の、「包容力」と「求心力」のある場をつくりだした。
ALS(筋萎縮性側索硬化症)など、他の施設では敬遠される重度患者を積極的に受け入れて、地域の看護介護を担っていく、強い意志・理念のもと、設立された看護小規模多機能居宅介護施設である。
入居者にとって、心地・美しさ・自然との繋がりを感じ、人生の終末期に安らかに生活をおくる事のできる、「包容力」のある場が必要であった。また、看護生活の拠点であり心の拠りどころとなる、人、光、周辺環境を取込む「求心力」のある空間であることも目指した。
看護生活を精神的に支える拠りどころとなる求心性を求め、建物を六角形とし、中央リビング+吹抜けから放射状に室がぐるりと囲む事で中央に磁力を持たせ、「求心力」を高めた。
中央リビング+吹抜に全ての室が面しており、このスペースの真ん中に立てば、利用者・患者みなの様子がわかる。声も聞こえる。光もいっぱい入る。六角形の建物形状ゆえに出来た、敷地の隙間は、近隣とのバッファとなり、不整形な外部スペースが周辺環境とこの建物を調停する余白となった。
内藤廣が2020年10月13日に行った講演『「ふたつの予測不可能性」と「未体験な社会」』等の動画。日本建設業連合会の主催で行われたものです。
一般社団法人日本建設業連合会は、建築本部の事業活動の基本方針の一つに「世界に誇れる未来の建築文化の創造」を掲げ、建築を担う次世代に向けての情報発信を目的として、建築セミナーを毎年開催しています。
2020年度は、「富山県美術館」で第60回(2019年)BCS賞を受賞された内藤廣氏を講師としてお招きし、講演会を実施いたしました。□第1部 講演 「ふたつの予測不可能性」と「未体験な社会」
講師 内藤 廣 氏(東京大学名誉教授)
□第2部 対談 内藤 廣 氏、尾﨑 勝 氏(日建連建築設計委員長/鹿島建設)
□開催日時:2020年10月13日(火)18:30~20:30
□開催場所:東京証券会館 8Fホール
以下は第二部の内藤廣と尾﨑勝の対談の動画です。



佐野文彦 / Fumihiko Sano Studioが設計した、京都市の「ソニーCSL 京都研究室」です。クライアント企業の公式サイトはこちら。
ソニーコンピュータサイエンス研究所(以下CSL)のコンセプトである、「人類のゆたかさに貢献する」、そんないろんな形でのイノベーションを起こすような場所には何が必要か。そんなことを思いながら空間を考えた。
それは、自由度と刺激なのではないだろうか。
インターネットによる情報のオンライン化で、研究者がラボに来ないことが問題と聞いていた中で、ラボに行く理由のある場所を作る、というのが今回のテーマでした。机や椅子がある、大きなテーブルは動かせる、イベントができる、キッチンがある、MTGルームがある。それは機能でしかありません。
この場所にはそれらの機能を叶えた非日常や心地よさが必要だと考えました。さまざまな樹種、色、テクスチャーの丸太たち。皮が残っているものもあれば、白太がなくなっているもの、硬いものも柔らかいものもある。


株式会社 羽田設計事務所の、設計スタッフ(経験者・新卒)、設計補助スタッフ募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
設計スタッフを募集致します。
経験者の方、新卒・補助スタッフなど、広く募集致します。
羽田設計事務所では、市庁舎・学校・保育園等の公共建築をはじめ、住宅・クリニック、オフィスなど分野を跨いだ大小様々なプロジェクトを手掛けています。
私達は、地域活性化や教育問題など、建築を通じて社会的課題と向きあうことで、あるべき建築空間の姿を導き、提案・実現することを大切にしています。そして、企画から設計・監理・インテリアまで、一貫してプロジェクトに関わることでクライアントとの連携・信頼を深め、目指す建築空間の実現に挑戦し続けています。プロポーザルにも積極的に参加しています。
一つ一つのプロジェクトに真摯に向き合い、意欲のある方、建築に情熱のある方、大歓迎です!



遠野未来建築事務所が設計した、東京・千代田区の洋館 九段ハウスの日本庭園につくられた「Earth Library」です。環境負荷低減の為、工事残土の建築活用の拡大を見据えたプロジェクト。
日本の建設発生土は平成30年で2億8998万㎥ そのうち場外搬出されているのが 1億3263万㎥、(東京ドーム124万㎥ 約106個分)と輸送によるエネルギー、CO2排出による環境負荷が大きく、それを建築に使うことができれば大きな削減になる。
このプロジェクトは、関東ローム層である「東京の工事残土」を再利用し、版築(はんちく/Rammed Earth)の壁による外寸の直径が1.7m、中のくぼみに人が一人入ることができるという極小空間である。単なる土塀ではなく、土の空間の今後の可能性として居住空間の中に取り入れることも想像しやすいように「本」もおける飾り棚を組み込んだ。敷地は東京・九段の洋館、九段ハウスの日本庭園で、円形の形状はその隣にある古い井戸と対応し、その土地の「地霊とのつながり」も意図している。
版築とは、1300年以上前の法隆寺の土塀にも見られる土を石灰などと混ぜ突き固めた構法で、海外では機械化やプレファブ化も含め現代建築への活用が進み、土の建築の「最先端」と注目されている。
版築構法は日本でここ20年ほどの間に実例ができてきているが、建築基準法上定まった基準がなく、各設計者独自の構造計算と安全基準の検証により行われている。ここでは、設計者と他の事例の圧縮試験データを元に構造の安全性を構造計算により確認し、高さ2m以下で建築物にも工作物にも当たらず、不特定多数の人が来ないことも踏まえて建設した。
ヴェネチアビエンナーレ等にも出展している、インドの女性建築家アヌパマ・クンドゥーへのインタビュー動画「More Common Than Different」です。制作はルイジアナ美術館。彼女のウェブサイトで手掛けた作品を閲覧できます。
“We all feel that human society deserves better.”
In this personal interview Indian architect, Anupama Kundoo reflects on her way into architecture. Growing up in Mumbai, she had an early interest in both the arts as well as math and science. Due to a test, which a family member suggested to her, architecture came up as a profession. “I stumbled into architecture, but it was a blessing. The second I realized it, there was no looking back. Architecture and design would allow me to develop my interest in everything. But they would also ground me and allow me to be of service.” Read less …Kundoo never wanted to become, what she calls a wage-slave. After school, she had applied to study in the US but decided to stay in her home country. Standing at a crossroad in your life are very important times, she says, “because you could choose the wrong road”.
“I had a very strong intuitive voice telling me to just prolong whatever I was doing, even though it did not seem clear from the outside. I decided to leave Bombay and move to South India to figure out and understand my country. I didn’t know where I was going. But I knew what I was leaving. I didn’t know what I wanted. But I knew what I didn’t want. If you see something, you cannot unsee it anymore.”
Kundoo ended up in Auroville, engaging herself for many years in a project that defines itself as a “universal town where men and women of all countries are able to live in peace and progressive harmony above all creeds, all politics and all nationalities. The purpose of Auroville is to realize human unity.”
Kundoo also speaks about time as the most important human resource. “I feel that a lot of the problems we have in today’s world have come because of that wrong notion that time is money. No, time is the only resource we have when we are alive.” While we’re saving other resources, Kundoo argues, we don’t seem to mind spending our own time freely on anything. This is why she encourages people to use their time wisely – to use fewer natural resources and more human resources: “Use more brain, use more muscle, use more time. Because people grow clever in the end when we do that.”
彫刻家 舟越桂の、渋谷区立松濤美術館での展覧会「私の中にある泉」の会場動画です。internet museumが制作したもの。こちらのページは会場写真も16枚掲載されています。会期は2021年1月31日まで。
以下は展覧会公式の概要です。
現代日本を代表する彫刻家、舟越桂(1951–)は、東京藝術大学大学院在学中に函館のトラピスト修道院から聖母子像制作の依頼を受けたことを契機に、本格的に木彫での人物像の制作を開始しました。1980年代にはじまる楠の木彫彩色の人物像は、1990年代前後から異形化が試みられるようになり、新たな表現領域が切り拓かれていきました。
舟越は、一貫して人間の姿を表すことにこだわり、「自分の中の水の底に潜ってみるしかない」と、創造にあたってまず自分自身と向き合う姿勢をとり続けてきました。その背後には「ある個人を特定して語っていく事、それが普遍的に人間について語る事になっていく」という思いがあり、また創作の源となる作者の内面は、ひそかに外につながる水脈を保つ地底湖のように、社会的あるいは個人的な様々な事象を受けとめ揺らぎ続けてもいるのです。
本展ではこの作家の心のありようを、「私の中にある泉」と呼びます。そして、1980年代から今日までの代表的な彫刻作品にくわえ、ドローイング、版画、何かを思うたびに書き留められるメモ、自作のおもちゃや小物などをつぶさに見ていくことで、作品が生み出される作家自身の内なる源泉の姿そのものを探ります。


“クリエイティブ・リソース”をテーマに資源循環の仕組みづくりを目指す「ASEI建築設計事務所」の、設計・研究開発チーム・静岡本社の各スタッフ募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
ASEI建築設計事務所では、設計スタッフ、研究開発チームスタッフ、静岡本社スタッフを募集しています。
ASEI建築設計事務所は、品川区西五反田を拠点に建築家・鈴木亜生が主宰する設計事務所です。
「クリエイティブ・リソース」をテーマに資源循環の仕組みをつくる活動を続けています。様々な地域で未利用な資源の価値を見出し、地域の技術を活用した材料を開発して、新たな構法・構造へと再編した環境建築を目指しています。現在はこうした設計活動と並行し、製造者・技術者・研究者・構造家・メーカーといった様々な専門家との協働による研究開発製造コンサル事業の準備を進めています。
□ 業務内容
・個人住宅、テナントビルなどの設計・監理などの業務全般
・地域資源と技術の研究リサーチ
・研究開発チームの運営管理
・静岡本社との連携業務
(設計・構造・設備・土木設計・測量・ドローンレーザースキャナ測量・地上レイザースキャナ測量・不動産開発営業など多岐にわたる)
何より私たちの設計活動に共感いただける方を募集しています。その共感から好奇心を膨らませて仕事に臨んでもらえるような方が最適です。様々な経歴・立場の方からのご応募お待ちしています。さらに静岡本社との業務連携により、静岡勤務を希望される方も大歓迎です。
静岡本社についてはこちらの会社HP(www.artsogo-sekkei.com)を参照ください。
・静岡が地元でUターン就職・転職を検討されている方。
・静岡県内の大学出身・在学で設計事務所への就職を希望されている方。
・CIM(土木) 〜 BIM(建築)の設計に経験、あるいは意欲のある方。
・土木測量の経験を活かして建築設計にも携わっていきたい方。
・不動産開発の経験を活かして建築設計にも携わっていきたい方。




佐野文彦 / Fumihiko Sano Studioが設計した、京都・福知山市の、築約80年の古民家を改修した宿泊施設「菱屋」です。施設の公式サイトはこちら。
京都・福知山市にある明智光秀が作った城下町の風情を残す通りに建つ、築80年程の古民家をリノベーションするプロジェクト。
この通りはクライアント家族が育った通りだが、近年空家が増えている。クライアントは飲食店を経営しており、遠方から来られたお客様の宿泊先がビジネスホテルしかない事を憂いておられた。
賑わいや風情が失われていく街に何ができるか、を考えた際に、地域の素材や職人のもつ技術、地域文化を活かした宿を作ることとなった。
昔は頻繁に起こった由良川の氾濫に備え屋根裏部屋へ避難できるよう設けられた吹き抜けの意匠はそのままに、受付と階段ホール、4つの客室と小さな飲食店舗を作り、福知山の奥にあった蔵を解体し、広い庭を作った。
各部屋には丹波漆や福知山の藍、綾部の手漉き和紙、丹後檜、丹波石など様々な地域の素材を使い、地域の職人たちと作り上げた。


新居千秋都市建築設計の、新規スタッフ・アルバイト募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。
新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。
新居千秋都市建築設計では新規プロジェクト開始の為、新規スタッフ、アルバイトを募集しております。
◇最近のプロジェクト
最近は1200㎡程度のオフィスビル、4800㎡程度の堺市の小学校等の設計を進めています。
また、70㎡程度の伊賀市の公衆トイレ(グッドデザイン賞受賞)、弊社単独で取り組んだ両国の高さ約100m超、25000㎡程度の超高層ビルが竣工しました。6000㎡程度の小牧市の図書館、5600㎡程度の横浜市港南区の公共施設が、近日竣工予定です。
昨年は横浜の高さ約135m、65000㎡程度で大手設計事務所と協同で設計している超高層ビルが完成しました。
その他、3500㎡程度の流山市の図書館、700㎡程度の共同住宅や、台湾での共同住宅にも取り組んでいます。また、進行中のプロジェクトは多数あり、プロポーザルにも取り組んでいます。◇私達の設計への取り組み方
私達は今までに数多くの公共施設の設計に取り組んできました。どの地域に対してもきめ細かい設計をし、数々の賞、社会的評価を頂いています。大規模の建築、公共的に意義のある建築、大手ディベロッパーとの都市、住宅づくりを行っています。
また、2014年に金沢21世紀美術館で開催され、水戸芸術館でも開催された、「3.11以後の建築展」に出展しました。私達が続けてきた、ワークショップでのつくり方を展示しました。本も出版されていますので、是非ご覧になってください。また、UIAでの講演会をまとめた、3.11とグローカルデザイン(鹿島出版会)にも、私達の設計への取り組み方が掲載されています。合わせてご覧ください。
私達の事務所はこれまでに公共建築を35個、全てコンペで勝ち取ってきました。また、建築学会賞、日本建築大賞、公共建築賞、吉田五十八賞、村野藤吾賞、25年賞を含む、76の賞を受賞しており、その内、劇場を含む複合文化施設で56の賞を受賞しています。また、28の集合住宅、7の独立住宅をつくってきました。集合住宅はコンスタントにやりながら、独立住宅は何年かに一度、どうしても私達が良いという施主の依頼を受けています。
このように私達の事務所は、コンペが得意だという人、大きな規模の公共建築をやってみたい人に向いていると思います。又、時には大手設計事務所とコラボレーションすることもあります。そういう少し変わった経験をしたい人にも良いかもしれません。そして、そのような経験を通して、独立して自作を作りながら大学で教えてみたいという人にも向いていると思います。何人かの私達の事務所の卒業生は現在大学で教えています。又、ワークショップで市民の人達の意見を聞きながら設計をしたり、3Dを用いて、色々な難しい建物に挑戦しています。最近では、動画も用いて設計時にプレゼン、検討を行っています。